本記事は「2025年改正育児介護休業法シリーズ」の第33弾です。他のシリーズの記事はコチラから👉2025年育児介護休業法改正|企業がすべき対応と助成金情報
前回は、2025年4月から施行されている雇用保険法の改正が、育児を巡る社会にどのような変革をもたらすのか、その全体像について解説しました。
前回の記事は👉雇用保険法改正でどう変わる? 共働き・共育てを加速する育児関連給付金の新常識
特に、多くの共働き家庭が直面する育休中の収入減という課題に対し、「手取り実質10割」という画期的な給付が実現することをお伝えしたかと思います。
今回は、その「手取り実質10割」を実現する制度の中核をなす「出生後休業支援給付金」に焦点を当て、その全貌を深掘りしていきます。
なぜこの制度が必要とされたのか、誰がどのような条件でこの給付を受けられるのか、そして、従来の育児休業給付金と組み合わさることで、いかにして「手取り実質10割」が実現するのか――その驚くべきカラクリを徹底的に解説します。
2025年4月からの新たな給付金は、まさに共働き・共育て世帯にとっての「切り札」となるでしょう。
この制度を正しく理解し、最大限に活用することで、育児と仕事の両立における経済的な不安を解消し、より豊かな家族生活を築くための一歩を踏み出しましょう。
この記事は、2025年育児休業給付金改正の全体像を解説するハブ記事の一部です。全体像はこちらから

この記事で分かること
- 「出生後休業支援給付金」は、出生後8週間以内の休業を対象とした新設給付金
- 給付率が従来の67%から「約80%」へ引き上げられ、手取りで実質10割相当を保障
- 支給の鍵は「父母合計で14日以上の休業」。父親のわずかな育休でも要件を満たせる柔軟さ
- 給付金が「非課税」であることと、社会保険料の「全額免除」が実質10割を実現するカラクリ
- 専業主婦家庭やひとり親家庭でも、一定の条件で単独受給が可能というセーフティネット
出生後休業支援給付金の創設背景と制度の狙い|育児休業給付金との違いも解説
2025年4月、雇用保険法の改正により「出生後休業支援給付金」が新たに創設されました。
この給付金は、単なる経済的支援に留まらず、日本の少子化問題に歯止めをかけ、共働き・共育て社会を本格的に推進するための、政府の強い意志が込められた制度です。
なぜ出生後休業支援給付金で「手取り実質10割」が必要なのか|育児休業中の収入減対策
従来の育児休業給付金は、前回の記事でも触れた通り、休業開始時賃金の67%(育児休業開始から181日目以降は50%)が支給される仕組みでした。
確かに、育児休業期間中は社会保険料(健康保険・厚生年金保険)が免除され、さらに給付金自体が所得税や住民税の対象とならない非課税であるというメリットはありました。
しかし、育児休業前の給与と比べると、手取り額が減ってしまうという経済的な不安は拭えず、特に家計を支える層にとって、育児休業取得を躊躇させる大きな要因となっていました。
特に男性の場合、育児休業の取得は女性に比べてまだまだ一般的ではなく、収入減への懸念がそのハードルをさらに高めていたのが実情です。
この経済的な不安を解消し、より多くの親が、特に育児の初期段階で安心して休業を取得できる環境を整備することこそが、本制度創設の喫緊の課題でした。
経済的なインセンティブを最大化することで、育児休業が一部の特別な人だけのものではなく、誰もが当たり前に選択できる制度となることを目指しています。
制度創設の背景と少子化対策における出生後休業支援給付金の位置づけ|男性育休促進
近年、日本が直面する少子化問題は、社会全体で喫緊に取り組むべき最重要課題と位置づけられています。
政府が掲げる少子化対策では、その中核の一つとして「男性育休取得の促進」が強力に打ち出されました。
「男性の育休取得の促進」はコチラのシリーズから詳しく解説してます👇

この背景には、育児に男性が積極的に参画することで、女性の産後ケア期間の確保、産後うつのリスク軽減、女性のキャリア継続支援、そして夫婦間の育児負担の公平化といった多岐にわたるメリットが期待されていることがあります。
しかし、これまでの制度や社会慣習だけでは、男性の育休取得率は依然として低い水準にとどまっていました。
そこで、経済的な支援を大幅に強化することで、この現状を打破しようという議論が進められました。
「出生後休業支援給付金」は、男性育休取得を強力に後押しし、育児を社会全体で支えるという国の強いメッセージが込められた制度なのです。
男性育休取得を後押しする出生後休業支援給付金の目的|共働き・共育てを支援
出生後休業支援給付金は、共働き世帯における「手取り実質10割」の実現を通じて、特に男性が育児休業を取得しやすい社会の実現を強力に目指しています。
男性が育休を取得することは、単に父親が育児に参加するだけでなく、以下のような好循環を生み出すことが期待されます。
- 育児への男女共同参画の促進
- 夫婦が共に育児に参加する意識を高め、協力し合う関係性を築くきっかけとなります。
- 女性のキャリア継続支援
- 出産後の女性が安心して職場復帰できるよう、男性が育児を分担することで、女性の心身の負担を軽減し、キャリアの継続を強力にサポートします。
- 夫婦の育児負担の公平化
- 育児の喜びも大変さも夫婦で分かち合うことで、一方に偏りがちな育児負担を公平にし、家庭内の幸福度向上に繋がります。
このように、「出生後休業支援給付金」は、経済的なインセンティブを最大化することで、男性が育児休業を取得することのハードルを下げ、育児への積極的な関与を促し、結果として持続可能な社会、そして誰もが安心して子育てができる社会の実現に寄与することを目的としています。
出生後休業支援給付金の支給要件|誰が、どの条件で受け取れるか徹底解説
「出生後休業支援給付金」は、育児休業を検討している方々にとって、その経済的な不安を大きく軽減する魅力的な制度ですが、誰もが自動的に受け取れるわけではありません。
この給付金には、明確な支給要件が定められています。ここでは、その要件を詳しく掘り下げていきましょう。
原則的な支給要件|出生後休業支援給付金で夫婦両取りを実現する方法
この給付金の最も特徴的な要件は、まさに「共育て」を強力に推し進める姿勢が明確に打ち出されている点にあります。
父母がともに、子の出生後8週間以内に合計14日以上の休業を取得することが原則です。
これは、夫婦が子どもの出生直後に協力して育児に取り組むことを目的としています。
そのため、原則として、父親が「育児休業(出生時育児休業=産後パパ育休)」を、そして母親が労働基準法に基づく「産後休業」を、それぞれ取得している必要があります。
特に重要な点として、母親が取得する通常の「産後休業」期間は、この給付金の要件における「母親側の休業」としてカウントされます。
会社員である母親は出産後に産後休業を確実に取得するため、合計14日以上の休業期間はほとんどの場合、母親の産後休業だけで満たされます。
したがって、夫婦ともに雇用保険の被保険者である場合、この給付金が支給されるかどうかの最も重要なポイントは、父親が子の出生後8週間以内に、短期間でも「育児休業(出生時育児休業=産後パパ育休)」を取得するかどうかにあります。
各親の休業期間がそれぞれ14日以上である必要はなく、父母の休業期間の合計が14日以上であれば対象となります。
例えば、父親が2日間の育児休業を取得し、母親が通常の産後休業(出産日から8週間=約56日間)を取得するような組み合わせでも要件を満たします。
これは、夫婦それぞれの働き方や状況に合わせて柔軟に休業を取得できるよう配慮されたものです。
例外的な支給要件|夫婦の休業が困難でも出生後休業支援給付金を受ける条件
原則として父母ともに休業が必要ですが、以下のような特別な事情がある場合は、配偶者の育児休業取得を要件とせず、本人の育児休業のみで給付金の対象となることがあります。
- 配偶者が雇用保険の被保険者ではない場合(例:専業主婦・夫、自営業者、フリーランスなど)
- ひとり親家庭の場合
- その他、夫婦ともに育児休業を取得することが困難と認められる特定の事情がある場合
雇用保険の被保険者要件|出生後休業支援給付金を受ける条件とは
この給付金は雇用保険から支給されるため、受給者自身が以下の雇用保険の要件を満たしている必要があります。
- 休業開始前2年間で、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
- その他、従来の育児休業給付金と同様の雇用保険被保険者としての要件を満たすこと。
休業期間中の就業制限
産後パパ育休(出生時育児休業期間)中に就業した場合は、給付額が減額されたり、支給対象外となる場合があります。
- 具体的には、この期間中は、原則として休業期間中の就業日数が10日以下(10日を超える場合は80時間以下)である必要があります。
- この制限を超えて就業すると、給付金が支給されない可能性があります。
- また、就業により賃金が支払われた場合、その賃金の額によっては給付額が調整されることもあります。
「出生後休業支援給付金」実例で確認|父母別ケースごとの支給条件
「出生後休業支援給付金」は、夫婦で協力して育児に取り組む「共育て」を後押しするための給付金です。
この給付金が支給されるかどうかは、夫婦それぞれの雇用保険加入状況や、子の出生後8週間以内に誰がどのくらい休業を取得したかで決まります。
ここからは、具体的なケースをいくつか見ていきましょう。
1. 夫婦ともに雇用保険に加入している場合
夫婦ともに会社員で、雇用保険に加入している場合のパターンです。
この場合、母親は出産後に必ず労働基準法に基づく「産後休業」を取得します。この産後休業期間も、給付金の要件である「休業」としてカウントされるため、夫婦合計14日以上の休業期間はほぼ確実に満たされます。
したがって、このケースで給付金が支給されるかどうかの最も重要なポイントは、父親が子の出生後8週間以内に、短期間でも「育児休業(出生時育児休業=産後パパ育休)」を取得するかどうか、です。
- ケースA:父親が育休を取得した場合(〇 支給される)
- 例:父親が2日間育児休業を取得し、母親が通常の産後休業(出産日から8週間=約56日間)を取得した。
- この場合、夫婦合計の休業期間は58日となり、14日以上という条件を満たします。
- 最も重要な「父親が育児休業を取得している」という条件も満たすため、給付金が支給されます。
- ケースB:父親が育休を取得しなかった場合(× 支給されない)
- 例:父親は育児休業を取得せず、母親のみが通常の産後休業(出産日から8週間=約56日間)を取得した。
- 夫婦合計の休業期間は56日となり14日以上ですが、この給付金は「父母ともに休業する」ことが原則です。
- 父親が育児休業を取得していないため、この要件を満たさず、給付金は支給されません。
2. 夫婦のどちらかが雇用保険に加入していない場合(例外的な要件)
原則は「父母ともに休業」ですが、配偶者が雇用保険の被保険者ではない場合など、例外的に本人の育児休業のみで給付金の対象となることがあります。
- ケースC…会社員(雇用保険加入者)の父親が育休を取得した場合で、母親がフリーランスもしくは無業者である場合(〇 支給される)
- 例…父親は会社員(雇用保険加入者)で14日間育児休業を取得しましたが、母親はフリーランスのため、雇用保険には加入しておらず、産後休業もありません。
- この場合、母親は雇用保険の被保険者ではない「例外的な要件」に該当するため、父親が単独で育児休業を取得するだけで給付金の対象となります。
- ケースD…父親がフリーランスもしくは無業者である場合(× 支給されない)
- 例…父親はフリーランス(雇用保険に未加入)で育児休業を取得できず、母親のみが会社員(雇用保険加入者)で通常の産後休業(出産日から8週間=約56日間)を取得した。
- 父親が雇用保険の被保険者ではないため、給付金の対象者ではありません。
- この給付金は父親の育児休業取得を強く促進する制度であるため、母親のみの産後休業では、原則として支給対象とはなりません。
「出生後休業支援給付金」で実現する手取り実質10割|支給額と仕組みを徹底解説
育児休業中の収入減は、家計にとって大きな不安材料ですよね。
しかし、「出生後休業支援給付金」を含む育児休業給付金制度を利用すれば、「手取り実質10割」 という驚きのサポートを受けられる可能性があります。
これは、単に給付金の支給率が高いだけでなく、いくつかの重要なカラクリが組み合わさっているためです。
支給額の計算方法|給付率67%から約80%にアップした出生後休業支援給付金
「出生後休業支援給付金」は、単体で支給されるわけではありません。
まず、通常の育児休業給付金(または出生時育児休業給付金)がベースとなり、それに上乗せされる形で支給されます。
具体的には、以下の合計額が支給されます。
- 従来の育児休業給付金(または出生時育児休業給付金)
- 休業開始時賃金日額の67%相当額が支給されます(育児休業開始から180日間)。
- 出生後休業支援給付金
- 上記に加えて、休業開始時賃金の約13%相当額が上乗せ支給されます。
- この上乗せは最大28日間が対象です。
これにより、給付金自体の合計額は、従来の給付率67%と新給付金約13%で、合計約80%の支給率になります。
「手取り実質10割」の内訳|出生後休業支援給付金3つの仕組みを徹底解説
「給付金が約80%なら、なぜ『実質10割』なの?」と疑問に思うかもしれません。その秘密は、以下の3つの要素にあります。
- 育児休業期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の免除
- 育児休業期間中は、会社と従業員が負担する社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除されます。
- 通常、給与からはこれらの社会保険料が約14〜15%程度天引きされています。
- この大きな負担がなくなることで、手取り額が大幅に増えるため、「実質10割」に最も大きく寄与する要素と言えるでしょう。
- 育児休業給付金が非課税であること
- 育児休業給付金は、所得税法によって非課税所得と定められています。
- つまり、支給された給付金に対して、所得税や住民税がかからないのです。
- 通常、給与収入からはこれらの税金が差し引かれますが、給付金にはそれがありません。これも手取り額を増やす大きなメリットです。
- 具体的なシミュレーションで見る「手取り実質10割」
これらの要素が組み合わさることで、育児休業前の賃金とほぼ同水準の手取り額になることをシミュレーションで見てみましょう。
【シミュレーション例1:1ヶ月間(例えば30日)フルで育児休業を取得した場合】
- 休業開始前の月給(額面)
- 30万円
- 社会保険料(約15%と仮定)
- 4.5万円
- 税金(所得税・住民税、約5%と仮定)
- 1.5万円
- 育休前の手取り月収(概算)
- 30万円 – 4.5万円 – 1.5万円 = 24万円
- 育休取得中の本人の手取り額(「出生後休業支援給付金」支給期間中)
- 従来の給付金(67%)
- 30万円 × 67% = 20.1万円
- 新給付金(約13%)
- 30万円 × 13% = 3.9万円
- 給付金自体の合計額(約80%)
- 20.1万円 + 3.9万円 = 24万円
- 社会保険料の免除額
- 4.5万円
- 税金の免除額
- 1.5万円
- 育休中の手取り月収(概算)
- 24万円(給付金)+ 4.5万円(社会保険料免除分)+ 1.5万円(税金免除分) = 30万円
- 従来の給付金(67%)
上記のシミュレーションでは、育休前の手取り月収が約24万円だったのに対し、育休中は給付金自体は24万円ですが、社会保険料と税金の免除により、実質的な手取り額は約30万円となり、育休前の額面月収(30万円)とほぼ同水準になります。
【シミュレーション例2 2日間のみ育児休業を取得した場合】
この場合も、「手取り実質10割」の仕組み自体は適用されますが、実際に受け取る給付金の総額は休業日数に応じた日割り計算となります。
- 休業開始前の本人の月給(額面)
- 30万円
- 休業開始前の本人の賃金日額(概算)
- 30万円 ÷ 30日 = 1万円
- 2日間の育児休業で支給される給付金(概算)
- 1日あたりの給付金(約80%)
- 1万円 × 80% = 8,000円
- 2日間の給付金合計
- 8,000円 × 2日 = 16,000円
- 1日あたりの給付金(約80%)
- 社会保険料の免除
- 育児休業期間が月をまたがず、かつその月の末日を含む育児休業であれば、その月の社会保険料は免除されます(例:月の途中で2日間育休を取り、その月の末日まで育休が続く場合)。
- ただし、2日間だけの育休で月の途中に終了する場合、その月の社会保険料は免除されない可能性があります。
- 一般的には、社会保険料免除の恩恵を最大限に受けるためには、月末を含む形での育休取得が推奨されます。
育児休業中の社会保険料の免除に関しては

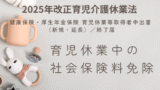
- 税金
- 支給された給付金16,000円は非課税です。
この例のように、短期間の育児休業でも給付金は支給されますが、その額は日割り計算となり、社会保険料の免除についても注意が必要です。
しかし、給付金自体の高い支給率と非課税というメリットは、休業期間の長短にかかわらず享受できます。
まとめ|出生後休業支援給付金で「手取り実質10割」を実現する仕組み
今回は、「出生後休業支援給付金」の仕組みと、「手取り実質10割」 という画期的な給付がどのように実現するのか、その驚くべきカラクリを詳しく解説しました。
この制度を最大限に活用するためには、「いつからいつまで給付が受けられるのか」という支給期間や、具体的な申請手続きについてもしっかりと理解しておくことが重要です。
次回予告|出生後休業支援給付金の受給タイミングと手続きのポイント
次回の記事では、これらの実務的な側面に焦点を当て、「いつ」「誰が」「どのように」給付金を申請し、受け取ることができるのかを徹底解説します。
ぜひご期待ください。
次回の記事は👉2025年4月新設「出生後休業支援給付金」徹底解説 総務担当者が知るべき申請手続きと実務ポイント
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。
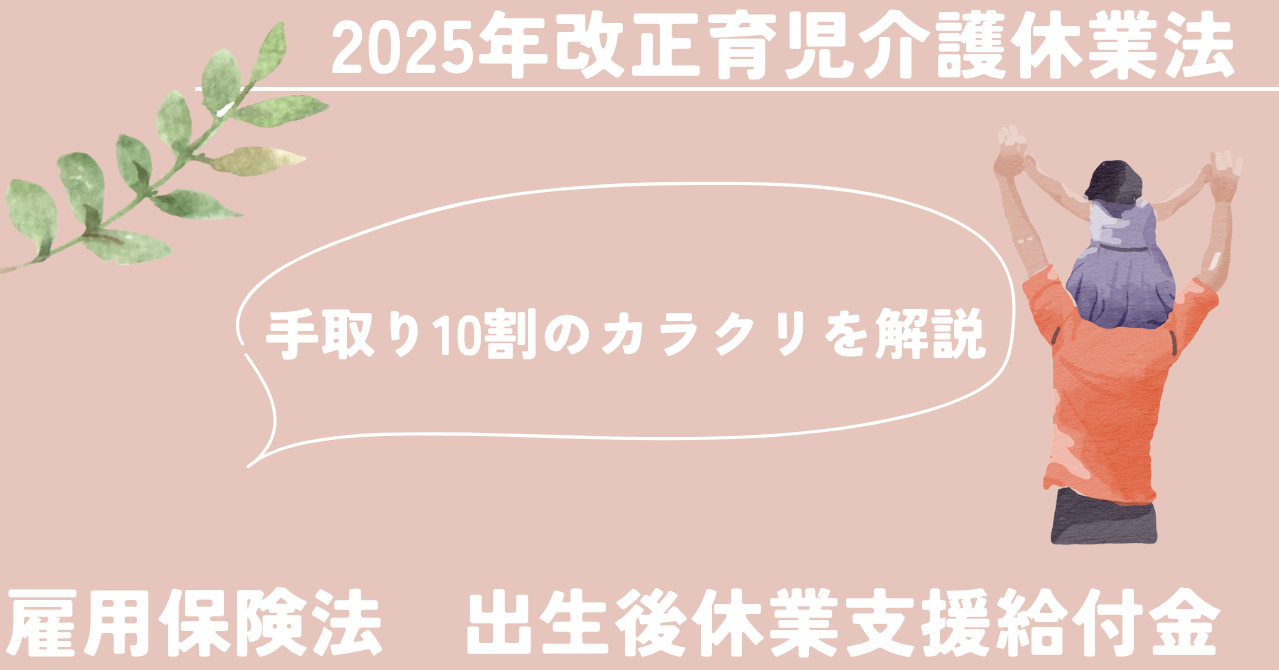

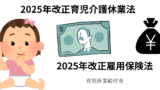
コメント