
執筆者:社会保険労務士 戸塚淳二
法改正対応のスペシャリスト。戸塚淳二社会保険労務士事務所 代表として、多岐にわたる労働関連法規の解説から、実践的な労務管理、人事制度設計、助成金活用まで、企業の「ヒト」と「組織」に関する課題解決をサポートしています。本記事では、事業主の皆さまが安心して法改正に対応できるよう、専門家の視点から最新情報をお届けします。
社会保険労務士登録番号:第29240010号
前回は、「育児休業取得状況の公表義務の拡大」について取り上げ、企業がどのように育休取得の実態を可視化していくべきか、そしてそれが男性の育休取得促進にどうつながるのかを解説しました。
今回は、同じく男性の育児休業取得を後押しする取り組みのひとつとして、2025年の法改正に新たに盛り込まれた「3歳未満の子を養育する労働者へのテレワーク選択肢の提供(※努力義務)」に焦点を当てていきます。
テレワークの選択肢があることで、育児と仕事を両立しやすい環境が整い、特にこれまで育児に関わりにくかった男性社員の参画を後押しする効果が期待されます。
この取り組みは、単なる働き方改革にとどまらず、家庭内での育児の在り方や企業文化そのものにも影響を与える大きな転換点となるかもしれません。
これまでの状況(2022年改正)
これまでは(2025年改正以前)、育児と仕事を両立するために企業側に求められる措置として、主に以下のような内容がありました。
法律に明文化された企業の「措置義務」(法律上、企業が対応しなければならないもの)
- 短時間勤務制度(必須) → すべての3歳未満の子を養育する労働者に、企業は短時間勤務制度(所定労働時間6時間程度)を提供する義務がありました。
しかしながら、企業は、次のような状況下において、短時間勤務制度の代替措置として、以下のいずれかを講じることが求められていました。
- 対象労働者からの申出があったが、やむを得ない事情で短時間勤務制度を利用できない場合
- 就業場所や業務の性質等からして、短時間勤務制度の導入が著しく困難であると認められる場合
この場合、企業は代替措置を講じる義務を負うとされています。以下の5つの内、1つ以上の代替措置を提供しなければならないのです。
- 育児休業に関する制度に準ずる措置
- フレックスタイム制度
- コアタイムなし・短縮コアタイムなどの柔軟な勤務時間を設定できる制度の導入。
- 始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ制度
- 例えば、「通常9:00〜18:00の勤務を、8:00〜17:00や10:00〜19:00に変更できる」といった対応。
- 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇の付与(例:育児目的休暇)
- 子どもの学校行事や保護者面談、急な病気での通院に対応するための休暇。
- 子どもの発熱や学校の急なイベントに合わせて、1日の勤務時間を柔軟に調整することができる。
- 事業所内保育施設の設置・運営
- 企業内に保育施設を設ける、または提携保育園を利用できる制度を整備する。
法律に明文化されていない努力義務(企業が導入するかどうかは自主的な判断に委ねられていた。対応が望ましい)
- テレワークの導入
- 残業の免除制度
- 企業独自の育児支援(特別休暇や費用補助)
改正前の法律では、テレワークという働き方は「努力義務」として位置づけられていたものの、法律上に明文化された努力義務ではありませんでした。
企業が導入するかどうかは自主的な判断に委ねられ、「望ましい取組み」として紹介されるにとどまっていました。
当時は、テレワーク=感染症対策の一環という印象が強く、国としても育児や介護の両立支援という観点からは、さほど重要視していなかったことがうかがえます。
2022年の改正時点では、あくまで企業の裁量に委ねられた「あると良い制度」の一つという位置づけだったのです。
2025年改正 子の年齢で変わる企業の育児支援義務
2025年の育児・介護休業法改正により、テレワークの導入は企業にとって、従業員の育児支援における新たな重要課題となります。
今回の法改正では、お子さんの年齢に応じて、企業に求められるテレワークへの対応や、その他の育児支援義務が具体的に変化するのが大きな特徴です。
この記事ではまず、2025年4月1日から施行される「3歳未満の子を養育する労働者」に向けた企業の義務について詳しく解説していきます。
そして、次回の記事では「3歳以上小学校就学前の子を養育する従業員」に関する10月からの改正義務について掘り下げていきます。
2025年4月からの育児支援 3歳未満の子を持つ従業員向け 新たな企業の義務と期待
2025年4月1日より、企業は3歳未満のお子さんを養育する従業員に対し、より手厚い支援措置を講じることが求められるようになります。
この改正は、少子化対策や女性活躍推進の観点からも非常に重要であり、仕事と育児の両立を支援する新たな一歩となります。
継続される必須の義務 短時間勤務制度
今回の改正において、企業に課せられる義務の一つは、短時間勤務制度の継続的な必須義務です。
これは以前から企業に義務付けられていた措置であり、3歳未満の子を持つ従業員が希望した場合、所定の労働時間を短縮できる制度を必ず導入し、運用しなければなりません。
小さなお子さんを育てる時期は、急な発熱や保育園からの呼び出しなど、時間的な制約が非常に大きいため、この短時間勤務制度は、従業員がキャリアを中断することなく働き続けるための土台となる、極めて重要な制度です。
企業は、この制度が形骸化することなく、従業員が実際に利用しやすい環境を整える必要があります。
ただし、業務の性質上、短時間勤務制度の導入が著しく困難な場合もあります。
そのような企業のために設けられているのが代替措置です(育児・介護休業法第23条第2項)。2025年4月1日からは、この代替措置の選択肢が以下のようになります。企業はいずれか1つ以上を講じることで義務を果たすことができます。
- 育児休業に関する制度に準ずる措置
- フレックスタイム制度
- 始業時刻の変更等(時差出勤)
- 事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
- テレワーク(今回の改正で新たに追加)(育児・介護休業法第23条第2項第1号)
- 育児目的休暇
この場合、代替措置としてテレワークを選択した場合は、努力義務ではなく義務となります。
新たに明文化される「努力義務」 テレワーク導入
そして二つ目の柱として、今回の法改正で新たに加わるのが、テレワーク導入の「努力義務」の明文化です。
これまでもテレワークは柔軟な働き方の一つとして推奨されていましたが、2025年4月1日からは、3歳未満の子を養育する従業員がテレワークを利用できるよう、企業がその導入に努めなければならないことが法律に明確に記されます(育児・介護休業法第24条第2項)。
さて、ここまでテレワークが育児・介護休業法の改正でどのように位置づけられるかを見てきましたが、もしかしたら「あれ?テレワークって2回出てきたぞ?」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんね。
ご安心ください、それは正しい気づきです!
実は、今回の法改正(4月改正)で「テレワーク」という言葉は、それぞれ異なる目的で、2つの条文に登場するんです。
ここが少しだけ複雑に感じられるかもしれませんが、ご説明すると納得いただけると思います。
テレワークが出てくる2つの文脈
- 短時間勤務制度の代替措置(第23条第2項)
- 同じく2025年4月1日からの改正で、3歳未満の子を養育する従業員に対して、企業が短時間勤務制度を講じることが困難な場合の代替措置として、育児・介護休業法第23条第2項にテレワークが選択肢の一つとして追加されました。
- これは、企業が法で定める義務を果たすための具体的な選択肢の一つとして、テレワークが位置づけられたものです。
- ここで、選択肢として「テレワーク」を選びますと「義務」となります。
- 事業主の努力義務(第24条第2項)
- 2025年4月1日からは、3歳未満の子を養育する従業員がテレワークを利用できるよう、企業がその導入に努めなければならないことが、育児・介護休業法第24条第2項に明確に記されます。
- これは、企業に対してテレワークの導入を積極的に検討し、環境整備を行うよう促す「努力義務」です。
このように、テレワークは「導入の努力義務」と「代替措置の選択肢」という、異なる条文と目的で言及されているわけですね。
さらに、もう一つの文脈(2025年10月1日施行)
そして、話はこれで終わりではありません。
次回の記事まで読み進めていただければわかりますが、2025年10月1日施行の改正で、もう一度「テレワーク」に関する条文が追加されますので、最終的には3つの文脈で登場することになります。
この新しい「テレワーク」の位置づけについては、引き続き読み進めてご確認ください。
これは「努力義務」であるため、違反した際に直接的な罰則はありません。
しかし、国が育児支援策としてテレワークを強く推奨し、企業にその導入を促す強いメッセージとなります。
テレワークの導入は、育児中の従業員にとって計り知れないメリットをもたらします。
通勤時間の削減は身体的・精神的な負担を軽減し、育児に充てる時間を創出します。
また、子どもの急な体調不良や保育園・幼稚園からの呼び出しなど、突発的な事態にも自宅から柔軟に対応できるようになるため、仕事と育児の板挟みになるストレスを大きく軽減できます。
企業に期待されること
この「短時間勤務制度の必須義務」と「テレワーク導入の努力義務」の組み合わせにより、3歳未満の子を持つ親は、より多様な働き方を選べるようになります。
なお、短時間勤務制度の導入が困難な場合、その代替措置としてテレワークを選択した企業には、そのテレワークの提供が義務となります。
しかしながら、企業側にとっても、この改正は単なる義務の追加にとどまりません。
柔軟な働き方を推進することは、優秀な人材の確保や定着、ひいては企業の競争力強化に直結します。
多様な働き方を許容する企業文化は、従業員の満足度を高め、生産性の向上にも寄与するでしょう。
今回の改正を機に、企業は単に制度を導入するだけでなく、それが従業員に最大限活用されるような職場環境の整備に、より一層力を入れることが求められます。
まとめ:2025年4月1日施行の改正と企業が今すべきこと
2025年4月1日から施行される育児・介護休業法の改正では、3歳未満の子を養育する従業員に対する企業の対応が強化されます。
特に「テレワーク」は、短時間勤務制度の代替措置(第23条第2項)として義務が生じる場合があること、そしてその導入自体が事業主の努力義務(第24条第2項)となること、この2つの異なる文脈で登場することをしっかりと理解しておくことが重要です。
企業は、今回の改正を単なる法対応として捉えるだけでなく、従業員が安心して働き続けられる環境を整備し、より魅力的な職場を作る好機ととらえるべきでしょう。
就業規則の見直し、制度の社内周知、そしてテレワーク環境の整備など、4月1日までの準備期間を有効活用し、従業員が仕事と育児を両立できる柔軟な働き方を推進していきましょう。
次回予告
次回は、2025年10月1日から施行される育児・介護休業法のさらなる改正に焦点を当てます。
特に、3歳以上小学校就学前の子を養育する従業員に対する企業の新たな義務と、そこで選択肢の一つとして登場する3つ目のテレワークの文脈について、詳しく解説します。どうぞご期待ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

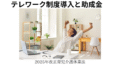
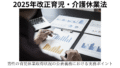
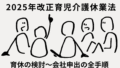
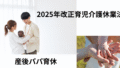

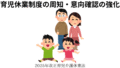
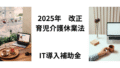
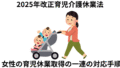
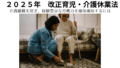
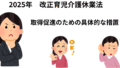

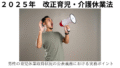

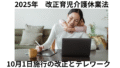
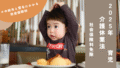
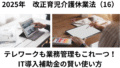
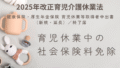
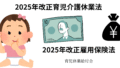
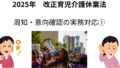


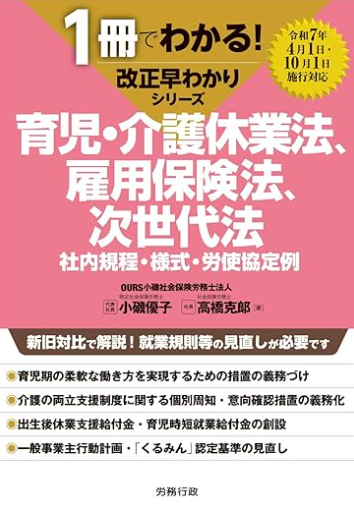

コメント