本記事は「2025年改正育児介護休業法シリーズ」の第32弾です。他のシリーズの記事はコチラから👉2025年育児介護休業法改正|企業がすべき対応と助成金情報
前回までの「男性育休『合わせ技』徹底ガイドシリーズ」では、夫婦で協力して育児休業を取得する具体的なメリットや、その活用戦略について深掘りしてきました。
前回の記事は👉実例付き|育休中と産前産後の社会保険料免除の制度完全ガイド
この記事で分かること
- 2024年の出生数速報値(68万人台)が示す少子化の危機と、改正の切実な背景
- 2025年4月施行「改正雇用保険法」が目指す、共働き・共育ての経済的基盤
- 育児休業給付金の受給資格(前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間)の基本
- 給付額のベースとなる「休業開始時賃金日額」の計算方法と上限・下限の仕組み
- 新設される「出生後休業支援給付金(10割支援)」と「育児時短就業給付金」の概要
男性の育休取得の壁|経済的不安を解消するポイント
育児と仕事の両立を考える上で、特に休業中の経済的な不安は、育児休業取得を躊躇させる男性にとって最大の要因の一つです。
多くの女性が育児休業を取得している一方で、男性は家計の主たる稼ぎ手としての意識や職場への影響を懸念し、休業中の収入減が大きなハードルとなっていました。
2025年改正|育児介護休業法と雇用保険法で共働き・共育て支援が強化
このような状況を打破すべく、国は「異次元の少子化対策」の一環として、多角的な法改正を進めています。
その中で、2025年4月1日には「改正育児介護休業法」と「改正雇用保険法」が同時施行され、育児関連の制度が大きく変更されました。
この連携した改正は、単に育児休業の取得しやすい環境を整備するだけでなく、働く親の経済的な懸念を解消するため、給付金制度にも画期的な変更をもたらしています。
本シリーズでは、この「2025年改正育児介護休業法」の全体像を捉えつつ、今回は特に、雇用保険法改正による育児関連給付金の手厚い拡充が、どのように共働き・共育てを強力に後押しするのかに焦点を当てます。
これまで経済的な理由で育児休業を断念せざるを得なかった男性、そしてより長期・柔軟な育休を望みながらも経済的な不安を感じていた夫婦にとって、今回の「手取り実質10割相当」という強力な経済支援は、育児休業取得をより現実的な選択肢に変える可能性があります。
これからの子育て世代が、経済的な心配を軽減しながら安心して育児に専念し、男女ともにキャリアを継続できる社会を目指す上で、知っておくべき必須知識となるでしょう。
なぜ2025年育児関連法制は大改正されたのか?背景と目的を解説
私たちが暮らす日本では、少子化が社会全体の喫緊の課題として認識されて久しいです。
2023年の出生数は約75万人となり過去最低を記録しました。
さらに2024年には出生数(速報値)が68万6,061人となり、統計史上初めて70万人を割り込むという、極めて深刻な状況に直面しています。
このままでは社会保障制度の維持や経済活力の低下が避けられないと懸念されており、政府は「異次元の少子化対策」を掲げ、強力な施策を打ち出し始めました。
深刻化する少子化問題と政府の異次元の少子化対策の全体像
少子化は単に出生数が減るだけでなく、労働力人口の減少、社会保障制度の持続可能性への影響、地域社会の活力低下など、多岐にわたる問題を引き起こします。
政府が掲げる「異次元の少子化対策」は、こうした複合的な課題に対し、経済的支援の強化、働き方改革の推進、そして地域社会での子育て支援の充実など、包括的なアプローチで対応しようとするものです。
育児とキャリアの両立支援が急務|働く親の現状と課題
その柱の一つが、「育児とキャリアの両立支援」の強化です。現代では共働き世帯が主流となり、夫婦ともに仕事を持ちながら子育てをするのが当たり前になっています。
しかし、現実には多くの親が、仕事と育児の板挟みになり、どちらか一方を諦めざるを得ない状況に直面しています。
特に、育児休業の取得は、女性にとってはキャリアの停滞、男性にとっては職場での立場への不安や経済的な懸念から、依然として高いハードルが存在していました。
このような背景から、国は単に子育て支援を強化するだけでなく、働く親が安心して育児に専念し、同時にキャリアを継続できるような環境整備を急ピッチで進めています。
その象徴ともいえるのが、2025年4月1日に施行された「育児介護休業法」の大改正です。
このことに関する記事は「2025年改正育児介護休業法」シリーズをお読みください。
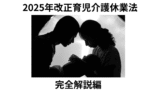
今回は、この大きな法改正の全体像を捉えながら、特に育児中の家庭にとって経済的な安心をもたらす雇用保険法改正による育児関連給付金の給付に焦点を当てて解説していきます。
給付金請求の手続き関する記事は
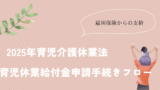
この給付金制度の変更が、私たちの子育てや働き方にどのような変化をもたらすのかを、具体的な情報とともにお伝えしていきます。
2025年改正雇用保険法の全体像|育児関連給付金の変更点を解説
この記事は、2025年育児休業給付金改正の全体像を解説するハブ記事の一部です。全体像はこちらから

2025年4月1日に、育児介護休業法と並行して施行された改正雇用保険法は、単に育児関連の支援を強化するだけではありません。
日本が直面する少子化、労働力不足、そして多様な働き方への対応といった複合的な課題に対応するための、広範な見直しを含んでいます。
この法改正は、雇用保険制度全体を「人への投資」を強化し、持続可能なものとしていくことを目的としています。
雇用保険法改正の目的とは?社会変化に対応するセーフティネットの強化
雇用保険法改正は、主に以下の3つの大きな目的を掲げています。
- 少子化対策、「人への投資」、多様な働き方への対応
- 変化する社会構造に対応するため、育児支援の強化はもちろんのこと、働く人がスキルアップを図り、新しい職場で活躍できるよう、教育訓練や転職支援の給付を拡充します。
- また、短時間労働者など多様な働き方をする人々へのセーフティネット機能も強化し、誰もが安心して働き続けられる社会を目指します。
- 制度の持続可能性の確保
- 雇用保険制度は、失業給付や育児休業給付など、働く人々の生活と雇用を支える重要な社会保険です。
- 少子高齢化が進む中で、この制度が将来にわたって安定的に機能し続けるよう、財政的な側面からの見直しも行われています。
2025年改正における育児関連給付金の位置づけと役割
今回の雇用保険法改正の中でも、育児関連給付金の拡充は、特に重要な柱として位置づけられています。
その背景には、「異次元の少子化対策」を実効性のあるものとするため、育児休業取得を経済的に強力に後押しし、「共働き・共育て」を社会全体で加速させるという強い国の意思があります。
育児休業制度の取得促進は、単に法律で「取れます」と定めただけでは十分に進みません。
休業中の経済的な不安が大きな障壁となるため、この不安を解消し、誰もが安心して育児に専念できる環境を整えることが不可欠です。
今回の給付金の見直しは、まさにその経済的支援を飛躍的に強化し、育児休業の利用を現実的な選択肢とするための鍵となるものです。
2025年育児関連給付金改正の主要ポイントと概要
2025年4月1日に施行された雇用保険法の改正では、育児関連給付金に関して、特に以下の2つの画期的な制度が創設されました。
詳細については次話以降で詳しく解説しますが、ここではその概要をご紹介します。
「出生後休業支援給付金」の創設
手取り実質10割支援の実現
- これは、男性の育児休業取得を強力に後押しし、夫婦で協力して子育てをすることを促進するための目玉となる給付金です。
- 父母がともに一定期間育児休業を取得した場合に、従来の育児休業給付金に上乗せして支給されます。
- 社会保険料の免除や給付金が非課税であることも含めると、休業前の手取り賃金とほぼ同額(実質10割相当)が支給されるため、経済的な不安を大幅に軽減し、これまで育休取得をためらっていた層も安心して休業できるようになります。
「育児時短就業給付金」の創設
育休明け時短勤務者の支援
- 育児休業から職場に復帰した後、育児のために短時間勤務を選択する方は多くいますが、それに伴い賃金が減少することが課題でした。
- この給付金は、2歳未満の子を養育するために時短勤務を行った際に、賃金が低下した場合にその一部を補填するものです。
- 育児休業期間だけでなく、その後の働き方も含めて経済的に支援することで、より長期的な視点での育児と仕事の両立をサポートします。
これらの育児関連給付金の他にも、雇用保険法全体として以下のような見直しも行われています。
以下のものは育児関連給付金とは直接的な関係はありませんが、雇用保険制度が社会の変化に対応するための重要な改正点です。
- 高年齢雇用継続給付の見直し
- 60歳以上65歳未満の労働者に対する給付率が段階的に引き下げられます。
- 自己都合離職者の給付制限期間の短縮
- 自己都合で会社を辞めた場合の基本手当の支給制限期間が、原則2ヶ月から1ヶ月に短縮されます(ただし、一部例外あり)。
これらの改正は、雇用保険制度が単なる失業給付の枠を超え、働く人の多様なライフステージとキャリア形成、そして社会全体の持続可能性を支える、より包括的なセーフティネットへと進化していることを示しています。
育児休業給付金の改正前制度の基本と支給ルール
2025年4月からの雇用保険法改正によって、育児関連給付金は大きく拡充されましたが、その基盤となるのが、これまで運用されてきた「育児休業給付金」の制度です。
新制度を深く理解するためにも、まずはそのベースとなる従来の育児休業給付金の基本的な仕組みを改めて確認しておきましょう。
育児休業給付金とは?定義と目的をわかりやすく解説
育児休業給付金とは、雇用保険の被保険者が、子の養育のために育児休業を取得した場合に、休業期間中の生活を保障し、安心して子育てに専念できるよう、またその後の円滑な職場復帰を支援するために支給される給付金です。
この制度は、雇用保険法を法的根拠としています。
具体的には、雇用保険法第61条の4に「育児休業給付金」が定められています。
そして2022年10月に男性の育児参加を促進するために創設された「産後パパ育休(出生時育児休業)」に対応する「出生時育児休業給付金」が同法第61条の6に定められています。
これらの条文に基づき、詳細は雇用保険法施行規則などで細かく規定されています。
育児休業給付金の支給要件とは?受給条件をわかりやすく解説
育児休業給付金を受給するためには、以下の基本的な要件をすべて満たす必要があります。これらは2025年4月の改正前からの主要な要件であり、新制度の基礎にもなっています。
雇用保険の被保険者期間
- 育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が、通算して12ヶ月以上あることが原則です。
- これは、育児休業給付金が、雇用保険料を納めてきた実績に基づくものであることを意味します。
【例外】被保険者期間の算定期間の延長
- 上記の原則となる「育児休業開始日の前2年間」の期間中に、疾病や負傷、出産(産前産後休業)、育児(別の育児休業期間)、事業所の休業、その他本人の責めに帰すことのできない理由により、継続して30日以上賃金の支払いを受けることができなかった期間がある場合は、その日数分(最長2年分)を通常の算定期間に加算し、最長で4年間まで遡って被保険者期間を計算できるようになります。
- 例えば、妊娠・出産に伴う産前産後休業期間や、過去に病気で長期休業していた期間など、本来は働けるにもかかわらずやむを得ない事情で働けなかった期間があったとしても、この特例によって受給資格が確保される可能性があります。
育児休業の取得
- 原則として、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得していることが必要です。
- ただし、保育所に入所できないなど、一定の理由がある場合には、子が1歳6ヶ月、さらに2歳に達するまで支給期間を延長することが可能です。
- また、父母が交代で育児休業を取得する「パパ・ママ育休プラス」などの制度も利用できます。
休業期間中の就業制限
- 育児休業期間中、完全に仕事をしないことが理想ですが、一時的に就業することも認められています。
- ただし、支給単位期間(原則1ヶ月)ごとに、就業している日数が10日以下であること、または就業している時間が80時間以下であることが条件となります。
- この基準を超えて就業した場合、給付金が減額されたり、支給されなかったりする場合があります。
育児休業給付金の支給額と支給期間の計算方法・基本ルール
育児休業給付金の支給額と支給期間も、以下の基本的な算定方法とルールが適用されます。
支給額の算定方法
基準となる「休業開始時賃金日額」 支給額は、原則として「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率」で計算されます。
この計算における「休業開始時賃金日額」とは、育児休業が始まる前の6ヶ月間に当該労働者に支払われた賃金総額を、180(日)で割って算出される1日あたりの平均賃金です。
総務担当者様向け詳細
賃金総額の範囲
- 所得税・社会保険料控除前の額面金額です。基本給、通勤手当、役職手当、残業手当など、名称の如何を問わず、労働の対償として毎月(または1ヶ月以内)支払われる全ての手当が含まれます。
含まれない賃金
- 賞与(ボーナス)など、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入されません。その他、退職金や結婚祝い金なども対象外です。
180日で割る理由
- これは雇用保険法に定められた平均賃金算出のための固定的な日数であり、実際の稼働日数や暦日数に関わらず一律に適用されます。
上限額と下限額
- 「休業開始時賃金日額」には、毎年8月1日に見直しが行われる上限額と下限額が設定されています。
- 上限額の意義
- 高収入の方の給付額が青天井にならないよう、制度の公平性と財源の維持のために設定されています。
- この上限額を超える賃金日額は、給付金算定の基礎とはなりません。
- 下限額の意義
- 最低限の生活保障という給付金制度の目的を果たすため、賃金が比較的低い労働者でも一定の給付額が確保されるよう設定されています。
- 総務担当者様は、これらの上限額・下限額の最新情報を常に確認し、正確な給付額の試算および申請書類作成に反映させる必要があります。
- 毎年8月1日に見直しが行われる支給限度額や休業開始時賃金日額の上限額・下限額については、厚生労働省の資料で確認できます。
- 正確なURLは毎年変わる可能性がありますが、厚生労働省が公開している「高年齢雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付の受給者の皆さまへ」といったタイトルのPDF資料になります。
- 上限額の意義
給付率の段階的変化
育児休業給付金の給付率は、育児休業の取得期間によって段階的に変化します。
- 育児休業を開始してから180日目まで
- 休業開始時賃金日額の67%
- 181日目以降
- 休業開始時賃金日額の50% この給付率の変更は、長期の育児休業取得を念頭に置いた制度設計です。
- 支給期間
- 育児休業給付金の支給期間は、原則として子が1歳に達する日の前日までです。
- ただし、保育所に入所できないなど、法律で定められた特定の要件を満たす場合は、子が1歳6ヶ月、さらに最長で2歳に達する日まで延長が可能です。
- 総務担当者様は、延長申請に必要な書類や手続きについても把握しておく必要があります。
これらの基本的な仕組みを正確に理解しておくことは、次話以降で解説する2025年4月からの改正内容、特に「出生後休業支援給付金」や「育児時短就業給付金」といった新しい給付金が、従来の制度にどのように上乗せされ、働く親の経済的支援がどのように強化されたのかを深く把握するための基盤となります。
まとめ|育児休業給付金の支給要件・期間・金額と2025年改正のポイント
今回の記事では、2025年4月1日に施行された「改正育児介護休業法」と「改正雇用保険法」の背景にある深刻な少子化の現状と、それに対する政府の「異次元の少子化対策」について深く掘り下げました。
特に、育児休業給付金の基本、その支給要件、そして支給額の算定における「休業開始時賃金日額」の重要性について、皆様の実務に役立つよう、詳細かつ正確に解説しました。
育児休業取得を躊躇させる最大の要因の一つである「休業中の経済的な不安」に対し、政府がどのような施策を打ち出しているのか、その基礎となる制度をご理解いただけたかと思います。
次回予告|いよいよ本丸!「出生後休業支援給付金」で手取り実質10割支援の衝撃
次回の記事では、いよいよ今回の雇用保険法改正の目玉ともいえる「出生後休業支援給付金」に焦点を当てて詳しく解説します。
この新しい給付金制度は、育休中の手取り実質10割相当の収入を保障するという画期的な内容で、特に男性の育児休業取得を強力に後押しし、共働き・共育ての推進に大きな影響を与えることが期待されています。
- 「出生後休業支援給付金」とは具体的にどのような制度なのか?
- 支給されるための条件は?
- 従来の育児休業給付金とどう連携するのか?
- 従業員にどのように案内し、申請手続きを進めるべきか?
といった疑問に、具体的な事例を交えながらお答えしていきます。
男性育休取得促進のゲームチェンジャーとなり得るこの制度について、次回の記事もどうぞご期待ください!
次回の記事は👉出生後休業支援給付金とは?2025年新設で「手取り実質10割」を実現するカラクリを徹底解説!
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。
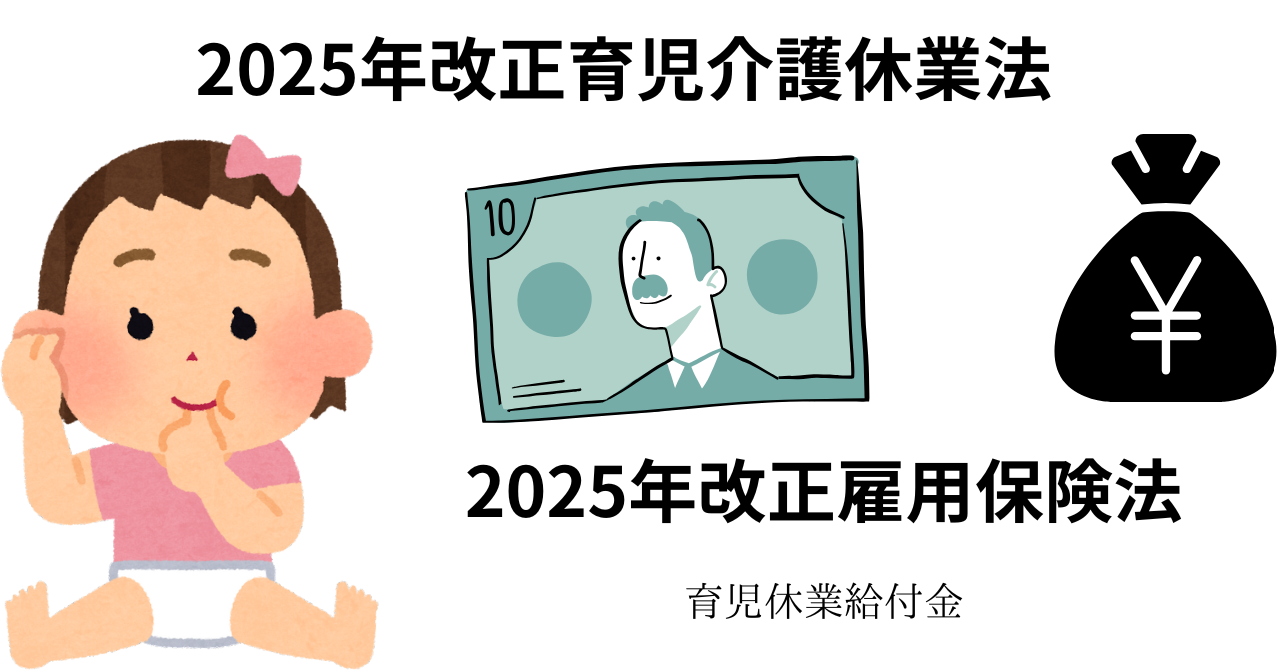

コメント