本記事は「2025年改正育児介護休業法シリーズ」の第37弾です。他のシリーズの記事はコチラから👉2025年育児介護休業法改正|企業がすべき対応と助成金情報
2025年4月・10月と段階的に施行された育児・介護休業法の改正により、「個別意向確認の義務化」「テレワークの選択肢提供」「育休取得状況の公表義務拡大」など、企業が担う両立支援の実務は大きく変わりました。
前回までの記事では、複数回に渡り、こうした改正の流れを受けて創設された雇用保険法の「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」に注目し、企業が産後パパ育休取得者および時短勤務者への支援をどう形にするかを解説しました。
では、育児や介護と仕事の両立を、より制度的・継続的に支えるには?
今回からは、企業の取り組みに応じて国から支給される「両立支援等助成金」をテーマに、各コースの活用方法をシリーズで解説していきます。
第1話となる本稿では、まず助成金全体の構造と2025年改正法との関係性を俯瞰し、企業が「制度を活かす側」に立つための視点を整理します。
この記事で分かること
- 両立支援等助成金は、コスト補填だけでなく「人材定着」と「生産性向上」を狙う戦略的ツール
- 2025年4月の「個別意向確認・周知義務化」の徹底を支える各コースの役割
- 令和7年度(2025年度)から拡充された「育休中等業務代替支援コース」のインパクト
- 2025年10月施行の「就学前までの柔軟な働き方」義務化に向けた、助成金の先回り活用術
- 「申請のハードル」を越え、制度を“知る”から“使いこなす”フェーズへ進むための視点
両立支援等助成金の目的|育児・介護と仕事の両立支援
両立支援等助成金とは、厚生労働省が管轄する、仕事と家庭(育児・介護)の両立支援に取り組む事業主を対象とした助成金制度です。
この助成金は、単に企業のコストを補填するだけでなく、より本質的な目的を持っています。
それは、従業員が育児や介護のためにキャリアを諦めることなく、安心して働き続けられる職場環境を整備することにあります。
具体的には、以下のような多角的な目的のために活用されます。
育児・介護休業等を取得しやすい職場環境の整備
従業員が育児休業や介護休業をためらうことなく取得できるような社内体制や雰囲気作りを促進します。
休業後の円滑な職場復帰支援
休業後の従業員がスムーズに職場に戻り、その能力を十分に発揮できるよう、復帰支援策を後押しします。
男性の育児休業取得促進
男性の育児参加を促し、育児休業の取得を当たり前にすることで、育児負担の偏りを解消し、女性の活躍も支援します。
多様な働き方の導入サポート(テレワーク・時短勤務)
短時間勤務制度やテレワークなど、従業員のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方を導入する企業をサポートします。
人材定着と企業生産性の向上
これらの支援を通じて、優秀な人材の離職を防ぎ、従業員のモチベーション向上や企業全体の生産性向上に貢献します。
両立支援等助成金の種類と対象企業|育児・介護支援制度の活用法
両立支援等助成金には、企業のさまざまな取り組みを支援するために、複数のコースが設けられています。
それぞれのコースには、目的や対象となる取り組み、支給要件が定められています。
主なコースとしては、以下のようなものがあります。
出生時両立支援コース(男性育休取得促進)
- 男性労働者が育児休業を取得しやすい環境を整備し、出生後8週間以内に一定日数(1人目5日以上、2人目10日以上、3人目14日以上)育休を取得した場合に支給(第1種)
- 育休取得率が前年度比で30ポイント以上増加し50%以上、または連続して前年以降70%以上を達成した場合には第2種を支給(60万円、加算あり)。
育児休業等支援コース(育休復帰プラン)
育児休業の取得や職場復帰を支援する制度(育休復帰支援プラン)の策定・活用により、20万~25万円の助成金が支給されます。
育休中等業務代替支援コース(代替要員確保の支援)
育児休業や短時間勤務を利用する社員の業務を代替する人員体制を整備し、代替者に手当を支給するなどの取り組みに対して、最大125万円が支給(2025年度から支給額が拡充)。
柔軟な働き方選択制度等支援コース(テレワーク・時短勤務など)
テレワークや時差出勤、短時間勤務、保育サービス費補助などの制度を導入・利用した従業員1人あたり20万〜25万円(複数制度導入で25万円)を支給、上限は1事業主5名分まで。
介護離職防止支援コース(介護休業制度の導入)
介護休業支援や柔軟な働き方の導入、業務代替体制の整備に対し、最大60~67.5万円(加算制度あり)を支給。
これらの助成金は、基本的に雇用保険の適用事業主であれば、企業規模や業種を問わず申請対象となる可能性があります。
特に令和7年度(2025年度)からは、一部のコースで支給対象が「常時雇用労働者の数が300人以下の事業主」にまで拡大されるなど、より多くの企業が利用しやすくなっています。
ただし、コースごとに詳細な要件が設定されているため、自社の取り組みがどのコースに該当し、どのような要件を満たす必要があるかを確認することが重要です。
2025年4月1日および10月1日から段階的に施行されている改正育児介護休業法の内容に応じて、両立支援等助成金の各コースの内容や支給要件が見直されたり、新たなコースが設けられたりしています。
そのため、常に厚生労働省のウェブサイト等で最新の情報を確認し、法改正への対応と助成金活用を戦略的に進めることが、企業にとって非常に重要になるでしょう。
両立支援等助成金と2025年改正育児介護休業法の関係|制度活用のポイント
2025年に段階的に施行されている育児介護休業法の改正は、企業にとって単なる「義務の追加」ではありません。
少子化対策という国の重要課題に対し、企業もまたその一翼を担うことを強く求められている、というメッセージでもあります。
この改正に対応するためには、単に社内規程を修正するだけでなく、実効性のある制度として運用し、従業員が利用しやすい環境を整える「具体の実装」が不可欠です。
そして、その実装を強力に後押しするのが、両立支援等助成金なのです。
1. 2025年改正育児介護休業法の主な改正点と施行時期
改正育児介護休業法は、主に以下の点が段階的に施行されています。
個別意向確認・制度周知の義務化の強化(2025年4月1日施行)
従業員からの妊娠・出産や家族の介護の申し出があった際、企業側から個別に育児休業や介護休業に関する制度を周知し、取得の意向を確認することがより具体的に義務付けられます。
👇関連記事は👇

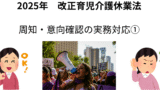
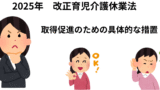
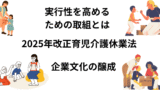

3歳未満の子を養育する従業員へのテレワーク選択肢提供の努力義務化(2025年4月1日施行)
対象となる従業員に対して、在宅勤務やリモートワークといった柔軟な働き方の選択肢を提供することが、企業の努力義務として明記されます。
👇関連記事は👇

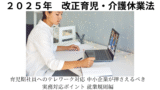

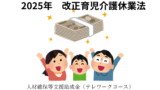
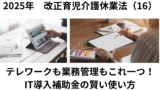
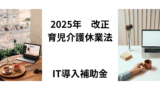
育児休業取得状況の公表義務の対象拡大(2025年4月1日施行)
これまで常時雇用労働者が1,000人を超える企業に義務付けられていた男性の育児休業取得状況の公表が、常時雇用労働者が300人を超える企業にまで拡大されます。
👇関連記事は👇


3歳以上小学校就学前の子を養育する従業員を対象とした柔軟な働き方を実現するための措置の義務化(2025年10月1日施行)
- 企業は、3歳以上小学校就学前の子を養育する従業員が、仕事と育児を両立できるよう、以下のいずれかの措置を講じることが義務付けられます。
- これにより企業は、当該従業員が仕事と育児を両立できるよう、短時間勤務制度、フレックスタイム制度、テレワーク、始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ、その他従業員が選択できる柔軟な働き方のいずれかを講じることが義務付けられます。
2.改正育児介護休業法対応に役立つ両立支援等助成金の概要
これらの法改正に対し、両立支援等助成金は企業の実務を具体的に後押しする形で設計されています。
改正内容と、それに対応する主な助成金コース、企業が取るべき実務の関連性は以下の通りです。
| 改正内容(2025年) | 対応する主な助成金コース | 企業が助成金を活用して行う実務 |
|---|---|---|
| 個別意向確認・制度周知の義務化(強化) | 柔軟な働き方選択制度等支援コース | 面談記録の整備、休業制度に関する社内文書の作成・周知、相談窓口の設置など、従業員への情報提供と手続きの明確化 |
| 3歳未満へのテレワーク選択肢提供(努力義務化) | 柔軟な働き方選択制度等支援コース(テレワークに関する要件を満たす場合) | テレワーク規定の整備、必要なICT環境の導入、従業員への周知、テレワーク導入に伴う相談体制の確立 |
| 男性の育休取得状況の公表義務(対象拡大) | 出生時両立支援コース(主に男性育休の取得促進を支援) 育児休業等支援コース(男性育休の取得や職場復帰を支援) | 男性育休の取得促進策の導入、社内研修の実施、取得状況の可視化と改善、代替要員の確保 |
| 3歳以上小学校就学前の子を養育する従業員への柔軟な働き方の提供義務化 | 育休復帰支援コース(短時間勤務制度の導入・利用を支援) 柔軟な働き方選択制度等支援コース(フレックスタイム、テレワーク等の導入支援) | 短時間勤務制度、フレックスタイム制度、テレワークなどの規定整備と運用、従業員への周知と利用促進 |
この改正内容を“助成金”で具体的に実装するという視点が重要です
上記の表からも分かるように、両立支援等助成金は、単に「法改正に準拠しました」という形式的な対応に留まらず、実際に従業員が制度を利用し、働きやすい環境を実感できるような「具体的な実装」を促す設計となっています。
例えば、男性育休の取得状況の公表義務が拡大された背景には、数値目標だけでなく、実際の取得率を上げて男性の育児参加を促したいという国の強い意図があります。
これに対し、出生時両立支援コースは、男性従業員が育休を取得した場合に企業に助成金を支給することで、企業が男性育休を積極的に推奨し、取得しやすい雰囲気を醸成する具体的な動機付けとなります。
また、代替要員の確保費用なども対象となり得るため、企業は人手不足を懸念することなく、男性従業員が安心して育休を取得できる体制を整えることが可能になります。
テレワーク導入と助成金
同様に、3歳未満の子を持つ従業員へのテレワーク選択肢提供が努力義務化されたことに対して、職場環境改善コースは、テレワーク導入に必要な規程整備や設備投資を支援します。
これにより、企業は努力義務を「努力」に終わらせず、実効性のあるテレワーク制度を導入し、従業員の柔軟な働き方を具体的に支援できるようになります。
柔軟な働き方の義務化と助成金
さらに、2025年10月からの3歳以上小学校就学前の子を持つ従業員への柔軟な働き方提供義務化に対しても、育休復帰支援コースや職場環境改善コースを活用することで、企業は多様な働き方制度を導入・運用し、従業員のニーズに応えることが可能になります。
3.法改正を見据えた企業の育児・介護休業制度対応と戦略
2025年改正育児介護休業法への対応は、待ったなしの状況です。
企業は、以下の点を踏まえ、助成金を戦略的に活用しながら計画的な対応を進めるべきです。
- 社内規程の速やかな見直し
- 改正法に則った育児・介護休業規程、短時間勤務規程、テレワーク規程、フレックスタイム規程などを整備します。
- 従業員への周知徹底と個別対応
- 新しい制度の内容を全従業員に周知するだけでなく、個別の相談を通じて取得を検討する従業員の意向を丁寧に確認します。
- 助成金の活用計画の策定
- 自社の状況と改正法の義務・努力義務を照らし合わせ、どの助成金コースが最適かを検討し、申請準備を進めます。
- 職場環境の継続的な改善
- 助成金を活用して制度を導入した後も、従業員の声を聞きながら、真に働きやすい職場環境の構築を目指します。
法改正を単なる負担と捉えるのではなく、助成金を活用しながら組織全体の生産性向上や従業員エンゲージメントの強化に繋がるチャンスと捉えることが、持続的な企業成長の鍵となります。
両立支援等助成金のメリットと企業活用が進まない理由
厚生労働省が支給する両立支援等助成金は、企業が育児や介護と仕事の両立を支援するために行う取組に対して、経済的なインセンティブを与える制度です。
この助成金を上手に活用することで、人材定着の促進や職場の活性化、企業のイメージアップにもつながる可能性があります。
両立支援等助成金で実現する人材の定着と育成
従業員のライフステージに寄り添った柔軟な働き方や支援制度の導入は、離職の防止に大きく寄与します。
育児や介護のために優秀な人材が離職してしまうのは、企業にとって大きな損失。制度導入を通じて「働き続けられる環境」を整えることで、人材の定着と戦力化が実現します。
両立支援等助成金で企業イメージを向上させる方法
最近では、採用活動において「子育て・介護と両立しやすい職場であるか」を重視する求職者が増加しています。
助成金の活用を通じて社内制度を整えることは、外部からの信頼性向上や「選ばれる企業」になるための重要な一歩となります。
両立支援等助成金で制度導入コストを補填する方法
新たな制度の導入や環境整備には、どうしても一定のコストや時間がかかります。
両立支援等助成金を活用すれば、研修費用や制度整備にかかる費用の一部を国から補助してもらえるため、中小企業でも取り組みやすくなります。
それでも進まない「両立支援等助成金の活用率」の実態
なお、出生時両立支援コースを含む本助成金については、制度自体は充実しているにもかかわらず、『企業の制度理解不足』や『申請のハードルの高さ』などが指摘され、実務上は活用が進んでいない現状があります。
実際、厚労省も『制度の周知と活用促進』を今後の重点課題として位置づけています。
その背景には、大きく分けて以下のような課題が存在しています
- 制度そのものを知らない企業が多い
- 特に中小企業では、人事担当者が専任でないことも多く、情報が届きにくい現実があります。
- 知っていても「実務が煩雑そう」と感じて敬遠されがち
- 「書類が多そう」「申請の要件が複雑そう」「ハローワークとのやりとりが不安」といった声がよく聞かれます。
- 制度導入と助成申請のタイミングを誤るケースも
- 助成金の多くは「事前の計画提出」や「取得前の面談実施」など、事後申請ができない要件があるため、知らずに機会を逃す例も散見されます。
まとめ|本シリーズの目的|両立支援等助成金を“知る”から“使いこなす”へ
こうした現状を踏まえ、本シリーズでは「両立支援等助成金」を単に知識として紹介するのではなく、「実際に使いこなすための視点」を重視して解説していきます。
- どんな企業が対象になるのか
- どういう手順で申請すればいいのか
- 何に注意すべきか
- どこでつまずきやすいか
こうした疑問を一つひとつ丁寧に解消しながら、現場で制度を活用し、人材が定着する仕組みを整えることができるように、実務目線でご案内していきます。
次回予告|育児休業等支援コースの申請条件と活用ポイント
次回からは、助成金の各コースごとに分けて、実際の申請要件や活用方法について詳しく解説していきます。
まずは「育児休業等支援コース」からスタートです。どうぞお楽しみに。
次回の記事は👉育児休業等支援コース|助成金申請フローと必要書類|徹底解説
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。
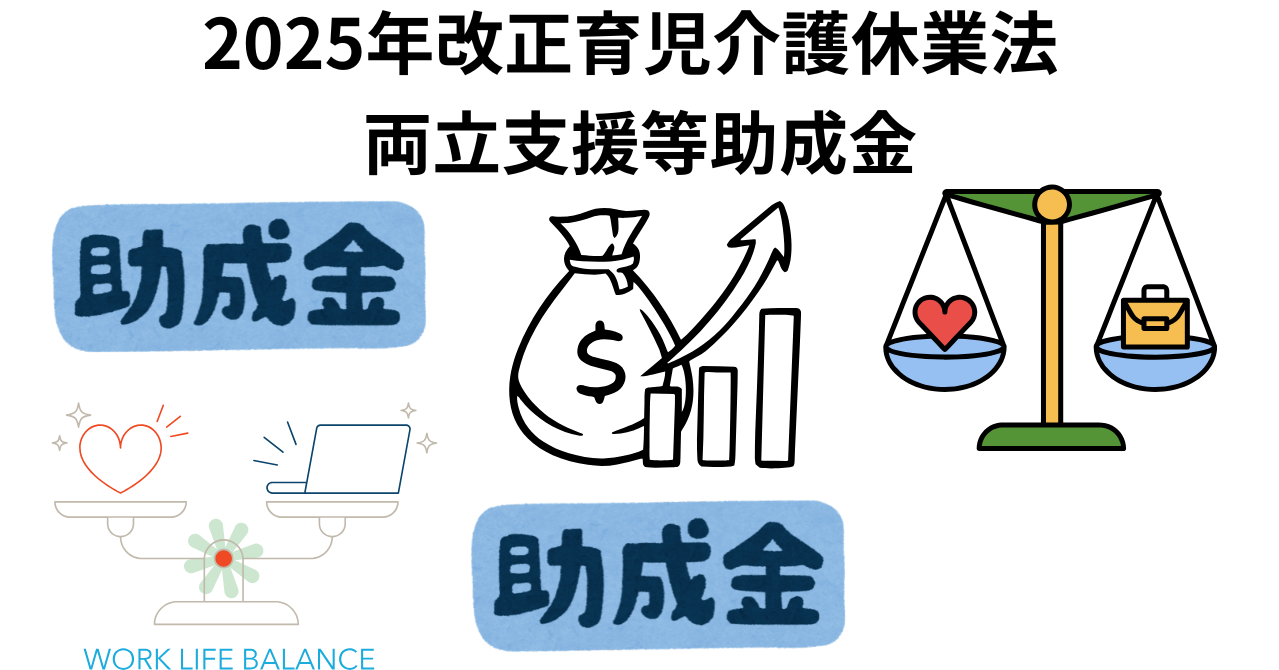

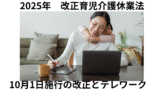
コメント