本記事は「2025年改正育児介護休業法シリーズ」の第34弾です。他のシリーズの記事はコチラから👉2025年育児介護休業法改正|企業がすべき対応と助成金情報
2025年4月から施行された「出生後休業支援給付金」は、共働き・共育てを強力に後押しする画期的な制度です。
前回の記事では、その創設背景と「手取り実質10割」を実現するカラクリについて詳しく解説しました。
前回の記事は👉2025年4月新設 出生後休業支援給付金 ➀「手取り実質10割」を実現するカラクリを徹底解説!
今回は、企業の総務ご担当者様向けに、この給付金を従業員の方がスムーズに受け取れるよう、支給期間、具体的な申請先、必要書類、申請時期、そして詳細な申請フローについて徹底的に解説します。
この給付金は、貴社の育児と仕事の両立支援策を強化し、従業員満足度向上にも繋がる重要なポイントです。
この記事は、2025年育児休業給付金改正の全体像を解説するハブ記事の一部です。全体像はこちらから

この記事でわかること(総務ご担当者様向け)
- 給付金の基本的な期間|子の出生後8週間以内に取得した最大28日間の父親向け休業が対象
- 申請の実施主体と窓口|従業員本人ではなく企業(事業主)がハローワークに申請する流れ
- 申請に必要な書類|賃金証明書や母子健康手帳の写しなど、企業と従業員が準備すべき書類一覧
- 申請の時期とフロー|休業終了後2ヶ月以内の申請期限と、企業とハローワークの具体的な手続きの流れ
- 総務が押さえるべき点|社会保険料免除(月末育休)や給付金の非課税など、従業員へのサポート情報
出生後休業支援給付金の支給期間と対象者|最大28日間の父親向け育休支援
「出生後休業支援給付金」は、育児休業(特に産後パパ育休)を取得する父親を主な対象とし、子の出生後8週間以内に取得した育児休業期間に対して支給されます。
最も重要な点は、この給付金の対象となる期間は産後パパ育休(出生時育児休業)の期間に合わせているため、上限28日間であることです。
- 対象期間の起算点
- 原則として、子の出生日が起算日となります。この出生日から8週間(56日間)の間に父親が取得した育児休業が対象です。
- 支給の対象となる日数
- 父親が上記期間内に取得した育児休業の実際の日数が対象となりますが、その上限は28日間です。
- 例えば、父親が産後パパ育休を10日間取得した場合、10日間分の給付金が支給されます。
- 28日を超えて取得した場合でも、この給付金の上乗せは28日間までとなります。
- 分割取得の場合
- 産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に2回まで分割して取得できます。
- この場合、それぞれの休業期間を合算して最大28日間が支援の対象となります。
- 例:1回目に10日間、2回目に18日間取得した場合、合計28日間が給付対象。
- 例:1回目に15日間、2回目に15日間取得した場合、合計30日間だが、上乗せ給付は28日間が上限。
この「最大28日間」という期間は、特に男性が育児の初期段階に集中的に育児参加できるよう設計されており、通常の育児休業給付金とは別に上乗せされるため、従業員の方の経済的なメリットは非常に大きいです。
出生後休業支援給付金の申請先と申請方法|事業主経由でハローワークに提出
「出生後休業支援給付金」を含む育児休業給付金全般の申請先は、管轄のハローワークです。
そして、最も一般的な申請方法は、従業員本人ではなく「事業主(企業)を経由しての申請」 です。
これは、企業が従業員の雇用保険の加入状況、休業期間中の賃金情報、育児休業の取得状況などを正確に把握しており、必要書類の多くを企業側で作成・確認する必要があるためです。
総務ご担当者様としては、以下の点を理解しておくことが重要です。
- 従業員からの申し出
- まずは従業員から育児休業(産後パパ育休)取得の申し出と、給付金申請の意向を確認します。
- 企業側の役割
- 育児休業制度の案内と取得促進。
- 育児休業給付金(出生時育児休業給付金を含む)の受給資格確認。
- 必要書類の作成と準備。
- ハローワークへの申請手続き代行。
- 給付金の支給決定通知の受領と従業員への伝達。
従業員が安心して育児休業を取得し、給付金を確実に受け取れるよう、企業側が積極的にサポートする体制が求められます。
出生後休業支援給付金の必要書類と申請時期|スムーズな手続きの準備ポイント
給付金の申請には、いくつかの書類の準備と、適切な時期での申請が求められます。
出生後休業支援給付金の必要書類一覧と準備のポイント
ハローワークに提出する主な必要書類は以下の通りです。これらは、企業側で準備するものと、従業員から提出してもらうものに分かれます。
お勧めのクラウド勤怠管理システムソフト👉パソコンで勤怠管理3 スマートパッケージ版
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 育児休業開始前の賃金状況を証明する書類です。給付金の支給額算定の基礎となります。
準備方法「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」
この証明書は、育児休業給付金(「出生後休業支援給付金」含む)の支給額を算定するための非常に重要な書類です。
この書類は、会社(事業主)が作成し、ハローワークへ提出する義務があります。従業員の方が個人で作成する書類ではありません。
正確かつ迅速な作成が、従業員のスムーズな給付金受給に直結するため、総務ご担当者様は以下のポイントをしっかりと押さえておきましょう。
「賃金日額」算定の基本 対象期間と賃金の特定
給付金の支給額は、休業開始前の「賃金日額」を基に計算されます。この「賃金日額」を算出するための元となる賃金月額を、証明書に記載していくことになります。
1. 対象期間の特定
- 期間: 育児休業を開始する日の前の2年間です。
- 例: 従業員が2025年6月15日に育児休業を開始する場合、対象期間は2023年6月15日~2025年6月14日までの2年間となります。
2. 賃金としてカウントされる月の条件
- 上記の2年間の中で、給付金の計算に使える月は、「賃金支払基礎日数(賃金が支払われた日数)が11日以上ある月」 に限られます。
- 賃金支払基礎日数とは?
- 会社から賃金が支払われた日数のことです。
- 例えば、月給制で欠勤がなければその月の歴日数(30日や31日)となることが多いですが、日給制や時給制の場合は実際に働いた日数と一致します。
- なぜ11日以上?
- これは、その月にある程度まとまって雇用されていた期間があることを確認するための要件です。
- 賃金が支払われていない月(例:休職手当がない休職期間、または給与計算期間の途中で入社・退職した月のうち勤務日数が極端に少ない月など)はカウントされません。
- 賃金支払基礎日数とは?
3. 賃金日額の算定基礎となる「12ヶ月分の賃金」
- 上記で特定した「賃金支払基礎日数11日以上ある月」の中から、育児休業開始日に最も近い直近の12ヶ月分の賃金月額を選びます。
- もし、直近2年間で11日以上勤務した月が12ヶ月に満たない場合、原則として給付金の受給資格はありません。
- 選定した12ヶ月分の賃金月額(税金や社会保険料が控除される前の額面総支給額)をすべて合計します。
- 賃金に含まれるもの
- 基本給、通勤手当、住宅手当、役職手当など、原則として労働の対価として支払われるすべての賃金が対象です。
- 賃金に含まれないもの
- 賞与(ボーナス)、結婚祝い金などの慶弔金、福利厚生として現物支給されるものなどは原則として含みません。
- 賃金に含まれるもの
この12ヶ月分の賃金月額の合計額を12で割ることで、1ヶ月あたりの平均賃金が算出されます。そして、この1ヶ月あたりの平均賃金をさらに30で割ったものが、給付金計算の基礎となる「賃金日額」 の算定基礎となります。
証明書の様式入手と記入方法
1. 様式の入手
- ハローワークのウェブサイト
- 最も一般的な方法は、厚生労働省またはハローワークの公式ウェブサイトから様式をダウンロードすることです。
- 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(育児)」の様式は、以下の厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます。
- 厚生労働省 雇用保険関係書類記入例作成お役立ちツール (このページ内の「休業開始時賃金月額証明書(育児)[XLSX形式:44KB]」をご利用ください。)
- 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(育児)」の様式は、以下の厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます。
- 最も一般的な方法は、厚生労働省またはハローワークの公式ウェブサイトから様式をダウンロードすることです。
- 電子申請システム(e-Govなど)
- 電子申請を利用する場合は、システム上で直接入力・作成が可能です。
2. 記入する主な項目
- 被保険者情報
- 従業員の氏名、生年月日、雇用保険被保険者番号などを正確に記入します。
- 事業主情報
- 会社名、事業所番号、所在地、代表者氏名などを記入します。
- 休業開始日と休業終了予定日
- 従業員の育児休業開始日と、終了予定日を記入します。
- 賃金情報(重要)
- 賃金計算の対象となる期間を、休業開始日を挟んで適切に区切ります。
- 通常、給与計算期間(例:毎月1日~末日、または21日~翌20日など)に合わせます。
- 各賃金計算期間の賃金支払基礎日数と、その期間に支払われた賃金月額(額面総支給額)を記入します。
- 特に、「賃金支払基礎日数11日以上ある月」を直近12ヶ月分、間違いなく記入します。
- 賃金の対象期間と賃金計算期間の区切りに注意し、正確に記載することが求められます。
3. 内容の確認と添付書類
- 記入内容の徹底確認
- 記入漏れや誤りがないか、特に賃金月額や日数の記載に間違いがないか、複数人でクロスチェックを行いましょう。
- これらの誤りは、給付金の支給遅延や誤支給の原因となります。
- 押印または電子署名
- 紙の書類で提出する場合は、社印(代表者印)の押印が必要です。電子申請の場合は、電子署名を行います。
- 添付書類の準備
- 原則として、証明書に記載した賃金月額や賃金支払基礎日数が確認できる賃金台帳の写しや出勤簿の写しの添付が求められます。
- これらの書類も、対象期間のものが全て揃っているか確認しましょう。
総務担当者への実践的アドバイス
- 早期着手と連携
- 従業員から育児休業の申し出があったら、すぐに賃金データの収集に取り掛かりましょう。
- 従業員が安心して休業に入れるよう、余裕を持った準備が大切です。
- 過去の賃金台帳の保管
- 最長で過去2年間の賃金データが必要になるため、賃金台帳や給与明細などの記録は適切に保管しておく必要があります。
- 電子申請の活用推奨
- 従業員数が多い企業や、今後も育児休業給付金の申請が頻繁に予想される場合は、電子申請システムの導入を検討しましょう。
- 書類作成の手間が省け、ハローワークとのやり取りも効率化されます。
- 社会保険労務士との連携
- 複雑なケースや、書類作成に不安がある場合は、社会保険労務士に相談・依頼することも有効な選択肢です。
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」は、単なる事務手続きではなく、従業員の生活を支える重要なプロセスの一部です。
正確かつ丁寧な対応を心がけ、従業員が安心して育児に専念できる環境をサポートしていきましょう。
育児休業給付金支給申請書(出生時育児休業給付金支給申請書)
- 従業員の基本情報、育児休業期間、口座情報などを記載します。
- ハローワークインターネットサービス – 利用上の注意 – 育児休業給付金支給申請書👈こちらからダウンロードできます。
- 最寄りのハローワークの窓口でも直接、申請書を入手することができます。窓口で質問しながら記入したい場合や、印刷環境がない場合に便利です。
- e-Gov(イーガブ)を利用して電子申請を行う場合は、専用のシステム上で入力・作成するため、紙の様式をダウンロードする必要はありません。
- 2回目以降の申請書は、初回申請後にハローワークから郵送されてくる場合が多いため、企業側で改めてダウンロードする必要がないことが一般的です。
育児休業取扱通知書
- 従業員から育児休業の申し出を受け、会社として承認したことを証明する書類です。
- 会社(事業主)が従業員に対して発行する社内文書であり、ハローワークなど公的機関からダウンロードする 公式な申請書類ではありません。
- 育児休業の承認内容や期間などを従業員へ正式に通知し、会社と従業員間の認識を明確にするための大切な書類です。
賃金台帳・出勤簿
- 賃金台帳・出勤簿は休業開始前の賃金や出勤状況を証明するために提出を求められることがあります。
従業員から提出してもらう書類
- 母子健康手帳の写し
- 出生年月日や親子の氏名などが記載されているページ(通常は表紙と出生届出済証明のページ)が必要です。子の出生を証明するために用いられます。
- 住民票の写し
- 世帯全員が記載されており、申請者と子の氏名、続柄が確認できるものが必要です。
- これは、申請者と子が同居していることを確認するためです。
- 振込口座の通帳の写し
- 給付金の振込先口座を確認するために必要です。
- 育児休業申出書
- 従業員が会社に育児休業を申し出る際に提出する書類です。
- 会社と従業員の間で交わされる社内文書であり、公的機関が定める公式な様式ではありません。
- しかし、従業員が育児休業を正式に申し出るための重要な書類として、会社の人事・労務管理において不可欠な役割を担います。
総務担当者へのアドバイス
これらの書類は、企業の管理体制や従業員の状況によって準備の負担が異なります。
スムーズな手続きのためには、育児休業の申し出があった時点で、必要書類のリストを従業員に渡し、早めに準備を依頼することが肝心です。
特に、母子健康手帳や住民票の写しは従業員自身が用意するものですので、余裕を持った案内を心がけましょう。
出生後休業支援給付金の申請時期|原則は休業終了後2か月以内
給付金の申請は、育児休業期間が終了した後、原則として2ヶ月以内に行う必要があります。
- 申請のタイミング
- 「出生後休業支援給付金」は、出生時育児休業(産後パパ育休)が終了した後にまとめて申請します。
- もし、出産日以降に複数の期間に分けて育児休業を取得した場合でも、最後の育児休業期間が終了した後に、一括して申請することになります。
- 申請期限の重要性
- この2ヶ月という申請期限を過ぎてしまうと、原則として給付金を受け取ることができなくなります。
- 総務ご担当者様は、従業員が期限内に申請できるよう、育児休業終了のタイミングに合わせてリマインドや手続きのサポートを行うことが非常に重要です。
出生後休業支援給付金の申請フロー|企業と従業員の連携でスムーズ手続き
ここでは、育児休業給付金(出生後休業支援給付金を含む)の申請フローを、企業側の視点から具体的に見ていきましょう。
従業員の育児休業申し出手続き|出生後休業支援給付金の申請準備
- 従業員から育児休業(特に産後パパ育休)の申し出があります。
- 企業は、育児・介護休業法に基づき、休業期間や制度について説明し、育児休業申出書を提出してもらいます。
- この際、給付金の申請についても意向を確認し、必要書類の準備を案内します。
企業内での情報整理と書類準備|出生後休業支援給付金申請のポイント
- 従業員の休業期間中の賃金(休業開始時賃金日額算定のため)や出勤状況を確認します。
- 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」 などの会社作成書類を作成します。
- 従業員から提供された「母子健康手帳の写し」「住民票の写し」「通帳の写し」などを収集します。
ハローワークへの申請書提出|出生後休業支援給付金の手続き方法
- 育児休業期間が終了した後、「育児休業給付金支給申請書(出生時育児休業給付金支給申請書)」 に必要事項を記入し、上記で準備した書類を添付して、管轄のハローワークへ提出します。
- 提出方法は、窓口への持参、郵送、または電子申請(e-Govなどを利用)が可能です。企業規模や申請件数に応じて、効率的な方法を選択しましょう。
ハローワークによる審査|出生後休業支援給付金の受給可否確認
- 提出された書類に基づき、ハローワークが受給資格の有無や支給額の算定を行います。
- 審査の過程で、追加の資料提出を求められる場合もあります。
支給決定通知と給付金の受け取り|出生後休業支援給付金の支給手続き
- 審査が完了すると、ハローワークから事業主宛てに「育児休業給付金支給決定通知書」が送付されます。
- この通知書を確認後、給付金が従業員本人の指定口座に直接振り込まれます。
- 支給は申請から数週間から1ヶ月程度かかることがあります。
従業員への通知と情報共有|出生後休業支援給付金の手続き状況を伝える方法
- 支給決定通知書の内容を従業員に速やかに伝え、給付金が振り込まれたことを確認します。
総務担当者へのアドバイス|出生後休業支援給付金の申請をスムーズに進めるポイント
育児休業給付金の手続きは、書類が多く、専門的な知識も必要とされる場合があります。
従業員が安心して制度を利用できるよう、社内で手続きマニュアルを整備したり、人事労務の専門家(社会保険労務士など)と連携したりすることも有効です。
総務担当者が知っておくべき追加ポイント|出生後休業支援給付金の申請と管理
「出生後休業支援給付金」のスムーズな運用と、従業員への的確なサポートのために、総務ご担当者様がさらに押さえておくべき点を解説します。
社会保険料免除で差が出る「月末育休」の活用ポイント
「手取り実質10割」の大きな要素である社会保険料の免除には、一つ重要な条件があります。
それは、「育児休業期間が、その月の末日を含むこと」です。
- 例えば、 7月1日から7月31日まで育休を取れば、7月分の社会保険料は免除。
- 例えば、7月1日から7月10日まで育休を取り、7月11日に復帰した場合、7月分の社会保険料は原則として免除されません(月の途中で育休が終了するため)。
- 但し、特例としては、2022年10月より、育休期間が14日以上であれば、その月に育休が開始し、その月の途中で終了しても社会保険料が免除されるようになりました。
- しかし、この「出生後休業支援給付金」の対象となる産後パパ育休は最大28日間で、かつ分割取得が可能です。短期間の育休を月末を含まずに取得する場合、社会保険料免除の恩恵を受けられない可能性があるため、従業員への説明が必要です。
社会保険料免除の詳しい記事は👇

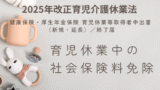
従業員が社会保険料免除のメリットを最大限に享受できるよう、育児休業の取得計画段階で、月末を含む期間設定や、14日以上の取得を検討するようアドバイスすることが望ましいでしょう。
出生後休業支援給付金と所得税・住民税、年末調整の関係まとめ
育児休業給付金(出生後休業支援給付金を含む)は非課税所得です。
このため、年末調整や確定申告において、給付金自体を収入として計上する必要はありません。
しかし、育児休業中は給与収入が減少するため、源泉徴収される所得税額や、翌年の住民税額が変動する可能性があります。
総務担当者としては、従業員からこれらの税金に関する質問があった際に、正確な情報を提供できるよう、基本的な知識を把握しておくことが推奨されます。
企業の育児支援制度と出生後休業支援給付金の連携方法
「出生後休業支援給付金」の導入は、貴社が従業員の育児支援に積極的に取り組んでいる姿勢を示す絶好の機会です。
この給付金制度を、既存の社内育児支援制度(例:育児休業中の賃金補填、ベビーシッター補助、育児コンシェルジュサービスなど)と組み合わせて案内することで、従業員のエンゲージメントをさらに高めることができます。
育児休業ガイドラインの改訂や、従業員への説明会の開催などを通じて、新しい給付金の情報を積極的に発信し、社員が安心して育児とキャリアを両立できる環境整備を進めましょう。
まとめ|出生後休業支援給付金の手続きと企業対応のポイント
「出生後休業支援給付金」は、特に男性の育児参加を強力に後押しし、共働き・共育て社会を実現するための重要な制度です。
企業の総務ご担当者様がこの給付金の支給期間、申請手続き、そして関連する注意点を正確に理解し、従業員の方々を適切にサポートすることは、貴社の人材定着や企業イメージ向上にも大きく貢献します。
複雑に感じる部分もあるかもしれませんが、一つ一つのステップを丁寧に踏み、従業員と密に連携することで、スムーズな手続きが可能です。このガイドが、貴社の育児支援体制強化の一助となれば幸いです。
次回予告|育児時短就業給付金の申請手続きと支給条件
なお、今回ご紹介した「出生後休業支援給付金」と並び、2025年の制度改正により新たに創設された注目の制度がもう一つあります。
それが「育児時短就業給付金」です。
こちらは、育児と仕事を両立しながら時短勤務を選択した方を経済的に支援する制度であり、特に育休からのスムーズな職場復帰を後押しする重要な仕組みです。
次回は、この「育児時短就業給付金」の支給対象や金額、申請手続きの流れ、企業が知っておくべき実務ポイントについて詳しく解説します。
次回の記事は👉2025年4月施行!「育児時短就業給付金」徹底解説【制度の概要と支給額シミュレーション】
ぜひ、引き続きご覧ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。


コメント