本記事は「2025年改正育児介護休業法シリーズ」の第47弾です。他のシリーズの記事はコチラから👉2025年育児介護休業法改正|企業がすべき対応と助成金情報
前回までの「両立支援等助成金制度」に関する記事においては、主に「育児」に関する助成金を解説してきました。
関連記事
- 両立支援等助成金 育児休業等支援コース➀|助成金の申請条件を解説
- 両立支援等助成金 育児休業等支援コース➁|助成金申請の実務と注意点を徹底解説
- 両立支援等助成金 出生時両立支援コース➀|中小企業がもらえる男性育休助成金とは?
- 両立支援等助成金 出生時両立支援コース➁助成金受給の要件と手続き徹底解説
- 両立支援等助成金 出生時両立支援コース➂第2種を解説|最大70万円の助成金制度とは?
- 両立支援等助成金「柔軟な働き方選択制度等支援コース」➀|中小企業向け助成金活用ガイド
- 両立支援等助成金「柔軟な働き方選択制度等支援コース」➁|申請フロー|テレワーク導入で20万円!
- 育休中等業務代替支援コースを徹底解説|新設助成金の支給額・申請フロー・活用メリット
- 育休中等業務代替支援コース|助成金の申請方法・必要書類・注意点を徹底解説
しかしながら、従業員の「仕事と家庭の両立」に関する課題は「育児」だけではありません。
超高齢社会を迎えた今、次に企業が直面する重要な課題は「介護」です。
家族の介護のために、仕事を辞めざるを得ない「介護離職」は、従業員本人だけでなく、企業にとっても貴重な人材を失う深刻な問題となっています。
しかし、この課題を解決するために国が企業を支援する助成金があります。それが、今回ご紹介する「介護離職防止支援コース」です。
この助成金を活用することで、企業は従業員が安心して働き続けられる環境を整え、人材流出を防ぐことができるのです。
この記事で分かること
- 介護離職は「個人の問題」ではなく、貴重な人材を失う「企業の経営リスク」
- 「制度整備・利用」「業務代替」「職場復帰」の3つのフェーズで助成金が用意されている
- 介護休業20日以上の取得で28.5万円(取得時)+28.5万円(復帰時)の受給が可能
- 「介護支援プラン」の策定と、就業規則への明確な規定が申請の絶対条件
- 生産性要件を満たせば、最大72万円(2回合計)まで受給額がアップする
介護離職防止支援コースとは?企業が従業員の介護と仕事の両立を支援する方法
介護離職防止支援コースは、従業員が仕事と介護を両立できるよう企業が環境を整備し、その結果、介護を理由とした離職を防ぐことを目的とした助成金です。
この助成金は、介護休業制度などを整え、従業員がスムーズに制度を利用できるような支援を行う事業主を対象としています。
特に、中小企業の取り組みを強力に後押しする制度です。
大企業も要件を満たせば助成金を受け取ることができます。
ただし、中小企業と大企業では支給される金額が異なります。
一般的に、大企業への支給額は中小企業よりも少なく設定されています。
両立等における「中小企業」の区分基準
| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時雇用する労働者数 |
|---|---|---|
| 小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| その他(製造業、建設業、運輸業など上記以外全て) | 3億円以下 | 300人以下 |
補足事項
- 「常時雇用する労働者数」とは、2か月を超えて雇用される者であり、かつ、週当たりの所定労働時間が、その事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等(概ね40時間)である者を指します。パートタイマーやアルバイトであっても、上記の要件を満たせば「常時雇用する労働者」に含められます。
- 資本金がない場合(一般社団法人、NPO法人)は、常時雇用する労働者数のみで判断されます。
- ご自身の会社が上記の「中小企業」の定義に当てはまらない場合、自動的に「大企業」として扱われ、助成金額も大企業向けに設定されたものが適用されます。
- いわゆる「みなし大企業」(中小企業の条件を満たしていても、実質的に大企業の子会社や関連会社である場合)の扱いについては、助成金の種類や詳細な状況によって判断が異なる場合がありますので、具体的な申請時には管轄の労働局や専門家にご確認いただくのが確実です。
介護離職防止支援コース|制度別3種類の助成金と受給のポイント
この助成金には、企業の取り組みに応じて主に3つのコースが用意されています。
介護休業制度の整備を支援|制度整備・利用コースの助成金
- このコースは、介護休業制度を新しく整備したり、休業を取得する従業員の代替要員を確保したりするためにかかる費用を助成します。
- 従業員が安心して介護休業を取得できる環境づくりを支援することが目的です。
介護休業中の業務代替費用を助成|業務代替支援コースのポイント
- 従業員が介護休業を取得した際、その期間中の業務を代替する要員を新しく雇い入れたり、既存の従業員に業務を引き継いだりする費用を助成します。
- これにより、従業員が介護に専念している間も、企業は業務を円滑に継続できます。
介護休業後の円滑な復帰をサポート|職場復帰支援コースのポイント
- 介護休業から戻ってきた従業員がスムーズに職場に復帰できるよう、復帰後の面談や配置転換、時短勤務などの支援にかかる費用を助成します。
- これにより、介護と仕事の両立を継続的に支援し、従業員の長期的な定着を促します。
これらの助成金を活用することで、企業は従業員の介護離職を防ぎ、貴重な人材を守りながら、持続的な事業運営を目指すことができます。
介護離職防止支援コースの具体的な助成金額と支給条件
介護離職防止支援コースの助成金は、企業の取り組みに応じて支給されます。
ここでは、各コースの具体的な支給条件と、目安となる助成金額を見ていきましょう。
1. 制度整備・利用コース
このコースは、介護支援プランを策定し、従業員が介護休業を取得した場合に助成金が支給されます。
支給額は、介護休業の取得時と職場復帰時の2回に分けて受け取ることができます。
- 介護休業取得時
- 従業員が連続して20日以上(有期雇用労働者は10日以上)の介護休業を取得した場合に28.5万円(生産性要件を満たす場合は36万円)が支給されます。
- 職場復帰時
- 業員が職場に復帰し、6か月以上継続して雇用された場合に28.5万円(生産性要件を満たす場合は36万円)が支給されます。
「生産性要件を満たす場合〇〇円」と触れましたが、この生産性要件とは、企業全体の生産性が向上している場合に、助成金の支給額が割り増しされる仕組みです。
具体的には、助成金の申請を行う会計年度の直近3年間で、「労働者の付加価値」が6%以上伸びていることが主な要件となります。
「労働者の付加価値」の具体的な計算方法
「労働者の付加価値」は、以下のいずれかの方法で計算されます。
- 最も一般的な計算式(簡便法)
- 付加価値 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費 + 動産・不動産賃借料 + 租税公課
- もう一つの計算式
- 付加価値 = 売上高 - (売上原価 + 販売費・一般管理費 - 人件費 - 減価償却費 - 動産・不動産賃借料 - 租税公課)
これらの費用項目は、原則として会社の決算書(損益計算書など)の数値を使用します。
一般的な会計の「限界利益」や「粗利益」とは異なる、助成金制度独自の概念である点にご注意ください。
いつの期間の生産性を比較するの?
生産性の向上を判断するためには、過去と現在の「労働者の付加価値」を比較します。
- 比較対象期間
- 助成金の支給申請を行う会計年度の直近3年間を使用します。
- たとえば、会社の会計年度が4月1日~3月31日で、令和7年7月に助成金を申請する場合、比較対象となるのは令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)と令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)の付加価値です。
- 比較基準
- 基準期間
- 直近3年間の中で最も古い会計年度(最初の1年間)の「労働者の付加価値」
- 先ほどの例では令和4年度
- 比較期間
- 直近3年間の中で最も新しい会計年度(最後の1年間)の「労働者の付加価値」
- 先ほどの例では令和6年度
- 基準期間
- OKとなる基準
- [比較期間(令和6年度)の付加価値 - 基準期間(令和4年度)の付加価値] ÷ 基準期間(令和4年度)の付加価値 この計算結果が 6%以上 であれば、生産性要件を満たしたと判断されます。
なぜ生産性が上がると助成金が増額されるのか?
この点に疑問を持つ読者も多いでしょう。
「育児休業を取得したから生産性が上がった」と断言できるほど、単純な話ではありません。
育休期間中にたまたま別の要因で業績が伸び、生産性が上がったというケースもいくらでも考えられます。
しかし、助成金制度には、以下のような考え方があります。
企業の成長を後押しするため
- 助成金は単に制度を導入したから支給されるだけでなく、企業が実際に生産性を向上させるような経営努力をしている場合に、より多くの支援をすることで、企業の持続的な成長を促す目的があります。
財源(雇用保険)の有効活用
- 国民から集められた雇用保険料を財源とする以上、その活用は効果的であるべきです。
- 生産性が向上している企業に厚く助成金を出すことで、その投資がより大きな経済効果や社会的なリターン(例:雇用安定、人材育成)に繋がると考えられています。
「働きやすさ」と「生産性」の好循環を期待
- 「従業員を大切にし、働きやすい環境を整える経営努力をしている企業は、他の面でも生産性を上げるための工夫をしている可能性が高い」という、間接的な相関関係に着目しています。
- つまり、両立支援の取り組み自体が、従業員のモチベーション向上や優秀な人材の定着、業務の効率化など、長期的に企業の潜在的な生産性向上に寄与する「投資」と捉えられているのです。
簡単に言えば、生産性要件は、「助成金を出すに値する、成長意欲のある健全な企業であるか」を測るための、一つの指標として使われています。
これにより、助成金がより効果的に、そして適切に活用されることを目指しているのです。
この生産性要件を満たしているかどうかの確認や、詳細な計算方法、必要書類については、厚生労働省のパンフレットや、社会保険労務士などの専門家にご確認いただくことを強くお勧めします。
2. 業務代替支援コース
介護休業中の従業員の業務を代替する要員を確保した場合に助成金が支給されます。
- 代替要員を新規雇用した場合
- 業務を代替する従業員を新たに雇い入れた場合に、介護休業期間に応じて1日1,000円(中小企業の場合は1日2,000円)が支給されます。
- 既存の従業員に代替させた場合
- 介護休業中の業務を既存の従業員に担当させた場合に、代替要員を雇用した場合と同じく、介護休業期間に応じて助成金が支給されます。
3. 職場復帰支援コース
従業員が介護休業から円滑に職場復帰できるよう、面談や情報提供などの支援を実施した場合に助成金が支給されます。
- 職場復帰支援
- 従業員の円滑な復帰を目的とした制度を整備・実施した場合に1人当たり28.5万円(生産性要件を満たす場合は36万円)が支給されます。
介護離職防止支援コース|助成金申請の重要ポイントと注意点
「介護離職防止支援コース」の概要と支給額を理解したら、いよいよ申請に向けた準備に入りましょう。
助成金を確実に受け取るためには、手続きの流れを把握し、必要な書類を正確に揃えることが何よりも重要です。
介護離職防止支援コースの助成金申請フロー
申請は、大きく分けて3つのステップで進みます。
この流れを事前に把握しておけば、スムーズに手続きを進めることができます。
- 計画届の提出
- 介護支援プランを策定したら、制度を導入する前に「介護離職防止支援コース 計画書」を労働局に提出します。
- 制度の実施
- 計画に基づき、従業員の介護休業取得や、それに伴う業務代替、職場復帰支援などを実際に実施します。
- 支給申請
- 制度の実施後、必要な書類を揃えて労働局に支給申請を行います。
介護離職防止支援コース|申請時に用意すべき主な必要書類
申請時には、計画届提出時と支給申請時で異なる書類が必要です。以下に主な書類をリストアップしました。
- 介護支援プラン
- 従業員の介護休業取得や職場復帰を支援するための具体的な計画書。
- 就業規則
- 介護休業や介護休暇に関する規定が記載されている就業規則。
- 賃金台帳・出勤簿
- 従業員の賃金や勤務時間を証明する書類。
- 雇用契約書
- 業務代替のために新規雇用した従業員の雇用契約書など。
- 面談記録
- 従業員との面談内容を記録した書類。
これらの書類を漏れなく揃え、いつでも提示できるようにしておくことが大切です。
申請時に特に注意すべき3つのポイント
- 就業規則の明確な規定
- 助成金の支給要件として、就業規則に介護休業や介護休暇に関する規定が明確に盛り込まれていることが必須です。
- 規定が不十分な場合、申請が認められない可能性があるため、事前に必ず確認・整備しておきましょう。
- 証明できる「事実」の確保
- 助成金は、単に制度があるだけでなく、「労働者が実際に介護休業を取得し、企業が支援を実施した」という事実に基づいて支給されます。
- 面談記録や業務代替の記録など、申請内容を客観的に証明できる資料をきちんと保管しておく必要があります。
- 書類の正確な保管と提出
- 必要書類の記入漏れや添付書類の不足があると、審査が遅れたり、最悪の場合、不支給になったりすることがあります。
- すべての書類が揃っているか、記載内容に誤りがないかを提出前に何度もチェックしましょう。
介護離職防止支援コースは、従業員と企業双方にとってメリットのある制度です。これらのポイントを押さえて、スムーズに申請手続きを進めてください。
まとめ|介護離職防止支援コースを賢く活用して企業と従業員の未来を守る
ここまで、「介護離職防止支援コース」の概要から具体的な支給額、そして申請時の注意点までを詳しく解説しました。
この助成金は、単なる資金援助ではなく、従業員が介護と仕事を両立できる環境を整え、貴重な人材の離職を防ぐための強力な支援策です。
超高齢社会において、介護はどの企業にとっても他人事ではありません。
この助成金を活用することは、従業員が安心して働き続けられる環境を整える「社会的責任」を果たすことにつながります。
結果として、従業員のモチベーション向上や企業への信頼感が高まり、企業の生産性維持、ひいては持続的な成長に貢献する、有効な経営戦略と言えるでしょう。
この機会に、ぜひ貴社の両立支援制度を見直し、助成金の活用を検討してみてください。
次回予告|介護離職防止支援コースの実践編を徹底解説
次回は、この「介護離職防止支援コース」を「机上の空論」で終わらせないための「実践編」です。
実際に助成金を活用した企業の成功事例を交えながら、申請の各段階で具体的に何をすべきかを徹底解説します。
- 計画段階
- どのような書類を、いつまでに、どうやって作成するのか?
- 実施段階
- 介護休業中の業務を円滑に回すための具体的な方法とは?
- 申請段階
- 複雑な書類を漏れなく揃え、確実に申請を成功させるためのフローは?
次回記事を読めば、あなたの会社もスムーズに助成金を受け取り、介護離職を防ぐための具体的な一歩を踏み出せるはずです。
次回の記事は👉介護離職防止支援コース|申請方法・フローと助成金活用の事例
どうぞご期待ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。
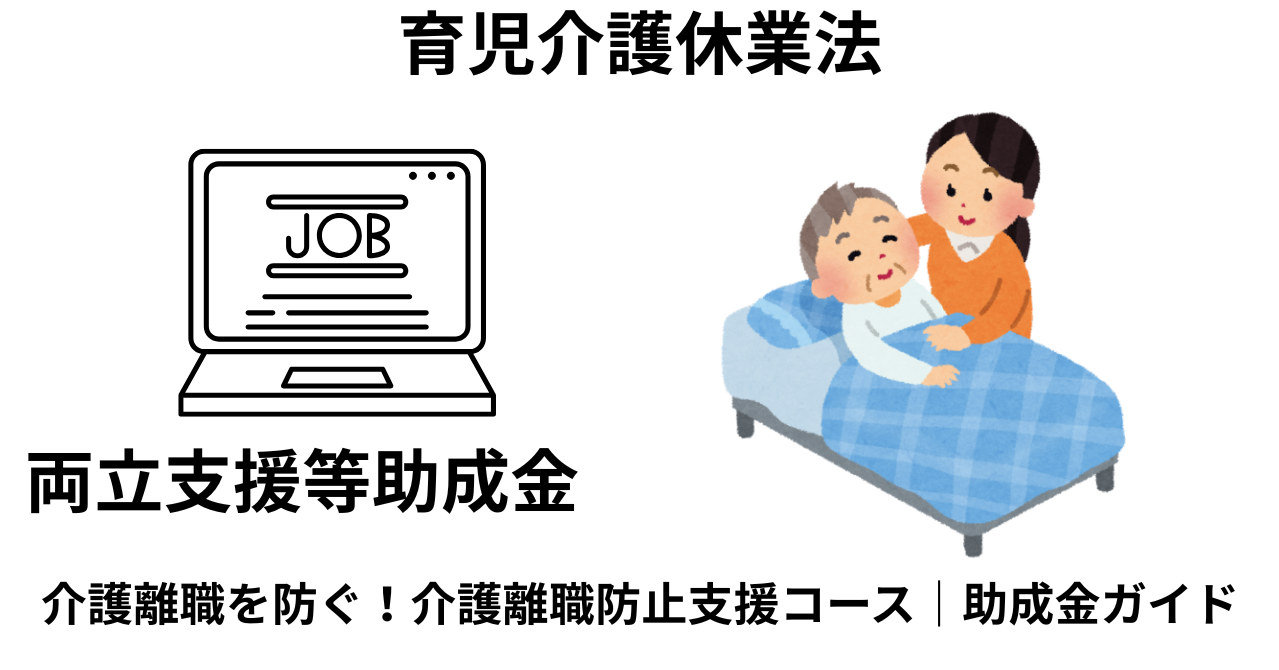


コメント