本記事は「【社労士が解説】企業のための熱中症対策 実践講座」シリーズの第4話です。第1話は👉熱中症は「他人事」ではない!企業に求められる安全配慮義務の基礎
シリーズ全体の記事はコチラからご覧ください👇
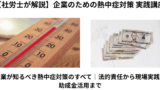
前回の記事では、熱中症対策の基礎となるWBGT値の適切な運用と、作業時間・休憩時間の効果的な管理について解説しました。
前回の記事は👉職場の熱中症対策 WBGT測定から休憩ルールまで実務チェックリスト
これらの物理的・時間的な対策は重要ですが、労働者の安全を確保するためには、個々の状況に応じたきめ細やかな配慮と、対策が確実に実行されていることを示す適切な記録管理が不可欠です。
本記事では、熱中症リスクの高い労働者への個別対応に焦点を当てて解説します。
現場の熱中症対策をより盤石なものにするための実践的なステップを見ていきましょう。
高齢者・体調不良者の熱中症リスクと個別配慮
熱中症対策は、全ての労働者に対して一律に行うだけでなく、個々の健康状態や特性に応じた個別配慮が不可欠です。
特に高齢者や持病を持つ方、体調が優れない方は、熱中症のリスクが格段に高まります。
これらの見過ごされがちなリスクに対し、企業がどのように向き合うべきかを解説します。
熱中症リスクの高い労働者の把握方法と情報共有
まず、企業は熱中症リスクの高い労働者を正確に把握し、その情報を適切に共有する体制を整える必要があります。
- リスク要因の理解
- 高齢者、肥満者、糖尿病や高血圧などの持病を持つ方、睡眠不足や疲労が蓄積している方、前日に深酒をした方などは、熱中症になりやすい傾向があります。
- これらのリスク要因を管理者だけでなく、現場のリーダーや同僚も理解しておくことが重要です。
- 情報共有の仕組み
- 個人情報保護に配慮しつつ、熱中症リスクの高い労働者の情報を、業務上必要な範囲で管理者や関係者間で共有する仕組みを作りましょう。
- 健康診断の結果や、産業医からの情報提供なども活用できます。
熱中症リスク者への作業内容・作業時間の調整方法
リスクの高い労働者に対しては、WBGT値の基準だけでなく、その日の体調や健康状態に応じて、柔軟な作業内容や作業時間の調整を行うことが求められます。
- 作業の軽減
- 炎天下での重労働や、長時間の連続作業は避けるよう配慮しましょう。
- 軽作業への変更、屋内でできる作業への振り分け、作業量の調整などを検討します。
- 休憩の強化
- 一般的な休憩ルールに加え、より頻繁な休憩や、長めの休憩時間を確保するなど、個別の休憩計画を立てることも有効です。
- 作業時間の変更
- 可能であれば、暑さのピーク時(午後)の作業を避け、比較的涼しい早朝や夕方などに作業時間を変更することも考慮に入れましょう。
熱中症リスク者への定期的な健康チェックと声かけ方法
リスクの高い労働者は、自身の体調変化に気づきにくい場合や、無理をしてしまう傾向があるため、周囲からのきめ細やかな配慮が重要です。
- 作業前の体調確認
- 作業開始前に、体温、血圧、疲労度などを確認する「健康チェック」を習慣化しましょう。
- 体調不良が見られる場合は、無理をさせずに休養を促す勇気ある判断が求められます。
- 巡回と声かけ
- 管理者は、定期的に現場を巡回し、リスクの高い労働者の様子を注意深く観察しましょう。
- 積極的に声かけを行い、「体調はどうか」「無理していないか」といったコミュニケーションを通じて、異変を早期に察知することが大切です。
- セルフケアの指導
- 水分補給の重要性や、初期症状に気づいた際の対処法など、労働者自身が行えるセルフケアについて、繰り返し指導することも効果的です。
熱中症リスク者の持病・服薬状況の確認と個別配慮
特定の持病や服用している薬によっては、熱中症リスクを高めるものがあります。
これらの情報を事前に把握し、個別に配慮することが非常に重要です。
- 情報収集の徹底
- 入社時や健康診断時などに、持病や常用薬の有無について確認する機会を設けましょう。
- 個人情報の取り扱いには十分注意し、産業医や保健師を通じて適切なアドバイスを得ることが望ましいです。
- 産業医・専門家との連携
- 持病や服薬状況に応じた具体的な作業制限や配慮事項については、産業医や外部の専門家と連携し、医学的な知見に基づいた判断を行いましょう。
- 緊急時の情報共有
- 万が一、熱中症を発症した場合に備え、持病やアレルギー、緊急連絡先などの情報を、関係者間で速やかに共有できる体制を整えておくことも命を守る上で不可欠です。
熱中症リスクの高い労働者に対して、適切な個別配慮がなされているかを確認しましょう。
高齢者や体調不良者への個別配慮チェックリスト
- 熱中症リスクの高い労働者の把握と情報共有
- 高齢者、持病を持つ方、肥満者など、熱中症リスクが高い労働者のリストを把握していますか? (はい / いいえ)
- 個人情報保護に配慮しつつ、熱中症リスクに関する情報を業務上必要な範囲で関係者(管理者、リーダーなど)と共有する仕組みがありますか? (はい / いいえ)
- 健康状態に応じた作業内容・作業時間の調整
- 熱中症リスクの高い労働者に対し、その日の健康状態やWBGT値に応じて、作業内容(例:軽作業への変更)や作業時間の調整を行っていますか? (はい / いいえ)
- より頻繁な休憩や長めの休憩時間など、個別に応じた休憩計画を検討・実施していますか? (はい / いいえ)
- 可能な場合、暑さのピーク時を避けた作業時間帯への変更を考慮していますか? (はい / いいえ)
- 定期的な健康チェックと声かけの実施
- 作業開始前に、リスクの高い労働者の体温や疲労度などの健康チェックを行っていますか? (はい / いいえ)
- 管理者は定期的に巡回し、リスクの高い労働者の体調変化に注意を払い、積極的に声かけを行っていますか? (はい / いいえ)
- 労働者自身が体調の異変を早期に申告できるよう、セルフケアに関する指導を行っていますか? (はい / いいえ)
- 持病や服薬状況の確認と、それに応じた配慮
- 入社時や健康診断時などに、持病や常用薬の有無について確認する機会を設けていますか? (はい / いいえ)
- 持病や服薬状況に応じた具体的な作業制限や配慮事項について、産業医や専門家と連携して判断を行っていますか? (はい / いいえ)
- 緊急時に備え、持病やアレルギーなどの情報を、速やかに共有できる体制を整えていますか? (はい / いいえ)
まとめ|個別配慮で熱中症リスクを最小限にする方法
今回の記事では、熱中症対策において見過ごされがちな個別配慮の重要性と、その具体的な実践方法をチェックリスト形式で詳しく解説しました。
高齢者や持病を持つ方、体調不良者など、熱中症リスクの高い労働者へのきめ細やかな対応は、単に「義務だから」というだけでなく、従業員一人ひとりの命と健康を守る上で不可欠です。
日々の健康チェックや作業内容の調整、そして管理者からの積極的な声かけを通じて、それぞれの状況に応じた対策を講じることが、職場の熱中症リスクを最小限に抑える鍵となります。
これらのチェックリストをぜひ活用し、従業員全員が安心して働ける職場環境の実現を目指しましょう。
次回予告|熱中症予防教育と記録管理で安全配慮義務を履行
次回は、対策の「抜け漏れ」を防ぎ、万が一の際に企業を守るための重要なステップに焦点を当てます。
具体的なテーマは、熱中症予防教育の進め方と、対策が適切に実施されていることを示す記録管理の徹底です。
従業員全員の意識を高め、企業が安全配慮義務を確実に履行していることを明確にするための、実践的なヒントとチェックリストをお届けします。どうぞご期待ください!
次回の記事は👉職場の熱中症対策 予防教育と記録管理で法的証拠を残す
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。
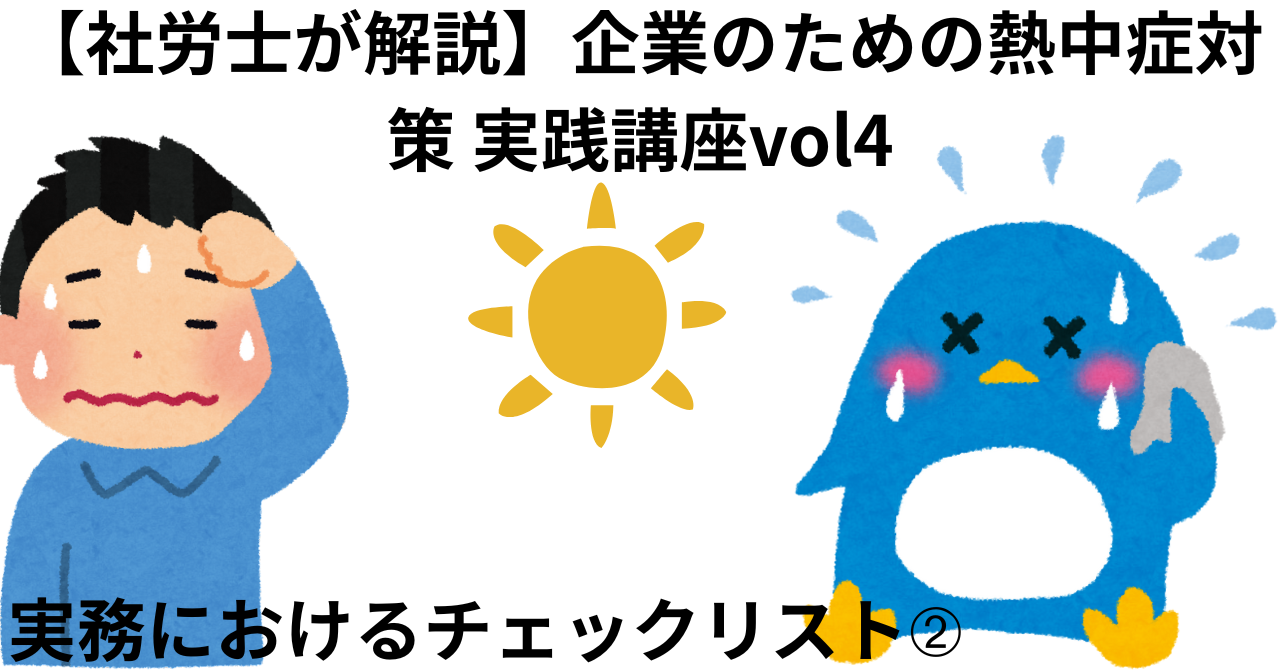
コメント