本記事は「2025年改正育児介護休業法シリーズ」の第46弾です。他のシリーズの記事はコチラから👉2025年育児介護休業法改正|企業がすべき対応と助成金情報
前回、「育休中等業務代替支援コース」の概要と、具体的な助成金額について解説しました。
前回の記事は👉育休中等業務代替支援コースとは?助成金額・活用メリットを解説
この助成金が、育児休業取得者の増加という社会の変化に対応し、企業が業務を円滑に維持するための強力な支援策であることをご理解いただけたかと思います。
この制度は、中小企業だけでなく、大企業も対象となる点が大きな特徴です。
規模を問わず、すべての企業が従業員の育児と仕事の両立を支援できるよう、国が後押しする仕組みと言えます。
今回は、その「知っている」を「活用できる」に変えるための実践編です。
この記事で分かること
- 助成金受給の成否は、育休開始「前日」までの計画届提出で決まる
- 代替要員の「雇用保険加入」が必須条件。加入漏れは即不支給のリスク
- 賃金台帳や出勤簿だけでなく、業務分担表などの「客観的証明」が重要
- 中小企業(100人以下)でも「一般事業主行動計画」の策定・届出が絶対条件
- 申請先は「雇用環境・均等部(室)」。郵送や持込時の事前確認がスムーズな審査のコツ
育休中等業務代替支援コースの助成金|知識だけでなく申請・活用まで押さえる
「育休中等業務代替支援コース」は、育休中の業務を円滑にカバーする中小企業にとって、非常に心強い制度です。
しかし、この制度がどれほど魅力的でも、「知っている」だけで終わってしまっては意味がありません。
助成金を受給するためには、複雑な申請手続きを正確に行う必要があります。
たった一つの書類の不備や、提出期限の遅れが原因で、せっかくの助成金が受け取れなくなるケースは少なくありません。
専門知識が必要な場面も多いため、申請の準備には時間と労力がかかります。
しかし、この準備を怠ると、申請がスムーズに進まず、本業の負担が増えてしまうという本末転倒な事態になりかねません。
育休中等業務代替支援コースの助成金申請で押さえるべき3つの重要ポイント
この記事では、そんな課題を解決するために、助成金申請の重要なポイントを3つに絞って解説します。
- 必要な書類は何か?
- 書類の提出先はどこか?
- 申請時に特に注意すべき点は何か?
これらの情報を事前に把握し、計画的に準備を進めることが、助成金を確実に受け取るための成功の鍵となります。
育休中等業務代替支援コース助成金|3ステップでわかる申請手順と全体フロー
育児休業等業務代替支援コースの助成金を受け取るには、複雑に感じるかもしれません。
流れは大きく3つのステップに分かれています。
この流れを事前に把握しておけば、スムーズに申請を進めることができます。
前回の記事のフローもご覧ください。👉育休中等業務代替支援コースとは?助成金額・申請の流れを解説
ステップ1|育休中等業務代替支援コースの計画作成と提出方法をわかりやすく解説
これは、助成金を申請するための最初の、そして最も重要なステップです。
育児休業に入る従業員がいることが決まったら、速やかに手続きを開始しましょう。
まず、「育児休業等業務代替支援計画書」を作成します。
この書類には、育休を取得する社員の名前や休業期間、そしてその業務を誰がどのように代替するのかといった詳細を記入します。
この計画書は、育児休業開始日の前日までに、会社の所在地を管轄する労働局に提出する必要があります。
ステップ2|育休中等業務代替支援コースでの業務代替と育休実施のポイント
計画書を提出したら、いよいよ計画を実行に移します。
このステップでは、計画通りに代替要員を雇用し、育児休業者が実際に休業を取得することが重要です。
代替要員の雇用日や業務内容、支払われる賃金などが、最初に提出した計画書の内容と一致しているか、常に確認しましょう。
事前に代替要員を雇用し、引き継ぎを行うことは現実的で推奨されます。
しかし、助成金の対象となるのは、育児休業開始日以降の業務代替期間のみである点に注意してください。
ステップ3|育休中等業務代替支援コースの支給申請書提出方法と注意点
最後のステップは、助成金の支給を正式に申請することです。
育児休業期間の終了後、または代替要員の雇用期間が終了した後に、「育児休業等業務代替支援コース支給申請書」を提出します。
この書類は、計画がきちんと実行されたことを証明するものです。
提出期限は育児休業終了日の翌日から2ヶ月以内と定められています。
書類の不備がないよう、事前にしっかりと確認した上で提出しましょう。
この3つのステップを一つずつ丁寧にクリアしていくことで、助成金を確実に受け取ることができます。
育休中等業務代替支援コース|申請時に必要な書類一覧と準備のポイント
「育休中等業務代替支援コース」の助成金申請は、「計画届出時」と「支給申請時」の2段階で、それぞれ異なる書類を提出します。
必要な書類を事前に把握し、漏れなく準備することが、スムーズな申請の鍵です。
計画届出時に必要な書類と提出手順|育休開始前の助成金申請準備
この段階では、助成金を活用して業務代替体制を整備する計画を、労働局に届け出ます。
1. 両立支援等助成金支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
- 事業主が助成金の支給要件を満たしていることを申し立てる書類です。
2. 育児休業等業務代替支援計画書(【育】様式第3号)
- 助成金申請の基礎となる書類です。
- 育児休業者の情報や代替要員の予定などを記入します。
3. 育児休業の申出書(写し)
- 育児休業を取得する社員から提出された正式な申出書のコピー。
- 育休の事実を証明します。
4. 母子手帳の写し
- 出産日または出産予定日がわかるページのコピー。
- 育児休業の前提となる出産事実を確認するために必要です。
5. 一般事業主行動計画の策定届出の写し
- 両立支援等助成金の支給を受けるための必須要件です。
- 一般事業主行動計画の策定・変更届の様式や、詳しい情報は、厚生労働省:一般事業主行動計画の策定・届出等についてのウェブサイトで確認できます。
支給申請時に必要な書類と注意点|育休終了後の助成金申請ガイド
育児休業が終了し、計画通りに業務代替が実施されたことを証明するための書類です。
1. 両立支援等助成金支給申請書(共通要領様式第1号)
- 助成金全体に共通の基本申請書です。
2. 育児休業等業務代替支援支給申請書(【育】様式第4号)
- 実際に業務代替が行われた期間や代替要員に支払った賃金などを詳細に記載する書類です。
3. 賃金台帳、出勤簿
- 代替要員に支払った賃金の金額や勤務時間、育休者の休業期間を証明するために不可欠です。
4. 就業規則、労使協定など
- 育児・介護休業に関する規定や、業務代替手当に関する規定が適切に整備されているかを確認するために提出します。
5. 育児休業取得者の育児休業申出書、母子手帳の写し
- 計画届出時と同じ書類ですが、支給申請時にも再度提出を求められます。
6. 代替要員の雇用契約書、労働条件通知書
- 実際に代替要員が雇用されたことを証明します。
7. 労働保険・社会保険の加入状況を確認できる書類
- 労働保険料納付書など、事業主が適切な労働環境を整備しているかを確認します。
8. 会社(事業主)の概要がわかる書類
- 商業登記簿謄本など、法人の存在を確認するために必要です。
9. 業務分担表など
- 育休取得者の業務が適切に代替されたことを客観的に証明する資料です。
10. 面談シート(様式第2号)
- 育児休業を申し出た従業員との面談内容を記録するものです。
11. 育休復帰支援プラン(様式第3号)およびその周知記録
- 従業員の円滑な育休取得と職場復帰を支援する具体的な計画であり、両立支援への取り組みを示す重要な書類です。
12. 両立支援のひろばに公表したことがわかる書類
- 情報公表加算を申請する場合に提出します。
- 公表ページのスクリーンショットなどが一般的です。
公表方法・公表場所等の詳細は

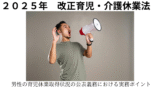
これらの書類を漏れなく揃え、正確に記入することが、助成金を確実に受け取るための重要なステップとなります。
育休中等業務代替支援コースの申請書提出先|都道府県労働局の管轄部署を詳しく解説
助成金申請の準備が整ったら、あとは提出するだけです。
しかし、提出先を間違えたり、思わぬ落とし穴にはまったりしないよう、最後の確認が重要です。
育休中等業務代替支援コースの申請書類は、会社の所在地を管轄する都道府県労働局に提出します。
都道府県労働局には、「雇用環境・均等部(室)」という部署があり、助成金に関する相談や書類の受付を行っています。
直接持ち込むか、郵送で提出するのが一般的です。
育休中等業務代替支援コース申請時の注意点|押さえるべき5つのポイント
書類がすべて揃ったと思っても、提出前に以下の点をもう一度チェックしましょう。
1. 雇用保険への加入は必須
- 助成金の申請は、雇用保険の適用事業所であることが前提です。
- 育休を取得する社員だけでなく、代替要員を雇用した場合も、雇用保険に加入させていることが支給の条件となります。
2. 書類の不備に要注意
- 書類に不備があると、審査が大幅に遅れたり、最悪の場合、助成金が不支給になったりすることがあります。
- 提出前には、記載漏れや計算ミスがないか、すべての添付書類が揃っているか、チェックリストを使って必ず確認しましょう。
3. 記録は正確に、そしてしっかりと保管
- 賃金台帳や出勤簿、雇用契約書などの記録は、助成金の審査で非常に重要となります。
- これらの書類は、申請内容の正当性を証明する根拠となるため、正確に記録し、決められた期間、大切に保管しておく必要があります。
4. 必要に応じて専門家を頼る
- 申請手続きは複雑で、慣れていないと難しいと感じるかもしれません。
- もし不安な点があれば、社会保険労務士などの専門家に相談することを検討しましょう。
- 専門家のサポートを受けることで、手続きをスムーズに進め、確実に助成金を受け取ることができます。
5. 一般事業主行動計画の策定・届出も必須
- 両立支援等助成金の支給を受けるためには、「一般事業主行動計画」を策定し、管轄の都道府県労働局に届け出ていることが必須となります。
- これは、「次世代育成支援対策推進法」に基づき、従業員101人以上の企業には義務付けられているものです。
- 従業員100人以下の企業の場合も、助成金受給のためには努力義務を超えてこの要件を満たす必要があります。
- この計画は、企業が従業員の仕事と子育ての両立を支援するための目標や具体的な取り組みを定めたものであり、助成金が単なる資金援助ではなく、実効性のある両立支援への取り組みを評価するものであることを示しています。
- 一般事業主行動計画の策定・変更届の様式や、詳しい情報は、厚生労働省:一般事業主行動計画の策定・届出等についてのウェブサイトで確認できます。
これらの注意点を押さえて、助成金申請を成功させましょう。
まとめ|育休中等業務代替支援コースの助成金を活用して働きやすい会社を作る
「育児休業等業務代替支援コース」は、育児休業中の業務を円滑にカバーするためのコストを国が支援してくれる、非常に有効な制度です。
今回解説したように、この制度をうまく活用すれば、育児休業を「企業の課題」ではなく「企業の成長機会」と捉えることができます。
従業員が安心して長く働ける環境を整えることは、企業の魅力向上にもつながる、重要な経営戦略の一つと言えるでしょう。
次回予告|仕事と介護の両立を支援!「介護離職防止支援コース」を徹底解説
今回は、「育休中等業務代替支援コース」の概要から申請方法までを詳しく解説しました。
しかし、従業員の「仕事と家庭の両立」に関する課題は、育児だけではありません。
次に重要なのが「介護」です。
次回は、従業員が介護を理由に離職するのを防ぐために企業が活用できる助成金、「介護離職防止支援コース」に焦点を当てます。
制度の概要、支給額、申請のポイントまで、詳しく解説します。
次回の記事は👉介護離職防止支援コース助成金の制度概要と基礎知識
この助成金は、超高齢社会を迎える日本において、企業が直面する重要な課題を解決する鍵となります。
ぜひ次回の記事も参考にしてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。


コメント