本記事は「2025年改正育児介護休業法シリーズ」の第40弾です。他のシリーズの記事はコチラから👉2025年育児介護休業法改正|企業がすべき対応と助成金情報
これまで2回にわたり、両立支援等助成金の中でも「育児休業等支援コース」について詳しく解説してきました。
今回は、同じく両立支援等助成金の制度の一つで、特に中小企業の方々からご相談の多い「出生時両立支援コース」に焦点を当てて、その核心に迫ります。
この記事では、この助成金の背後にある政府の狙いから、具体的な助成金額、そして受給するための条件まで、一つ一つ丁寧に解説していきます。
制度を理解し活用することで、企業の持続的な成長につなげていきましょう。
この記事で分かること
- 「出生時両立支援コース」は、男性の育児参画を促し、女性のキャリア継続を支える戦略的助成金
- 第1種(取得時)は、中小企業の「1人目の男性育休」で最大30万円(基本20万+環境整備加算10万)
- 受給には、子の出生後8週間以内に「連続5日以上」の育休取得が必要
- 「育児休業取得率向上助成金」により、取得率が大幅アップすれば最大60万円の上乗せも
- 申請の絶対条件は、休業開始前の「一般事業主行動計画」の策定・届出・公表
出生時両立支援コースの目的|政府が男性育休取得を後押しする理由
「出生時両立支援コース」は、単なる資金援助ではありません。この助成金の背後には、社会全体を変えていこうとする政府の明確な狙いがあります。
男性育休取得を後押しする政府の施策と社会的背景
この助成金の最大の目的は、男性が育児休業(育休)を取得しやすくすることです。
男性の家事・育児への関わりを増やし、性別に関わらず仕事と育児を両立できる社会を目指しています。
これにより、女性が出産後もキャリアを継続しやすくなり、少子化対策や女性活躍推進にも繋がることが期待されています。
関連記事👇


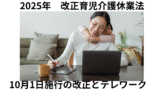


男性の育休取得を支える企業の職場環境改善
育休を取得しやすい雰囲気作りや、制度整備を企業に促すことで、従業員が働きやすい職場環境を整えることを狙いとしています。
「男性の育休は取りづらい」という職場の雰囲気を変え、誰もが安心して育児休業を取得できるような文化を醸成していくためのインセンティブとして、この助成金が機能しています。
育休取得支援で人材定着を実現する職場づくりの戦略
ライフイベントに応じて働き続けられる環境を整備することは、企業にとっても大きなメリットとなります。
特に中小企業にとっては、優秀な人材が育児を理由に離職するのを防ぐことが重要です。
制度を整備し、実際に育休取得を支援することで、従業員のエンゲージメント(愛着心)が高まり、長期的な定着に繋がります。
結果として、企業の生産性向上にも貢献するという目的があります。
出生時両立支援コース|男性育休取得・職場復帰で受けられる助成金の種類と条件
「出生時両立支援コース」の助成金は、企業の取り組みを「育休取得時」と「職場復帰時」の2つのフェーズに分け、それぞれに助成金を支給することで、一貫した支援を促しています。
出生時両立支援コース第1種|男性育休取得時に企業が受けられる助成金
この助成金は、男性従業員が育児休業を取得しやすい職場環境を整備し、実際に取得させた企業に支給されるものです。
単に制度があるだけでなく、それを活用できる環境作りが重要視されています。
支給の対象となる主な活動
- 育児休業の制度整備
- 育児・介護休業法に基づく育児休業制度について、就業規則等に明確に規定していることが必須です。
- 社内周知
- 従業員に対して、育児休業制度や、この助成金の活用に関する情報を周知する取り組みを行います。
- 具体的には、社内掲示板やメールでの案内、個別面談などが含まれます。
- 育休取得
- 上記の環境整備を行った上で、実際に男性従業員が育児休業を取得したことが支給の要件となります。
出生時両立支援コース第2種|職場復帰時に企業が受けられる助成金
第1種を受給後、育休を取得した従業員が安心して働き続けられる環境を整えることを目的とした助成金です。
支給の対象となる主な活動
- 職場復帰
- 児休業を終えた男性従業員が、元の職場または元の職務にスムーズに復帰すること。
- 継続雇用
- 職場復帰後、一定期間(原則として6か月以上)継続して雇用していることが支給の要件となります。
第1種(育休取得時)|具体的な助成金額【令和7年度版】
出生時両立支援コースの助成金は、企業の取り組みに応じて段階的に支給されます。
以下は、主に中小企業に適用される令和7年度(2025年度)の支給額です。
※本記事では、第1種(育休取得時)の助成金について解説します。第2種(職場復帰時)の助成金額については、こちらの記事で👉両立支援等助成金 出生時両立支援コース➂第2種を解説|最大70万円の助成金制度とは?
①育休取得時の助成金|男性従業員1人目で最大30万円を受給育休取得時の助成金|最大30万円支給
この助成金は、その企業にとって何人目の男性従業員が育児休業を取得したかに応じて支給されます。
お子さんの人数ではなく、御社で育休を取得した男性従業員の人数がカウントの対象となります。
ここでは、具体的な事例を挙げてご説明します。
- 1人目の取得 最大30万円
- その企業で初めて育児休業を取得する男性従業員が、連続5日以上の育児休業を取得した場合に支給されます。
- 基本額:20万円
- 増額:+10万円(合計30万円)
- 基本額に加えて、育休促進のための「雇用環境整備措置」を4つ以上実施している場合に加算されます。
- その企業で初めて育児休業を取得する男性従業員が、連続5日以上の育児休業を取得した場合に支給されます。
- 2人目・3人目の取得 10万円
- 1人目の取得後、2人目、3人目と続けて、それぞれ連続5日以上の育児休業を取得した場合に支給されます。
- 4人目以降の取得
- 4人目以降の取得者については、この「育休取得時」の助成金の直接的な支給対象にはなりませんが、後述する「育休取得率向上」の助成金の算定には含まれます。
雇用環境整備措置とは?
男性従業員が育児休業を取りやすくするために、企業が職場の環境や制度を整える取り組みのことです。
たとえば、育休制度に関する社内研修の実施や、相談窓口の設置、育休を取得した先輩の事例紹介などが含まれます。
こうした取り組みによって、「制度はあるけれど使いにくい」という状況を改善し、安心して育休を取れる職場づくりを目指します。
以下のうち、4項目以上を実施することで加算対象(+10万円)となります。
雇用環境整備措置15項目
| 番号 | 項目名 | 内容の概要 |
|---|---|---|
| 1 | 育児休業に関する制度の研修実施 | 管理職や従業員向けに、育休制度の研修を実施する |
| 2 | 育児休業に関する相談窓口の設置 | 育休取得についての相談ができる体制を設ける(人事部門など) |
| 3 | 社内報・掲示板・メール等による育児休業制度の周知 | 制度の内容を周知し、取得しやすい環境を作る |
| 4 | 育児休業を取得しやすい職場環境の醸成に関する方針の明確化 | 経営層からのメッセージや社内方針を明確化する |
| 5 | 育児休業取得事例の紹介 | 社内での取得実績やエピソードを共有する(社内報など) |
| 6 | 取得希望者に対する個別説明 | 対象者に個別面談等で制度の詳細を説明する |
| 7 | 取得希望者の上司への個別説明 | 取得者の上司に対し、制度内容や対応方法を説明する |
| 8 | 育児休業取得者の業務の見える化 | 業務の棚卸しや分担を通じてスムーズな引き継ぎ体制を整える |
| 9 | 代替要員確保等の業務カバー体制整備 | 取得期間中の業務をカバーする体制を事前に整える |
| 10 | 育児休業取得予定者への業務負担軽減措置 | 育休前の繁忙抑制など配慮を行う |
| 11 | 育児休業からの復帰後の支援 | 復帰後の面談や育児との両立支援を行う |
| 12 | 業務マニュアルの整備 | 育休による引き継ぎがスムーズになるようマニュアル化 |
| 13 | 育児休業取得の意向確認を制度化 | 配偶者の出産予定に応じて意向確認を行う社内制度の整備 |
| 14 | 取得率向上に向けた数値目標設定とその公表 | 育休取得率の目標を定め、社内外に公表する |
| 15 | その他厚生労働大臣が適当と認める取組み | 個別事情に応じた独自施策など(※要相談) |
加算対象となるための要件
- 上記15項目のうち「4つ以上」を助成金申請時点で実施していること
- 実施したことを示す記録(例:周知メール、研修資料、面談記録など)を整備しておくこと
- 申請時に「雇用環境整備実施報告書」とともに添付資料を提出
【事例】
とある中小企業に勤務する男性従業員AさんとBさんがいるとします。
- 2025年5月
- Aさんが、初めてのお子さんの誕生に伴い育児休業を連続7日間取得しました。
- この時点で、Aさんは「企業にとって1人目の育休取得者」となります。
- 育休期間が「連続5日以上」という要件を満たしているため、会社は最大30万円の助成金を受給できます。
- Aさんが、初めてのお子さんの誕生に伴い育児休業を連続7日間取得しました。
- 2025年8月
- Bさんが、初めてのお子さんの誕生に伴い育児休業を連続6日間取得しました。
- この時点で、Bさんは「企業にとって2人目の育休取得者」となります。
- 育休期間が「連続5日以上」という要件を満たしているため、会社は10万円の助成金を受給できます。
- Bさんが、初めてのお子さんの誕生に伴い育児休業を連続6日間取得しました。
- 2026年2月
- Aさんが、2人目のお子さんの誕生に伴い、再度育児休業を連続10日間取得しました。
- Aさんはすでに1人目の取得者としてカウントされているため、この取得は3人目のカウントとはなりません。
- Aさんが、2人目のお子さんの誕生に伴い、再度育児休業を連続10日間取得しました。
➁育児休業取得率向上助成金|男性育休取得率向上で最大60万円を受給
こちらは、男性の育休取得率が一定水準を超えた場合に支給される助成金です。
- 育休取得率の上昇等
- 最大60万円
- 申請年度の前年度を基準として、男性の育児休業取得率が30ポイント以上上昇し、かつ50%以上になった場合に支給されます。
- 取得率50%以上70%未満
- 30万円
- 取得率70%以上
- 60万円
- 最大60万円
育児休業取得率の計算方法と事例
ここでは、育児休業取得率の計算方法と、先ほどの事例に当てはめた場合どうなるかをご説明します。
育児休業取得率の計算方法
育児休業取得率は、以下の計算式で算出します。
男性の育児休業等取得率=子の出生日が含まれる事業年度に在職していた男性労働者の数÷育児休業等を取得した男性労働者の数×100
【計算のポイント】
- 分子(育児休業等を取得した男性労働者の数)
- 子の出生後8週間以内に、連続5日以上(育児休業、産後パパ育休)の育児休業等を取得した男性従業員の数がカウントされます。
- 育休取得時助成金の対象となる1人目、2人目、3人目だけでなく、4人目以降の取得者もすべてカウントされます。
- 分母(子の出生日が含まれる事業年度に在職していた男性労働者の数)
- 子の出生日が含まれる事業年度(例:2025年4月1日~2026年3月31日)に在職していた、配偶者が出産した男性従業員の合計人数です。
先ほどの事例に当てはめてみましょう
前年度(2024年度)の男性育休取得率が0%だった中小企業で、今年度(2025年度)に2人の男性従業員(AさんとBさん)に配偶者の出産があったとします。
- 2025年度
- Aさん:育児休業を連続7日間取得
- Bさん:育児休業を連続6日間取得
この場合、育児休業を取得した男性労働者は、AさんとBさんの2名です。
育児休業取得率は、以下のようになります。
男性の育児休業等取得率=2名(AさんとBさん)÷2名(AさんとBさん)×100=100%
このケースでは、前年度の0%から100%へと大幅に上昇してます。要件である「30ポイント以上の上昇」と「50%以上」の両方を満たしています。
基準はクリアしています
この事例の企業は、育休取得率向上の助成金支給の基準をクリアしています。
ただし、最終的な支給は、提出書類の不備や、要件の遵守状況に関する厳格な審査によって決定されます。
この制度を活用して、企業の働きやすい環境づくりと、助成金受給の両方を目指しましょう。
育休取得時助成金|受給条件・申請手順をわかりやすく解説
この助成金を受給するためには、以下の要件を満たし、所定の手続きを行う必要があります。
申請を検討する前に、自社がこれらの点をクリアしているか必ず確認しましょう。
育休取得時助成金|申請前に押さえる必須条件と受給要件
- 一般事業主行動計画の策定と公表
- 労働者の人数にかかわらず、一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出て、社内と外部に公表することが必須です。
- この計画には、男性の育児休業取得に関する目標や具体的な取り組み内容を盛り込む必要があります。
- 育児休業制度の整備と周知
- 育児・介護休業法に基づき、就業規則等で育児休業制度を明確に定めていることが必要です。
- この制度は、全ての従業員が平等に利用できるものでなければならず、その内容を従業員に周知することも求められます。
- 育児休業取得のための措置
- 単に制度があるだけでなく、男性が育休を取得しやすい職場環境を整えるための具体的な取り組みを行うことが求められます。
- 例えば、育休に関する研修の実施、相談窓口の設置、社内での育休取得事例の共有などがこれに該当します。
- 男性従業員の育休取得
- 実際に男性従業員が育児休業を取得し、一定期間(原則5日以上)の休業を確認できることが、受給の必須要件となります。
育休取得時助成金|申請手順と必要書類をわかりやすく解説
- 労働局への届け出
- 一般事業主行動計画を策定したら、企業の所在地を管轄する都道府県労働局に届け出を行います。
- 必要書類の提出
- 育休開始日など、定められた期日内に、必要書類を揃えて申請を行うことが必要です。申請期限を過ぎると、受給資格を失ってしまうため、注意が必要です。
まとめ|出生時両立支援コース助成金申請の準備とポイント
今回は、出生時両立支援コース(第1種|育児取得時)の具体的な助成金額と、受給のための要件と手続きについて解説しました。
この助成金は、男性育休を促進する企業に、大きな金銭的メリットをもたらす強力な制度です。
しかし、その分、満たすべき要件は多岐にわたります。
特に「一般事業主行動計画の策定」や「育児休業取得のための措置」といった項目は、日々の業務と並行して進めるには負担に感じられるかもしれません。
次回予告|出生時両立支援コース助成金の詳細と申請実務
さて、次回の記事では、今回ご紹介した「受給するための要件と手続き」について、各項目の詳細な内容や、具体的な取り組み例をさらに掘り下げて解説します。
次回の記事は👉出生時両立支援コース|第1種(育児取得時)助成金の申請手順
ぜひ、次回の記事もご覧いただき、助成金申請に向けた準備を万全に整えましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。
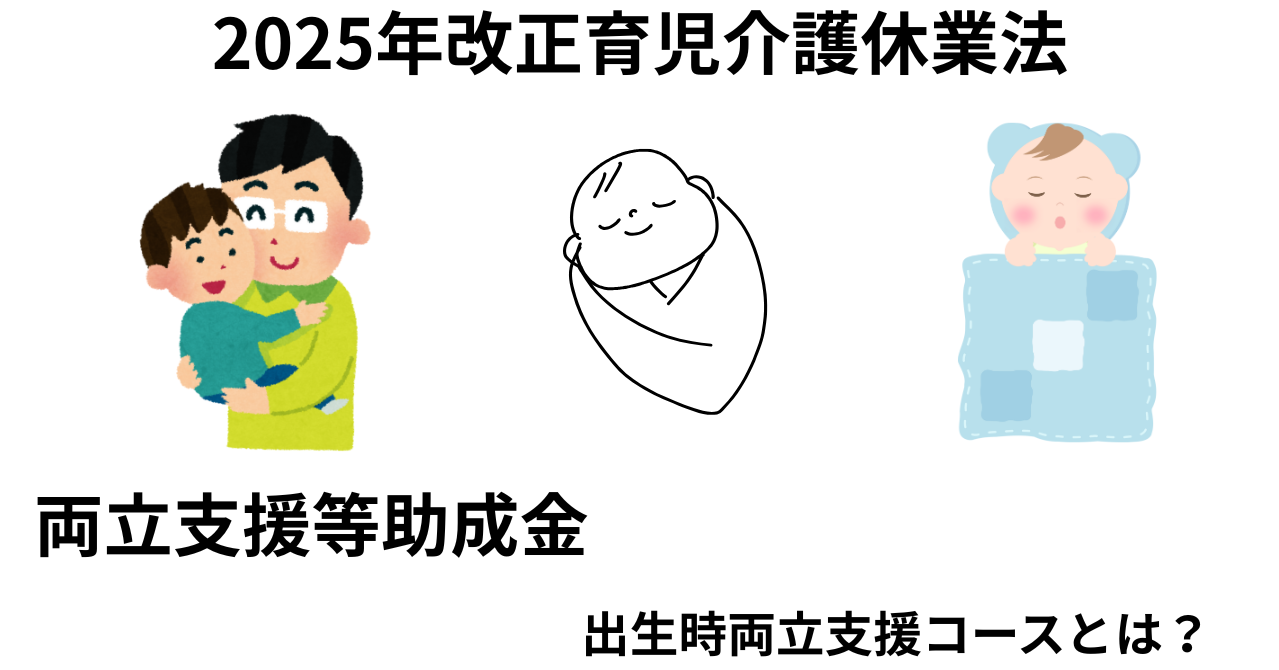

コメント