本記事は「2025年改正育児介護休業法シリーズ」の第23弾です。他のシリーズの記事はコチラから👉2025年育児介護休業法改正|企業がすべき対応と助成金情報
前回の記事では、2025年4月から施行されている産後パパ育休(出生時育児休業)の制度について、中小企業における男性育休推進の重要性を解説しました。
前回の記事は👉中小企業必見|男性育休!産後パパ育休(出生時育児休業)活用術
男性の育児参加を促し、夫婦での子育てを支援する動きは、現代社会においてますます重要になっています。
今回の記事では、育児休業期間をさらに柔軟に、そして長く活用できる「パパ・ママ育休プラス」に焦点を当てます。
この制度がいつから、そしてなぜ生まれたのかという背景を簡潔に知ることは、中小企業が男性育休を戦略的に推進するための重要な一歩となるでしょう。
この記事で分かること
- 子どもが1歳2ヶ月になるまで育休を延長できる「パパ・ママ育休プラス」の仕組み
- 制度を利用するために夫婦で満たすべき3つの適用条件と、具体的な取得パターン
- 1歳2ヶ月以降のさらなる延長(2歳まで)と、2025年4月からの厳格化された審査基準
- 従業員側・企業側それぞれの視点による、スムーズな申請と受入れのための実務フロー
- 「産後パパ育休」と組み合わせることで、男性の育児参加を強力に後押しする戦略
パパ・ママ育休プラスの基本|夫婦で育休を取得する方法と条件
「パパ・ママ育休プラス」は、育児介護休業法の改正により、2010年6月30日から施行された制度です。
これは、2022年10月に施行された「産後パパ育休」よりもはるか以前から存在する制度である点がポイントです。
この制度は、男性従業員、女性従業員のどちらか一方だけが利用するものではありません。
夫婦で協力して育児休業を取得することを前提とした制度です。
ですから、夫婦どちらか一方しか育児休業を取得しない場合は、「パパ・ママ育休プラス」は適用されません。
夫婦のどちらも利用の対象となります。
政府がこの制度を導入した主な狙いは、以下の通りです。
- 男性の育児参加を促し、夫婦での育児分担を推進すること。
- 女性の育児負担を軽減し、キャリア継続を支援すること。
- 安心して子どもを産み育てられる社会を構築し、少子化対策に寄与すること。
- 育児休業の利用期間に柔軟性を持たせ、保育園入所などの状況にも対応すること。
このように、「パパ・ママ育休プラス」は、夫婦で協力して子育てを支援し、育児休業をより柔軟に利用できるようにするという明確な意図のもとに設計された制度なのです。
「パパ・ママ育休プラス」の適用条件と制度のポイント
「パパ・ママ育休プラス」は、夫婦ともに育児休業を取得する場合に、原則1歳までの育児休業期間を、子が1歳2ヶ月になるまで延長できる制度です。
ただし、延長できる期間は、夫婦それぞれの育児休業取得期間を合計して1年間が上限となります。
この制度を適用するためには、以下の全ての条件を満たす必要があります。
- 配偶者が子の1歳到達日より前に育休を取得していること
- 夫婦それぞれの育休開始日が、子の1歳の誕生日以前であること
- 夫婦それぞれの育休期間が、子の1歳2ヶ月到達日までであること (ただし、取得できる期間は、夫婦で取得した期間を合計して1年間が上限)
具体例
- たとえば、「まず妻が産後から子どもが1歳になるまで育休を取得します。
- そして夫が子どもが1歳になる直前に育児休業を開始します。
- 妻の育休終了後、子どもが1歳2ヶ月になるまで育休を取得します。」といったケースが考えられます。
- この場合、夫の育休期間が「パパ・ママ育休プラス」によって延長されることになります。
パパ・ママ育休プラス後も延長可能?1歳2ヶ月超の育児休業の仕組み
「パパ・ママ育休プラス」を活用することで育休期間を最長1歳2ヶ月まで延ばせるのは非常に有用です。
しかし、保育園への入園が叶わないなど、子どもの養育状況によってはそれ以降も育休が必要となる場合があります。
この1歳2ヶ月を超えての育児休業延長は、「パパ・ママ育休プラス」によるものではなく、通常の育児休業の延長制度として認められています。
「パパ・ママ育休プラス」を利用したからといって、子どもが2歳2ヶ月まで育休が取れるわけではない点にご注意ください。
主な延長条件は、保育所への入所を希望し、入所申込みを行っているにもかかわらず、入所できない場合です。
ただし、2025年4月からは、この延長手続きの審査が厳格化されています。
単に不承諾通知があるだけでなく、ハローワークが「速やかな職場復帰のために保育所等の利用を希望している」と認める必要があります。
中小企業としては、これらの延長制度についても従業員に適切に情報提供し、必要に応じて手続きをサポートすることが、従業員の安心感と定着に繋がります。
パパ・ママ育休プラスの取得手順|中小企業と従業員向け完全ガイド
ここでは、「パパ・ママ育休プラス」を利用する際の具体的な流れを、企業側と従業員側の双方の視点から解説します。スムーズな育休取得のために、各段階での準備と連携が重要です。
従業員向け「パパ・ママ育休プラス」取得フロー|中小企業の育児休業
まずは、従業員自身が「パパ・ママ育休プラス」を活用して育休を取得する際の全体的な流れを理解することが重要です。
男性・女性それぞれの育休開始日や期間を調整し、夫婦で協力して計画を立てることが、スムーズな取得と職場復帰につながります。
ここでは、従業員側が実際に行う具体的なステップを順を追って解説します。
1. 夫婦での育休計画の検討
- 夫婦でいつ、どちらが、どのくらいの期間育休を取得するかを具体的に話し合いましょう。「パパ・ママ育休プラス」の活用を検討し、最長1歳2ヶ月までの期間をどう活用するかを計画します。
2. 会社への相談・申請
- 育児休業の申し出は、原則として育休開始予定日の1ヶ月前までに会社(人事・総務担当者、または上長)に行います。
- 女性従業員の場合、育児休業の開始日は産後休業終了の翌日となります。そのため、産前休業に入る前、あるいは産前休業中など、余裕を持って早めに申し出るのが実務上は一般的です。
- 配偶者の育休取得状況(開始日、終了日など)を伝え、「パパ・ママ育休プラス」を利用したい旨を明確に伝えましょう。
3. 育児休業申出書の提出
- 会社の定める育児休業申出書に必要事項を記入し、提出します。添付書類(母子手帳の写し、住民票の写しなど、会社が指定するもの)があれば合わせて提出してください。
- 1歳2ヶ月を超えて育休延長を希望する場合は、通常の育休延長制度として別途申請が必要となるため、この点も念頭に置きましょう。
4. 育児休業給付金の申請
- 育児休業開始後、会社を通じてハローワークへ育児休業給付金の申請を行います。
- 必要に応じて、配偶者の育休取得状況を証明する書類(育児休業取扱通知書など)の提出が必要となる場合があります。
5. 育休取得と育児への専念
- 計画した期間、育児休業を取得し、育児に専念しましょう。
6. 職場復帰
- 育児休業終了後、職場に復帰します。
企業向けパパ・ママ育休プラス取得支援フロー|中小企業の対応手順
中小企業において、従業員が「パパ・ママ育休プラス」をスムーズに取得できるようにするには、企業側の明確な対応フローが不可欠です。
制度の周知や相談窓口の設置、申請手続きのサポートなど、段階的に整備することで、従業員の育児参加を後押しし、企業の人材定着や働きやすい職場づくりにもつながります。
ここからは、具体的な企業側の対応手順を順を追って解説します。
1. 制度の周知と相談体制の整備
- 従業員に「パパ・ママ育休プラス」を含む育児休業制度を周知する(就業規則、社内ポータル、説明会など)ことが重要です。
- 従業員からの育休相談を受け付ける窓口(人事担当者など)を設置し、気軽に相談できる雰囲気を作りましょう。
2. 育休申出の受付と確認
- 従業員からの育児休業申出を受け付けます。「パパ・ママ育休プラス」の適用条件(配偶者の育休取得状況、夫婦の育休開始日など)を満たしているか確認しましょう。
3. 育児休業取扱通知書の交付
- 従業員に対し、育児休業期間、復帰予定日などを明記した「育児休業取扱通知書」を交付します。これは、育児休業給付金の申請にも必要となる重要な書類です。
4. 業務引き継ぎ・代替要員の検討・手配
- 育休取得者の業務内容を把握し、スムーズな引き継ぎが行われるよう調整します。
- 必要に応じて、他の従業員への業務分担、派遣社員の活用、採用などを検討・手配しましょう。
5. 育児休業給付金申請のサポート
- 従業員からの依頼に基づき、ハローワークへの育児休業給付金の申請手続きをサポートします。
- 添付書類の準備や、必要に応じてハローワークとの連絡調整をサポートすることも重要です。
6. 育休中の状況確認(任意)
- 従業員の希望に応じて、育休中の状況確認や情報共有を行うことができます。
- ただし、休業中の従業員への過度な連絡は避け、あくまでサポートの姿勢を保ちましょう。
7. 職場復帰支援
- 復帰前の面談などを実施し、復帰後の業務内容や働き方についてすり合わせを行います。
- 必要に応じて、時短勤務や時差出勤などの両立支援制度を案内し、スムーズな復帰を後押ししましょう。
男性育休を強化!「産後パパ育休」と組み合わせた取得支援方法
2022年10月に施行された「産後パパ育休(出生時育児休業)」は、男性が子どもの出生後8週間以内に最大4週間まで、2回に分けて取得できる柔軟な育休制度です。
そして、2025年4月からは給付金制度の拡充がされております。
両親がともに一定期間育休を取得した場合、手取り10割相当の給付金が支給されるなど、男性が育休を取得しやすい環境がさらに整います。
詳細は
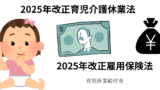
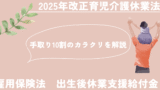
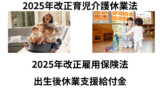
この「産後パパ育休」と、今回ご紹介している「パパ・ママ育休プラス」を組み合わせることで、男性の育児休業取得はさらに強力に推進されます。
「産後パパ育休」で育休取得の第一歩を
まずは出生直後の特に手厚いケアが必要な時期に、男性が短期間でも育児に参加する「きっかけ」を作ります。
これにより、育児のリアルを体験し、その後の育児参加への意識を高めます。
「パパ・ママ育休プラス」で長期的な育児参加と柔軟性を確保
産後パパ育休で育児の重要性を実感した後、夫婦で話し合い、「パパ・ママ育休プラス」を活用することで、子どもが1歳以降も必要な期間、男性が育児休業を取得できる選択肢が生まれます。
これにより、保育園入所までの繋ぎや、子どもの成長に合わせたきめ細やかな育児が可能となり、夫婦の育児負担を分散させることができます。
中小企業は、これらの制度を従業員に積極的に周知し、取得を奨励することで、従業員のエンゲージメント向上、優秀な人材の確保、企業イメージの向上といったメリットを享受できます。
男性が安心して育児休業を取得できる環境を整えることは、従業員満足度を高め、ひいては企業の持続的な成長へと繋がる投資となるのです
まとめ|パパ・ママ育休プラスと産後パパ育休で進める男性育休取得支援
「パパ・ママ育休プラス」は、夫婦で子育てを支え、男性の育児参加を促す上で非常に重要な制度です。
2025年の「産後パパ育休」給付金拡充と相まって、中小企業が男性育休を推進するための強力なツールとなります。
柔軟な働き方を推進し、多様な人材が活躍できる企業文化を醸成することは、今後の競争力を高める上で不可欠です。
本記事で解説した「パパ・ママ育休プラス」の背景、実際の利用フロー、そして産後パパ育休との組み合わせを理解し、従業員と共に成長する未来の中小企業を目指しましょう。
次回予告|中小企業向け男性育休「分割取得」と「合わせ技」活用法を徹底解説
今回の記事で、「パパ・ママ育休プラス」の基本や、夫婦で育休を取得することの重要性を解説しました。
次回の記事では、まだ一般的ではないものの、今後は確実に増えると予想される育休制度の「合わせ技」に焦点を当てます。
次回の記事は👉育児休業の分割取得と男性育休「合わせ技」戦略|フローで解説
前回の「産後パパ育休」、今回の「パパ・ママ育休プラス」、そして「通常の育休分割取得」──これら全てを組み合わせ、最も効率的に育休を取得するための具体的なフローを、実務的な視点と事例を交えながら徹底的に解説します。
複雑に思える育休制度ですが、賢く活用すれば、従業員のワークライフバランスと企業の生産性向上を両立できます。
男性育休のさらなる取得促進に向けた実践的な内容となりますので、どうぞご期待ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。


コメント