本記事は「知っておきたい!年次有給休暇のすべて」シリーズのvol13です。
前回の記事では、従業員側からの有給休暇に関するトラブル事例として、突然の申請や退職時の有給消化、そして取得理由の申告拒否といったケースを取り上げ、それぞれの対処法を掘り下げました。
従業員との認識のズレがトラブルの根源となることが多いことをご理解いただけたかと思います。
前回の記事は👉会社の都合を無視した有給申請への対抗策と時季変更権の限界
企業側が招く有給休暇トラブル事例とその具体的対処法
さて、今回は視点を変え、企業側が意図せず、あるいは避けられない事情からトラブルを引き起こしてしまうケースに焦点を当てます。
人手不足、繁忙期、人事評価…日々の企業運営で直面する課題が、時に有給休暇の運用とぶつかり、思わぬトラブルに発展することがあります。
ここでは、企業側が陥りやすい「NG行動」と、それを未然に防ぎ、適切に対処するための具体的な方法を解説していきます。
企業が注意すべき有給取得制限・拒否の法的リスク
企業側の主張
- 「今は人手が足りないから休めない」
- 「繁忙期だから有給は無理だ」
これは、実際の問題としては、企業の人事労務担当者もしくは経営者と労働者との間での行き違いではありません。
現場の管理職と従業員との間で起こることです。
従業員が感じる有給取得時の不満とトラブル事例
- 「また今度」と言われて、いつになったら休めるのか分からない。結局、有給は取れないものだと諦めてしまう。
- このような不満は、従業員の労働意欲を著しく低下させ、企業への不信感につながります。
- 最悪の場合、労働基準監督署への申告や訴訟に発展するリスクもあります。
- 企業側としては、業務の円滑な遂行を優先したい気持ちは理解できますが、従業員の有給休暇取得は法律で保障された権利です。
1. 時季変更権の厳格な要件を再確認する
- 企業が有給休暇の時季を変更できる「時季変更権」は、関連記事でも詳しく解説しましたが、その行使には厳格な要件があります。
- 単に「忙しい」「人手が足りない」というだけでは認められません。
- 「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、代替要員の確保が著しく困難である、その労働者が休むことで特定の業務が停止し、事業全体に具体的な損害が出るなど、客観的かつ具体的な事実に基づいている必要があります。
- 安易な拒否は、労働基準法違反となる危険性が非常に高いため、慎重な判断が求められます。
2. 安易な拒否の危険性を管理職と共有する
- 現場の管理職が、従業員の有給申請を安易に拒否していないか、定期的に確認しましょう。
- 管理職に対して、時季変更権の正しい知識と、不適切な拒否が企業にもたらす法的リスク(罰則、賠償責任、企業イメージの低下など)について教育を徹底することが重要です。
3. 代替要員の確保と業務平準化の努力
- 恒常的な人手不足や、特定の時期に業務が集中する繁忙期がある場合は、根本的な業務体制の見直しが必要です。
- 代替要員の確保
- 派遣社員の活用、非正規雇用者の多能工化、他部署からの応援体制の構築などを検討しましょう。
- 業務平準化の努力
- 特定の時期に業務が集中しないよう、年間スケジュールを見直したり、事前にできる業務を進めておくなど、計画的な業務配分に努めることで、従業員が有給を取得しやすい環境を整えることができます。
- 代替要員の確保
有給休暇取得者への不利益な扱いと法的リスク
企業側の行動
- 「有給をよく取る社員は評価を下げよう」
- 「ボーナスを減らすか、昇進を遅らせよう。」
有給休暇取得に対する従業員の不満事例
- 「有給を取ったら査定に響いた。」「休暇を取ったせいで重要な仕事を任されなくなった。」といった事態は、従業員に「有給を取ると損をする。」という認識を与え、結果として誰も有給を取りたがらなくなる職場環境を生み出します。
- これは、労働者の権利行使に対する報復行為であり、法的に厳しく禁じられています。
1. 不利益取り扱いの禁止を徹底する
- 労働基準法附則第136条により、企業は労働者が年次有給休暇を取得したことを理由として、賃金の減額その他不利益な取扱いをしてはならないと明確に定められています。
- 人事評価、昇進、配置転換、賞与、退職金など、あらゆる面において、有給取得を理由とした不利益な取り扱いは許されません。
- この原則を社内に周知徹底し、違反がないか定期的にチェックする体制を構築しましょう。
2. 人事評価制度の見直しと透明化
- 人事評価項目に、有給休暇の取得状況を直接的・間接的に評価するような項目がないか確認し、あれば削除しましょう。
- 評価基準を明確にし、従業員が納得できる公平な評価が行われているか、評価者である管理職への研修を強化することが重要です。
- 評価はあくまで「業務遂行能力」や「成果」に基づくべきであり、有給取得の有無は関係ありません。
3. 管理職への教育を徹底する
- 管理職が、有給取得は正当な権利行使であり、それを理由に部下を不当に扱うことが許されないことを深く理解することが不可欠です。
- 個々の管理職が持つ誤解や偏見が、知らないうちに不利益取り扱いにつながることがあります。
- 定期的な研修や、労務担当者による個別指導を通じて、正しい知識と適切なマネジメント意識を醸成しましょう。
- 管理職自身が率先して有給を取得する姿勢を見せることも、良い職場文化を作る上で効果的です。
年5日取得義務の対応遅れで起こるトラブルと法的リスク
企業側の状況
- 「年5日取得義務があることは知っていたが、対応が後手に回ってしまった。」
- 「まさか義務化されているとは知らなかった。」
従業員側の影響
年5日間の有給休暇取得義務は、労働者が確実に休暇を取得し、心身のリフレッシュを図るための重要な制度です。
企業がこの義務を怠ると、従業員は有給消化が進まず、ストレスや疲労を蓄積しやすくなります。
そして、これは単に従業員の不満にとどまらず、企業側には明確な罰則が科されるリスクがあります。
1. 法改正の再確認と社内体制の緊急構築
- 2019年4月1日から施行された年5日取得義務化は、全ての企業に課せられた重要な義務です。
- まだ対応が不十分な企業は、速やかに自社の就業規則や勤怠管理体制を見直しましょう。
2. 年次有給休暇管理簿の整備と活用
- 年5日取得義務化に伴い、年10日以上の有給休暇が付与される全ての従業員について、「年次有給休暇管理簿」の作成・保存が義務付けられました。
- この管理簿は、誰がいつ何日有給を取得したか、残日数は何日か、義務日数を達成しているかなどを正確に記録・把握するためのツールです。
- デジタルツール(勤怠管理システムなど)の導入も検討すると、管理の手間を大幅に軽減できます。
3. 計画的付与の検討
- 年5日取得義務を確実に達成するための有効な手段の一つが「年次有給休暇の計画的付与」制度です。
- これは、労使協定を締結することで、あらかじめ企業が有給休暇の取得日を指定できる制度です。
- これにより、計画的に有給消化を進め、義務達成の確実性を高めることができます。
関連記事
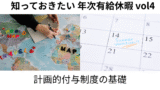
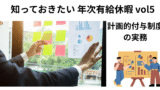
有給休暇トラブルを未然に防ぐための労使共通の予防策
これまでの記事で、従業員側、そして企業側から発生しがちな有給休暇を巡るトラブル事例と、その対処法について解説してきました。
トラブルが発生した際の対応も重要ですが、最も理想的なのは、そもそもトラブルが起こらないように予防することです。
ここでは、労使双方が協力し、有給休暇に関するトラブルを未然に防ぐための具体的な予防策を、実践的な視点からご紹介します。
これらの予防策を講じることで、従業員は安心して有給休暇を取得でき、企業は円滑な事業運営を維持し、結果として労使間の信頼関係をより強固なものにできるでしょう。
有給休暇ルールを就業規則で明確化し従業員に周知する方法
有給休暇に関するルールは、就業規則に具体的に明記し、従業員全員に周知徹底することがトラブル予防の第一歩です。
- 規定の具体化(以下の項目を曖昧さを排除して具体的に記載しましょう。)
- 有給休暇の付与日数
- 取得条件
- 申請手続き(いつまでに、誰に、どのような方法で申請するか)
- 時季変更権を行使する際の基準
- 年5日取得義務に関する会社の対応方針(計画的付与の有無など)
- 退職時の有給休暇の取り扱い(買い上げの有無や条件など)
- 周知徹底
- 就業規則は作成するだけでなく、従業員がいつでも確認できる状態にしておくことが重要です。
- 入社時の説明会での丁寧な説明はもちろん、社内イントラネットでの公開、定期的な説明会の開催、変更があった際の個別通知など、様々な方法で従業員への周知を図りましょう。
- 従業員がルールを正しく理解していれば、不要な誤解や不満を防ぐことができます。
有給休暇トラブル防止のための労使コミュニケーション活性化法
ルールだけを一方的に押し付けるのではなく、日頃から労使間で有給休暇について話し合えるオープンな雰囲気を作ることが重要です。
- 定期的な面談
- 上司と部下との間で、業務状況だけでなく、有給休暇の取得希望や今後の計画について定期的に話し合う機会を設けましょう。
- これにより、従業員は事前に休暇希望を伝えやすくなり、企業側も業務調整の時間を確保できます。
- 相談しやすい雰囲気作り
- 従業員が有給休暇の取得に関して疑問や不安を感じた際に、気軽に相談できる窓口(人事担当者、信頼できる上司など)を明確にし、相談しやすい雰囲気を作りましょう。
- 一方的な指示ではなく、対話を通じて解決策を探る姿勢が信頼関係を築きます。
有給休暇トラブル回避のための管理職教育・研修のポイント
有給休暇に関するトラブルの多くは、現場の管理職と従業員の間で発生しますそのため、管理職への教育は極めて重要です。
- 有給休暇制度の理解(以下の有給休暇制度に関する正しい知識を管理職に徹底的に教育しましょう。)
- 労働基準法の基本原則(有給は労働者の権利であること、年5日取得義務など)
- 時季変更権の厳格な要件
- 不利益取り扱いの禁止
- 適切なマネジメント方法
- 従業員の有給取得希望を尊重しつつ、業務を円滑に進めるためのマネジメントスキル(業務の優先順位付け、チーム内での協力体制構築、代替要員の育成など)を研修を通じて習得させましょう。
- 管理職自身が率先して有給を取得する姿勢を見せることも、部下が休暇を取りやすくなる良い手本となります。
有給取得促進のための柔軟な働き方導入の実務ポイント
従業員が有給休暇を取得しやすい環境を整備するために、柔軟な働き方の導入も有効な手段です。
- 時間単位年休の活用
- 関連記事でも解説した「時間単位年休」は、半日や1日単位での取得が難しい場合に、時間単位で有給休暇を取得できる制度です。
- 従業員が私用や通院などで短時間だけ抜けたい場合に利用でき、有給消化を促進します。
- テレワーク・リモートワーク
- 業務内容によっては、テレワークやリモートワークを導入することで、従業員が自宅で業務を行いながら、プライベートな用事も済ませやすくなり、有給休暇の取得を補完する効果が期待できます。
- その他
- フレックスタイム制度や裁量労働制など、従業員が自身のライフスタイルに合わせて働き方を調整できる制度の導入も、有給休暇取得の促進に繋がります。
関連記事

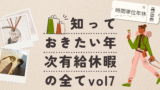
有給休暇トラブル解決のための社会保険労務士活用法
自社だけで解決が難しい問題や、法的な判断に迷う場合は、迷わず外部の専門家を頼りましょう。
- 社会保険労務士など
- 労働法に関する専門知識を持つ社会保険労務士は、就業規則の作成・見直し、有給休暇の適切な運用方法、トラブル発生時の対応など、幅広い相談に乗ってくれます。
- 顧問契約を結んでおくことで、日頃から気軽に相談できる体制を整えることができます。
- 相談先の明確化
- 従業員にも、会社が外部の専門家と連携していること、必要に応じて相談できる体制があることを伝えておくことで、安心感を与えることができます。
まとめ|健全な有給休暇運用で労使トラブルを防ぎ、従業員満足と企業成長を両立する方法
ここまで、年次有給休暇を巡る様々なトラブル事例とその対処法について、労使双方の視点から深く掘り下げてきました。
従業員からの突然の申請や退職時の有給消化、企業側の取得制限や不利益取り扱い、そして年5日取得義務の未達成といった、日々の業務で起こり得る具体的なケースとその解決策を学んできたかと思います。
トラブル防止は企業リスク管理の要|有給休暇運用で労使トラブルを未然に防ぐ
有給休暇に関するトラブルは、一見すると些細なことのように思えるかもしれません。
しかし、これらを放置すると、従業員のモチベーション低下や不満の蓄積を招き、最悪の場合、労働基準監督署からの指導や罰則、さらには訴訟といった大きなリスクに発展する可能性があります。
企業イメージの悪化や優秀な人材の流出にも繋がりかねません。だからこそ、トラブルを未然に防ぎ、適切に対処することの重要性は計り知れません。
有給休暇は生産性向上のカギ|従業員のリフレッシュで業務効率アップ
有給休暇は、単に法律で定められた義務ではありません。
従業員が心身ともにリフレッシュし、仕事への活力を養うための大切な時間です。
従業員が計画的に休暇を取得し、リフレッシュできる職場環境は、結果として企業の生産性向上にもつながります。
疲労が蓄積した状態では、ミスが増えたり、創造性が低下したりする可能性がありますが、適切な休息はこれを防ぎ、業務効率を高める効果があるのです。
最終的に目指すべきは、労使が協力し、働きやすい環境を構築することの意義を共有することです。
従業員が安心して有給休暇を取得できる職場は、エンゲージメントを高め、離職率を低下させ、企業の持続的な成長に貢献します。
このシリーズを通じて、有給休暇に関する正しい知識と運用方法を習得し、ぜひ貴社の健全な発展に役立ててください。
次回予告|有給休暇制度の未来と企業が備えるべきこと
さて、年次有給休暇シリーズも、いよいよ大詰めに入ります。
vol1から今回まで、有給休暇の基本から多様な働き方への対応、具体的なトラブル事例と対処法、そして予防策まで、多岐にわたるテーマを深掘りしてきました。
次回は、これまでの総仕上げとして、「法改正・判例から見る有給休暇の最新動向と企業が備えるべきこと」に焦点を当てます。
次回の記事は👉2025年最新!有給休暇運用ガイド:法改正と判例でトラブル回避
労働法は常に変化しており、有給休暇に関する新たな解釈や判例が生まれることも少なくありません。
例えば、最近のフリーランス保護新法のように、働き方の多様化に合わせて有給休暇に関する議論も進んでいます。
次回の記事では、企業が今後も法令遵守を徹底し、適切に有給休暇を運用していくために知っておくべき、最新の法的トレンドや注意点を分かりやすく解説します。
複雑に思える有給休暇の運用も、このシリーズを通して学んだ知識があれば、きっと自信を持って対応できるはずです。どうぞご期待ください!
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。





コメント