本記事は「【社労士が解説】企業のための熱中症対策 実践講座」シリーズの第3話です。第1話は👉熱中症は「他人事」ではない!企業に求められる安全配慮義務の基礎
シリーズ全体の記事はコチラからご覧ください👇
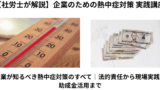
前回の記事では、熱中症対策における法整備の進化と、それが現場で直面する「実務ギャップ」について考察しました。
前回の記事は👉職場の熱中症対策|法改正と現場での実務ギャップを徹底解説
法律が定める安全配慮義務を単なる「絵に描いた餅」に終わらせず、労働者の命と健康を確実に守るためには、具体的な行動への落とし込みが不可欠です。
本記事では、企業が安全配慮義務を果たすために「具体的に何をすべきか」を網羅したチェックリスト形式で解説します。
現場での熱中症リスク管理を強化し、従業員の安全を確実に守るための実践的なステップを、分かりやすくご紹介します。
この記事で分かること
- 気温だけではなく湿度や日射を考慮したWBGT値で見えない暑さを可視化すること
- 作業場所を代表する地点で定期的に測定し推移を継続的にモニタリングすること
- 測定値に応じて休憩時間の延長や作業の中断などの具体的な行動ルールを定めること
- 決められた休憩以外にも本人の体調に応じた臨時休憩を積極的に奨励すること
- 涼しい休憩場所の確保や水分と塩分の提供により休憩の質を向上させること
職場の熱中症対策|気温・湿度とWBGTで見えない暑さを可視化
これまでの記事で触れてきたように、熱中症対策は単に気温を見るだけでは不十分です。
私たちが体感する暑さ、そして熱中症リスクは、気温だけでなく湿度、日差し(輻射熱)、風といった複合的な要素に大きく左右されます。
これらを総合的に評価し、人の熱ストレスを客観的に示すのがWBGT(湿球黒球温度)値です。
熱中症対策に必須|WBGT値の正しい見方と測定方法
WBGT値は、「人が感じる暑さ」を数値化したものです。
気温が同じでも、湿度が高ければ汗が蒸発しにくく、体に熱がこもりやすくなります。また、直射日光が当たる場所では、気温以上に輻射熱による影響が大きくなります。
WBGT値はこれらの要素を複合的に計算するため、熱中症リスクを判断する上で最も信頼性の高い指標とされています。
このWBGT値を正しく理解し、定期的に測定することが、熱中症予防の第一歩です。
WBGT値が高いほど熱中症の危険性が増すため、現場の状況を正確に把握するためには、WBGT計を用いた測定が不可欠なのです。
WBGT計の設置場所と定期モニタリングの実務ポイント|熱中症対策
WBGT計を導入しても、その設置場所が適切でなければ意味がありません。
例えば、「日陰に置けば安全だろう」と安易に判断されたり、実際の作業場所から離れた場所で測定されたりすると、現場の真のリスクを見誤る可能性があります。
- 設置場所の適正化
- WBGT計は、実際の作業環境を代表する地点に設置することが重要です。
- 屋外であれば直射日光が当たる場所、屋内であれば熱源の近くなど、最も熱中症リスクが高まる可能性のある場所を選びましょう。
- 継続的なモニタリング
- 気温や湿度は刻一刻と変化します。一日のうち特定の時間だけ測定し、その数値だけで判断するのは危険です。
- 午前、午後、夕方など、時間を決めて定期的に測定し、その推移を継続的にモニタリングすることが不可欠です。
- 作業内容の変更や天候の変化に応じて、柔軟に測定頻度を増やすことも検討しましょう。
WBGT値と気温・湿度データを組み合わせた熱中症リスク評価方法
WBGT値は非常に有効な指標ですが、気温や湿度といった基本的なデータと併用することで、より多角的にリスクを評価し、きめ細やかな対策を講じることができます。
例えば、WBGT値がまだ警戒レベルに達していなくても、湿度が異常に高い場合は、発汗による体温調節機能が低下しやすいため、より注意が必要です。
また、風が弱い日は体感温度が高くなりやすいため、WBGT値と合わせて風の状況も考慮すると良いでしょう。
これらのデータを複合的に見て判断することで、「数値だけでは見えない危険」を察知し、先手を打った対策が可能になります。
測定値から導く現場での熱中症対策|具体的行動ルールの作り方
せっかく測定したWBGT値や気温が、具体的な行動に結びつかなければ意味がありません。
測定結果に基づいて「何を」「いつ」「誰が」行うのか、あらかじめ明確な行動基準を定めておくことが非常に重要です。
厚生労働省は、WBGT値に応じた作業中止や休憩取得の目安を提示しています。これらを参考に、自社の作業内容や現場の特性に合わせて、具体的なルールを策定しましょう。
WBGT値と推奨される行動基準
| WBGT値(℃) | 熱中症の危険度と推奨される行動の目安 |
|---|---|
| 31以上 | 危険 運動は原則中止。特別の場合以外は運動を中止すべき。特に子どもの場合は中止。高齢者は安静状態でも危険性が大きい。 |
| 28以上31未満 | 厳重警戒 熱中症の危険性が高い。激しい運動や持久走など、体温が上昇しやすい運動は避ける。頻繁に休憩をとり、水分・塩分を補給する。 |
| 25以上28未満 | 警戒 熱中症の危険が増す。積極的に休憩を取り、適宜、水分・塩分を補給する。激しい運動では30分おきくらいの休憩が目安。 |
| 21以上25未満 | 注意 熱中症による死亡事故が発生する可能性もある。熱中症の兆候に注意し、運動の合間に積極的に水分・塩分を補給する。 |
| 21未満 | ほぼ安全 通常は熱中症の危険は小さいが、適宜水分・塩分補給は必要。市民マラソンなどではこの条件でも熱中症が発生することがある。 |
行動基準の具体的な策定と周知
この基準を基に、「WBGT値が〇℃を超えたら、〇分休憩を〇回追加する」「〇℃以上になったら、屋外作業を〇時間に短縮する」といった具体的な指示を明文化し、関係者全員に周知徹底しましょう。
さらに、体調不良者が出た際の連絡フローや、応急処置の手順も併せて明確にしておくことで、迅速かつ適切な対応が可能になります。
WBGT値の測定と、それに基づく具体的な行動基準の策定・実行は、熱中症から労働者を守るための強力なツールとなります。
熱中症リスクを下げる作業時間と休憩の管理方法
高温多湿な環境下での作業は、労働者の身体に大きな負担をかけます。
熱中症予防のためには、作業内容や環境に応じた適切な作業時間・休憩時間の運用が不可欠です。
単に休憩を取るだけでなく、その質を高めることが重要になります。
現場で使える!WBGT値に応じた効果的な休憩・作業スケジュール
労働安全衛生法では休憩時間に関する一般的な規定がありますが、熱中症リスクが高い時期・場所においては、よりきめ細やかな配慮が必要です。
WBGT値や気温、湿度などの測定結果に基づき、作業負荷や環境に応じた休憩時間の設定を検討しましょう。
- WBGT値に応じた休憩の目安
- 厚生労働省が示すWBGT値の基準を参考に、例えば「WBGT値が28℃を超えたら、作業30分ごとに10分以上の休憩を義務付ける」といった具体的なルールを設けることが有効です。
- 作業負荷の考慮
- 重労働や集中力を要する作業など、身体的・精神的負荷が高い作業の場合は、WBGT値が比較的低くても休憩頻度を増やす、または作業時間を短縮するなどの調整が必要です。
熱中症対策|体調に応じた臨時休憩の取り方と奨励方法
休憩は、あらかじめ決められた時間だけでなく、作業員自身の体調変化に応じて柔軟に取得できる環境が重要です。
「まだ大丈夫」という過信や、周囲への遠慮から休憩をためらうことがないよう、企業として積極的に臨時休憩の取得を奨励しましょう。
- 自己申告の徹底
- 作業員が少しでも体調に異変を感じたら、すぐに作業を中断し、管理者に報告できる体制を整えましょう。
- そのためには、日頃から「無理はしない」というメッセージを伝え、安心して申告できる雰囲気作りが不可欠です。
- 管理者の声かけと観察
- 管理者は、定期的に作業員に声かけを行い、顔色や動き、発汗の様子などから体調の変化を早期に察知するよう努めましょう。
- 異変が見られた場合は、積極的に休憩を促す、または作業から離脱させる判断が求められます。
熱中症対策の休憩環境|涼しい場所と水分・塩分補給の整備方法
休憩は、単に作業を中断するだけでなく、熱を効果的にクールダウンできる場所で行うことが重要です。
- 涼しい休憩場所の確保
- 日陰や空調の効いた屋内、送風機やミストシャワーを設置した場所など、体温を下げられる環境を確保しましょう。
- 屋外作業の場合は、移動式の休憩所やテントの設置も検討が必要です。
- 水分・塩分補給の提供
- 冷たい水やスポーツドリンク、塩飴などを、作業員がいつでも自由に補給できる場所に十分に用意しましょう。
- 自動販売機の設置や、定期的な巡回による提供も有効です。
- 冷却グッズの活用
- 首元を冷やすタオル、冷却ベスト、携帯扇風機など、個人で利用できる冷却グッズの導入や推奨も、休憩時のクールダウンを助けます。
熱中症リスクを下げる作業負荷の軽減策|作業内容・人員配置の工夫
作業環境や休憩時間の調整だけでなく、作業そのものの負荷を軽減することも、熱中症予防には欠かせません。
- 作業内容の見直し
- 炎天下での作業や重労働は、可能な限り涼しい時間帯(早朝や夕方)に移行する、または屋内で実施できる作業に切り替えるなどの工夫をしましょう。
- 人員配置の調整
- 一人あたりの作業負荷を減らすため、人員を増やす、または交代制を導入して、連続作業時間を短縮することを検討しましょう。
- 機械化・自動化の推進
- 人力に頼る作業を機械やロボットに代替することで、労働者の身体的負担を軽減し、熱中症リスクを低減できます。
まとめ|現場で役立つ熱中症対策のポイント総括
ここまで、熱中症対策におけるWBGT値の活用、そして作業時間・休憩時間の効果的な運用について掘り下げてきました。
これらは、現場の物理的な環境と労働の負荷を管理し、熱中症リスクを軽減するための重要な基盤となります。
しかし、真に労働者の安全を守るためには、一人ひとりの状況に合わせた個別のアプローチが欠かせません。
次回予告|高リスク労働者への熱中症対策チェックリストを解説
次の記事では、高齢者や体調不良者への具体的な配慮、について解説していきます。
お楽しみに。
次回の記事は👉高齢者・体調不良者向け|現場で実践|熱中症リスク管理の最小化
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。
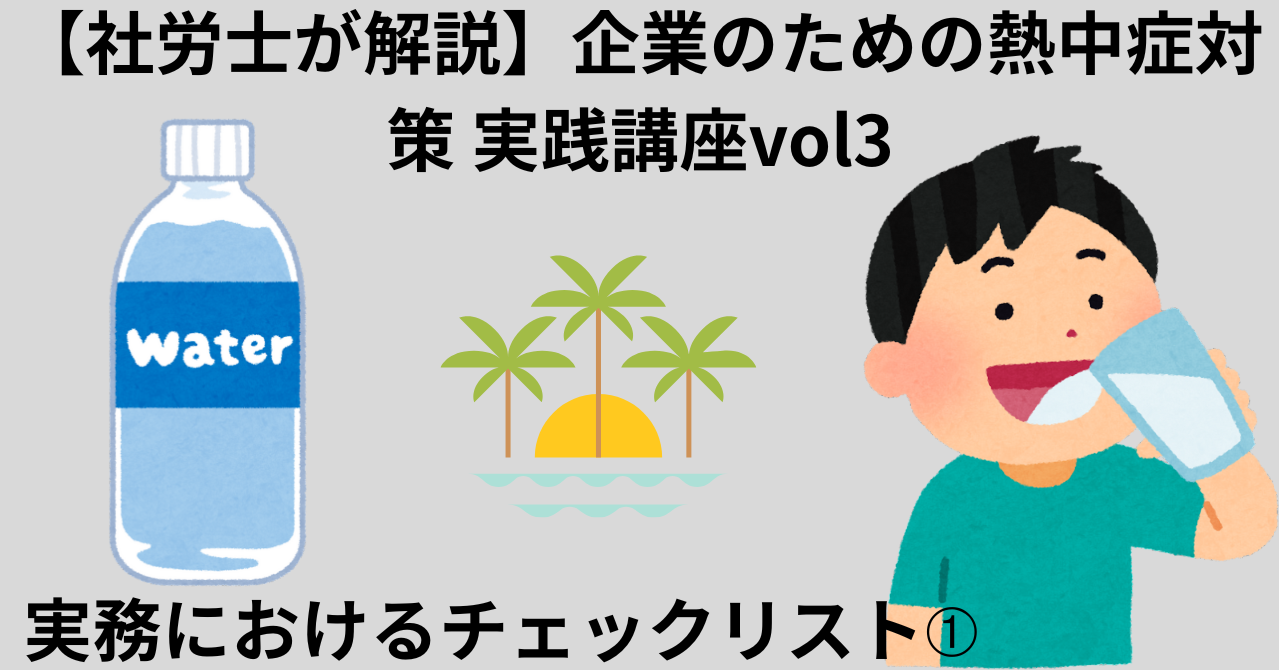

コメント