副業社労士の戸塚淳二です。いつもご拝読ありがとうございます。さて、「静かな退職」に関する考察もいよいよ大詰め、今回で4回目となります。
静かな退職シリーズの記事です。👇
- 静かな退職とは?やりがい搾取の終わりと現代の働き方(副業社労士の考察1)
- 静かな退職がもたらす影響 個人と企業、光と影の真実(副業社労士の考察2)
- 静かな退職は企業の「ツケ」?「合成の誤謬」の落とし穴(副業社労士の考察3)
- 「静かな退職」を乗り越える 企業が従業員の「合理性」を再構築(副業社労士の考察4)👈今回の記事です。
今回で終えられるような感覚がしています。あくまで私の個人的な考察ですので、悪しからず。
前回、私たちは「静かな退職」が単なる個人の「やる気」の問題ではなく、企業が長年積み重ねてきた「ツケ」であると指摘しました。
そして、この現象が社会全体に広がった際に起こりうる「合成の誤謬」、つまり個人にとって合理的な行動が社会全体では不合理な結果を招く可能性についても触れました。
誰もが「必要最低限」に留まることで、最終的にその影響がブーメランのように自分自身を傷つけることになりかねない、と。
静かな退職に対応する企業の合理性再構築|従業員のモチベーション向上策
前回の記事でも申し上げた通り、「個人を変える」のではなく、「企業が変わるべき」という大前提は揺るぎません。
その上で、企業は、単に福利厚生や勤務形態といった表面的な制度を変えるだけでは不十分だと思います。
従業員が「会社で頑張ることが、結果的に自分にとって最も得策であり、幸せに繋がる。」と心から思えるよう、その「合理性の物差し」自体を企業が作り替え、従業員に示していく責任があると考えています。
短期的な合理性から脱却|静かな退職時代に企業が示すべき長期的な合理性
現在の「静かな退職」に見られる個人の「合理的」な行動は、多くの場合、「心身の疲弊から身を守る」「コスパ良く働く」といった、目の前の状況に対応する短期的な合理性に根ざしています。
しかし、この短期的な合理性が、本当に長期的な個人の幸福やキャリア形成に繋がるのか、という問いを企業が従業員と共に考える必要があるのです。
例えば、少子化問題を考えてみましょう。個々人が子どもを持たない選択をすることが、経済的負担やキャリアへの影響を考慮すれば「合理的」とされがちです。
しかし、もし、子どもを持つことが個人にとって経済的、精神的、社会的に「メリット」を強く感じられるような社会環境が整備されたなら、個人の選択と社会全体の目指す方向は一致しやすくなるはずです。
これと同じ構造を、企業と従業員の関係にも当てはめるべきだと考えます。
企業は、従業員が「企業内での頑張りや貢献が、単なる消耗ではなく、自身の幸福や将来の利益に直結する。」という、より広い意味での「合理性」を自ずと認識できるよう、環境と仕組みを整える責任があるのです。
企業がすべきこと|従業員の合理性を長期視点で再定義して静かな退職に備える
この新たな「合理性」を従業員に認識してもらい、企業と個人のベクトルを一致させるためには、企業が具体的な行動を起こすことが不可欠です。
従業員の努力が報われる仕組みを可視化|静かな退職対策としての評価と保証
- 「どうせ頑張っても報われない。」という従業員の諦めを払拭するためには、企業が「頑張りが正当に評価され、報われる」仕組みを明確にし、それを運用する責任を果たす必要があります。
- 公正で透明性の高い評価制度の確立
- どのような行動や成果が評価に値するのかを明確にし、評価基準とプロセスをオープンにすることで、従業員は納得感を持って業務に取り組めるようになります。
- 年功序列に偏らず、個々のパフォーマンスやスキルアップを正当に評価し、賃金に反映させる仕組みが必要です。
- 成果に応じた報酬と昇進機会の提供
- 貢献度に応じたインセンティブや、明確な昇進・昇格の機会を設けることで、「頑張れば報われる」という実感を伴った「合理性」を従業員に提供します。
- 公正で透明性の高い評価制度の確立
キャリアパスを明確化し成長機会を提供|静かな退職を防ぐ人材育成戦略
- 終身雇用の崩壊が囁かれる現代において、従業員は自身のキャリアに対する不安を抱えています。
- 企業は、その不安を解消し、長期的な視点での「合理性」を見出せるよう支援すべきです。
- 多様なキャリアパスの提示
- 管理職への昇進だけでなく、専門職としての道や、社内での部署異動、さらには副業を奨励するなど、多様なキャリアパスを提示することで、従業員が自身の未来を具体的にイメージできるよう支援します。
- 継続的な学習・スキルアップ支援
- 研修制度の充実、資格取得支援、社内勉強会の開催などを通じて、従業員が自身のスキルや市場価値を高められる機会を提供します。
- これは、従業員が会社に貢献するだけでなく、自身の将来への投資だと捉えられる「合理的」な選択肢となります。
- 多様なキャリアパスの提示
従業員エンゲージメントを高める環境作りと仕事の意味付け|静かな退職対策
- 従業員が「やらされ仕事」と感じるのではなく、自身の仕事に意味を見出し、主体的に取り組めるような環境を醸成することも重要です。
- パーパス(存在意義)・ビジョンの浸透
- 企業が何のために存在し、何を成し遂げようとしているのか、その中で個人の仕事がどう社会や顧客に貢献するのかを、具体的に、そして継続的に伝えることで、単なる業務を超えた「意味」を従業員が感じられるようにします。
- 適切な裁量とフィードバック
- 従業員に一定の裁量を与え、自律的に業務を進める機会を提供することで、仕事へのオーナーシップを高めます。また、定期的なフィードバックを通じて、自身の貢献がどのように評価され、次なる成長に繋がるのかを実感させることが重要です。
- パーパス(存在意義)・ビジョンの浸透
静かな退職の警鐘を経営改革に活かす|従業員主体の未来志向経営
これまで4回にわたり、「静かな退職」という現象について考察してきました。
これは決して一過性のブームではなく、日本の労働環境、ひいては社会全体の構造的な課題が顕在化したものだと私は考えています。
「静かな退職」は、従業員からの「もうこれまでと同じやり方では通用しない」という明確なメッセージです。
この警鐘を真摯に受け止め、企業が率先して従業員の「合理性」を再定義し、その上で働きがいや成長を実感できる環境を再構築すること。これこそが、企業が持続的に成長し、変化の激しい時代を乗り越えていくための唯一の道です。
従業員を単なる労働力として「使い捨て」にする時代は完全に終わりを告げました。
これからの企業経営は、いかに従業員一人ひとりの潜在能力を引き出し、彼らが「会社で頑張ることが、自分自身の豊かな人生に繋がる。」と心から思えるような、企業と個人のWin-Winの関係を築けるかにかかっています。
「静かな退職」という現象は、確かに企業にとって大きな課題です。
しかし、同時に、これまでの慣習を見直し、より良い未来を創造するための絶好の機会でもあります。この機会を逃さず、企業が変革の旗手となることを強く願ってやみません。
このシリーズが、読者の皆様にとって、この現象を多角的に捉え、ご自身の職場やキャリアについて考える一助となれば幸いです。
- 「静かな退職」について深く知るなら、以下の調査結果が参考になります。Great Place To Work®の**「静かな退職に関する調査2025年」**では、その実態や対策時期を詳細に分析 (👉 https://hatarakigai.info/news/2025/0304_3848.html)。
- マイナビキャリアリサーチLabの特集ページでは、定義から年代別の意識まで多角的に解説 (👉 https://career-research.mynavi.jp/column/feature/quiet_quitting/)。
- さらに、パーソル総合研究所の提言では、「静かな退職者」を4パターンに分類し、具体的なマネジメント方法を提案しています (👉 https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/column/202506160001.html)。
長らくのご拝読、誠にありがとうございました。
他のテーマの記事も是非ご覧ください。👉奈良の社労士|戸塚淳二労務相談室|企業と働く人のためのブログ

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|29240010号)
- 会社員歴30年以上、転職5回を経験した氷河期世代の社会保険労務士です。自らが激動の時代を生き抜いたからこそ、机上の空論ではない、働く人の視点にたった情報提供をモットーとしています。あなたの働き方と権利を守るために必要な、労働法や社会保険の知識、そしてキャリア形成に役立つヒントを、あなたの日常に寄り添いながら、分かりやすく解説します。
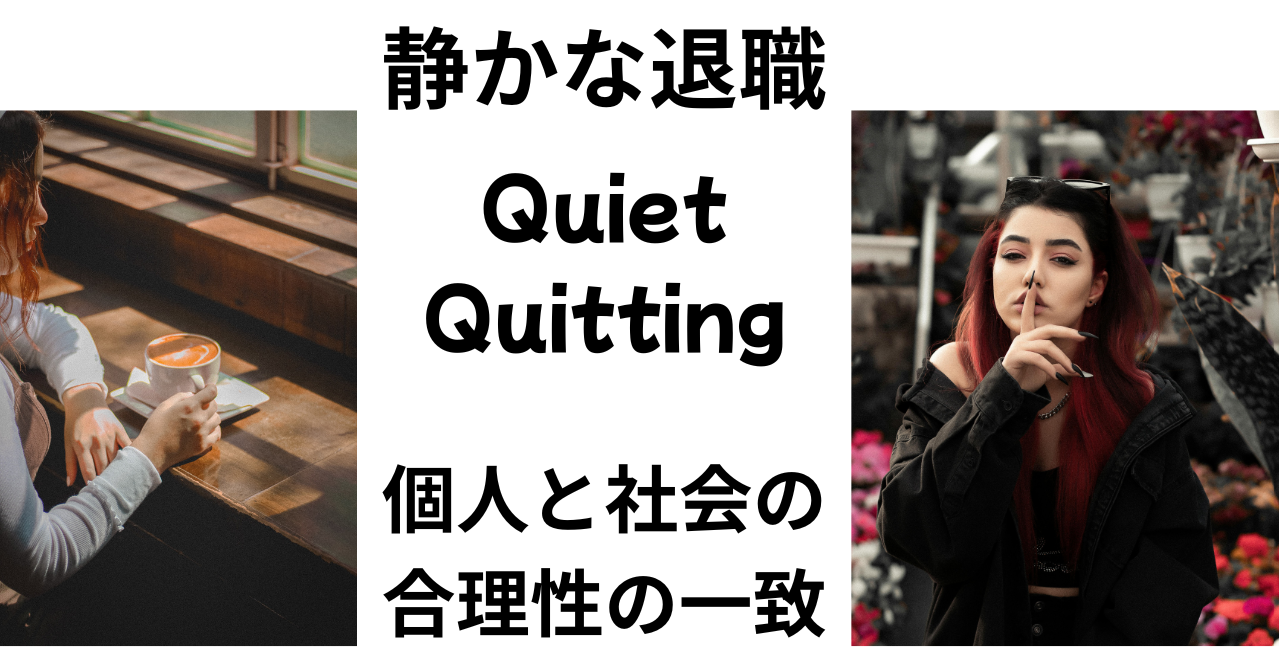
コメント