副業社労士の戸塚淳二です。毎度ありがとうございます。「静かな退職」に関して書いておりますが、今回で3回目です。次回くらいで終われるような感じがしてます。あくまで私の個人的な考察ですので、悪しからず。
静かな退職シリーズの記事です。👇
- 静かな退職とは?やりがい搾取の終わりと現代の働き方(副業社労士の考察1)
- 静かな退職がもたらす影響 個人と企業、光と影の真実(副業社労士の考察2)
- 静かな退職は企業の「ツケ」?「合成の誤謬」の落とし穴(副業社労士の考察3)👈今回の記事です。
- 「静かな退職」を乗り越える 企業が従業員の「合理性」を再構築(副業社労士の考察4)
前回は「静かな退職」が個人と企業に与える具体的な影響を、その光と影の両面から考察しました。
この現象が、個人の「やる気の問題」だけでは片付けられないことは、ご理解いただけたかと思います。では、この「静かな退職」を、私たちはこのまま看過して良いのでしょうか?
私、副業社労士の戸塚淳二は、「静かな退職」はただの個人の働き方の変化にとどまらず、今の日本社会が抱える深い課題のひとつじゃないかと感じています。
だからこそ、ちゃんと向き合っていく必要があると思うんです。
個人の問題ではない「静かな退職」|企業が変革すべき時
この「静かな退職」が蔓延する現状を見て、「最近の若者は…」「働きがいがないなら辞めればいい」といった声も耳にします。
しかし、私は、個人の生き方や考え方だけを変えようとするアプローチは、根本的な解決には繋がらないと考えています。
なぜなら、この現象の根底には、企業が長年積み重ねてきた「ツケ」が今、回ってきているという側面が色濃くあると思うからです。
日本企業の旧来型働き方が招く静かな退職の原因
高度経済成長期からバブル期にかけて、多くの日本企業は「モーレツ社員」を是とし、長時間労働や滅私奉公を美徳とする文化を築き上げてきました。
「24時間戦えますか?ビジネスマーン、ビジネスマーン、ジャパニーズビジネスマーン♪」というCMも流れていましたが、今思えばシャレになりません。
年功序列や終身雇用を背景に、従業員は会社に人生を捧げることで、将来の安定と引き換えにしてきたのです。しかし、時代は変わりました。
- 「やりがい搾取」の常態化
- 成果に見合わない低賃金での過重労働や、精神論で乗り切らせようとする姿勢が、若手を中心に「やりがい搾取」として認識され、不信感を生んでいます。
- キャリアの不透明性
- 終身雇用が崩壊し、会社の成長が鈍化する中で、「頑張っても報われない」「出世の道が見えない」と感じる従業員が増えました。
- 個人の価値観の多様化
- 仕事以外の人生の充実を求める声が高まり、会社中心の生き方に疑問を抱く人が増えました。
労働力不足時代に終わる「辞めたら代わりはいる」文化と「静かな退職」
このような状況に加え、少子高齢化による労働力人口の減少と慢性的な人材不足が深刻化しています。
かつてのような豊富な労働力があれば、企業は「辞めるなら代わりはいくらでもいる」という態度も取れたかもしれません。
しかし、今はそうはいきません。
企業は、これまで従業員に無理をさせてきたことの「ツケ」が、まさに「静かな退職」という形で回ってきているという現実を直視すべきなのです。
従業員を「使い捨て」のように扱ってきた結果、若者は会社に期待しなくなり、中高齢層は「もう会社のために頑張るのはやめよう」と割り切るようになりました。
企業側が従業員の「やりがい」や「成長」を本気で考えず、短期的な利益追求やコスト削減ばかりに目を向けてきた代償が、この「静かな退職」の広がりとして現れているのです。
だからこそ、今、企業側こそが大きく変わるべき時なのです。
静かな退職と合成の誤謬|個人の選択が社会に与える影響
しかし、この「静かな退職」が社会全体に広がったとき、私たち個人の行動にも、思わぬ落とし穴が潜んでいる可能性も否定できません。それが経済学でいうところの「合成の誤謬(ごびゅう)」です。
合成の誤謬とは、「個人にとっては合理的な行動でも、それが多くの人に広がることで、社会全体としては不合理な結果を招く」という考え方です。
この問題は、まさに今の日本で問題となっている「少子化」や「人口の一極集中」などと全く同じ構図になっているような気がしています。
「静かな退職」を選ぶ個人にとっては、心身の健康を守り、ワークライフバランスを改善する合理的で健全な選択です。
静かな退職が広がったときに起こる合成の誤謬のメカニズム
しかし、もし多くの人が「必要最低限の仕事しかしなくなる」という選択をしたとしたら、どうなるでしょうか?
- 企業全体の生産性は確実に低下し、競争力は失われます。
- 新しいイノベーションは生まれにくくなり、社会全体の活力が失われる可能性があります。
- 結果として、企業の業績悪化に繋がり、給与水準の低下や、最悪の場合はリストラや倒産といった形で、結局は私たち個人の生活にも悪影響が及ぶ可能性があります。
誰もが自分にとって最も合理的だと思う行動をとること(例えば必要最低限の業務に留めるという選択)で、社会全体が停滞し、最終的にその影響がブーメランのように自分のところに戻ってきます。そして「自分自身」を傷つける、ということになりかねません。
個人も主体的にキャリア戦略を見直す時代|静かな退職を考える
もちろん、これは「また個人に頑張れと言うのか」という話ではありません。企業が変わるべき大前提は揺るぎません。
しかし、私たち個人も、企業に変化を求めるだけでなく、この「合成の誤謬」の可能性を認識し、自身の「静かな退職」という選択が、巡り巡って自分自身や社会にどう影響するかを、より広い視点で考える必要性があるのではないでしょうか。
例えば、
- 必要最低限の業務をこなす中でも、自身のスキルアップや市場価値向上には意識的に投資を続ける。
- 「会社に依存しない」という意識を持つ一方で、自身の専門性を高め、社会への貢献を意識する。
- 副業などで自身の多角的なキャリアを築き、リスク分散を図る。
静かな退職を機に描く、働き方とキャリアの戦略的プラン
企業が変わることを強く求めつつも、私たち個人も、ただ「静かに退職」するだけでなく、自身のキャリアや人生を主体的にデザインし、変化する社会の中でどう立ち位置を確立していくか、より戦略的な視点を持つことが求められているのかもしれません。
- 「静かな退職」について深く知るなら、以下の調査結果が参考になります。Great Place To Work®の**「静かな退職に関する調査2025年」**では、その実態や対策時期を詳細に分析 (👉 https://hatarakigai.info/news/2025/0304_3848.html)。
- マイナビキャリアリサーチLabの特集ページでは、定義から年代別の意識まで多角的に解説 (👉 https://career-research.mynavi.jp/column/feature/quiet_quitting/)。
- さらに、パーソル総合研究所の提言では、「静かな退職者」を4パターンに分類し、具体的なマネジメント方法を提案しています (👉 https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/column/202506160001.html)。
さてさて、またまた長くなってしまいましたね。
次回からは、いよいよ「静かな退職」に対する企業側の具体的な対策について深掘りしていきたいと思います。このまま放置すればどうなるのか、そして企業は何をすべきなのか。
次回の記事は👉「静かな退職」を乗り越える 企業が従業員の「合理性」を再構築(副業社労士の考察4)
では、また。ご拝読ありがとうございました。
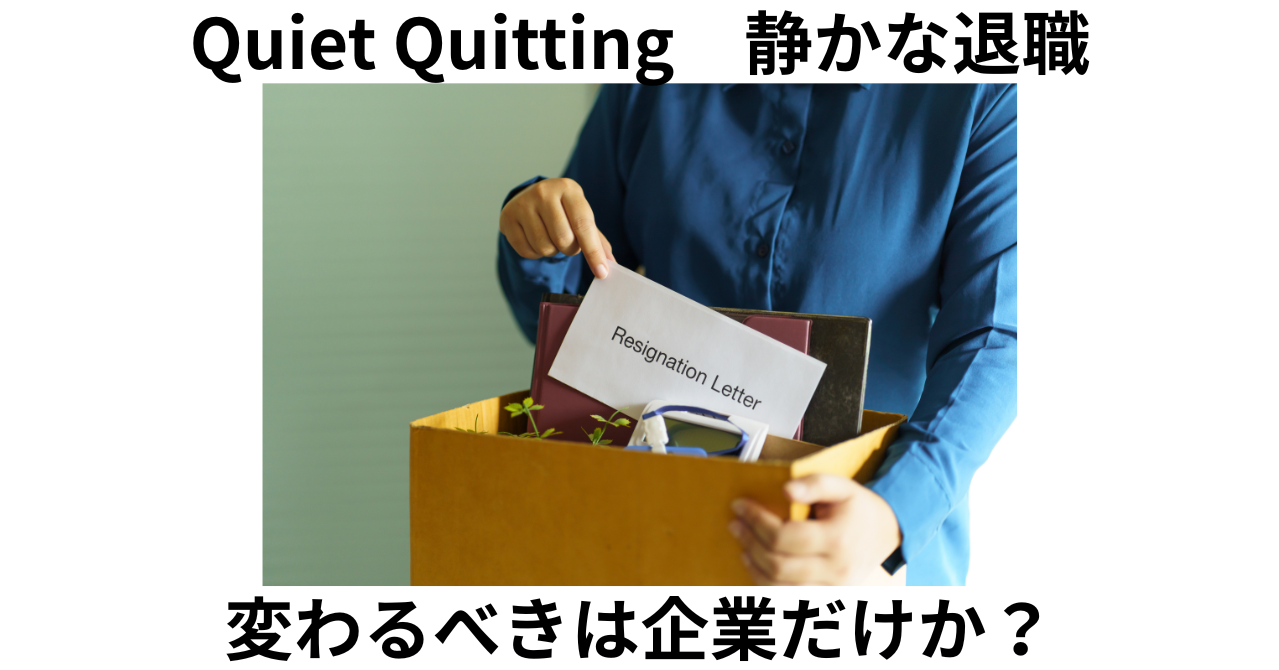
コメント