本記事は「2025年改正育児介護休業法シリーズ」の第11弾です。他のシリーズの記事はコチラから👉2025年育児介護休業法改正|企業がすべき対応と助成金情報
前回の記事では、男性の育児休業等取得状況の公表に関して「どこで公表すればよいのか?」についてご紹介しました。
前回の記事は👉男性の育児休業取得状況|公表場所と公表方法|2025年改正対応
今回はその続きをテーマに、「いつまでに」「どのような形で」公表すればよいのか?実務で迷いやすいポイントを整理しながら、わかりやすく解説していきます。
公表義務の対象となる企業が増える中で、対応のタイミングや正しい書き方を把握しておくことは非常に重要です。
ぜひ、この記事をチェックリスト代わりにご活用ください。
法改正の詳しい内容は👇

男性の育児休業取得状況|公表タイミングと実務のポイント
2025年の改正では、「毎事業年度ごとに公表すること」が義務づけられています。
基準年度の決め方と対象期間
対象となるのは、「公表前事業年度」、すなわち直近の会計年度における取得実績です。
たとえば、2025年4月~2026年3月が事業年度の企業であれば、2026年4月以降に2025年度の取得状況を公表する義務が発生します。
男性育休取得状況の公表期限|いつまでに対応すべきか
法律では明確な「期限」は設けられていないものの、可能な限り速やかに公表することが求められています。
一般的には、決算報告や事業報告とあわせて6月末までに公表するケースが多く、これが実務上の目安とされています。
- 実務ポイント
- 決算確定後、数値の集計と確認を行い、6月末〜7月初旬にはウェブサイトに掲載する流れを組んでおくとスムーズです。
- 公表日を毎年固定する(例:6月30日など)ことで、社内の作業効率化にもつながります。
育児休業取得状況の掲載期間|公表情報はいつまで表示すべきか
法令上、公表した内容の掲載期限は明記されていません。
しかし、一般的には「次回の公表まで」情報を維持することが望ましいとされています。つまり、前年分の取得率は最低1年間は閲覧可能な状態を保つことが適切です。
- 【注意点】
- 情報の更新がなかった場合も「更新日」や「最新の公表時期」を明記しておくと、透明性が高まります。
- 過去分のアーカイブを残しておくと、求職者や社内からの問い合わせにも対応しやすくなります。
男性の育児休業等取得状況|公表すべき内容と実務上のポイント
公表前事業年度の期間|男性育児休業取得状況の対象年度
- 意味
- 「取得割合」を算出する対象期間です。直近の事業年度(たとえば、2025年4月1日〜2026年3月31日など)を明記する必要があります。
- ポイント
- 暦年ではなく事業年度ベースで記載する。
- 「○年○月○日~○年○月○日」と正確な開始日・終了日を記載。
- 会社の定款や決算期に合わせて設定。
育児休業等の取得割合と育児目的休暇を含めた取得率|男性社員向け
- どちらか一方を公表すればOK
- 育児休業等の取得割合
- 育児休業等および育児目的休暇の取得割合
- 公表例(厚労省の例)
- 育児休業等の取得割合:30.5%
- 育児休業等及び育児目的休暇の取得割合:45.0%
算出方法
分母に含めるのは「育児休業の対象となる男性労働者」
つまり…
「公表前事業年度の開始日から終了日までに在籍していた、配偶者が出産した男性労働者」が対象になります。
分子に含めるのは「実際に育児休業を取得した男性労働者」(日数の長短は問わない・1日でも取得すればよい)
育児休業等(+育児目的休暇)を取得した男性労働者数 ÷ 配偶者が出産した男性労働者数 × 100
具体例で説明します。
仮に、ある会社に男性社員が100人いて、そのうち 「その年度に配偶者が出産した人」が10人いたとします。その10人のうち、5人が実際に育児休業を取得した場合は――
- 分母:10人
- 分子:5人
- 5人÷10人×100=50
- よって、育児休業取得割合は 50.0%
よくある誤解(NG例)
「全男性社員100人中5人が育休取った → 5%」
→ これは誤りです!
なぜなら…
配偶者が出産していない社員はそもそも「育児休業取得の対象者ではない」からです。
用語の補足
「配偶者が出産した男性労働者」
事業年度内に配偶者が出産した男性社員の数。本人が既に退職していても対象期間内に該当すれば含めることがある。
育児休業(いわゆる「育休」)
- 育児休業
- 原則1歳まで、一定条件で2歳まで延長可能
- 出生時育児休業(いわゆる「産後パパ育休」)
- 子の出生後8週間以内に最大4週間取得可能(分割可)⇨ここまでの2項目は育児休業(いわゆる「育休」)に含まれる
- 有給休暇(育児目的での使用)
- 年休で休暇を取得し、育児に充てたものは、育児休業(いわゆる「育休」)には含まれない
育児休暇(この言葉が指す内容は実は2つあります)
「育児休暇」という言葉は、制度上は正式な用語ではありませんが、実務上でいろいろな意味で使われることがあり、混乱を招いています。
この言葉(育児休暇)が表す内容は以下の2つです。
結論を先に申し上げますと「男性の育児休業等+育児目的休暇」の取得率の計算に入れるのは、1番目の会社独自の「育児目的休暇」です。2番目の法定の「子の看護休暇」は入りません。
- 会社独自の「育児目的休暇」
- このような会社独自の育児休暇は、有給であることが多いですが、それも企業の裁量です。
- 企業が任意に制度化する有給の特別休暇
- 法律で義務付けられているわけではない(= 努力義務や自主的な制度)
- 例:子どもの予防接種・学校行事・体調不良の付き添いなどのために、有給の休暇を設けるケース
- 法的根拠:育児・介護休業法 第24条の2(努力義務として「育児目的休暇制度の導入が望ましい」と規定)
- このような会社独自の育児休暇は、有給であることが多いですが、それも企業の裁量です。
- 法定の「子の看護休暇」
- こちらは法律上定められている「休暇」ですが、有給である必要はなく、企業によっては有給扱いにしている場合もあります。
- 法的に定められた無給の休暇
- 育児・介護休業法 第16条の2
- 小学校3年生修了前までの子どもを養育している従業員が、看病や予防接種などのために使える
- 年間5日(子が2人以上の場合は10日)まで取得可
- 正社員だけでなく、パートなど有期契約の方にも適用されます(要件あり)
- こちらは法律上定められている「休暇」ですが、有給である必要はなく、企業によっては有給扱いにしている場合もあります。
公表に必要なデータとは?|男性の育児休業等取得状況
2025年4月以降の改正法により、企業が公表する際には、次の2パターンのいずれかで公表しなければなりません。
必要な数字は、配偶者が出産した男性労働者/育児休業等を取得した男性労働者/育児目的休暇を取得した男性労働者数です。
| 公表方法 | 公表に含める内容 | 育児休業等の意味づけ |
|---|---|---|
| ① 法定制度の取得率 | 育児休業+出生時育児休業 | 上記「育児休業等」の定義そのまま |
| ② 法定制度+育児目的休暇の合算 | 育児休業+出生時育児休業+企業独自の育児目的休暇 | この場合、「育児休業等」という語には含まれず、「育児休業等および育児目的休暇」として別途明示する必要があります |
公表用テンプレート|男性育休取得率の記載例と入力方法
以下のようなExcel項目を設定すれば、厚労省の公表様式に準じた内容になります。
| 項目 | 内容記入欄 | 備考 |
|---|---|---|
| 企業名 | ○○株式会社 | 事業者名 |
| 公表前事業年度の期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 | 決算期等により調整 |
| 育児休業等(+会社独自の育児目的取得)の取得割合(男性) | 33.3% | 小数第1位まで推奨 |
| 算出方法 | 取得者数 ÷ 配偶者が出産した男性労働者数 × 100 | 正確に記述 |
| 備考 | 取得者数:3人/配偶者が出産した男性労働者数:9人 | 任意で補足 |
企業が行うべき次のステップ|男性育児休業取得状況の公表準備
- 上記テンプレートに基づいて自社の数値を入力
- そのまま自社のホームページに張り付けてもいいです。
- 「両立支援のひろば」にログインし、該当箇所に入力
- 自社の行動計画・取組を登録・修正する ⇦こちらからログインして該当箇所に入力
- 公表完了後、自社HPなどに転載するのもOK
男性育児休業等取得状況の公表で企業が押さえるべきポイント
企業によっては、「育休を取得した男性3人のうち、1人は1か月、1人は2週間、1人は3か月」といった情報まで公表したいというケースもあります。
しかし、こうした個別の取得期間や取得者数の内訳までは、法的な公表義務の対象外です。
このような詳細な情報は、公表「してもよい」が「する必要はない」と思います。
詳細に書くことで透明性は高まるが、企業リスクも意識すべき
取得実績をより具体的に示すことで、「男性もちゃんと長く育休を取っている」「企業として柔軟な支援をしている」ことをアピールできる可能性はあります。
ただし、以下のような懸念点もあります
- 対象者が少ない企業では個人の特定につながるおそれ
- 年によって取得状況にばらつきがある場合、ネガティブに受け取られる可能性
- 過度な情報提供により、個人情報やプライバシーの問題が発生することも
したがって、取得者の人数や期間などの詳細情報を積極的に公表する必要はありません。
あくまで公表義務を満たすためには「取得率(%)」の開示で十分であり、余計なリスクを避けたい場合は簡潔な記載にとどめるのが無難です。
まとめ|男性の育児休業等取得状況の公表ポイント
本記事では、男性の育児休業等取得状況の「いつまでに」「どのような形で」公表すればよいのかについて、実務で迷いやすいポイントを中心に詳しく解説しました。
算出方法の誤解や、育児目的休暇との違いなど、現場でつまずきやすい点にフォーカスして整理しましたので、実際の公表準備にぜひご活用ください。
次回予告|育児期社員へのテレワーク対応の実務ポイント
さて、次回は改正法のもう一つの注目ポイント、「3歳未満の子を養育する労働者に対するテレワークの選択肢提供(※努力義務)」について取り上げます。
次回の記事は👉テレワーク導入と運用のコツ|3歳未満の子を持つ社員への提供
こちらも、「実務でどう対応すればよいのか?」に重点を置いて、チェックリスト的に整理していきますので、ぜひ次回もお読みください!
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。
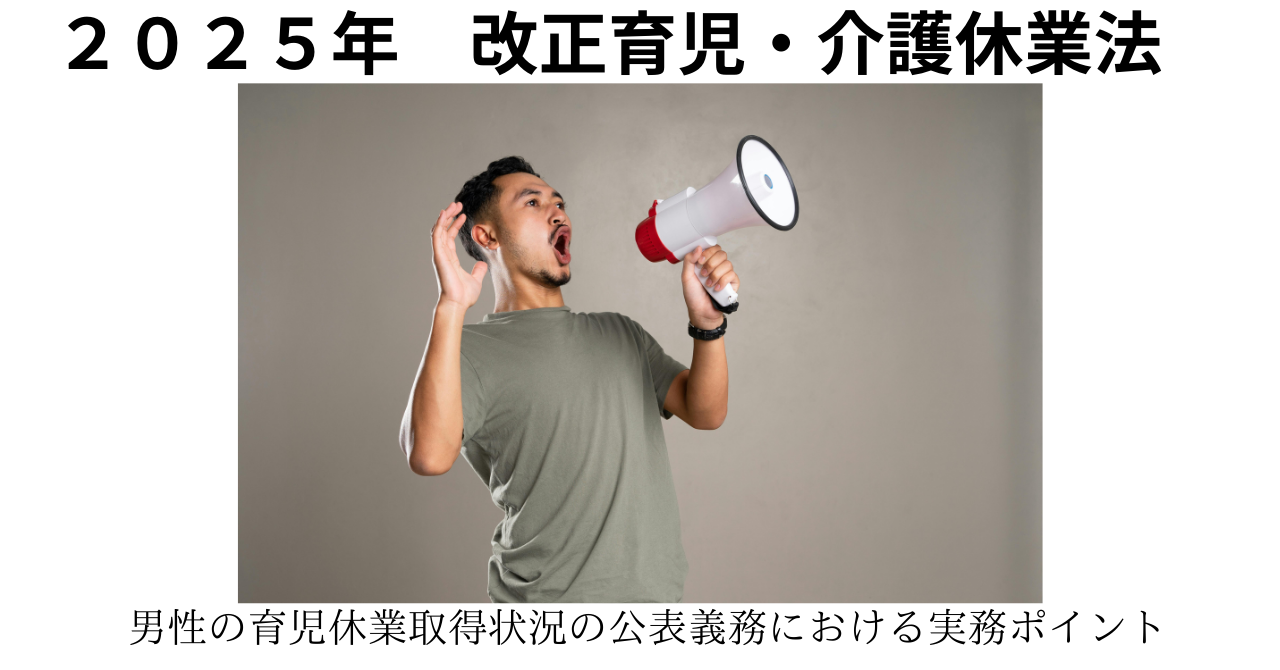

コメント