本記事は「2025年改正育児介護休業法シリーズ」の第42弾です。他のシリーズの記事はコチラから👉2025年育児介護休業法改正|企業がすべき対応と助成金情報
前回は、男性従業員の育児休業取得を支援する「出生時両立支援コース(第1種)」について、その目的から具体的な申請要件、手続きまでを詳しく解説しました。
前回の記事は👉出生時両立支援コース|第1種(育児取得時)助成金の申請手順
この助成金が、単に資金を受け取るだけでなく、男性の育児参加を促し、職場環境を根本から改善するための強力なツールであることをご理解いただけたかと思います。
しかし、助成金制度は「育休を取ったとき」だけで終わりではありません。
育休を終えた従業員がスムーズに職場に復帰し、その後も安心して働き続けられる環境を整えることこそが、企業の持続的な成長には不可欠です。
そこで今回は、育休からの円滑な職場復帰を支援する「第2種(職場復帰時)」に焦点を当てて解説します。
さらに、第1種と第2種を組み合わせ、男性従業員の育休取得から職場復帰までのプロセス全体を、時系列に沿ったロードマップとしてご紹介します。
このロードマップを通じて、貴社がこの制度を最大限に活用し、真に働きやすい職場を築き上げるための一助となれば幸いです。
この記事で分かること
- 第2種(職場復帰時)は、育休からの「原職復帰」と「6か月以上の継続雇用」が受給の鍵
- 中小企業向け加算が手厚く、取得率が30ポイント以上上昇(かつ50%以上達成)で最大60万円加算
- 第1種(最大30万)と第2種(最大70万)を合わせ、1社で合計100万円超の受給も可能
- 申請時期は「復帰から6か月後」の翌日から2ヶ月以内。第1種とは異なる管理が必要
- 情報公表加算(2万円)やプラチナくるみん認定加算(15万円)など、上乗せメニューの活用術
出生時両立支援コース第2種(職場復帰時)とは|助成金の概要と対象
出生時両立支援コースは、男性従業員の育児休業取得を支援する「第1種(育休取得時)」と、育休後の円滑な職場復帰を支援する「第2種(職場復帰時)」の二つのフェーズから構成されています。
第1種が男性従業員が育児休業を取得した実績を評価するものであるのに対し、第2種は育休終了後の職場定着を促すことを目的としています。
育休後の定着支援|第2種助成金の対象企業とは
この助成金の最大の目的は、単に育児休業を取得させるだけでなく、育休を終えた男性従業員が安心して職場に復帰し、長期的に働き続けられる環境を整備することにあります。
第2種の助成金の支給対象となる企業は、以下の要件を満たす必要があります。
- 男性従業員が職場に復帰していること
- 育児休業を終了した男性従業員が、元の職場または元の職務に準ずる業務に復帰していることが必要です。
- 職場復帰後も継続して6か月以上雇用されていること
- 復帰後も継続して雇用されていることを確認するため、一定期間(6か月)の勤務実績が求められます。
なお、第2種の助成金には、育児休業の日数に関する要件はありません。
短期間の育児休業であっても、取得実績として評価されます。
第2種助成金(職場復帰時)の助成金額と加算措置の具体例
第2種(職場復帰時)の助成金額は、令和5年4月1日以降の育児休業開始を対象に、一律10万円が支給されます。
さらに、中小企業のみを対象として、男性の育児休業取得を積極的に推進する企業には、以下の特定の要件を満たすことで上乗せの加算を受けることができます。
育児休業取得率上昇加算
この加算は、単に「育休を取った人がいる」だけでなく、「会社全体で男性の育休取得を積極的に増やした」中小企業を特に高く評価するものです。
具体的には、第1種を受給後、男性従業員の育児休業取得率を30ポイント以上上昇させ、かつ取得率が50%以上を達成することが条件となります。
この条件を満たした場合、達成した期間に応じて加算額が変動します。
具体的な事例
- 1年以内に成果を出した場合
- 60万円加算
- 短期間で成果を上げたA社
- 男性従業員20名(取得率15%)のA社は、積極的な取り組みの結果、1事業年度以内に12名が育休を取得し、取得率が60%に上昇しました。
- 取得率が30ポイント以上上昇し、かつ50%以上を達成したため、A社には60万円の加算が支給されます。
- 短期間で成果を上げたA社
- 60万円加算
- 2年以内に成果を出した場合
- 40万円加算
- 着実に成果を積み重ねたB社
- 男性従業員15名(取得率10%)のB社は、粘り強く育休制度の周知を行った結果、2事業年度以内に8名が取得し、取得率が53%に上昇しました。
- 取得率が30ポイント以上上昇し、かつ50%以上を達成したため、B社には40万円の加算が支給されます。
- 着実に成果を積み重ねたB社
- 40万円加算
また、従業員数が少ない企業向けの特例措置も設けられています。
- 3年以内に成果を出した場合
- 20万円加算
- 時間をかけて成果を上げたC社
- 男性従業員10名(取得率20%)のC社は、育休制度の周知や面談を丁寧に実施した結果、3事業年度以内に5名が育休を取得し、取得率が50%に上昇しました。
- 取得率が30ポイント以上上昇し、かつ50%以上を達成したため、C社には20万円の加算が支給されます。
- 時間をかけて成果を上げたC社
- 20万円加算
第2種助成金|育休後職場復帰時の最大加算額はいくら?
これらの加算措置をすべて適用した場合、中小企業が第2種で受給できる助成金の最大額は以下の通りです。
- 基本額(10万円)
- 育児休業取得率上昇加算(最大60万円)
合計すると、最大で70万円の助成金を受給できる可能性があります。
これは、企業の積極的な取り組みが大きく評価されることを意味します。
これらの加算要件は、制度改正により変更される可能性があるため、申請前に必ず厚生労働省のウェブサイトやパンフレットで最新の情報を確認することが非常に重要です。
出生時両立支援コース|第1種と第2種の違い
両者の違いを明確にすることで、制度の全体像がより理解しやすくなります。
| 項目 | 第1種(育休取得時) | 第2種(職場復帰時) |
| 焦点 | 男性従業員の「育児休業取得」 | 育休終了後の「職場復帰と定着」、および「取得率の向上」 |
| 助成金の目的 | 育休取得のための環境整備と、初めての育休取得を評価 | 育休後の継続就業を促し、育児と仕事の両立を支援 |
| 支給時期 | 育休が終了した後に申請 | 職場復帰後、6か月経過した後に申請 |
| 加算措置 | 中小企業の場合、雇用環境整備措置の実施で10万円加算 | 中小企業の場合、育休取得率の上昇で20〜60万円加算 |
このように、第1種と第2種はそれぞれ異なる目的と役割を担っています。
この両方を活用することで、企業は育児休業の取得を促進するだけでなく、優秀な人材の離職を防ぎ、安定した雇用環境を構築することができるのです。
出生時両立支援コース第2種|助成金の受給要件と申請手順
出生時両立支援コースの助成金(第2種)を確実に受け取るには、定められた期間内に適切な手続きを行うことが不可欠です。
出生時両立支援コース第2種|職場復帰時の助成金受給要件
この助成金を受給するには、以下の2つの要件をすべてクリアする必要があります。
- 育児休業を取得した従業員が原職等に復帰していること
- 育休を終えた男性従業員が、育休に入る前と同じ職場や職務に復帰していることが求められます。
- 復帰後、6か月以上継続雇用されていること
- 職場復帰が一時的なものではなく、長期的な雇用を前提としていることを証明する必要があります。
- 申請時には、復帰後の6ヶ月間の賃金台帳や出勤簿などで、継続して雇用されていることを示す書類の提出が求められます。
出生時両立支援コース第2種|申請手続きと期限の注意点
第2種の申請手続きは、第1種とは異なるスケジュールで進める必要があります。
計画的に準備を進めることが、申請の成功を左右する鍵となります。
申請期限は「職場復帰から6か月後」が起点
第2種の申請は、男性従業員が育児休業を終えて職場復帰した日から6か月が経過した日の翌日から、2か月以内に行う必要があります。
この期限を過ぎると、せっかくの取り組みが無駄になってしまうため、事前のスケジュール管理が非常に重要です。
- 例
- 4月1日に育休から職場復帰した場合、10月1日に6か月が経過します。申請期限は、その翌日の10月2日から起算して2か月以内となります。
出生時両立支援コース第2種|申請書類の確認リスト
第1種の助成金受給を前提とした、第2種の申請に必要な書類は以下の通りです。
これらの書類をすべて準備することで、スムーズな手続きが可能です。
- 第2種専用の支給申請書(様式は年度により異なる)
- 支給要件確認申立書(【共通要領】様式第1号)
- 第1種助成金の支給決定通知書の写し
- 雇用契約書、就業規則(第1種申請時と変更がないかを確認するため、控えを提出)
- 復帰後の賃金台帳や出勤簿(職場復帰日から6ヶ月間の雇用継続を証明できるもの)
- 支払方法・受取人住所届(助成金の振込先口座を指定する書類)
- 会社の登記事項証明書(発行から3ヶ月以上経過している場合など、必要に応じて提出)
- 育児休業取得率を明らかにする書類(育児休業取得率上昇加算を申請する場合)
- 委任状(代理人による申請の場合)
これらの書類に不備がないか、申請前に管轄の労働局に相談することをおすすめします。
もし、第1種の助成金の申請をしていない場合は、「一般事業主行動計画策定・変更届(様式第一号)の控え」や「就業規則の写し」など、必要となります。
詳しくはコチラの記事の「出生時両立支援コース(育休取得時)必要書類チェックリスト」をご覧ください。👉出生時両立支援コース|第1種(育児取得時)助成金の申請手順
出生時両立支援コースを徹底解説|中小企業が助成金112万円を受け取るまで
男性の育児休業取得を促進する「出生時両立支援コース」は、中小企業にとって大きなメリットがある助成金制度です。
しかし、制度の仕組みや申請のタイミングが複雑なため、手続きに戸惑う企業も少なくありません。
この記事では、男性社員20名の企業を例に、最大112万円の助成金を確実に受け取るための具体的なフローを、時系列でわかりやすく解説します。
ステップ1|第1種助成金(育休取得時)の申請
第1種は、男性従業員が育児休業を取得した際に、個別に申請する助成金です。
ここでは、社員3名が育休を取得した事例をもとに、申請期限と受給額を整理します。
| 育休取得者 | 育児休業終了日 | 第1種申請期限 | 想定受給額 |
| Aさん(1人目) | 2025年5月31日 | 2025年7月31日 | 32万円 |
| Bさん(2人目) | 2025年7月10日 | 2025年9月10日 | 10万円 |
| Cさん(3人目) | 2025年9月20日 | 2025年11月20日 | 10万円 |
※1人目のAさんは、基本額に加え、「雇用環境整備措置」と「情報公表」の加算措置で合計32万円を受給。
ステップ2|第2種助成金(職場復帰時)の申請
第2種は、育休からの職場復帰と、前年度よりも育休取得率が向上したことを確認してから申請します。
この「取得率向上」の要件が、申請タイミングを決定する上で最も重要です。
育休取得率の上昇を確認
- 前年度(2024年度)取得率
- 33%(取得対象者3名中1名が取得)
- 本年度(2025年度)取得率
- 80%(取得対象者5名中4名が取得)
本事例では、取得率が前年度から47ポイント上昇し、50%以上という要件を満たしました。この確定は、年度が終了する2026年3月31日以降となります。
申請のタイミングと受給額
第2種の申請期限は、第1種の対象となった社員のうち、最も復帰が遅かったCさんの「職場復帰から6ヶ月後」の翌日から2ヶ月以内です。
- 申請期限
- 2026年5月20日
- 申請日
- 加算要件が確定する2026年4月1日以降に、Cさんの申請期限までにまとめて申請するのが最も安全かつ効率的です。
- 想定受給額
- 取得率の要件を満たしているため、60万円
出生時両立支援コース|第1種・第2種の助成金額と受給額の目安
このフローに沿って申請することで、企業は以下の合計金額を受け取ることができます。※受給金額は、企業規模・取得人数・加算要件の達成状況により変動します。
- 第1種合計
- 52万円
- 第2種合計
- 60万円
- 総合計
- 112万円
男性育休の取得は、従業員のワークライフバランス向上だけでなく、企業の助成金受給にも直結します。ぜひ、計画的な申請でこの制度を有効活用してください。
まとめ|出生時両立支援コースを最大限に活用するために
出生時両立支援コースは、単に助成金を受け取るだけの制度ではありません。
第1種と第2種の両方を活用することで、男性の育児休業を「取得」から「職場復帰後の定着」まで、一貫して支援することが可能になります。
助成金は、あくまで「働きやすい職場環境の構築」という目的を達成するための重要なツールです。
制度の真価は、育休を取得した従業員が安心して復帰し、長期的に活躍できる環境を整えることで発揮されます。
本コースの助成金を確実に受給するためには、以下の点が鍵となります。
- 計画的な準備
- 育休制度の整備や行動計画の策定を、早めに行うこと。
- 丁寧な記録管理
- 申請期限を逃さないよう、育休の期間や復帰後の雇用継続状況を正確に記録すること。
これらの取り組みを通じて、企業は経済的なメリットを得るだけでなく、従業員のエンゲージメントを高め、優秀な人材の定着に繋げることができるでしょう。
次回予告|「柔軟な働き方選択制度等支援コース」を詳しく解説
さて次回は、同じく働き方改革を支援する助成金である「柔軟な働き方選択制度等支援コース」について解説します。
次回の記事は👉柔軟な働き方選択制度等支援コース|支給対象と支給事例を紹介
テレワークや時差出勤などの柔軟な働き方を導入・実施する際に活用できる助成金であり、多様な働き方を推進したい企業にとって非常に有益な情報です。
ご期待ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。
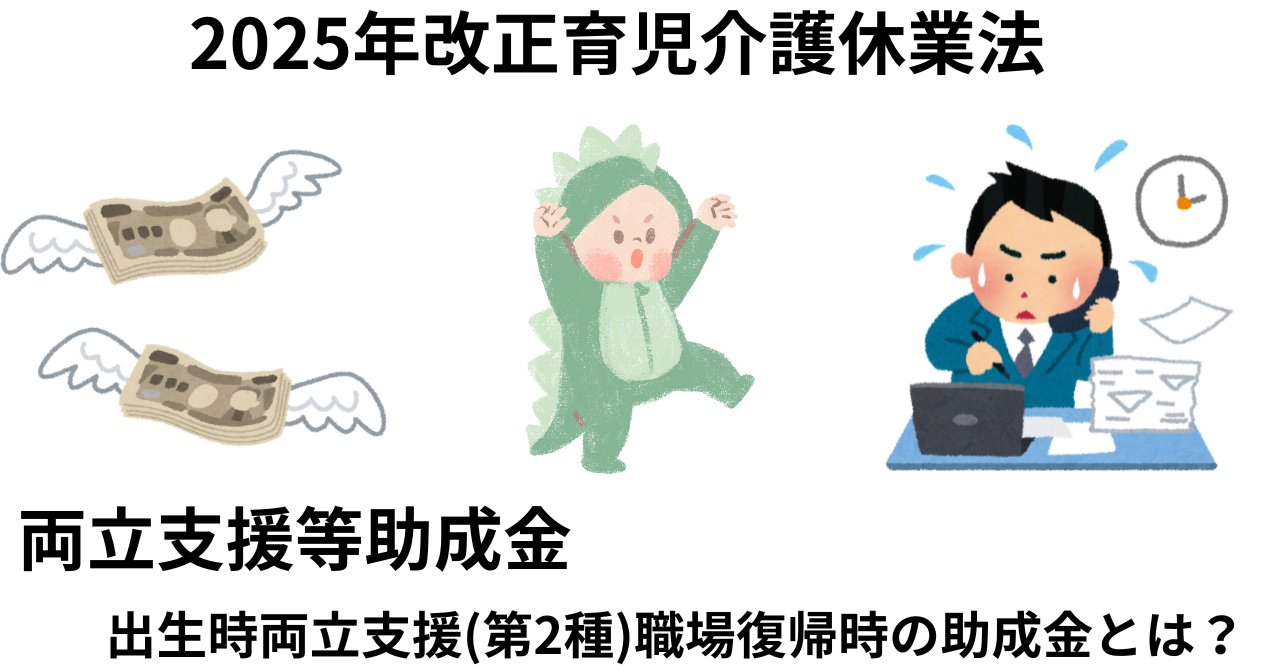

コメント