2年目に突入します。能天気に2年目に突入してもダメです。
「準備を怠ることは、失敗を準備することである」
この言葉、アメリカ独立宣言の起草にも携わったベンジャミン・フランクリンの名言です。
計画と準備の重要さを端的に言い表しています。
成功を目指すなら、ただ願うだけではなく、目標に向かって行動し、しっかりと準備を整えることが必要なんだなと改めて思います。
※1年目の道のりをまだ読んでいない方は、まずはこちらからどうぞ。
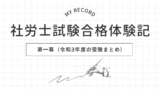
令和4年度社労士試験に向けてとりあえず、再スタート
ただ、私の場合は「準備を怠った」というのは多少語弊があります。「準備を怠った」というよりは「そこそこ準備をしたつもりが、実は準備不足だった」というほうがしっくりきます。
試験の翌日からすぐに勉強を再開します。
この時点ではまだ年間1,000時間のプランは立てていません。
でも、完璧なプランができるまで勉強をストップするというのもおかしな話なので、とりあえず走りながら考えていこう、というスタンスでいきます。
生活の変化と勉強時間確保の工夫|社労士試験2年目の挑戦
試験の約3週間前に加工部へ移動したのは以前のブログで書いた通りなのですが、出勤時間も変わりました。
私が加工部に配属される2,3日前まで責任者であったO係長がいなくなり、さらに人手不足がひどくなっておりました。
一部社員の残業時間が月100時間を超え、早急な対応が必要という状況です。
私の出勤時間はAM9時、休憩2時間、退勤時間PM19時という形になります。事細かに書いてしまう長くなるので割愛します。これが、他の社員の労働時間を削減するには適切だろう、ということで決まりました。
営業部のときと明らかに違うのは、この出退勤時間ではなく、帰宅した後での自宅での過ごし方でした。
以前の営業部のときは、帰宅後、洗濯物を取り入れ、それを畳み、皿を洗い、コメを炊き、風呂掃除をして風呂をたく。
その合間を縫って、バイヤー、店舗の主任さんに売り込み、仕入れの確認、現場への指示書の作成等、やることが多すぎて、所謂サービス残業のようなことをしておりました。
しかし、加工部に異動になってからは、それは完全になくなり、しかも帰宅時間がPM20時半頃となってしまったため、帰宅してからの家事というのが無くなりました。
まぁ、これは妻のほうへ負担が移動したということになるので一概には喜べませんが(喜んだら怒られる)、時間の余裕はでてきます。
社労士試験という「敵」と「自分」を知る
「彼を知り己を知れば百戦危うからず」孫子の兵法の中の言葉です。
「彼を」というのは社労士試験そのもの、各科目の出題傾向・難易度のことです。
「己」というのは文字通り自分のことです。
敵を知るというのは当然のことです。
敵がどれくらいの戦力、難敵であるのかをしっかり把握していないと話になりません。
あとは自分のことです。自分というのはどういう状態であればマックスのパフォーマンスを発揮できるのか、要するにどういう状態で勉強に臨めば効率的に実力を上げていけるのか、をしっかり考え、試行錯誤していかなければなりません。
また、翌年の5月以降は模試なども受けて、自分の立ち位置もしっかり把握しておかなければなりません。
AM7時半ころ家を出て、PM20時半くらいに帰宅する。
どこで(時間のこと)勉強をするか?最初にしばらくやっていたのは、帰宅して、食事して、風呂に入って、そこから2時間か3時間の勉強する。
実はこれが全然ダメでした。やはり仕事で脳みそが疲れているのでしょう。全く集中出来ないのです。
やっても無駄、とまでは言いませんが、これはかなりの効率の悪さだ、と気づきます。きっと自分には向いていないのでしょう。
通勤電車と早朝時間を活用した社労士試験勉強法|効率的インプット術
実は「この勉強時間をどうするのか、どの時間帯にやるのがベストなのか」という試行錯誤を繰り返すこと、約2か月の時を費やしました。
いろいろ試しにやってみた結果、朝勉と通勤電車内勉を中心に日々の勉強をしていき、休日は丸々できる限り勉強をする。
今の勤務体制ならできる、という結論に達します。
- AM5時起床~AM7時まで朝勉。基本問題集をひたすら解く。
- 通勤時間というより電車に乗っている時間往復で約1時間40分、基本インプットの時間にあて、ひたすらテキストを読み込む。
ある程度このような感じでいこうというのが10月くらいで固まりこのまま突っ走ります。
令和4年度社労士試験合格に向けての次の戦略は?
「彼を知り己を知れば百戦危うからず」という状態には、まだ到達していないかなと思います。
今の段階では、勉強時間の確保という一つの命題が一応解決した、というところです。
次は「どのような武器を装備するか?」という新たな命題に取り組んでいくことになります。
これを解決して「己を知る」という段階に近づいていくのでしょう。
敵の戦力を把握し、自分の戦力も把握する。そして両者を分析した結果、「勝てる」という確信が生まれる。
そうなって初めて「百戦危うからず」の境地に達するのでしょう。続く

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 50歳を目前に、会社員として働きながら、様々な事情により社会保険労務士試験への独学での挑戦を決意しました。不合格という苦い経験もしましたが、そこで諦めることなく合格を勝ち取りました。
- このブログでは、自身の経験を踏まえ、特に「仕事と受験勉強の両立に悩む会社員の方」や「独学で合格を目指す方」にとって有益となる社労士試験合格への道のりをお届けします。
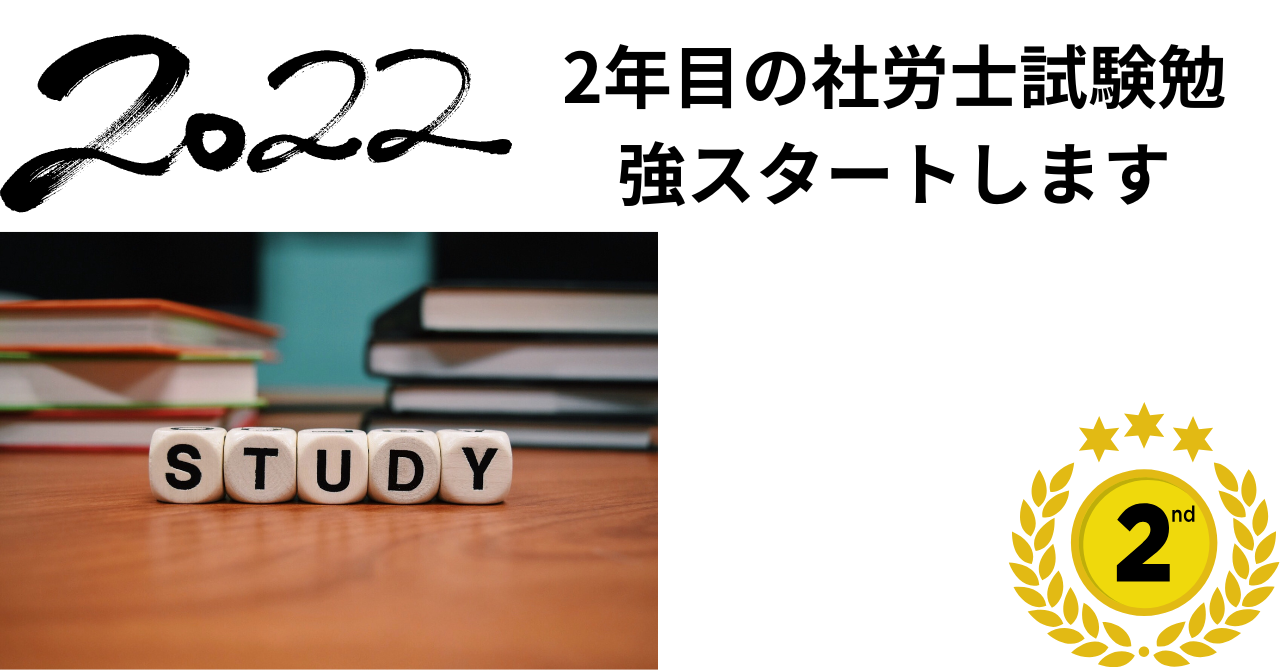
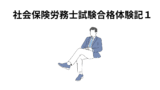

コメント