本記事は「2025年改正育児介護休業法シリーズ」の第43弾です。他のシリーズの記事はコチラから👉2025年育児介護休業法改正|企業がすべき対応と助成金情報
前回までの記事では、育児休業等支援コースと出生時両立支援コースについて詳しく解説してきました。
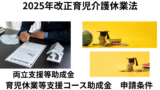
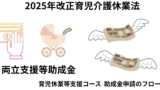

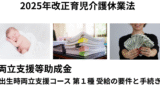
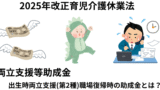
今回は、これらの育児休業に関わる支援とは少し趣の異なる、柔軟な働き方選択制度等支援コースに焦点を当てていきます。
このコースは、育児や介護に限らず、従業員一人ひとりの多様な事情に応じた働き方を可能にする制度導入を支援するものです。
働き方の選択肢を増やすことで、従業員がより長く、いきいきと働き続けられる職場環境づくりを目指す企業にとって、非常に重要な助成金と言えるでしょう。
この記事で分かること
- 育児・介護に限らず、全従業員の多様なライフスタイルを支える「柔軟な働き方」への助成
- テレワーク、フレックスタイム制、短時間勤務など、1制度の新規導入で20万円が支給
- 制度を作って終わりではなく、実際に「1人以上の利用者」が出ることが受給の必須条件
- テレワークやフレックスは、その後の「利用者増加」に対しても追加助成(1人あたり最大5万円等)がある
- 優秀な人材の確保と定着(リテンション)という、中小企業にとって最大の経営課題を解決するツール
育児や介護と仕事の両立を支援|柔軟な働き方選択制度等支援コース
働き方改革が進む現代において、育児や介護と仕事の両立は、多くの従業員にとって大きな課題となっています。
子育てや親の介護で時間の制約があるために、働き続けることを諦めてしまう優秀な人材も少なくありません。
このような状況は、企業にとっても大きな損失です。
「従業員の離職を防ぎ、働きやすい職場を作りたい」とお考えの事業主、担当者の皆さま。
その解決策の一つとして、「柔軟な働き方選択制度等支援コース」の活用をご提案します。
この制度は、従業員が育児や介護と仕事を両立できるような多様な働き方(テレワーク、フレックスタイム制、短時間勤務など)を導入する事業主を支援する助成金です。
この記事では、「柔軟な働き方選択制度等支援コース」の概要から、受給するための条件、申請の流れ、そして実際の活用事例まで、皆さまが知りたい情報をすべて網羅します。
この記事を最後まで読んでいただくことで、助成金を活用して従業員が安心して長く働ける環境を整備する方法が明確になります。
ぜひ、この機会に助成金を活用し、企業と従業員双方にとってメリットのある、より良い職場づくりを実現してください。
両立支援等助成金「柔軟な働き方選択制度等支援コース」とは?制度概要と対象を解説
「柔軟な働き方選択制度等支援コース」は、育児や介護を行う従業員が、仕事と家庭生活を両立できるよう、多様な働き方を選択できる制度を導入する事業主を支援するための助成金です。
この助成金は、厚生労働省が提供する「両立支援等助成金」の一つであり、従業員がその能力を最大限に発揮できる職場環境づくりを促進することを目的としています。
柔軟な働き方の具体例|助成金対象となる制度とは
このコースの対象となる働き方は多岐にわたります。主な制度は以下の通りです。
- フレックスタイム制
- 従業員が日々の始業時間や終業時間を自由に決定できる制度です。
- 子どもの送り迎えや通院など、個々の事情に合わせて柔軟な働き方が可能になります。
- テレワーク
- 従業員が、会社に出社することなく、自宅やサテライトオフィスなどで業務を行う働き方です。
- 通勤時間の削減や、地理的な制約にとらわれない働き方が実現できます。
- 短時間勤務制度
- 育児や介護を行う従業員のために、1日の所定労働時間を短縮する制度です。
- 法律で定められた期間を超えて、企業が独自に制度を設ける場合などが対象となります。
これらの制度以外にも、企業独自の多様な働き方制度が対象となる場合があります。
柔軟な働き方選択制度等支援コースの目的|企業が得られるメリットとは
この助成金の最大の目的は、仕事と家庭の両立を支援することで、従業員の離職を防ぎ、働きやすい職場環境を整備することです。
企業がこの助成金を活用して柔軟な働き方制度を導入することは、以下のような多岐にわたるメリットをもたらします。
- 従業員の離職率低下
- 育児や介護を理由に離職せざるを得なかった従業員が、働き続けることが可能になります。
- これは、企業が培ってきた貴重なノウハウや経験の流出を防ぐことにもつながります。
- 生産性の向上
- 従業員が自身のライフスタイルに合わせて働き方を選べることで、モチベーションが向上し、結果的に生産性の向上に繋がります。
- また、通勤時間の削減は、従業員の負担軽減にも貢献します。
- 優秀な人材の確保
- 柔軟な働き方ができる企業は、求職者にとって魅力的に映ります。
- これにより、多様な働き方を求める優秀な人材を確保しやすくなります。
- 企業イメージの向上
- 従業員を大切にする企業として社会的に評価され、企業イメージやブランド力の向上にも繋がります。
このように、「柔軟な働き方選択制度等支援コース」は、助成金という金銭的な支援を受けながら、企業価値を高めるための重要な施策と言えるでしょう。
柔軟な働き方選択制度等支援コース|助成金の支給対象と支給額を徹底解説
この助成金は、中小企業事業主を主な対象としています。
柔軟な働き方選択制度等支援コース|助成金の支給対象となる事業主とは
具体的な要件は、以下のいずれかの基準を満たす必要があります。
| 業種分類 | 資本金または出資額 | 常時雇用する従業員数 |
| 小売業(飲食業を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 製造業、建設業、その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
これらの要件を満たさない大企業でも、制度導入の対象となる場合がありますので、詳細は必ずご確認ください。
柔軟な働き方選択制度等支援コース|助成金の支給要件と申請条件
助成金を受給するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 計画の策定・届出
- 制度導入計画を策定し、管轄の労働局に提出すること。
- 就業規則等の整備
- 柔軟な働き方制度(テレワーク、フレックスタイム制など)に関する規定を就業規則に明記し、労働者へ周知すること。
- 制度の実施
- 実際に制度を導入し、規定に従って運用すること。
- 利用者の存在
- 制度の導入後、実際にその制度を利用する従業員がいること。
- この制度は「形だけ」の導入ではなく、実際に活用されることが求められます。
これらの要件をクリアすることで、助成金の申請が可能になります。
柔軟な働き方選択制度等支援コース|助成金の支給額と計算例
助成金の支給額は、導入する制度の種類や、制度を利用する従業員の人数によって異なります。
このコースには、「新規導入時」と「利用者の増加時」という2つのフェーズで助成金が支給される仕組みがあります。
1. 新規導入時の助成
これまで柔軟な働き方制度を導入していなかった事業主が、新たに制度を導入し、実際に利用者が発生した場合に支給されます。
- 支給額(例)
- 1制度につき最大20万円
- フレックスタイム制
- 制度を新規導入し、利用者が1人以上いる場合に支給。
- テレワーク
- 制度を新規導入し、利用者が1人以上いる場合に支給。
- 短時間勤務制度
- 制度を新規導入し、利用者が1人以上いる場合に支給。
- フレックスタイム制
- 1制度につき最大20万円
2. 利用者の増加時の助成
既に柔軟な働き方制度を導入している事業主が、制度の利用者を増やすための取り組みを行った場合に支給されます。
- 支給額(例)
- テレワーク利用者の増加
- 利用者が1人増えるごとに最大5万円(上限あり|1年度あたり1つの事業主につき、延べ5名まで)。
- フレックスタイム制利用者
- 利用者が1人増えるごとに最大2万円(上限あり|1年度あたり1つの事業主につき、延べ5名まで)。
- 短時間勤務制度利用者
- 利用者増加に対しては、追加の助成金はありません。
- テレワーク利用者の増加
これらの支給額は年度によって変動する可能性があります。
正確な金額や詳細な条件については、必ず厚生労働省の最新情報を確認してください。
この助成金を活用することで、企業の負担を軽減し、よりスムーズに働きやすい環境整備を進めることができるでしょう。
柔軟な働き方選択制度等支援コース|中小企業での導入事例
実際に「柔軟な働き方選択制度等支援コース」を活用し、働き方改革に成功した企業の事例をいくつかご紹介します。
これらの事例は、助成金が単なる経済的支援にとどまらず、企業と従業員双方に大きなメリットをもたらすことを示しています。
事例 Webデザイン制作会社「株式会社T」
株式会社Tは従業員数70名の中小企業です。
新型コロナウイルスの流行をきっかけにテレワークを導入しましたが、本格的な制度として整備していませんでした。
従業員から「今後もテレワークを続けたい」という要望が強く寄せられたため、助成金を活用して「テレワーク制度」を正式に導入・整備することにしました。
制度導入前
- 従業員構成
- 従業員70名。
- 課題
- 従業員の要望に応え、より働きやすい環境を整備したい。
- 地方在住の優秀なデザイナーを雇用したいが、通勤がネックとなっていた。
制度導入と助成金の活用
- 就業規則の改定
- テレワークの対象者、利用可能な業務、情報セキュリティに関するルールなどを明文化し、就業規則に追記しました。
- 制度の周知
- 社内研修を実施し、テレワーク勤務時のコミュニケーションツールやセキュリティ対策について周知徹底しました。
- 助成金の申請
- 制度導入計画を労働局に届け出た後、従業員10名がテレワーク制度を利用し始めたため、「テレワーク制度導入」として助成金を申請しました。
導入後の成果と支給された助成金額
- 従業員の働きやすさ向上
- 従業員は通勤時間を削減でき、時間を有効活用できるようになりました。
- 優秀な人材の確保
- 地方に住む経験豊富なWebデザイナーを2名採用。
- 物理的な場所に縛られず、多様な人材を確保できる体制が構築できました。
- 支給された助成金額
- この事例では、テレワークという1つの柔軟な働き方制度を新規に導入したことで、両立支援等助成金「柔軟な働き方選択制度等支援コース」から20万円の助成金が支給されました。
事例 住宅関連サービス会社「株式会社F」
株式会社Fは従業員数150名の事業主です。
育児や介護と両立しながら働く従業員が増え、特に「朝のラッシュ時間を避けたい」「子どもの学校行事に参加したい」といった声が上がっていました。
そこで、従業員一人ひとりのライフスタイルに合わせた働き方を可能にするため、助成金を活用して「フレックスタイム制」を導入しました。
制度導入前
- 従業員構成
- 従業員150名。
- うち育児・介護中の従業員が15名。
- 課題
- 従業員のワークライフバランスが課題。
- 特に朝夕の時間帯に柔軟な働き方を求める声が多かった。
制度導入と助成金の活用
- 就業規則の改定
- コアタイム(必ず勤務する時間帯)を10時から15時までと設定し、フレキシブルタイム(自由に勤務できる時間帯)を設ける規定を就業規則に追記しました。
- 制度の周知
- 制度の目的と利用方法を全従業員に説明する会を実施し、周知を徹底しました。
- 助成金の申請
- 制度導入計画を労働局に届け出た後、従業員8名がフレックスタイム制を利用し始めたため、「フレックスタイム制導入」として助成金を申請しました。
導入後の成果と支給された助成金額
- 従業員の満足度向上
- 従業員は自身の都合に合わせて出勤・退勤時間を調整できるようになり、ワークライフバランスが大幅に改善。
- 生産性の維持
- コアタイムを設けることで、チーム内の連携を確保。
- 個人の裁量が増えたことで、時間内に効率良く業務を終わらせようという意識が高まりました。
- 支給された助成金額
- この事例では、フレックスタイム制という1つの柔軟な働き方制度を新規に導入したことで、両立支援等助成金「柔軟な働き方選択制度等支援コース」から20万円の助成金が支給されました。
事例 ITソフトウェア開発会社「株式会社S」
株式会社Sは従業員数40名の中小企業で、従業員の約半数が30代の子育て世代でした。
育児休業から復帰する従業員が何人かいたものの、「フルタイムでの勤務は難しい」という声が上がっていました。
離職を防ぐため、同社は助成金を活用して「短時間勤務制度」を整備することにしました。
制度導入前
- 従業員構成
- 従業員40名。うち育児中の従業員が6名。
- 課題
- 育児中の従業員が「子どものお迎え時間」を理由にフルタイム勤務を続けることが難しく、離職を検討していた。
制度導入と助成金の活用
- 就業規則の改定
- 育児・介護休業法で定められた期間を超えて、小学校就学前の子どもを持つ従業員全員が利用できる短時間勤務制度を新設しました。
- 制度の周知
- 社内掲示板とメールで全従業員に制度の概要と利用方法を周知しました。
- 助成金の申請
- 制度導入計画を労働局に届け出た後、育児中の従業員5名が実際に短時間勤務制度を利用し始めたため、「短時間勤務制度導入」として助成金を申請しました。
利用状況
- 利用人数
- 5名(うち3名は育児休業からの復帰者、2名は育児中の既存従業員)
- 具体的な勤務時間
- 従業員A(3歳の子どもを持つ開発者)は、午前9時から午後4時までの勤務を週5日利用するなど、個々の希望に応じて柔軟に対応しました。
導入後の成果と支給された助成金額
この取り組みにより、株式会社Sは以下のような成果を得ることができました。
- 離職率の低下
- 短時間勤務制度を利用した従業員は全員、離職することなく働き続けることができています。
- 生産性の維持
- 勤務時間が短くなった従業員の業務は、チーム内で分担して対応。
- 時間的な制約があるからこそ、短時間で効率的に業務をこなす意識が社内全体で高まりました。
- 企業イメージの向上
- 「子育てと仕事を両立しやすい会社」として、採用活動においてもアピールポイントとなり、優秀な人材の確保につながりました。
- 支給された助成金額
- この事例の場合、短時間勤務制度という1つの柔軟な働き方制度を新規に導入したことで、両立支援等助成金「柔軟な働き方選択制度等支援コース」から20万円の助成金が支給されました。
まとめ|柔軟な働き方選択制度等支援コースの導入メリットと助成金活用ポイント
この記事では、両立支援等助成金「柔軟な働き方選択制度等支援コース」について、その概要とメリット、そして具体的な事例を交えて解説しました。
- 制度の目的と対象
- 育児や介護と仕事の両立を支援するため、テレワークやフレックスタイム制、短時間勤務制度といった多様な働き方を導入する中小企業を対象とした助成金です。
- 助成金の支給額
- 新規導入時
- 1制度の導入につき20万円が支給されます。
- 利用者増加時
- テレワークやフレックスタイム制では、利用者が増えるごとに追加の助成金が支給されます。(上限あり)
- 新規導入時
助成金を活用することで、企業は金銭的な負担を抑えつつ、従業員が働きやすい環境を整備でき、離職率の低下や生産性の向上といったメリットを享受できます。
お勧めのクラウド勤怠管理システムソフト👉パソコンで勤怠管理3 スマートパッケージ版
次回予告|柔軟な働き方選択制度等支援コースの助成金申請の手順と注意点
柔軟な働き方選択制度等支援コースの助成金の申請手続きについて解説します。
- 助成金申請の具体的な流れ
- 必要書類や注意点
- スムーズに申請を進めるためのポイント
次回の記事を読めば、実際に助成金を受け取るまでのプロセスが明確になります。
次回の記事は👉柔軟な働き方選択制度等支援コース|申請から受給までフロー解説
ぜひご期待ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。


コメント