本記事は「2025年改正育児介護休業法シリーズ」の第41弾です。他のシリーズの記事はコチラから👉2025年育児介護休業法改正|企業がすべき対応と助成金情報
前回、両立支援等助成金の「出生時両立支援コース」についてその制度の目的から、具体的な助成金額、そして育休取得時と職場復帰時という2つのフェーズに分かれた助成金の種類について詳しく解説しました。
前回の記事は👉出生時両立支援コースとは?助成金の種類と第1種の助成金額解説
男性の育児参加促進、企業の職場環境改善、そして優秀な人材の定着という、この助成金の背後にある政府の明確な狙いもご理解いただけたかと思います。
しかし、これらの助成金は「知っている」だけで自動的に支給されるわけではありません。
多岐にわたる複雑な要件をクリアし、適切な手続きを踏んで初めて、企業は助成金を受け取ることができます。
この記事で分かること
- 中小企業でも「一般事業主行動計画」の策定・届出・公表が受給の絶対条件
- 「両立支援のひろば」への外部公表は、企業の透明性を高める有効な手段
- 基本額20万円に10万円を加算する「4項目以上の環境整備措置」の具体策
- 「育休開始前」と「育休終了後」の2段階で進める、計画的な書類収集フロー
- 労働局への事前相談と、すべての証拠(メール、議事録)を残すことの重要性
制度活用のステップ|出生時両立支援コースを受給するためのロードマップ
特に、中小企業にとって、この制度を活用できるか否かは、経営戦略や人材確保に大きな影響を与えます。
本記事では、この出生時両立支援コースを確実に受給するためのロードマップとして、特に重要な「受給するための要件と手続き」に焦点を当てて深掘りしていきます。
複雑に感じられる手続きも、ポイントを押さえて一つずつ実行すれば、決して難しいものではありません。
この記事を通じて、貴社が助成金を活用し、働きやすい職場環境をさらに整備するための一助となれば幸いです。
出生時両立支援コース第1種の助成金申請の第一歩|必須要件を押さえる
出生時両立支援コースの助成金を受給するためには、申請の前に必ず満たしておくべき必須要件があります。
これらは単に書類を提出すれば良いというものではありません。
日頃から企業として取り組んでいる姿勢が問われます。
1. 出生時両立支援コース申請に必須の一般事業主行動計画の策定・届出・公表
一般事業主行動計画の策定・届出・公表は、法律上、常時雇用する労働者が101人以上の企業に義務付けられています。
しかし、この出生時両立支援コースの助成金を受給しようとする場合は、企業の規模に関わらず(100人以下の企業も含む)、この行動計画の策定・届出・公表が必須要件となります。
一般事業主行動計画の策定・変更届の様式や、詳しい情報は、厚生労働省:一般事業主行動計画の策定・届出等についてのウェブサイトで確認できます。
- 策定のポイント
- 目標設定の具体性
- 「男性従業員の育児休業取得率を〇〇%以上にする」といった、具体的な数値目標を盛り込むことが重要です。漠然とした目標ではなく、達成すべきゴールを明確にしましょう。
- 取り組み内容の明確化
- 目標達成のために、「社内研修を実施する」「育児休業に関する相談窓口を設置する」など、具体的なアクションプランを記載します。
- 記入例は👉一般事業主行動計画策定・変更届 記入例
- 目標設定の具体性
この様式は、大きく分けて「事業主の情報」と「行動計画の概要」の2つのパートで構成されています。
1. 事業主の基本情報
- 一般事業主の氏名または名称
- 法人名など
- 代表者の氏名
- 法人の代表者名
- 主たる事業
- 住所
- 電話番号
- 常時雇用する労働者の数
- 男女別の内訳も含む
2. 行動計画の概要
- 行動計画を策定・変更した日
- 行動計画の計画期間
- 開始日と終了日
- 育児休業制度の整備状況
- 有期契約労働者も対象に含めているか
- 外部への公表方法
- インターネットの利用(両立支援のひろば、自社HPなど)やその他の方法
- 労働者への周知方法
- 掲示、書面交付、電子メールなど
- 次世代育成支援対策の内容
- 様式第1号の第二面・第三面に、具体的に定めた事項を記載します。
- 雇用環境の整備に関する事項
- 妊娠中や子育てを行う労働者等を支援するための制度の整備
- 働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備
- その他の次世代育成支援対策の内容
- 託児施設の設置や地域のNPO等への参加など、子どもの健全な育成のための活動
- その他の次世代育成支援対策の内容
- 雇用環境の整備に関する事項
- 様式第1号の第二面・第三面に、具体的に定めた事項を記載します。
様式には、これらの項目に加え、「くるみん認定」や「プラチナくるみん認定」の申請予定の有無なども記載します。
なお、様式や記載内容は、法改正などによって変更されることがあります。最新の様式は、必ず厚生労働省のウェブサイトで確認してください。
- 届出方法
- 策定した計画は、企業の所在地を管轄する都道府県労働局に届け出る必要があります。
- 届出には専用の様式が用意されており、厚生労働省のウェブサイトでダウンロードできます。👉厚生労働省:一般事業主行動計画の策定・届出等について
- 公表方法
- 計画は、社内外に公表しなければなりません。
- 社内周知
- 社内掲示板への掲示、全従業員へのメール、社内イントラネットへの掲載など、従業員がいつでも確認できる状態にしておきましょう。
- 外部公表
- 厚生労働省が運営する「両立支援のひろば」への掲載が最も一般的です。
- これにより、自社の取り組みを外部へアピールすることもできます。
- 社内周知
- 計画は、社内外に公表しなければなりません。
2. 出生時両立支援コース申請に必要な育児休業制度の整備と周知体制
育児休業制度は、就業規則に明確に規定されている必要があります。
就業規則への規定
- 育児・介護休業法に基づき、育児休業制度を就業規則に定めることが必須です。
- 2025年改正など、最新の法改正内容を反映しているか必ず確認しましょう。
- パートタイマーや有期雇用労働者なども含め、従業員が平等に利用できる制度になっているかどうかも重要なポイントです。
周知の具体例
- 制度を定めているだけでなく、従業員に周知することも義務付けられています。
- 周知したことの証拠は、申請時に提出を求められる場合があるため、必ず保管しておきましょう。
- 全従業員への配布や説明会の実施
- 新入社員研修や全体会議などで、制度について直接説明する機会を設けるのも効果的です。
- 電子データでの共有
- 社内イントラネットや共有フォルダにPDFなどの電子データを掲載し、全従業員がアクセスできるようにします。
- 周知した証拠の保管
- 制度説明会の議事録、配布資料の控え、周知メールの送信履歴など、記録を忘れずに残してください。
- 全従業員への配布や説明会の実施
これらの必須要件は、助成金申請の土台となるものです。
まずは、この2つの要件を確実にクリアしているか確認し、不足があれば速やかに整備を進めましょう。
出生時両立支援コース第1種の加算要件とは?雇用環境整備措置の具体例
一般事業主行動計画の策定や育児休業制度の整備といった必須要件をクリアしたら、次に考えたいのが「加算要件」です。
この加算要件は、単に制度を整えるだけでなく、「実際に育休を取りやすい職場文化を醸成する」ための取り組みを評価するものです。
「育休取得時」の助成金において、初めて男性従業員が育休を取得した場合、基本額の20万円に加えて10万円の加算を受けることができます。
この加算を受けるためには、前回ご紹介した15項目の「雇用環境整備措置」の中から、4項目以上を実施することが条件となります。
それでは、自社にとって取り組みやすい4項目をどのように選べばよいか、具体的な例を見ていきましょう。
出生時両立支援コース第1種の加算要件に該当する具体的な取り組み例
- 研修実施
- 管理職や全従業員を対象に、育児休業制度や両立支援の重要性に関する研修を実施します。
- 外部講師を招いたセミナーだけでなく、自社で作成した資料を使ったeラーニングや、社内会議での情報共有でも構いません。
- 相談窓口
- 育休取得に関する相談を気軽にできる体制を整えます。
- 人事担当者や社会保険労務士など、相談窓口となる担当者の氏名や連絡先を社内報やメールで周知しましょう。
- 定期的な個別面談の機会を設けるのも効果的です。
- 社内周知
- 従業員が制度を「自分ごと」として捉えられるよう、積極的に情報を発信します。
- 経営層から全従業員へのメッセージ動画、育休を取得した先輩社員の体験談をまとめたインタビュー記事を社内報に掲載するなどが考えられます。
- 業務マニュアル整備
- 育休に入る社員が安心して休めるように、引き継ぎ体制を整えます。
- 業務内容を可視化するマニュアルを作成したり、タスク管理ツール(SaaSなど)を導入してチーム内での業務カバーをスムーズに行えるようにしましょう。
これら以外にも、自社の実情に合わせて取り組みやすい項目を選び、計画的に実行していくことが重要です。
これらの措置は、単に助成金をもらうためだけでなく、従業員が「この会社で長く働きたい」と思えるような、より良い職場づくりに繋がります。
出生時両立支援コース第1種助成金の申請注意点と計画的なスケジュール管理
一般事業主行動計画の策定や雇用環境整備措置の実施が完了したら、いよいよ助成金の申請です。
しかし、申請書類は多岐にわたり、一つでも不備があると審査が滞る原因となります。
ここでは、申請をスムーズに進めるための注意点と、すべての必要書類を網羅したチェックリストを解説します。
出生時両立支援コース第1種助成金申請|計画的なスケジュール管理が鍵
出生時両立支援コースの助成金は、男性従業員の育児休業開始日などを起算日として、定められた期日内に書類を提出しなければなりません。
申請期間を過ぎると、せっかくの努力が無駄になってしまうため、以下のステップで計画的に準備を進めましょう。
- 事前準備期間(育休取得前)
- 一般事業主行動計画の策定と届出、公表・周知を完了させます。
- 育児休業制度を就業規則に明確に規定し、従業員への周知を行います。
- 加算要件となる4項目以上の「雇用環境整備措置」を実施し、証拠となる記録を保管します。
- 申請準備期間(育休取得後)
- 育児休業申出書、住民票記載事項証明書など、育休取得者本人から提出された書類を収集します。
- 賃金台帳など、社内で作成する書類の準備を始めます。
- 最新の「支給申請の手引き」を入手し、必要書類の最終確認を行います。
出生時両立支援コース第1種助成金申請|完璧な書類準備の手順
申請の成否を分けるのは、添付書類の完璧さです。多岐にわたる書類を漏れなく揃えるため、以下のチェックリストを活用してください。
1. 申請書類
- 両立支援等助成金支給申請書(様式第1号)
- 出生時両立支援コース(第1種)支給申請書(様式第11号)
- 両立支援等助成金|厚生労働省⇦ここよりダウンロードできます。
2. 計画策定・届出関連書類
- 一般事業主行動計画策定・変更届(様式第一号)の控え(労働局の受付印が押されたもの)
- 労働者への周知を証明する書類(社内掲示板の写真、メールの控えなど)
- 外部への公表を証明する書類(「両立支援のひろば」掲載ページの写し、自社ホームページの画面など)
3. 就業規則関連書類
- 就業規則の写し(育児休業制度に関する規定が確認できる部分)
- 育児休業に関する協定書・労使協定書の写し(必要な場合)
- 就業規則の届出書(労働基準監督署の受付印が押されたもの)
4. 育児休業取得関連書類
- 育児休業申出書(男性従業員からの申出書)
- 育児休業等取得確認書(事業主が作成したもの)
- 住民票記載事項証明書(子の出生日や続柄を確認できるもの)
- 対象労働者の賃金台帳(育休開始月、休業中の賃金、復帰後の賃金が確認できる期間のもの)
5. 雇用環境整備措置関連書類
- 雇用環境整備実施報告書(様式第12号)
- 雇用環境整備措置を実施したことを証明する書類(4項目分):
- 研修実施
- 研修資料、議事録、出席者リスト
- 相談窓口
- 周知メールの控え、社内掲示物の写真
- 社内周知
- 社内報の写し、掲載ページのURL
- 業務マニュアル
- マニュアル本体の写しなど
- 研修実施
6. 企業情報関連書類
- 会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(発行から3ヶ月以内のもの)
- 助成金振込先口座の通帳の写し(口座番号や名義が確認できるページ)
出生時両立支援コース第1種助成金申請|不備を防ぐ最終チェックポイント
提出前の最終チェックが、手続きをスムーズに進めるための最も重要なステップです。
- 申請前に管轄労働局に相談する
- 労働局の窓口では、申請書類の事前確認や、疑問点への回答をしてもらえます。
- 記載内容や添付書類に不安がある場合は、申請前に一度相談することをお勧めします。
- 提出書類は全て控えを取る
- 提出する書類はすべてコピーを取り、控えを保管しておきましょう。
- 審査中の問い合わせや、万が一不支給になった場合の再申請に備えることができます。
- 様式の記載例を熟読する
- 厚生労働省が提供している様式には、ほとんどの場合、記入例が添付されています。
- これらの例を参考に、正確かつ漏れなく書類を作成してください。
これらの注意点を踏まえて、入念に準備を進めることで、助成金を確実に受給し、企業の働きやすい環境づくりと持続的な成長に繋げましょう。
まとめ|出生時両立支援コース第1種|成功のコツ
これまで解説してきたように、「出生時両立支援コース」は、単なる資金援助ではなく、企業が自社の働き方や職場環境を見つめ直す良い機会となります。
助成金を確実に受給し、この制度を最大限に活用するためには、いくつかの成功要因があります。
計画的な準備が第1種受給の鍵
- 助成金は、男性従業員が育休を取得した後に「突発的に申請する」ものではありません。
- 一般事業主行動計画の策定から、育休制度の周知、そして実際の育休取得、申請手続きに至るまで、すべてを一貫した計画に基づいて進めることが不可欠です。
- 計画があるからこそ、必要な準備を漏れなく進められます。
出生時両立支援コース第1種助成金申請で必須となる記録管理のポイント
- この助成金は、企業の取り組みを「証明」するものです。
- 口頭での説明だけでは認められず、就業規則、各種届出、社内周知のメール、研修の議事録など、すべての取り組みを証拠として残すことが成功の鍵となります。
- これらの記録を日頃から丁寧に管理することが、スムーズな申請に繋がります。
出生時両立支援コース第1種助成金申請|社内連携の重要性
- 「男性育休の取得」は、人事部門だけで完結するものではありません。
- 育休を取得する従業員本人、その上司、そして業務をカバーする同僚など、現場と人事部門との密な連携が不可欠です。
- 社内全体で育児と仕事の両立を支える文化を醸成することで、制度が形骸化することなく機能します。
両立支援等助成金は、これらの取り組みを後押しし、企業価値の向上と持続的な成長を実現するための強力なツールです。
ぜひこの制度を有効活用し、従業員にとっても企業にとってもメリットのある職場づくりを進めていきましょう。
次回予告|出生時両立支援コース第2種助成金の内容と申請ポイント解説
次回は、今回解説した「出生時両立支援コース」の続きとして、第2種(職場復帰時)に焦点を当てて解説します。
さらに、第1種と第2種を合わせた助成金活用の全体フローを、時系列に沿って詳しくご説明します。
次回の記事は👉出生時両立支援コース第2種(職場復帰時)助成金を詳細に解説
特に、「いつ」「どのタイミングで」申請すべきか、それぞれの申請期限や注意点についても掘り下げて解説しますので、ぜひご覧ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。
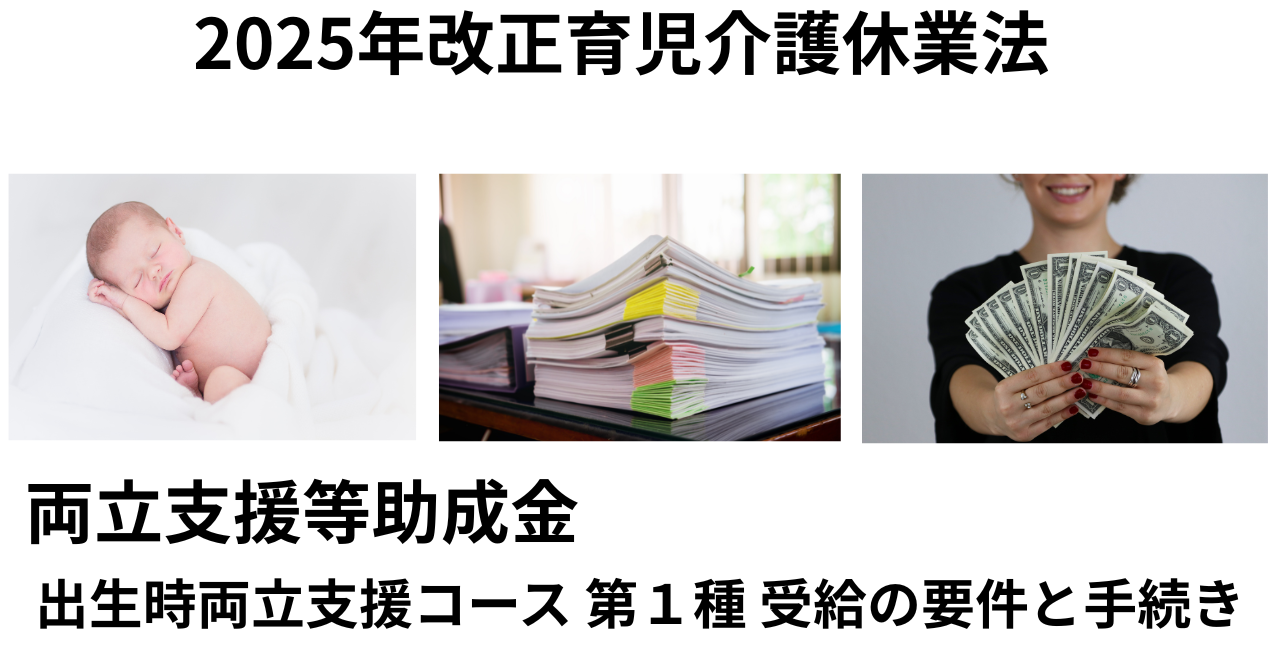

コメント