本記事は「2025年改正育児介護休業法シリーズ」の第35弾です。他のシリーズの記事はコチラから👉2025年育児介護休業法改正|企業がすべき対応と助成金情報
前回の記事では、2025年4月から施行された「出生後休業支援給付金」について、その創設背景や「手取り実質10割」のカラクリ、そして企業の総務ご担当者様向けに申請手続きの詳細を解説しました。
前回の記事は👉2025年4月新設「出生後休業支援給付金」徹底解説 総務担当者が知るべき申請手続きと実務ポイント
今回は、育児と仕事の両立をさらに強力に後押しする、もう一つの画期的な新制度「育児時短就業給付金」に焦点を当てて解説します。
この給付金は、育児休業からのスムーズな職場復帰を支援し、特に時短勤務を選択した際の経済的負担を軽減することを目的としています。
この記事は、2025年育児休業給付金改正の全体像を解説するハブ記事の一部です。全体像はこちらから

この記事でわかること
- 育児時短就業給付金の目的|時短勤務による賃金減少を補填し、育児と仕事の両立を経済的に支援すること
- 支給対象者の要件|2歳未満の子を養育する時短勤務者であり、一定の賃金減少率を満たすこと
- 支給額の基本的な仕組み|時短勤務中の賃金の10%相当額が支給されること
- 支給額の上限・下限のルール|基準賃金月額の上限・下限と、賃金と給付額の合計による減額・不支給の調整
- 具体的な計算事例|給与水準ごとの給付額シミュレーションと、不支給となるケースの判断基準
新設「育児時短就業給付金」とは|目的・概要をわかりやすく解説
「育児時短就業給付金」は、育児休業を終えて職場に戻った後も、育児のために柔軟な働き方を選ぶ労働者を経済的に支えるために創設されました。その主な目的と概要は次の通りです。
育児時短就業給付金の目的|育児と仕事の両立を経済的に支援
この給付金の最も大切な目的は、育児休業から職場復帰後に多くの人が直面する「時短勤務による賃金減少」という課題を解決することです。
子どもがまだ小さい時期は、フルタイムでの勤務が難しいケースも少なくありません。時短勤務は、育児と仕事を両立させる上で非常に有効な手段です。
しかし、時短勤務を選ぶと、どうしても給与が減ってしまいますよね。この給与の減少が、育児と仕事の両立を妨げる経済的な壁にならないよう、給付金で減収分を補うことで、安心して時短勤務を選び、子育てに集中できる環境を整えることを目指しています。
これにより、労働者はキャリアを諦めることなく、育児と両立しながら働き続けることが可能になります。
育児時短就業給付金の支給対象者|2歳未満の子を養育する時短勤務者
「育児時短就業給付金」の支給対象となるのは、以下の条件を満たす方です。
- 2歳未満の子を養育していること
- 給付の対象となるのは、原則としてお子さんが2歳の誕生日を迎えるまでの期間です。
- 所定労働時間を短縮して就業していること
- いわゆる「時短勤務」をしている方が対象です。
- 例えば、これまで1日8時間勤務だった方が、育児のために1日6時間勤務に変更した場合などがこれに当たります。
- 賃金が低下した労働者
- 所定労働時間の短縮によって、育児休業開始前の賃金に比べて賃金が一定割合以上低下した場合に支給されます。
支給要件の詳細 賃金減少率と被保険者要件
給付金を受け取るためには、さらに具体的な支給要件を満たす必要があります。
- 賃金減少率
- 短時間勤務に移行した結果、その期間の賃金が、育児休業開始前の賃金(育児時短就業開始時賃金月額)と比較して100%未満に減少していることが求められます。
- 特に、90%以下に減少した場合には、時短勤務中の賃金額の10%が支給されます。
- 賃金が90%を超え100%未満の場合には、減少率に応じて支給額が調整される仕組みです。 これにより、少しの減額でも給付の対象となるよう設定されています。
- 被保険者要件
- 育児休業給付金と同じく、雇用保険の被保険者であること、そして育児休業開始日より前の2年間に賃金が支払われた日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることなど、一定の被保険者期間の要件を満たす必要があります。
- その他の要件
- 実際に時短勤務に従事していること、ハローワークへの申請手続きを行うことなども含まれます。
育児時短就業給付金の支給額と期間|賃金の10%相当を補填
給付金の支給額は、原則として以下のようになります。
- 支給額
- 育児時短就業中に実際に支払われた賃金額の10%相当額が支給されます。
- 支給期間
- お子さんが2歳になるまでの期間が対象となります。ただし、実際に時短勤務を行い、支給要件を満たしている期間に限られます。
給付額を左右する二段階の上限・下限について
「育児時短就業給付金」の支給額を理解する上で、実は二段階の上限・下限が存在することを知っておくことが重要です。
1. 給付額算出の基準となる「育児時短就業開始時賃金月額」の上限・下限
- 給付金は「時短就業開始時賃金月額」の10%として計算されますが、この「時短就業開始時賃金月額」自体にも、上限と下限が設けられています。
- 上限:470,700円(2025年7月31日まで)
- 時短勤務中の賃金がこの金額を超える場合でも、給付金計算のベースとなる賃金は470,700円に抑えられます。
- 下限:86,070円(2025年7月31日まで)
- 時短勤務中の賃金がこの金額を下回る場合でも、給付金計算のベースとなる賃金は86,070円に引き上げられます。
- ※これらの金額は毎年8月1日に改定される可能性があります。
- 上限:470,700円(2025年7月31日まで)
2. 実際に支給される給付金そのものの下限(2,295円)
- 上記1.の基準賃金月額に10%を掛けて計算された給付額が、月額2,295円未満となる場合は、給付金は支給されません。
- この金額も毎年8月1日に改定される可能性があります。
3. 賃金と給付額の合計による調整(最も重要!)
- 最も重要なのは、「各月に支払われた賃金額と、支給された給付額の合計が、支給限度額(459,000円)を超える場合は、超えた部分が減額される」というルールです。
- これはつまり、「時短勤務中の賃金 + 育児時短就業給付金」が459,000円を超えて支給されることはない、ということです。もし合計が459,000円を超える場合は、その超過分が給付金から差し引かれる形になります。
これらの上限・下限が組み合わさることで、特定の収入層に過度な給付が集中したり、逆に最低限の支援が得られなかったりすることを防ぎ、制度全体としてバランスの取れた支援が実現されます。
具体例で見てみましょう
給付金がどのように支給されるか、具体的な金額でシミュレーションしてみましょう。
1. 育児休業前の月給が30万円で、育児時短勤務中の月給が約18.75万円の場合
- 元の所定労働時間
- 1日8時間
- 育児時短勤務後の所定労働時間
- 1日5時間(元の8分の5に短縮)
- 育児時短勤務中の月給
- 18.75万円(30万円 × 5/8)
- 「育児時短就業開始時賃金月額」(基準となる賃金)は18.75万円。これは基準賃金の上限・下限の範囲内(86,070円〜470,700円)なので、そのまま適用。
- 一時算出した給付額
- 18.75万円 × 10% = 1万8,750円
- 賃金と一時算出給付額の合計
- 18.75万円(賃金)+1万8,750円(一時算出給付額)=20万6,250円
- この合計額は支給限度額459,000円を下回っています。また、一時算出した給付額が給付金として支給される最低額(2,295円)を上回っているため、実際に支給される給付金
- 月に1万8,750円
2. 育児休業前の月給が50万円で、育児時短勤務中の月給が約37.5万円の場合
- 元の所定労働時間
- 1日8時間
- 育児時短勤務後の所定労働時間
- 1日6時間(元の8分の6に短縮)
- 育児時短勤務中の月給
- 約37.5万円(50万円 × 6/8)
- 「育児時短就業開始時賃金月額」(基準となる賃金)は37.5万円。これも基準賃金の上限・下限の範囲内なので、そのまま適用。
- 一時算出した給付額
- 37.5万円 × 10% = 3万7,500円
- 賃金と一時算出給付額の合計
- 37.5万円(賃金)+3万7,500円(一時算出給付額)=41万2,500円
- この合計額は支給限度額459,000円を下回っています。また、一時算出した給付額が給付金として支給される最低額(2,295円)を上回っているため、実際に支給される給付金
- 月に3万7,500円
3. 育児休業前の月給が80万円で、育児時短勤務中の月給が約70万円の場合(基準賃金の上限適用、かつ合計額で不支給となるケース)
- 元の所定労働時間
- 1日8時間
- 育児時短勤務後の所定労働時間
- 1日7時間(元の8分の7に短縮)
- 育児時短勤務中の月給
- 約70万円(80万円 × 7/8)
- 「育児時短就業開始時賃金月額」の上限適用
- 時短勤務中の賃金70万円は、基準賃金月額の上限470,700円を超えているため、給付金計算のベースは470,700円に調整されます。
- 一時算出した給付額
- 470,700円(調整後の基準賃金) × 10% = 4万7,070円
- 賃金と一時算出給付額の合計
- 70万円(賃金)+4万7,070円(一時算出給付額)=74万7,070円
- この合計額は、支給限度額459,000円を大幅に超えています。
- そのため、この場合、一時算出された給付額(47,070円)を加えると支給合計額(賃金+給付金)が支給限度額(459,000円)を大幅に超えてしまうため、給付金は支給されない(=不支給)という取り扱いになります。
4. 育児休業前の月給が10万円で、育児時短勤務中の月給が約5万円の場合(基準賃金の下限適用ケース)
- 元の所定労働時間
- 1日8時間
- 育児時短勤務後の所定労働時間
- 1日4時間(元の8分の4に短縮)
- 育児時短勤務中の月給
- 約5万円(10万円 × 4/8)
- 「育児時短就業開始時賃金月額」の下限適用
- 時短勤務中の賃金5万円は、基準賃金月額の下限86,070円を下回っているため、給付金計算のベースは86,070円に調整されます。
- 一時算出した給付額
- 86,070円(調整後の基準賃金) × 10% = 8,607円
- 賃金と一時算出給付額の合計
- 5万円(賃金)+8,607円(一時算出給付額)=5万8,607円
- この合計額は支給限度額459,000円を下回っています。また、一時算出した給付額が給付金として支給される最低額(2,295円)を上回っているため、実際に支給される給付金
- 月に8,607円
このように、給付金は育児中の収入減を補い、経済的な不安を軽減する役割を果たすことが期待されます。
まとめ|育児時短就業給付金の支給要件と活用ポイント
今回の記事では、2025年4月に施行される「育児時短就業給付金」の基本的な仕組みや支給要件、そして具体的な支給額の計算ロジックについて詳しく見てきました。
この給付金が、育児と仕事の両立を目指す皆さんにとって、どれほど心強い支援となるか、その概要をご理解いただけたのではないでしょうか。
この給付金は、育児中の収入減を補い、経済的な不安を軽減する役割を果たすことが期待されます。
しかし、総務担当者としてこの新しい制度を円滑に運用するには、給付金の具体的な申請フローや、企業としてどのような点に留意すべきかを知っておくことが不可欠です。
次回予告|育児時短就業給付金の申請フローと企業の活用ポイント
次回の記事では、【総務向け実践ガイド】「育児時短就業給付金」申請フローと企業が知るべき活用ポイントと題し、この給付金を実際に活用するための詳細な手続きや、企業が果たすべき役割、よくある疑問点などを徹底解説します。
ぜひ次の記事も参考に、貴社の育児支援体制強化にお役立てください。
次回の記事は👉2025年4月施行!育児時短就業給付金 徹底解説➁|申請フローと企業が知るべき活用ポイント【総務向け実践ガイド】
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。
お勧めのクラウド勤怠管理システムソフト👉パソコンで勤怠管理3 スマートパッケージ版

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。
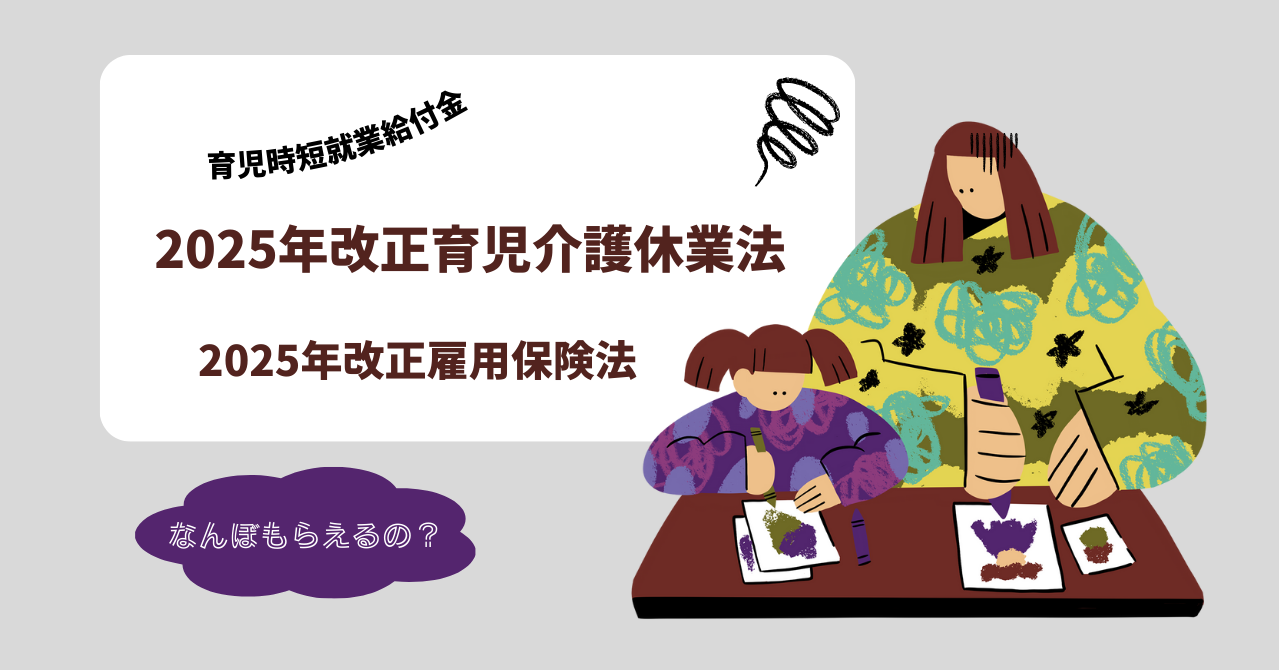

コメント