本記事は「やさしく学ぶ年休シリーズ」シリーズの第1話です。
「有給休暇」という言葉、みなさんも一度は耳にしたことがあるんじゃないでしょうか?
でも、「実際どんな制度なの?」「どうやってもらえるの?」と、その詳しい中身については意外と知らないかもしれませんね。
「会社を休むのは気が引けるな…」「休むとお給料が減っちゃうのかな?」そんな心配はご無用です!
年次有給休暇(通称:年休、有給) は、働く皆さんが心身をリフレッシュし、仕事への活力を養うために法律で定められた大切な権利なんです。
そして、休んでもお給料が減らない、つまり「給料がもらえるお休み」なんですよ。
このシリーズでは、働く皆さんがご自身の権利をきちんと理解し、上手に年休を活用できるよう、その基本から応用までを9回にわたって徹底解説していきます。
「やさしく学ぶ年休シリーズ」全9回のご案内
このシリーズでは、働く皆さんがご自身の権利をきちんと理解し、上手に年休を活用できるよう、その基本から応用までを徹底解説します。
- 第1回:年次有給休暇ってなんだ?働く人のための基本ガイド
- 年休の定義、付与の基本ルール、労働基準法上の位置づけなど、土台の説明。
- 第2回:年休はいつもらえる?何日もらえる?—付与要件と日数の計算方法
- 6か月・8割ルール、勤続年数による付与日数、労働日数が少ない人への比例付与など。
- 第3回:働く人のための有給休暇ガイド|パート・アルバイトの付与条件と日数
- 非正規労働者の年休権利、週所定労働日数別の比例付与表など。
- 第4回:年休の取り方・使い方—申請ルールと注意点
- いつ・どう申請する?会社は拒否できる?取り方のコツとNG事例。
- 第5回:計画的付与って何?—会社が決めた日に年休を取る仕組み
- 計画的付与制度の仕組み、対象となる日数など。
- 第6回:年次有給休暇の計画的付与で損しないために|労働者が押さえる注意点
- 強制との違い、計画的付与制度のメリット・デメリットなど。
- 第7回:【労働者・会社員向け】時季変更権とは?会社が年次有給休暇の申請を拒否できる条件を解説
- 会社側の「時季変更権」とは?その濫用は許されない。
- 第8回:退職する時に有給休暇は全部使える?法律と円満退社のポイント
- 退職時の年休消化、会社の対応、買い取りは合法かどうかなど。
- 第9回:有給休暇は2年で消滅する?会社員が知るべき時効の仕組みと自分でできる対策
- 2年で消えるって本当?失効しないためにできる工夫や対処法。
年次有給休暇(年休、有給)とは?
年次有給休暇は、その名の通り「毎年決まった時期に、まとまった日数が付与され、休んでも給料が支払われる休暇」のことです。
労働基準法という法律で、働く皆さんに与えることが義務付けられています。
年次有給休暇の定義とは?
- 年次有給休暇とは、労働基準法で定められた、給料が支払われる休暇のことです。
- 病気や個人的な事情で会社を休むと、その日はお給料が出ないのが一般的ですが、年休を使えば、休んだ日も通常通りのお給料が支払われます(無給ではありません)。
その主な目的は、毎日お仕事を頑張っている皆さんの心身の疲労回復や、リフレッシュ、そして生活の質の向上です。
趣味の時間に使ったり、家族と過ごしたり、病院に行ったりと、使い道はあなた次第です。
年次有給休暇の特徴|労働者が知っておくべき権利とポイント
- 労働者の権利
- 年休は、会社が「与えてあげる」ものではありません。
- 働く人自身が取得したい日を会社に申し出ることで、取得できる大切な権利です。
- 原則、会社は拒否できない
- 会社は、原則として労働者からの年休取得の申し出を拒否することはできません。
- ただし、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、会社には「時季変更権」という例外的な権利があります。これについては、別の回で詳しく解説しますね。
労働基準法で保障された年休の位置づけ
先ほども少し触れた通り、年次有給休暇は、単に会社からの「恵み」や「厚意」ではありません。
皆さんが当然持つべき権利として、日本の法律でしっかりと位置づけられています。
法律で守られた「休む権利」
私たちの働き方を守るための最も大切な法律が「労働基準法」です。
この法律は、皆さんが安心して、人間らしい生活を送りながら仕事ができるように、最低限の労働条件を定めています。
年次有給休暇は、まさにこの労働基準法の第39条に明確に記されているんです。
これは何を意味するかというと、会社が勝手に「うちは有給なし!」と決めたり、「有給は無給だよ」と言い張ったりすることは許されません。
会社には年次有給休暇を取得させる義務がある
会社(法律では「使用者」と呼びます)は、年次有給休暇を「与えるかどうか選択できる権利」を持っているわけではありません。
法律で定められた条件を満たした従業員に対しては、労働者の申し出があった場合に、原則として有給休暇を取得させなければならない義務 を負っています。
もし会社がこの法律に違反して年次有給休暇を付与しなかったり、皆さんが有給を取りたいと申し出たのに正当な理由なく取得を妨げたりした場合、それは法律違反となり、罰則が科されます。
つまり、年休は、皆さんが安心して働くために、そして必要に応じて休息を取るために、憲法で保障された「勤労の権利」を具体的に支える「休む権利」の一つとして、法律によって力強く守られているものなんです。
年次有給休暇が付与される基本ルール
「年次有給休暇は大切な権利だってことは分かったけど、じゃあ、会社に入社したらすぐに有給って取れるの?」
そんな疑問をお持ちの方もいるでしょう。
年次有給休暇が初めて付与されるには、法律で定められたいくつかの基本的な条件を満たす必要があります。
ここでは、年休が皆さんに「付与される」ためのルールについて解説します。
年休がもらえる2つの基本条件
年次有給休暇が皆さんに初めて付与される(もらえる)には、以下の2つの基本条件をクリアしている必要があります。
- 雇い入れの日から6ヶ月以上継続して勤務していること
- これは、会社に入社した日(雇い入れの日)から数えて、半年間(6ヶ月間)以上、その会社で働き続けているという条件です。
- 半年経たないと、原則として年休は付与されません。
- その期間の全労働日の8割以上出勤していること
- 半年間の間に、会社が定めた出勤日(全労働日)のうち、8割以上の日数で実際に出勤している必要があります。
- ここでいう「出勤」には、遅刻や早退も含まれますのでご安心ください。
- また、産前産後休業、育児休業、介護休業など、法律で定められた特別な休業期間は、原則として「出勤したもの」として扱われます。これらの休業によって年休が付与されなくなることはありません。
どんな雇用形態でも取得可能!年休の権利を確認しよう
「正社員じゃないから有給はもらえない…」そう思っていませんか?それは誤解です!
上記の2つの条件(「6ヶ月以上継続勤務」と「8割以上出勤」)を満たしていれば、正社員、パート、アルバイトといった雇用形態にかかわらず、すべての労働者に年次有給休暇は付与されます。
非正規雇用の方も、自身の有給休暇の権利をきちんと確認しましょう。
初めて付与される有給日数と、働き続けた場合の日数の変化
最初の年次有給休暇の付与日数は、通常、10労働日です。これは、週5日勤務など、一般的なフルタイムで働く方を想定した日数となります。
その後、皆さんが会社で働き続ける勤続年数に応じて、付与される年休の日数は増えていきます。
例えば、1年半勤務すれば次の日数が、2年半勤務すればまた次の日数が…というように増えていくのが一般的です。
具体的な付与日数や、労働日数が少ないパート・アルバイトの方の付与日数については、次回の記事でさらに詳しく解説していきますので、ぜひそちらも参考にしてください。
まとめ 年休はあなたの「休む権利」
今回は「やさしく学ぶ年休シリーズ」の第1回として、年次有給休暇の基本的な仕組みについて解説しました。
- 年次有給休暇は、休んでも給料がもらえる、法律で保障された大切な「休む権利」です。
- 会社は年休を「与えるかどうか選べる権利」を持っているのではなく、条件を満たした労働者には取得させなければならない義務があります。
- 初めて年休がもらえるのは、入社から6ヶ月以上働き、その期間の8割以上出勤していることが基本的な条件です。
- 雇用形態にかかわらず、パートやアルバイトの方も対象になります。
年休は、皆さんが心身をリフレッシュし、より充実した生活を送るためにある大切な制度です。
この機会にぜひ、自分の年休について正しく理解し、上手に活用してくださいね。
次回予告|年休の付与日数と計算方法をわかりやすく解説
第2回では、今回学んだ基本ルールをさらに深掘りしていきます。
具体的に「年休は何日もらえるの?」「パートやアルバイトの場合は日数が違うの?」といった、皆さんが一番気になるであろう付与日数やその計算方法について、詳しく解説します。
ぜひ次回の記事もチェックして、ご自身の年休をしっかり把握しましょう!
次回の記事は👉年休はいつもらえる?何日もらえる?—付与要件と日数の計算方法【やさしく学ぶ年休シリーズ 第2回】

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|29240010号)
- 会社員歴30年以上、転職5回を経験した氷河期世代の社会保険労務士です。自らが激動の時代を生き抜いたからこそ、机上の空論ではない、働く人の視点にたった情報提供をモットーとしています。あなたの働き方と権利を守るために必要な、労働法や社会保険の知識、そしてキャリア形成に役立つヒントを、あなたの日常に寄り添いながら、分かりやすく解説します。
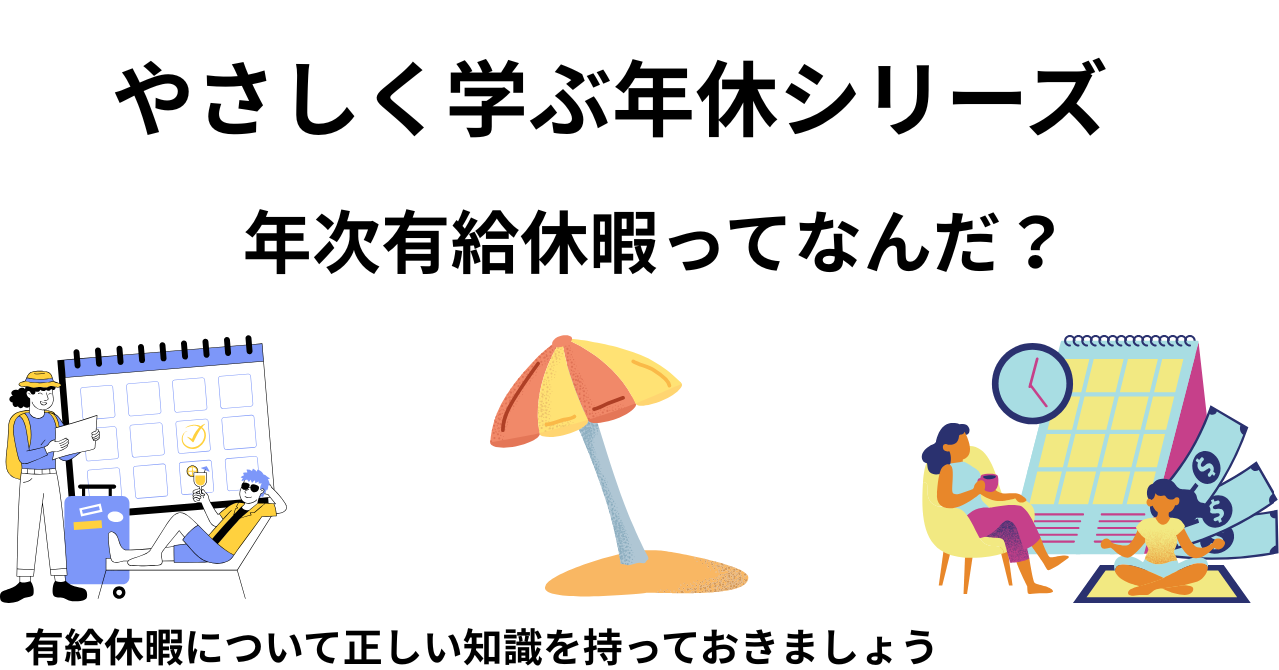
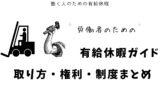
コメント