令和4年8月28日(日)暑い。昨年と同じく快晴です。
昨年と同じ轍は踏まない、と思っていたので、妻に弁当を所望しておきました。
この1年ずーっとダイニングテーブルで勉強をしていました。(炬燵は腰が痛くなるので止めました。)さすがに家族も「これは本気だな。」と思っているでしょう。
高校受験、大学受験の時を思い出します。やるべきことはやった。
最終1週間はアクシデントがあり、思っていたような最終調整は出来ませんでした。
しかし、もうこれ以上は出来ない、というところまではやったのではないか。あと合格するだけです。
いざ出陣|令和4年度社労士試験当日の開始と心境
鶴橋で尼崎行きに乗り換え、九条駅で中央線へ。コスモスクエア駅で下車すると、昨年と同じような光景です。
乗客がやたら多い。ほぼすべて社労士受験生でしょう。老若男女そろってます。
インテックス大阪までは駅から徒歩10分です。着席時刻AM10:00、選択式試験開始AM10:30です。9時半ごろに到着しました。
自分の席を探し着席します。周りの受験生はテキスト等を眺め、最終チェックでもしているのでしょう。
私はというと、ここまで来たらジタバタしても始まらん、と何故か達観したような心境です。
昨年はこの時間に眺めていた箇所がそのまま出題されてのラッキーがありました。
しかし、今年は最早そのような神頼みなど必要のないとこまで実力的には到達しているのではないか、と思っていたので、眼を瞑って精神集中をしていました。
令和4年度社労士試験始まります
10時になりアナウンスが始まります。「いよいよか・・・」精神状態としてはいい感じです。
社労士試験は運の要素が強い試験である、とよく言われます。それは、選択式の試験のことを言っているのでしょう。
各科目5問の出題で、3得点以上が必須です。労働関係科目、社会保険科目での初見でわからない問題というのはあまり出題されません。
労一・社一の問題、特に労一の問題で初見のもの、重箱の隅をつつくような問題が出た時にこの3点という基準点が取れない、という事を指して「運の要素が強い」と言われているのでしょう。
私の場合もやはり事前の模試で浮き彫りになった課題は、選択式の労一でした。
2度模試を受けて2度とも基準点割れでした。逆にここを突破できれば合格が見えるはずです。
労働関係科目|労働基準法・安衛法、労災法、雇用保険法
10時30分になりました。選択式試験の開始です。
まずは労働基準法・労働安全衛生法
ここは、やはり判例問題と安衛法でしょう。
まず1問目の労働基準法の普通の問題。これは落とせない。これを落とすと、間違いやすい判例問題と安衛法の問題が落とせなくなります。
第1問は解雇予告の問題。よっしゃ!これは確信歩きみたいな問題、打った瞬間ホームラン級に自信をもって解答。
続いて運命の判例問題。転勤に関する判例ですね。これは記憶にあるぞ。これは大丈夫だ。労働判例100のおかげか?
続いて安衛法の2問。安全衛生のための教育。労働者を雇い入れた時、「作業内容を変更した時」これは基本問題です。
最後に労働安全衛生法第3条の条文問題。「快適な職場環境の実現」これはいけた。
手ごたえは申し分なし。ただ選択式はいきなり見たこともないような問題が出てきたら一瞬で終了する特性があるため、浮かれている場合ではありません。
続いて労災法
感覚的に3点は取れるでしょ、と勝手に思っている科目です。
1問目2問目はさんざん勉強した業務災害の障害等級の加重の問題。確信解答しました。
3問目4問目5問目は中小事業主の特別加入の問題。少し迷うところもありましたが、ほぼ間違いないだろう、というところ。
雇用保険法
賃金日額と教育訓練給付金に関する問題です。これはかなり苦戦しました。
2問は確信して解答し、1問はさっぱりわからない。残り2問は最後まで2つまでに絞り込んだが・・・という感じでした。
少し不安を残しましたが、大丈夫じゃないかなぁ。5点は要らない。3点でいい。
社労士試験・一般常識科目
毎年、この科目は話題になることが多いですね。出題範囲の広さ、白書・統計からの出題など、難易度が高くなる要素が満載なのです。
運命の労務管理その他の労働に関する一般常識
障害者雇用率制度の問題が3問。残りはどうも判例問題のようです。
やはりここでは2つのリスク要因が顔を覗かせます。
一つ目のリスクは他の科目と比べて勉強不足なところがある、二つ目のリスクは範囲が広すぎて初見事項の出題の可能性が高い、ということです。
「あれ、どっちだっけ?」と最後まで悩んだ問題が一つ。初見の事項が一つ。
まず一つ目の悩んだ問題というのが、障害者の法定雇用率を満たしていない事業主(常用雇用労働者【□】の事業主に限る)から納付金を徴収する・・・この□に入る選択肢。
最初にパッと100人超と思ったのですが、あれ?50人超だったような気が・・・、と考え始めてしまう。
そして二つ目は初見すぎて全くわからない。
選択肢は恐らくこの4つ。ジョブコーチ、ジョブサポーター、ジョブマネージャー、ジョブメンター。さっぱりわかりません。
結論、一つ目は100人超え、二つ目はジョブメンターと解答。
残りの判例問題です。これもどこかで・・・とは思いましたが、おそらくこれだろう、という解答の仕方です。
やはり不安が残ります。これは微妙だ。
続いて、社一です
正直この科目はいける、というイメージが固まっています。
統計問題は必ずと言っていいほど1問は出ます。
しかし、模試の時もそうでしたが、それ以外は大体過去問、テキストからの出題になってくるので、確かに他の科目よりは勉強時間は不足していたのでしょうが、3点は確保できるだろう、と踏んでいました。
第1問目は国民医療費の65歳以上の構成割合の問題です。
これは「よくわかる社労士 別冊合格テキスト 直前対策 2022年度版 (TAC出版)最強の一般常識対策本」に載っていたという記憶だけはありました。
しかし憶えてませんでした。31%、46%、61%、76%という選択肢なのですが、たしか、とある年齢以上になると急激に医療費が激増する、というのは憶えていたので、「こんなの76%に決まってる」と確信をもって解答。
次の問いが企業型確定拠出年金です。これも迷いに迷った問題でした。「子」と「配偶者」で最後まで迷いました。最初は直感的に「配偶者」にしていたのですが、最後に時間が余ったので、その時間によくよく考えて「子」という解答にしました。
残りの3問は頻出の児童手当法と介護保険法の問題です。テキストからの出題で特に捻った問題ではなかったです。1問だけ「あれ?どうやったけなぁ」と思いながら解答をしましたが、まぁ大丈夫でしょう。
社会保険科目|健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法
健康保険法
これはもう、基本問題のオンパレードでした。
いや~ここで点数を稼いでおかないと、みたいな問題です。
例えば8科目全部3点だと合計24点で、基準点割れはしてないけど不合格、というのもあり得ない話ではないはずです。このような問題で確実に5点取っておかないとな。
今のところ、去年と比べると雲泥の差です。
予定通りと言っては何なのですが、やはり労一が多少不安ですが、手応え的にはいけてるのではないか?と感じながらやっています。
厚生年金保険法
第1問目と第2問目が産前産後休業の問題。基本だ。
第3問目が事例問題です。正直、これはよく分からなかったですね。適当にとか、そんなのではないのですが、これ以上考えても答えは出ないなぁ、と思ったので、一応これだと思ったもので解答。
残りは在職老齢年金制度と事後重症の障害厚生年金に関する問題でした。これも基本問題です。いけているはず。
最後に、国民年金法
障害基礎年金、寡婦年金、年金定期便、国民年金基金の問題でした。この国民年金基金の問題がちょっと分からなかったくらいで、他はいけたのではないか。
選択式試験は、どの受験生もそうだと思うのですが、時間が余ると思います。途中退出する受験生もチラホラいます。私も、途中退出してもよかったのですが、一応マークミスがないかの確認と、迷って解答した問題を再度見直しました。
11時50分。令和4年度社労士試験選択式終了です。
手応えはいいです。
しかし、やはり思った通り「労一」の結果次第じゃないでしょうか?合計点からの考えでは、8割前後は確信をもって解答したので、合計点割れはないなぁ、と感じていました。
とりあえず、選択式は終わりました。昼食を挟んで、午後からの択一式に臨みます。続く。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 50歳を目前に、会社員として働きながら、様々な事情により社会保険労務士試験への独学での挑戦を決意しました。不合格という苦い経験もしましたが、そこで諦めることなく合格を勝ち取りました。
- このブログでは、自身の経験を踏まえ、特に「仕事と受験勉強の両立に悩む会社員の方」や「独学で合格を目指す方」にとって有益となる社労士試験合格への道のりをお届けします。

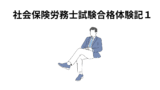

コメント