早朝の静寂の中、常温の牛乳コーヒーを片手に一問一答の問題集を開きます。
朝早く起床するのは慣れっこです。
通勤電車に揺られながら、テキストを読み、暗記に勤しみます。
社会保険労務士試験合格へ向けて、私の勉強ペースはまさに波に乗ってきています。
※1年目の道のりをまだ読んでいない方は、まずはこちらからどうぞ。
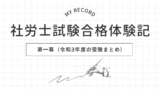
社労士試験勉強を「生活習慣」にするまでの試行錯誤
「勉強をする」ということを、やる気に依存すると良くない、とは思ってました。
「今日は気分が乗らないから、やめておこう」とか、「今日はいけそうだからやろう」とか。
そうやって日々の気分で判断していたら、1年近く続ける勉強なんてきっと続かない。そういう気がしていました。
だから私は、まず「ルーティン化すること」が大事だと考えました。
とはいえ、そこにたどり着くまでには、やはり試行錯誤が必要でした。
本業の仕事をこなしながら、体調にも気を配り、限られた時間をどう使い切るか。「勉強」を、単なる勉強ではなく「生活習慣そのもの」にしてしまおう、と考えました。
早朝に勉強する。通勤電車の中で勉強する。
こうして少しずつ自分なりのペースができてきて、なかなかいいリズムで続けられています。
生活リズムを崩す異動…社労士試験勉強への影響と対策
しかし、私の思いとは裏腹に、会社ではまたしても予期せぬ事態が起こりそうなのです。
本業の話に戻りますが、私が加工部に異動してから数週間後、私の後任だったKさんが退職したのは以前にも記した通りです。そのKさんの後を引き継いだのがN君でした。
しかしながら、彼も短命に終わります。「退職した」ということではないのですが、やはりあまり慣れていなかったというのもあります。
突然の会社からの指名というのもあり、準備不足だし、戸惑った、というのもあったと思います。売上がどうこうということではなく、まぁなかなかの損金が発生し、担当を外されてしまいます。
やはり、ここで何かが起こりそうな嫌~な予感がします。
社労士試験勉強中の営業部復帰危機と生活リズムへの影響
TK社長が私を営業部に戻そうとしている、という噂が流れます。
私が加工部に異動になった途端、後任が即座に退職します。
そのまた後任が、数か月で担当を外される、という事態が発生します。
完全に会社としては思惑が外れて「営業社員が不足してしまっている」という状況に陥ってしまっています。
「ヤバいやんけ」
私としては完全に焦りました。正直に言って、生活習慣が安定しており、早朝勉強、電車内勉強も習慣化して波に乗っており、いまのペースを崩されたくない、と思ってました。
営業の仕事に関しては、多少なりとも未練はありました。
でも、また早朝に出勤し、夕方前に帰宅し、家事をしながら仕事をし、床に就く。そんな生活に戻るとなると、どうしても無理が出てきます。
どうせ車通勤に戻るでしょうし、そうなれば、合格のために描いた生活の青写真は完全に崩れてしまいます。
TK社長と、膝を突き合わせて話をしてしまうと、とてもじゃないけど勝ち目は無く、押し切られるに決まってます。
なんとしてでも回避しなければ、とあれこれ考えました。
社労士受験生活を守る一筋の光明と実践的回避方法
そんな中、一筋の光明があるとすれば、これか!ということがありました。
それは加工部にいるH君が「一回営業というのをやってみたい」と言っている事でした。これは使えるかもしれない。
TK社長と直で話す羽目になる前に「H君が営業部に非常に興味がある」という噂を流します。
噂というのはちょっと大げさなのですが、事前に取締役のM部長から電話で打診があったときに、「今営業に戻るのはちょっと体力的にしんどいです。」と以前の大病の件を引っ張り出して切実にアピールします。
その上で「それよりも、H君が是非営業をやりたいといっているので、長い目で見ても彼を営業部に異動させたほうが会社にとってもいいのではないですか?」と、H君の意向を伝えました。
もちろんH君には了承を得ています。
職場異動の危機を回避!社労士受験生活を救ったH君のやる気
これが功を奏して、思惑通りにことが進みました。H君のやる気と私の「病気を理由にした現状維持」という訴えが、TK社長の耳に届いたのでしょう。
結果として、H君が営業部に異動することになり、私は加工部に残ることになります。
いや~よかった。今回もしH君を生贄にした、となれば後味が悪かったのでしょうが、H君はやる気満々だったので、結果的にはこれでよかったのだと思います。
「まさか」の連続、社労士合格への道は続く
この株式会社MS、中央卸売市場の仲卸業ですが、まぁ色々なことが起きます。じつはこの数か月後にも、「まじか!」ということが勃発います。それはまた追々述べていきます。
勉強のほうは、今のところ思い描いた通りに進んでいます。
とはいえ、なにせ独学です。どれだけ手応えがあっても、自分が今どれくらいの位置にいるのか──つまり、本当の実力がどの程度なのか──それがはっきりとは見えてきません。
勉強の「進捗」というのは、単に「これだけ勉強した」という量の話ではありません。
本当に大事なのは、「今の自分に、どれだけの力がついているのか」を客観的に把握できているかどうか、だと思うのです。
それがわかるのは、やはり5月や6月の模試を受けてみてから、なのかもしれません。続く

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 50歳を目前に、会社員として働きながら、様々な事情により社会保険労務士試験への独学での挑戦を決意しました。不合格という苦い経験もしましたが、そこで諦めることなく合格を勝ち取りました。
- このブログでは、自身の経験を踏まえ、特に「仕事と受験勉強の両立に悩む会社員の方」や「独学で合格を目指す方」にとって有益となる社労士試験合格への道のりをお届けします。
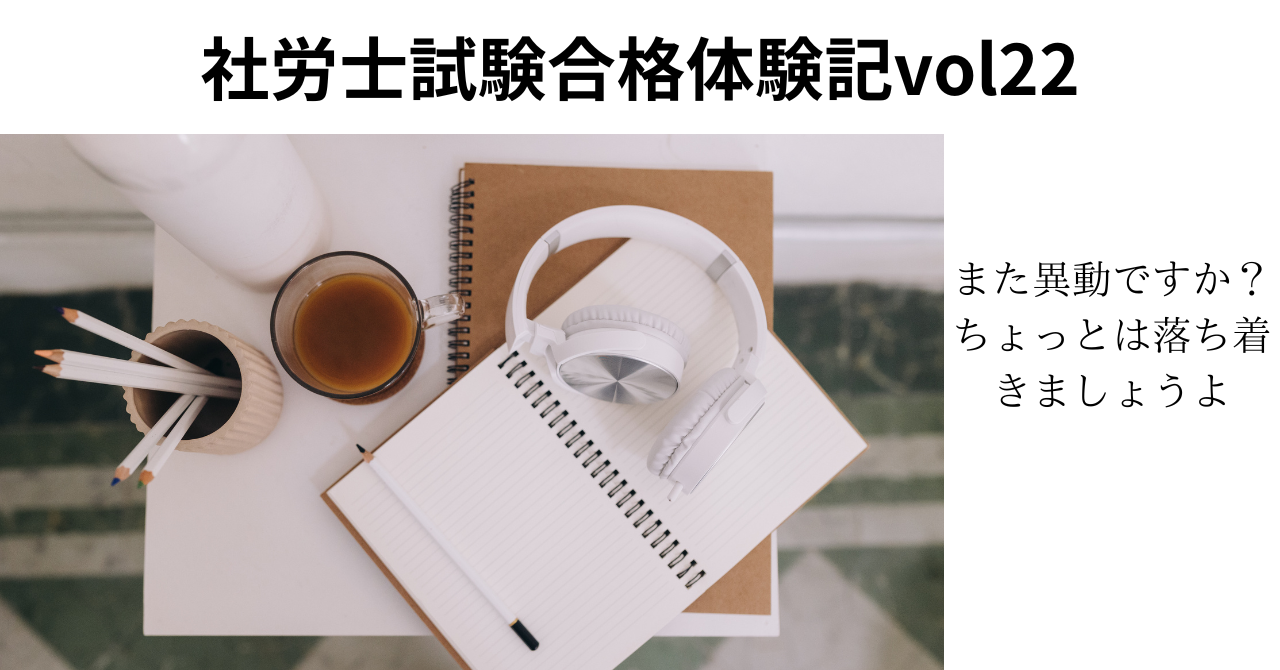
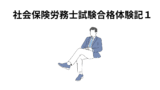

コメント