本記事は「知っておきたい!年次有給休暇のすべて」シリーズのvol12です。
前回は「非正規雇用・多様な働き方と有給休暇」をテーマに、シフト制アルバイトや時間単位年休、そして在宅勤務といった現代の多様な働き方における有給休暇の具体的な考え方や運用について深く掘り下げていきました。
前回の記事は👉多様な働き方に対応|有給休暇管理|フレックス等の実務ポイント
複雑に思える管理も、「正しい知識と具体的な対応策」 があれば円滑に進められることをお伝えできたかと思います。
有給休暇は、労働者の心身のリフレッシュを促し、ワークライフバランスを向上させるために、法律で定められた大切な権利です。
従業員が安心して休暇を取得できる環境は、企業の生産性向上やエンゲージメント強化にも繋がる、まさしく 「Win-Win」 の関係を築くための重要な要素と言えるでしょう。
有給休暇がトラブルの火種になる理由と背景
しかし、現実はどうでしょうか?残念ながら、有給休暇の運用を巡っては、労使間で様々なトラブルが後を絶ちません。
「まさかこんなことで揉めるなんて…」というケースも少なくないのが実情です。
なぜ、本来はポジティブな制度であるはずの有給休暇が、ときに労使間の摩擦やトラブルの火種となってしまうのでしょうか?
その根本には、主に以下の3つの要因が潜んでいます。
有給休暇トラブル、原因は本当に「認識のズレ」?
「有給休暇は、申請すれば好きな時にいつでも取れるはずだ。」と考える従業員と、「事業運営に支障がない範囲で、会社の事情も考慮して取得してほしい。」と考える企業側(特に管理職)との間には、時に大きな認識のギャップが存在します。
従業員は、労働者としての権利行使を前面に出しがちです。
しかし、企業側は、限られた人員で業務を滞りなく遂行するという責任があります。
このそれぞれの立場からの視点の違いが、有給休暇の申請・承認プロセスにおいて摩擦を生み出す、最も根深い原因の一つとなるのです。
有給休暇トラブルの原因|法律理解不足と運用体制の不備
年次有給休暇に関する労働基準法の規定は、一見するとシンプルに見えるかもしれません。
しかし、その具体的な解釈や、日々変化する実務への落とし込みには、実は多くの注意点や例外が存在します。
例えば、企業が有給休暇の取得時期を調整できる「時季変更権」の厳格な要件、退職時に残った有給休暇の取り扱い、そして近年義務化された「年5日の取得義務」など、これらのルール全てを正確に把握し、適切に運用できている企業は残念ながらまだ多くありません。
「この申請は法的に拒否できるのか?」「罰則のリスクはないのか?」といった法的な知識の不足や、あるいは社内での申請・承認フローが明確でなかったり、形骸化していたりする運用体制の不備が、トラブル発生の直接的な引き金となるケースが非常に多いのです。
特に、専任の労務担当者がいない中小企業では、最新の情報をキャッチアップし、制度を整備していくことに課題を抱えている場合も少なくないでしょう。
よくある有給休暇トラブル事例と発生の背景
こうした労使間の認識のズレや、法律・運用体制の不備が積み重なることで、「急な有給申請で現場が混乱した。」「退職直前に残っている有給を全て消化したいと言われた。」「有給休暇を取った従業員が、なぜか昇進で不利になった。」など、具体的なトラブルへと発展してしまいます。
これらの事例の背景には、単に制度的な問題だけでなく、職場のコミュニケーション不足や、従業員が「有給を取りにくい。」と感じてしまうネガティブな職場風土が影響していることも少なくありません。
本記事では、そうしたトラブルが発生した際の具体的な対処法や、労使双方の視点からトラブルを円満に解決するためのヒント、そして何よりもトラブルを未然に防ぐための予防策について、実践的な内容を掘り下げていきます。
従業員側から発生する有給休暇トラブル事例と具体的な対処法
有給休暇に関するトラブルは、企業側からの不適切な対応だけでなく、時に従業員からの申請方法や要求によって生じることもあります。
ここでは、企業が従業員からの有給休暇の申請に対して「困ったな…」と感じやすい具体的な事例と、それぞれの対処法を掘り下げていきましょう。
事例1|従業員の突然の有給休暇申請による業務への影響と対処法
「明日休ませてください。」「来週から1週間有給を使います。」といった、直前あるいは業務調整が難しいタイミングでの有給申請に、頭を抱えた経験はありませんか?
特に人手不足が慢性化している中小企業では、急な欠員は業務の停滞や他の従業員への過度な負担に直結し、時には事業の正常な運営に重大な支障をきたすリスクすらあります。
1. 時季変更権の適切な行使
原則として、従業員が指定した時季に有給休暇を与えなければなりません。
しかし、例外的に「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、企業は時季変更権を行使し、別の日に変更を求めることができます。
- ポイント
- この「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、単に忙しいというだけでは認められず、代替要員の確保が著しく困難であるなど、客観的かつ具体的に業務への重大な支障が証明できる場合に限られます。
- 安易な行使は違法と判断されるリスクがありますので、慎重な判断と、従業員への丁寧な説明が不可欠です。
- もし、この要件に該当する状況であれば、代替案(例:別日の提案、一部の期間だけ出勤を依頼など)を提示し、従業員と十分に話し合いましょう。
- 【企業向けガイド】有給休暇の取得希望と会社の対応|時季指定権・時季変更権の正しい運用法 を再度ご確認ください。
2. 事前の相談奨励とルール化
- 従業員に、有給休暇を取得する際はできるだけ早く、事前に相談するよう奨励しましょう。
- 就業規則に「有給休暇の申請は〇日前までに行うこと。」といったルールを明記し、社内への周知を徹底することも有効です。
- これは、あくまで「申請期限」であり、その期限を過ぎたからといって有給申請を拒否できるわけではありませんが、従業員に計画的な取得を促す意識付けにはなります。
3. 業務体制の見直し
- 根本的な解決策として、特定の業務が特定の人間に集中する「属人化」を解消し、誰かが休んでも業務が滞らないような多能工化や、業務の標準化を進めることが重要です。
- これにより、急な有給取得にも柔軟に対応できる体制を構築できます。
事例2|退職時の有給休暇一括消化要求によるトラブルと円満対応策
従業員が退職する際、残っている有給休暇を退職日までに消化することは一般的な流れです。
しかし、退職申し出のタイミングや残日数の多さによっては、引き継ぎ業務が十分に行えなかったり、後任者の確保が間に合わなかったりするなどで、業務に影響が出ることに企業として困惑するケースも稀に発生します。
多くの企業では、退職日と有給消化期間を考慮して最終出社日を決定するのが通例ですが、予期せぬ状況で調整が難航することもあります。
1. 円満退職に向けた話し合いと調整
- 法的に、退職予定者であっても有給休暇の取得を請求する権利は原則として認められます。
- 企業側に時季変更権を行使することは、退職日をすでに定めている以上、極めて困難です(「事業の正常な運営を妨げる」状況が退職によって避けられないため)。
- そのため、最も現実的かつ円滑な対処法は、従業員と十分に話し合い、双方にとって納得のいくスケジュールで円満な解決を図ることです。
- 退職の申し出があった時点で、まず有給休暇の残日数を確認し、最終出社日と有給消化期間の全体像を速やかに共有しましょう。
- 引き継ぎ期間の確保や残務処理の必要性を伝え、有給消化期間と業務遂行のバランスをどのように取るか、具体的な相談を進めてください。
- 必要であれば、一部の業務を他の従業員に早めに移管するなど、企業側も積極的に調整策を提示しましょう。
- 従業員の退職後の生活設計も考慮しつつ、双方が協力して無理のない退職プロセスを構築する姿勢が重要です。
2. 就業規則による明確化
- 退職時の有給休暇の取り扱いについて、就業規則に具体的なルールを定めておくことは、円滑なプロセスに繋がります。
- 「退職を理由とした有給休暇の取得に関する手続きや、引き継ぎの協力について」など、具体的なフローや、従業員に協力をお願いする旨を明確に記載し、周知しておきましょう。
- ただし、有給取得権を不当に制限する内容であってはなりません。
3. 有給買上げの検討(原則禁止の例外として)
- 年次有給休暇の買い上げは、労働基準法に直接的な規定はありません。
- しかし、有給休暇が労働者の心身のリフレッシュを目的とした「休暇」であり、金銭で代替されるべきではないという法の趣旨に基づく行政解釈(行政通達など)により、原則として禁止されています。
- しかし、ごく限られた状況においては、有給休暇の本来の目的を阻害しないと判断され、例外的に買い上げが認められるケースがあります。
- これは、主に行政通達(昭和30年11月30日 基収第4718号など)や、それを踏まえた過去の裁判例によって、違法とはならないとされているものです。
- 退職時に未消化で残っている有給休暇
- 退職日以降は雇用関係がなくなるため、有給休暇を行使する機会が失われます。
- この場合に限り、企業が残日数分を買い上げることは違法とされていません。
- これは、業務上の都合でどうしても消化期間の調整が難しい場合の、最終的な解決策の一つとなり得ます。
- 時効によって消滅した有給休暇
- 付与されてから2年間で時効により消滅し、もはや行使できない有給休暇を買い上げる場合です。
- この場合も、すでに権利行使ができないため、買い上げは違法とはなりません。
- 法定の日数を上回って付与された有給休暇
- 労働基準法で定められた最低限の有給休暇日数を超えて、企業が独自に付与している有給休暇(法定外の特別休暇など)の買い上げは、労使の合意があれば可能です。
- この部分は労働基準法の規制を受けないため、買い上げは違法とはなりません。
- 退職時に未消化で残っている有給休暇
重要ポイント
- これらのケースにおいても、企業に買い上げの義務はありません。
- あくまで企業が任意で行うものであり、従業員が買い上げを請求する権利があるわけではありません。
- 有給休暇の取得を妨げることを前提とした買い上げの予約や、本来取得すべき日数を減らす目的での買い上げは、労働基準法違反となります。
- 買い上げを検討する際は、労使間で十分に話し合い、法的解釈を正しく理解した上で行うことが重要です。
事例3|有給休暇取得理由の申告拒否トラブルと企業の対応ポイント
従業員が有給休暇を申請する際、理由を尋ねても「私用です」の一点張りで教えてくれない、あるいは理由を伝えること自体を拒否されるケースです。
企業側としては、業務調整のためにも理由を把握したいという心理が働くでしょう。
特に、連続休暇や長期休暇の場合、業務の段取りを組む上で情報がないと困る場面も出てきます。
1. 理由を尋ねることの合法性(原則不要)
- 結論から言えば、労働基準法上、従業員が有給休暇を取得する際にその理由を会社に申告する義務はありません。
- 企業が理由を尋ねることは可能ですが、それ自体を拒否したからといって有給申請を拒否することはできません。
- 有給休暇は、労働者が自由に利用できる権利だからです。
2. 業務調整のための協力要請の範囲
- ただし、業務の円滑な遂行のために、企業が従業員に対し「差し支えなければ、業務調整のために簡単な理由を教えてもらえないか」と協力を求めることは可能です。
- これはあくまで「お願い」であり、強制ではありません。
- 例: 「〇〇さんの業務は△△の対応が必要ですが、お休みの間に誰が対応するか調整するため、差し支えなければ簡単な目的をお聞かせいただけますか?」といった形で、具体的な業務上の必要性と紐付けて説明することで、従業員も理解を示しやすくなる場合があります。
3. プライバシーへの配慮
- 従業員のプライバシーに関わるデリケートな理由(例:通院、家庭の事情など)がある場合も少なくありません。
- 企業側は、理由を深掘りしすぎないよう、また、知り得た情報は適切に管理し、漏洩させないよう、細心の注意を払う必要があります。
- 従業員との信頼関係を損なわないためにも、プライバシーに配慮した対応が求められます。
まとめ|有給休暇トラブルは対話で解決!労使の信頼を築くポイント
ここまで、従業員側から発生しがちな有給休暇を巡るトラブル事例と、その具体的な対処法について見てきました。
突然の申請、退職時の有給消化、そして取得理由の申告拒否など、どれも「あるある」と感じられるケースだったのではないでしょうか。
これらのトラブルの根底には、法の正しい理解不足や、労使間のコミュニケーション不足、そして「有給休暇」に対する認識のズレが横たわっています。
しかし、ご安心ください。今回の解説で示したように、就業規則の明確化、そして何よりも従業員との丁寧な対話を通じて、多くの問題は未然に防ぎ、あるいは円満に解決へと導くことができます。
有給休暇は、従業員の権利であると同時に、企業が健全な経営を続けるための重要なツールでもあります。
従業員が心身ともにリフレッシュし、安心して働ける環境を整えることは、結果として企業の生産性向上や離職率の低下にも繋がります。
トラブルを恐れるのではなく、それを学びの機会と捉え、より良い職場環境を構築するための一歩としていきましょう。
次回予告|企業側から発生する有給休暇トラブル事例と予防策
次回は、今回に引き続いて「有給休暇を巡るトラブル」の深掘りを行います。
主に企業側から発生しがちなトラブル事例とその対処法に焦点を当てます。
「人手が足りないから有給を制限したい」「有給を取った社員を評価で冷遇してしまった」といった、企業側が陥りやすいNG行動と、その法的リスク、そして適切な対応策を解説します。
さらに、これらのトラブルを根本的に減らすための「トラブルを未然に防ぐ予防策」として、就業規則の整備、管理職への教育、そして柔軟な働き方の導入など、具体的なステップをご紹介します。
そして、今回と次回の記事の締めくくりとして、健全な有給休暇運用がいかに労使双方にメリットをもたらすか、その重要性を再確認します。
次回の記事は👉人手不足・繁忙期を理由にした有給拒否トラブルの正しい対処法
どうぞご期待ください!
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。
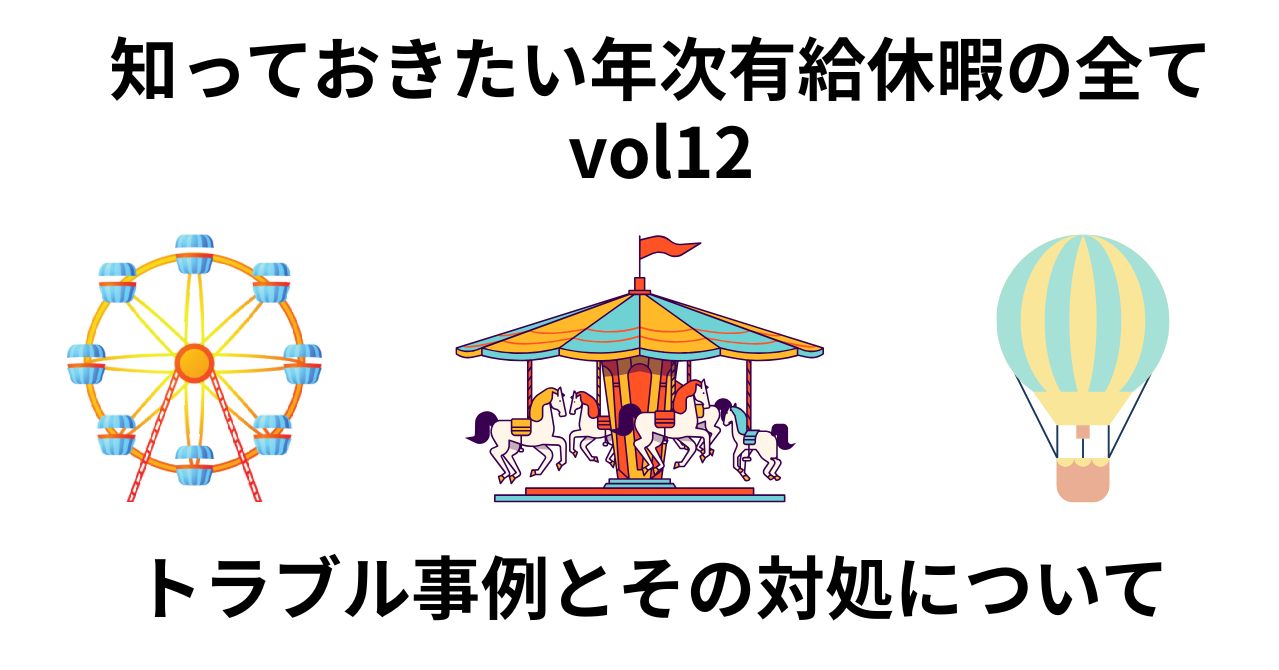

コメント