本記事は「【社労士が解説】企業のための熱中症対策 実践講座」シリーズの第1話です。
シリーズ全体の記事はこちらからご覧ください👇
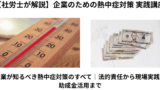
熱中症対策は企業の義務|職場で起こる労災リスク
気温35度を超える猛暑日が続く日本の夏。
そんな中、屋外の建設現場や配送現場だけでなく、空調の効きにくい倉庫内や工場、厨房といった「室内でありながら高温環境にさらされる職場」でも、熱中症のリスクは年々深刻さを増しています。
厚生労働省が公表している労災統計によれば、熱中症による労働災害の件数は近年上昇傾向にあります。
とりわけ中小企業や現場作業に従事する労働者において、その影響は無視できない状況です。
では、このような熱中症を引き起こす事態について、企業は「自然現象の一環だから」「自己管理の問題だから」といった理由で責任を回避できるのでしょうか?
――答えは「No」です。
労働災害としての熱中症|予見と回避の重要ポイント
熱中症は単なる自然現象にとどまらず、企業の安全配慮義務に密接に関係するリスクと見なされつつあります。
実際に、熱中症で労働者が死亡・重篤な状態に陥った事例で、企業の安全配慮義務違反が認定された裁判例も少なくありません。
職場における健康・安全の確保は、いまや企業の重要な責務のひとつとなっています。
特に、夏期の高温による健康被害は、予見可能です。適切な措置を講じることで回避可能な災害であるという認識が、社会的にも法的にも広がっています。
熱中症対策の企業責任とは?本記事で学べるポイント
本シリーズの第1話では、まず労働契約法における安全配慮義務の基礎を押さえた上で、
- なぜ、熱中症という自然現象が企業責任と結びつくのか
- 企業がどのような点で法的責任を問われ得るのか
- 「予見可能性」と「結果回避可能性」という裁判実務上の重要概念
といったポイントを整理していきます。
加えて、実際の裁判例や行政指導の流れをもとに、どのような状況で企業の対応が問題視されるのか、その全体像を明らかにします。
企業の安全配慮義務とは?法的根拠と熱中症対策の重要性
企業が労働者の安全を守る義務は、もはや「道徳」や「努力目標」ではありません。
これは明確な法的義務として定められています。
この義務を理解することが、熱中症対策を含むあらゆる労働災害防止の第一歩となるでしょう。
労働契約法第5条とは?企業が知るべき安全配慮義務の内容
企業の安全配慮義務の最も重要な法的根拠は、労働契約法第5条にあります。この条文は次のように定めています。
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」
この条文は、労働者が企業(使用者)と労働契約を結んで働く以上、使用者は労働者の安全に配慮する責任があることをはっきりと示しています。
安全配慮義務の明文化の意義
実は、この「安全配慮義務」という考え方は、以前は判例法理として、個別の裁判の判断が積み重なって形成されてきました。
つまり、法律に直接書かれていなくても、裁判所が「企業はこうした配慮をするべきだった」と判断することで、その義務が認められてきたのです。
しかし、2008年3月1日に施行された労働契約法によって、この重要な義務が法律の条文として明文化されました。
これは、企業が労働者の安全に配慮することが、雇用契約における基本的な、そして揺るぎない義務であることを社会全体に再確認させる大きな意味を持っています。
もはや「知らなかった」「昔は違った」という言い訳は通用しません。
安全配慮義務の具体内容と企業が負う責任範囲を解説
労働契約法第5条によって明文化された安全配慮義務は、単に「危険な場所を作らない」といった目に見える危険の除去だけにとどまりません。
その義務の内容は非常に広範囲に及び、企業のあらゆる活動において労働者の安全と健康に配慮することが求められます。
具体的には、企業には次のような多岐にわたる配慮が課せられます。
危険の予見と回避措置の実施
作業現場に潜む危険を事前に予測し、その危険を排除したり軽減したりするための具体的な措置を講じること。
適切な教育・指導の実施
労働者が安全に作業を行うための知識や技能を習得できるよう、安全衛生教育や危険予知訓練などを適切に行うこと。
作業環境の整備
温度、湿度、照度、騒音、換気など、労働者が健康的に働ける作業環境を維持・管理すること。
労働者の健康管理
健康診断の実施、過重労働の防止、メンタルヘルス対策、体調不良者への個別配慮など、労働者の心身の健康状態を把握し、悪化させないための対策を講じること。
適切な人員配置と作業体制の構築
無理な労働を避け、十分な人員を配置し、適切な作業指示を行うこと。
現代の安全配慮義務において重要なのは、これらの義務を「何もしないこと」が、そのまま「違法」と見なされる時代になった、という認識です。
例えば、高温環境下での作業が予測されるにもかかわらず、WBGT(暑さ指数)を測定せず、休憩や水分補給の具体的な指示も出さなかった結果、従業員が熱中症になったとします。
この場合、企業は「何も危険を予見せず、回避措置も講じなかった」と判断され、安全配慮義務違反を問われる可能性が極めて高くなるでしょう。
単にルールが存在するだけでなく、それが実効性のある形で運用されているかどうかが問われるのです。
熱中症が企業の責任になる理由と法的根拠
「熱中症は自然災害だから、仕方のないことだ」──そう考えている総務担当者の方はいませんか?
しかし、残念ながら現代の法的な視点から見るとそれは通用しません。
熱中症はもはや、単なる「自然現象」として片付けられる問題ではないのです。
熱中症は自然災害ではない|企業が責任を問われる理由
確かに、熱中症は気温や湿度といった自然現象が大きく影響します。
しかし、その発生は、「職場環境」に大きく左右されるという決定的な特徴があります。
- 屋外での長時間作業
- 空調設備のない工場や倉庫、厨房といった高温環境での業務
- 休憩や水分補給が十分に確保されていない状況
- 作業に適さない服装や保護具の使用
これらはすべて、企業が管理・改善できる要素です。
裏を返せば、熱中症の発症リスクがあるにもかかわらず、企業が適切な対応策を講じなかった場合、それは安全配慮義務違反と見なされることになります。
「自然現象だから仕方ない」という言い訳は、もはや通用しない、という認識を持つ必要があります。
厚生労働省の通達・ガイドラインが示す熱中症の「予防可能」の前提
熱中症が企業責任と結びつく最大の根拠の一つは、厚生労働省が熱中症を「予防可能な労働災害」と位置づけ、具体的な予防策を明文化していることにあります。
行政側は、企業が適切な措置を講じれば、熱中症の多くは防げるという前提で動いているのです。
特に重要なのが、「WBGT(暑さ指数)」の活用です。
WBGTは、気温だけでなく、湿度や輻射熱(太陽からの熱や、機械・地面からの照り返しの熱など)も考慮に入れた複合的な指標で、熱中症リスクをより正確に把握するために国際的に推奨されています。
関連記事

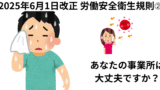
厚生労働省の通達やガイドラインでは、このWBGTを用いた作業環境の管理指針を明確に示しています。
具体的な情報源としては、以下の厚生労働省の資料をご参照ください。
「職場における熱中症の予防について」(通達)
この通達は、WBGT値の測定方法やWBGT基準値に基づく評価、休憩場所の整備、水分・塩分補給など、具体的な熱中症予防対策について詳しく記載されています。
「職場における熱中症予防基本対策要綱」
WBGT値の活用、WBGT基準値に基づく評価、熱中症予防対策(作業環境管理、作業管理、健康管理)が体系的にまとめられています。
これらの通達やガイドラインは、企業が講じるべき具体的な対策を明確に示しており、万一の際に「知らなかった」では済まされない状況を作り出しています。
行政が「予防可能」と明言し、その方法まで提示している以上、それを怠れば企業の責任が問われるのは当然の流れと言えるでしょう。
熱中症リスクと企業責任|予見可能性と結果回避可能性の関係
熱中症が発症してしまった際、企業の責任が問われるかどうかの重要なカギとなるのが、裁判所が重視する「予見可能性」と「結果回避可能性」という二つの視点です。
これらは、企業が安全配慮義務を果たしていたかを判断するための、具体的な基準となります。
熱中症裁判で企業責任が問われる2つの視点
労働災害における企業の責任は、多くの場合、以下の二つの問いに対する答えで判断されます。
- 予見できたか?
- これは、「その作業環境や状況において、熱中症が起こることを企業として事前に予測できたか?」という問いです。
- 例えば、連日の猛暑が予報され、作業場所が高温になることが分かっている、あるいは過去に同様のトラブルがあった場合など、客観的に熱中症のリスクを予測できたかが問われます。
- 気象情報(気温・湿度・WBGT)の入手状況や、作業内容の過酷さ、労働者の健康状態(持病など)の把握状況も判断材料となります。
- 回避できたか?
- 次に、「もし熱中症の発生を予測できたとして、適切な措置をとっていれば、その結果(熱中症の発症)を回避できたか?」という問いです。
- 具体的には、休憩時間の確保、水分・塩分補給の徹底指示、WBGT測定に基づく作業中断・変更、空調設備の導入、作業員の健康状態に応じた配置転換など、具体的な対策を講じていれば防げたはずではないか、という点が問われます。
企業が熱中症の発生を予見できたにもかかわらず、適切な措置を講じることでその結果を回避できたはずなのに、それを怠った場合に、安全配慮義務違反と判断され、責任を問われる可能性が極めて高くなります。
熱中症裁判の典型例から学ぶ企業責任のポイント
近年、熱中症を巡る裁判例は増加傾向にあり、多くのケースで企業側の安全配慮義務違反が認められています。
ここでは、実際に裁判で問題となりやすい典型的な事例をいくつかご紹介しましょう。
工場内での熱中症による死亡事故の例
- 夏季に工場内の温度が異常に高くなることを認識していながら、有効な冷却設備を導入せず、また適切な休憩指示や水分補給の徹底も怠った結果、労働者が熱中症で死亡したケースです。
- こうした事例では、企業が熱中症の発生を予見できたにもかかわらず、その結果を回避するための措置を怠ったと指摘される傾向にあります。
水分補給を制限された例
- 作業効率を重視するあまり、労働者への水分補給を制限したり、十分な休憩を与えなかった職場で、複数の労働者が熱中症を発症したケース。
- 企業が労働者の生命・身体の安全よりも業務効率を優先したとみなされ、責任が問われることがあります。
高温下の単独作業の例
- 誰にも気づかれにくい高温の作業場で、労働者が一人で作業中に熱中症で倒れ、発見が遅れて重篤な状態に陥ったケース。
- 企業が作業場所の温度管理を怠り、かつ単独作業のリスクを考慮した安全対策(巡回、連絡体制の確立など)を講じていなかった点が問題視されがちです。
これらの事例から分かるのは、「企業はWBGTの測定やその値に応じた休憩の確保、水分・塩分補給の徹底、作業体制の見直しなど、具体的な回避策を講じるべきだった」という点が、多くの場合、重要な判断基準となるということです。
つまり、「知らなかった」「運が悪かった」では済まされない、という姿勢が明確に示されています。
企業が知るべき熱中症予防の「予見」と「回避」
企業の総務担当者として、この「予見」と「回避」の視点を強く意識することは、非常に重要です。
- 「現場の判断に任せていたから大丈夫」は通用しない
- 「暑いと思ったら休んでいい」「各自で水分を取るように」といった、現場や労働者個人の判断に任せるだけでは、企業としての安全配慮義務を果たしたことにはなりません。
- 企業は、トップダウンで明確な安全管理体制を構築し、具体的な指示を出す義務があります。
- 「教育しなかった」「測定しなかった」「報告体制がなかった」は管理責任の放棄
- 熱中症リスクが高い環境にもかかわらず
- 予防のための知識を労働者に教育しなかった
- 暑さ指数(WBGT)を測定しなかった
- 体調不良の報告・共有体制がなかった
- このような状況は、いずれも安全配慮義務を果たすための具体的な行動を怠った、管理責任の放棄と見なされます。
- これは、企業が予見・回避措置を怠った明確な証拠となるのです。
- 熱中症リスクが高い環境にもかかわらず
熱中症対策は、単なる「注意喚起」で終わるものではありません。
具体的な行動と記録が、万が一の際の企業の責任を左右する重要な要素となることを肝に銘じておきましょう。
熱中症予防の行政指導と企業の安全配慮義務リスク
ここまで、熱中症が企業にとって予見・回避可能な「災害」であり、その対策が安全配慮義務として法的に求められていることを解説してきました。
では、実際に企業が熱中症対策を怠った場合、どのような行政からの指導や、より広範な企業リスクに直面する可能性があるのでしょうか。
熱中症予防|行政の是正指導・勧告事例と企業対応の傾向
労働基準監督署(労基署)は、職場における労働者の安全と健康を守るための監督指導を行っています。
熱中症予防に関しては、その指導が年々強化される傾向にあります。
特に、気温が上昇し熱中症リスクが高まる夏季には、労基署による「重点監督」や「臨検(立ち入り調査)」が積極的に実施されます。
これには、熱中症リスクが高いと見なされる建設業、製造業、運送業、屋外作業が多い事業場などが主な対象となりますが、業種を問わず実施される可能性があります。
熱中症におけるチェック項目
- WBGT(暑さ指数)計の設置と測定記録の有無
- 作業場所の温度・湿度管理の状況
- 適切な休憩場所(涼しい場所)の確保
- 水分補給のための設備の設置や塩分補給のための費用負担の状況
- 作業前後の健康状態の確認体制
- 熱中症予防に関する従業員への教育・周知の実施状況
- 緊急時の対応計画の有無
これらの項目で不備が見つかった場合、労基署は企業に対して是正指導や勧告を行います。
これにより、企業は具体的な改善計画を提出し、対策を実行することが求められます。指導に従わない場合や、重大な違反があった場合には、より厳しい措置が取られることもあります。
熱中症リスク|労災だけではない企業に及ぶ影響とは
熱中症の発症が労災として認定されることは、企業にとって直接的な影響をもたらしますが、リスクはそれだけにとどまりません。
むしろ、労災認定をきっかけとして、より広範で深刻な企業リスクが顕在化する可能性があります。
企業イメージの悪化・社会的信用の失墜
- 労働災害、特に熱中症のような「防げたはずの災害」が発生し、労災認定された場合、その事実は世間に知れ渡る可能性があります。
- メディア報道やインターネット上での情報拡散により、企業のブランドイメージは大きく損なわれ、社会的信用も失墜します。
- これは、優秀な人材の確保が難しくなったり、取引先からの信頼を失ったりすることにも繋がりかねません。
労基署の監視強化
- 一度労働災害が発生し、労基署の指導を受けた企業は、その後も継続的に監視対象となる傾向があります。
- 他の労働安全衛生法違反や労働基準法違反がないか、より厳しくチェックされる可能性が高まります。
高額な損害賠償請求のリスク
- 労災保険は、労働者の被った損害の一部を補償する制度ですが、企業の安全配慮義務違反が認められた場合、労災保険給付だけでは補いきれない部分について、労働者やその遺族から企業に対して直接、損害賠償を請求される可能性があります。
- 慰謝料や逸失利益など、その賠償額は高額になることも少なくありません。
- これは企業の経営に甚大な影響を与える可能性があります。
就業規則の不備を突かれることも
- 熱中症対策に関する具体的なルールが就業規則に明確に記載されていない場合、万が一トラブルになった際に、労使間の認識の齟齬が生じやすくなります。
- また、「企業が熱中症予防に関する明確なルールを定めていなかった」として、安全配慮義務違反の根拠の一つとして、就業規則の不備が指摘される可能性も出てきます。
- 就業規則は、単なる法令遵守のためだけでなく、労使間の無用なトラブルを回避するための重要な「ルールブック」であるという認識が不可欠です。
このように、熱中症対策を怠ることは、単に従業員の健康を害するだけでなく、企業の存続をも揺るがしかねない多角的なリスクを内包しているのです。
まとめ|熱中症は予測可能な災害として企業が備えるべき理由
熱中症は、もはや「不慮の事故」や「個人の問題」ではなく、企業が「予測でき、かつ適切な対策を講じれば回避できる災害」であるという認識が、社会の常識となっていることをご理解いただけたと思います。
そして、その対策を講じることは、労働契約法第5条に基づく企業の安全配慮義務として、法的に強く求められています。
この安全配慮義務は、単に企業の「従業員の生命と身体を守る義務」であると同時に、「自社を守る義務」でもあるのです。
適切な熱中症対策を怠れば、以下のような甚大なリスクを負うことになります。
- 従業員の健康被害と生命の危機
- 最も避けなければならない事態です。
- 高額な損害賠償請求
- 安全配慮義務違反が認定されれば、労災保険だけではカバーしきれない賠償金が発生する可能性があります。
- 行政指導・罰則
- 労働基準監督署からの是正勧告や、場合によっては刑事罰の対象となることもあります。
- 企業イメージの悪化
- 労働災害の発生は、企業の社会的信用を大きく損ない、採用活動や取引にも悪影響を及ぼします。
熱中症対策は、もはや「やれば良い」程度の話ではなく、「やらなければならない」企業の重要課題です。これを機に、貴社の熱中症対策を今一度見直すきっかけとなれば幸いです。
次回予告|「制度だけでは不十分?──実務でつまずく熱中症対策の盲点」
第1話では、熱中症に関する企業の法的責任とリスクを明確にしました。
しかし、実際に熱中症対策を進める上では、「法律で定められているから」という理由だけではうまくいかない実務上の課題が山積しています。
例えば、
- WBGT計は導入したものの、測定値の活用ができていない
- 休憩ルールは作ったが、現場で守られていない
- 対策はしているつもりでも、記録が残っておらず証明できない
など、「制度は作った、でも現場が追いつかない」といった典型的な「実務ギャップ」に悩む総務担当者の方も少なくないでしょう。
次回の第2話では、そうした現場での混乱や「実務の盲点」に焦点を当て、法改正だけでは解決できない熱中症リスクに「実務として」どう向き合うべきかを深掘りしていきます。
どうぞご期待ください。
次回の記事は👉熱中症対策義務化で現場がすべきこととは?WBGT測定の実務ポイント
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。
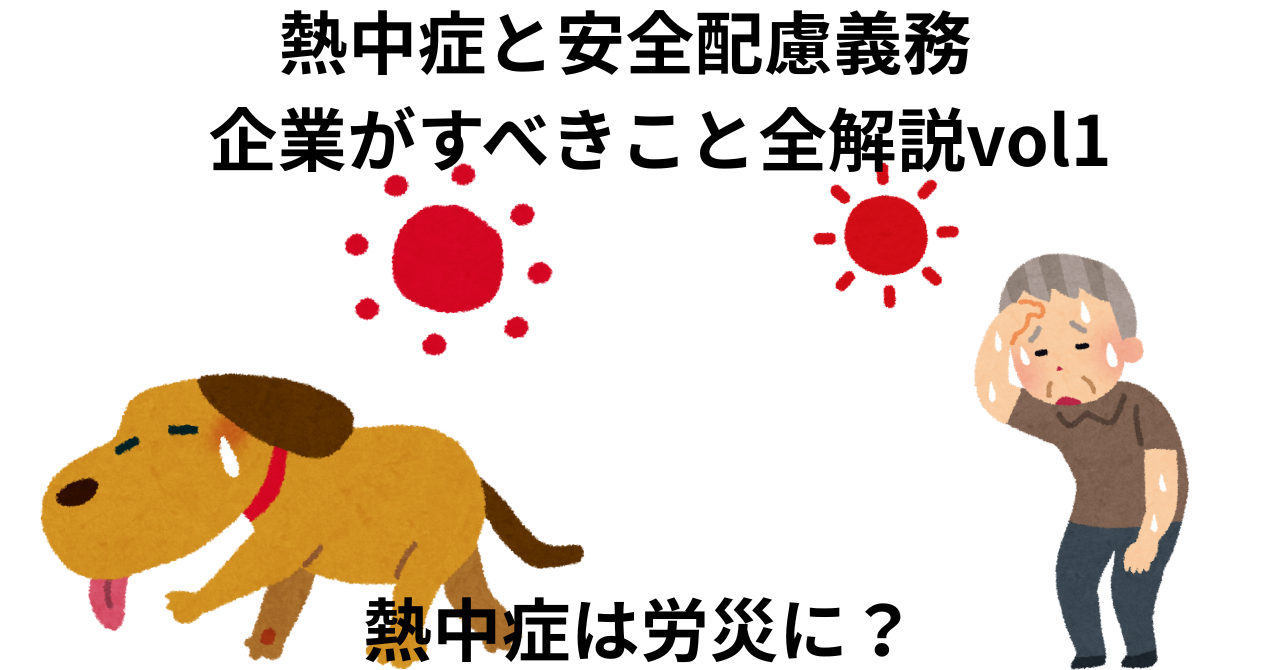

コメント