本記事は「インフルエンザ・コロナと企業の安全配慮義務」シリーズの第3話です。
シリーズの他の記事は👉インフルエンザ・コロナ対策と企業の安全配慮義務|実務ガイド
前回の記事では、冬季の感染症に備える上で、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の法的な位置づけが、企業が取るべき対策の基本となることをお伝えしました。
前回の記事は👉インフルエンザと新型コロナ|企業に休業させる法的義務はある?
確かに、これら5類感染症には法律上の就業制限義務はありません。
しかし、だからといって企業が対策を講じなくてもよいわけではありません。
企業には、感染拡大を防ぎ、従業員の健康を守るという社会的責任と、労働契約法に基づく安全配慮義務があります。
本記事では、季節性インフルエンザや現在の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)といった「5類感染症」に対し、企業が自主的に講じるべき具体的な対策を解説します。
まずは、感染拡大を防ぐための「社内ルール」の作り方から見ていきましょう。
この記事で分かること
- 企業が講じるべきインフルエンザ・コロナ対策の実務ポイント
- 感染時の就業ルールや給与(休業手当・有給休暇など)の扱い
- 感染拡大を防ぐための社内ルールづくりと就業規則への反映方法
- 流行期に活用できる柔軟な働き方(リモートワーク・時差出勤など)
インフルエンザ・コロナ感染拡大を防ぐための就業規則策定と周知
前回の記事で解説した通り、季節性インフルエンザや現在の新型コロナウイルスは「5類感染症」に分類され、感染症法による就業制限の対象ではありません。
そのため、行政からの命令で従業員を強制的に休ませる法的義務はないのです。
法的義務を超えた企業の感染症対策と安全配慮義務
しかし、これは企業が何もしなくてよいという意味ではありません。
感染症が蔓延すれば、職場の従業員の健康を害し、事業継続にも重大な影響を及ぼします。
また、労働契約法には「安全配慮義務」が定められており、企業は従業員が安全に働けるよう配慮する義務があります。
したがって、企業は自主的な判断で具体的な行動指針を定め、従業員に周知しておくことが不可欠です。
インフルエンザ・コロナ対策における3つの社内ルール
「少しぐらいの咳や熱なら…」と無理して出勤する従業員がいるかもしれません。
しかし、それがクラスター発生の引き金となる可能性があります。
1. 従業員の体調不良時の行動基準を明確にする
これを防ぐため、まず従業員が体調不良を訴えた際に、必ず医療機関を受診するよう周知することが最も重要です。
- 受診の徹底
- 発熱や咳、強い倦怠感といった症状が出た場合、自己判断で出勤せず、まずは医療機関を受診するよう明確に促します。
- 診断結果に基づく判断
- 診断結果がインフルエンザや新型コロナウイルス感染症(COVID-19)だった場合は、会社の定めるルールに則ってその後の対応を進めます。
- これらの感染症でなかった場合は、個人の判断で出勤するか欠勤するかを決定します。
- テレワークの活用
- 症状が軽快するまで在宅勤務に切り替えるなど、テレワークが可能な職場であれば、出勤以外の選択肢も有効です。
2. 感染時の報告・連絡体制を確立する
従業員が安心して療養に入れるよう、感染が判明した場合の報告・連絡フローを定めておくことも重要です。
- 誰に連絡するか
- 直属の上司、人事担当者、総務担当者など、連絡先を明確にします。
- 何を伝えるか
- 医療機関の診断結果、今後の療養期間見込み、直近の出勤状況などを伝える項目を定めておきます。
- 連絡手段
- メール、電話、チャットツールなど、状況に応じた連絡手段を共有しておきましょう。
この体制が曖昧だと、従業員は「会社に迷惑をかけるのでは」と躊躇し、報告が遅れる可能性があります。
3. 復帰の基準を設ける
感染した従業員がいつから出勤してよいかについても、明確な基準が必要です。
- 復帰の目安を明記
- 診断名が明確な場合は、医師の指示や厚生労働省が示す基準を参考に、具体的な復帰の目安を定めておきましょう。
- 例えば、インフルエンザの場合は「発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで」といった学校保健安全法施行規則を参考にすると良いでしょう。
- 診断書や療養証明書の提出
- 医師の診断書や療養証明書の提出を求めることも、ルールとして定めておくと、従業員も安心して療養に専念できます。
これらのルールを就業規則や社内規定に明記し、定期的に従業員に周知することで、いざという時に混乱せず、スムーズに対応することができます。
インフルエンザ・コロナ対策ルールを就業規則に明記する方法
策定した社内ルールは、従業員に周知徹底し、法的な効力を持たせるために、会社のルールブックである就業規則や社内規定に明確に記載する必要があります。
なぜ就業規則に明記するのか?
- 周知徹底の義務
- 労働基準法では、就業規則を従業員に周知することが義務付けられています。
- 規則に明記することで、ルールが従業員全員に共有され、認識の齟齬を防ぐことができます。
- 法的根拠の明確化
- 就業規則は、労使関係における重要なルールです。
- ここに定めることで、会社が従業員に協力を求める際の法的根拠が明確になり、万が一のトラブルを未然に防ぐことにつながります。
どこに、どのように記載するのか?
就業規則への記載方法にはいくつかのパターンがあります。
- 「服務規律」や「安全衛生」の条項に追加する
- 既存の条項に「インフルエンザに罹患した場合の報告義務」などを追記します。
- 「第5類感染症に関する特別規定」として独立させる
- インフルエンザ等(第5類感染症)対策に特化した、独立した規定を設ける方法です。
インフルエンザ・コロナ対策|従業員への情報提供と予防啓発の方法
感染症対策は、会社がルールを定めるだけでは不十分です。
最も重要なのは、従業員一人ひとりが正しい知識をもち、予防を実践することです。
企業は、従業員の意識を高め、自発的な行動を促すための啓発活動を継続的に行いましょう。
感染症対策啓発はいつから?従業員への情報提供の開始時期と継続のコツ
従業員の健康管理は、年間を通じて欠かせないものです。
例えば、春から夏にかけては熱中症対策を周知するように、秋から冬にかけてはインフルエンザ対策を始めるのが理想的です。
- 9月~10月|準備の時期
- この時期から、従業員への注意喚起を始めるのが理想的です。
- 特に、予防接種の費用補助や集団接種を検討している場合は、早めに情報を周知する必要があります。
- また、社内の消毒液やマスクの在庫を確認し、備蓄を始めましょう。
- 11月~3月|実践と注意喚起の時期
- 流行シーズン中は、継続的な情報提供と注意喚起が不可欠です。
- 「手洗いやマスク着用の徹底」「換気の推奨」などをこまめに呼びかけましょう。
インフルエンザ・コロナ対策|従業員への正しい感染症知識の共有方法
誤った情報や認識不足は、感染拡大のリスクを高めます。
企業は、インフルエンザの感染経路や効果的な予防策について、分かりやすい形で情報を提供しましょう。
- 感染経路の周知
- 飛沫感染や接触感染といった主要な感染経路を改めて説明することで、従業員は日々の行動の中でどこに注意すべきかを理解できます。
- 効果的な予防策
- 「手洗いの重要性」「正しいマスクの着用方法」「定期的な換気の必要性」など、基本的ながらも感染予防に欠かせない知識を定期的に発信します。
社内でできる感染症予防啓発の実践方法
情報を提供するだけでなく、従業員が実践しやすい環境を整えることが重要です。
- ポスターや掲示物
- 手洗いの手順や咳エチケットをイラスト付きのポスターにして、トイレや休憩室、給湯室など、従業員の目に触れやすい場所に掲示します。
- 社内メールやイントラネット
- 流行シーズン前に注意喚起のメールを送付したり、社内イントラネットに感染症対策の特設ページを設けたりして、情報を一元化します。
- 衛生用品の常備
- オフィス内にアルコール消毒液を複数箇所に設置し、マスクを常備しておくことで、従業員がいつでも予防策を実践できる環境を整えましょう。
これらの活動を通じて、企業が感染症対策に真剣に取り組んでいる姿勢を示すことは、従業員に安心感を与え、協力的な行動を促すことにつながります。
従業員が感染症で休む場合の勤怠・給与ルールとトラブル回避策
従業員がインフルエンザなどで休む場合、最もトラブルになりやすいのが「給与の扱い」です。
企業が労働基準法上の「休業手当」を正しく理解し、適切な対応を取ることが不可欠です。
インフルエンザ・コロナでの自主的病欠と会社休業命令の違いと給与対応
インフルエンザは5類感染症のため、法律上、企業は従業員を強制的に休ませる義務はありません。
このため、従業員が「体調が悪いので休みます」と自主的に休んだ場合は、私傷病による欠勤となり、賃金を支払う義務は発生しません。
これが最も重要なポイントです。
しかし、たとえ善意からであっても、企業が「感染拡大を防ぐため出社しないでください」と明確に休業を命じた場合、それは会社の都合による休業と見なされます。
この場合、労働基準法第26条に基づき、会社は平均賃金の60%以上の休業手当を支払う義務が発生します。
この違いを従業員と共有し、認識の齟齬がないようにすることが重要です。
病気休暇と有給休暇|インフルエンザ・コロナ時の給与確保
従業員が自主的に休む場合、給与が支払われない無給扱いとなるのが原則です。
そのため、従業員にとって経済的な不安が生じることがあります。
この問題を解決するために、企業は従業員に有給休暇の積極的な活用を促しましょう。
企業には、年10日以上の有給休暇が付与されている従業員に、毎年5日間は確実に取得させる義務があります。
この義務を考慮しても、従業員がインフルエンザなどで休む際に有給休暇の取得を推奨することは、非常に有効な手段です。
従業員が休業中に有給休暇を申請すれば、給与が満額支払われるため、安心して療養に専念できます。
関連記事


インフルエンザ・コロナ感染時に使える病気休暇制度の活用法
有給休暇とは別に、病気やケガで休んだ際に利用できる「病気休暇制度(特別休暇)」を設けることも有効な手段です。
法定の休暇ではありませんが、企業の福利厚生として導入することで、従業員はインフルエンザ等で休む際に有給休暇を温存できるため、安心して利用することができます。
これらの対策を明確にすることで、企業は労使間のトラブルを未然に防ぎ、従業員が安心して働ける環境を整えることができます。
感染症流行時の柔軟な働き方|リモートワーク・時差出勤の活用
インフルエンザが社内や地域で流行している時期には、満員電車などでの通勤時の感染リスクを軽減するための対策が有効です。
オフィスでのクラスター発生を防ぎ、従業員の健康を守るために、柔軟な働き方を検討しましょう。
インフルエンザ・コロナ流行時の職場での多様な勤務形態
感染拡大の兆候が見られた際、一時的な時差出勤やリモートワークの導入は非常に有効な手段です。
従業員が通勤ラッシュを避けることで、不特定多数との接触機会を減らし、感染リスクを大幅に下げることができます。
特にリモートワークは、従業員が自宅で業務を行うため、職場内での感染を完全に防ぐことができます。
感染症対策でのリモートワーク・時差出勤の制度ルール
こうした柔軟な働き方を導入する際は、事前にルールを明確に定めておくことが不可欠です。
- 適用条件
- どのような状況(例:社内で感染者が確認された場合、地域で感染者が急増した場合など)でリモートワークや時差出勤を適用するかを定めます。
- 申請・承認フロー
- 従業員が迷わず利用できるよう、申請方法や承認までの流れを明確にしておきましょう。
事前にルールを周知しておくことで、いざという時も混乱なく、スムーズにこれらの働き方へ移行できます。
まとめ|企業に求められるインフルエンザ・コロナ対策の実務ガイド
本記事で解説した実務的な対策は、感染症の蔓延を防ぐだけでなく、従業員が安心して働ける環境を整備することにもつながります。
企業の安全配慮義務を果たすことは、従業員との信頼関係を築く上でも不可欠です。
企業が主体的に対策を講じることで、社会全体のリスク低減にも貢献できます。
本記事でご紹介した各ポイントを参考に、ぜひ今シーズンに向けて具体的な行動計画を立ててみてください。
次回予告|家族の感染は?第5類そして第5類以外の感染症の場合はどうする?
ここまで、季節性インフルエンザや新型コロナウイルスといった第5類感染症に対する、企業の具体的な実務対策を解説してきました。
しかし、もし従業員の家族が感染症にかかった場合、企業はどのように対処すべきでしょうか?
次回の記事では、家族の感染というケースに焦点を当て、企業がとるべき対応を詳しく解説します。
さらに、感染症法で定められている第1種から第5種までの各感染症、そして新型インフルエンザなど、種類ごとに異なる企業の法的義務や対処法を徹底的に掘り下げていきます。
次回の記事は👉従業員の家族の感染症罹患の時の企業対応|出勤基準と休業手当
「家族が感染したら会社はどうすべき?」「感染症の種類によって対応は違うの?」といった疑問にお答えしますので、ぜひご期待ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。
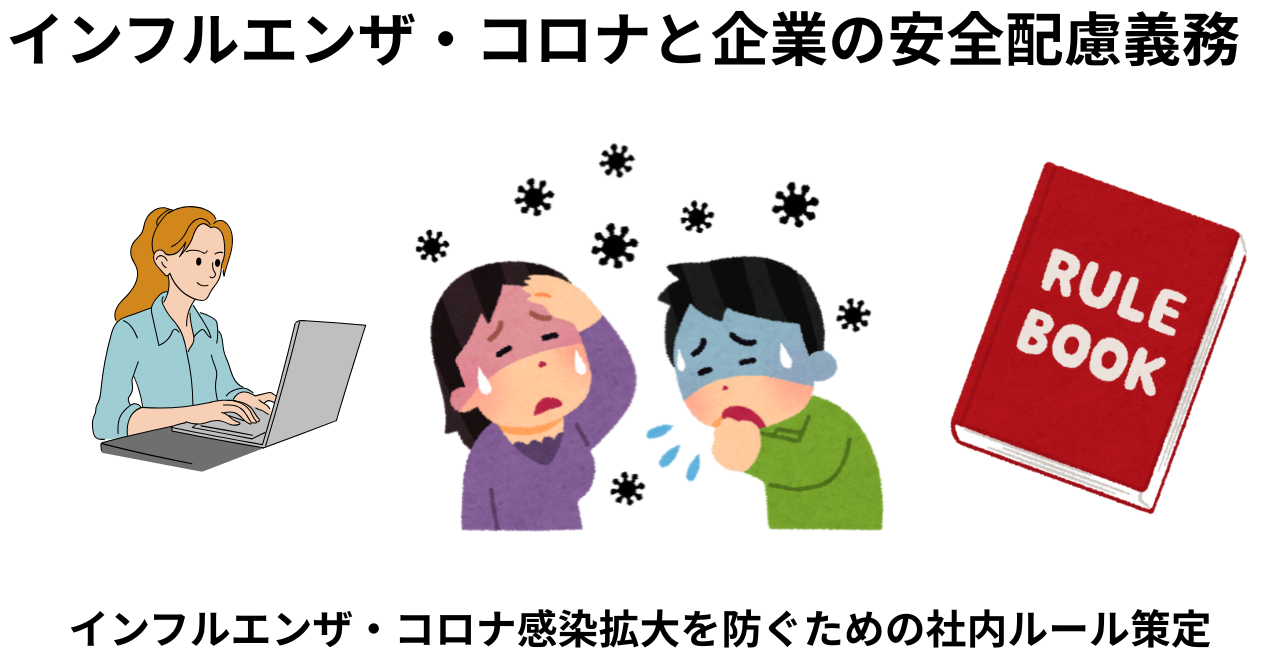

コメント