本記事は「副業時代の労務管理」シリーズの第2話です。
前回の記事では、現代の副業解禁は「人材育成」という戦略的側面と「給与転嫁」という経済的側面という、企業からの二重のメッセージを内包していることを解説しました。
前回の記事は👉副業解禁のメリットとリスク|人材確保と情報漏洩対策のバランス
そして、企業がこの新しい時代を生き抜くためには、リスク回避と人材活用を両立させるバランスの取れた制度設計が不可欠であると結論付けました。
しかし、いざ副業制度を設計しようとすると、「どこまで社員の自由を制限して良いのか」「禁止する規定は法的に有効なのか」という、法的かつ実務的な壁に直面します。
そこで今回は、企業が直面するこの課題を解決するため、就業規則における副業規定の設計に焦点を当てます。
まずは、すべてのルールの土台となる「副業・兼業をめぐる法的な大原則」と、「企業が制限できる限界ライン」から明確にしていきます。
この記事でわかること
- 副業・兼業に関する法的な大原則(職業選択の自由と企業の制限根拠)
- 企業が副業を制限できる「三つの正当理由(職務専念・秩序維持・安全配慮)」
- 副業をめぐる主要な裁判例と「合法」と「不合理」の線引き
- 現行の「副業禁止規定」が抱える法的リスクと合理性の限界
- 実務的に運用できる4つの副業ルール(届出制・許可制・禁止・無規定)とその設計ポイント
- 届出制・許可制の比較と、企業が取るべき現実的な対応方針
副業・兼業をめぐる法的な大原則と企業の制限の限界
現代の働き方において、副業・兼業はもはや個人の自由なキャリア形成の一環として社会的に認知されつつあります。
しかし、企業が従業員を雇用している以上、その自由には必ず一定の制約が伴います。
この制約の「正当なライン」を理解することが、企業にとって労務リスクを回避し、かつ従業員にとって納得感のあるルールを設計する上での第一歩となります。
労働者の「自由」と企業の「義務・権利」
1. 労働者の職業選択の自由(憲法上の大原則)
そもそも、労働者が勤務時間外にどのような活動をし、どのような仕事に就くかは、日本国憲法第22条で保障された「職業選択の自由」に基づき、原則として自由です。
これは、企業が就業規則で副業を禁止する場合、その禁止規定には極めて高度な合理性が求められることを意味します。
全面的な副業禁止は、この憲法上の権利を不当に侵害するとして、トラブルや訴訟の原因となりやすいのです。
2. 企業が副業を制限できる正当な根拠|三つの義務・配慮
では、企業はどのような場合に副業を制限できるのでしょうか。
その根拠となるのは、労働契約(雇用契約)から生じる、従業員の義務と、企業が負う法的義務です。
- 職務専念義務
- 労働者は、契約上の労働時間中は、本業の職務に専念する義務があります。
- 副業が本業の遂行に支障をきたす場合、企業はこれを制限できます。
- 企業秩序維持義務
- 企業は、健全な経営活動を維持するために必要な秩序(機密保持、信用維持など)を守る権利があり、副業がこの秩序を乱す場合は制限できます。
- 企業の安全配慮義務
- 企業は、労働契約法に基づき、労働者が心身の健康を損なうことなく安全に働けるよう配慮する義務を負っています。
- 副業による過重労働は、この義務違反のリスクを増大させるため、企業はこれを防ぐ目的で制限できます。
この「三つの義務・配慮」こそが、就業規則に副業禁止や届出・許可制を定める際の唯一かつ最大の合法的な根拠となります。
正当な副業制限の範囲|裁判例から見る線引き
副業の制限が「合法」と判断されるか「不合理」と判断されるか、その境界線は裁判例によって形成されてきました。
企業が副業を理由に懲戒処分を行う場合、この線引きを明確に理解しておく必要があります。
特に、以下の裁判例は、企業が制限できる「正当な根拠」と、それが「実質的に侵害されたかどうか」を判断する上での試金石となります。
副業関連の裁判例から読み解く「合法」と「不合理」の境界線
| 争点 | 処分が有効とされた主な事例(制限に合理性あり) | 処分が無効とされた主な事例(制限に合理性なし) |
| 過重労働 / 安全配慮 | 小川建設事件 (東京地決 昭57.11.19) 毎日6時間、深夜までキャバレーで無断就労。 本業の労務提供に支障を来す蓋然性が高い(過重労働・職務専念義務違反)と判断。 | 東京都私立大学教授事件 (東京地判 平20.12.5) 夜間・休日の語学学校講師。 本業への支障が認められないため、懲戒解雇は無効。 |
| 競業避止 / 企業秩序 | 橋元運輸事件 (名古屋地判 昭47.4.28) 管理職が会社の承諾なしに競業他社の取締役に就任。 企業の利益を侵害する行為と判断。 | 十和田運輸事件 (東京地判 平13.6.5) 運送会社の運転手が年に1~2回の貨物運送アルバイト。 職務専念義務の違反や信頼関係の破壊とまでは言えないと判断。 |
| 許可制の運用 | (有効例:上記の職務専念・競業に違反した無許可の場合) | マンナ運輸事件 (京都地判 平24.7.13) アルバイト許可申請を不合理な理由で不許可にしたことについて、慰謝料の支払いを命じた。 企業は合理的な理由なく自由を制限できない。 |
正当な副業制限の具体的な例
実務上、企業が副業を制限するために就業規則で規定すべき、正当性が認められやすい項目は主に以下の3点に集約されます。
- 過重労働・健康リスクの回避
- 副業を含む総労働時間が、労働基準法や企業の安全基準に照らして健康を害する可能性がある場合の禁止規定。
- 労働時間を把握するための届出制の法的根拠として最も重要です。
- 機密情報漏洩・競業避止義務違反
- 競合する同業他社で働くことや、自社のノウハウや顧客情報を利用する副業を明確に禁止する規定。
- 職務専念義務違反
- 本業の業務遂行に悪影響を及ぼすほど、肉体的または精神的な疲労をもたらす副業を禁止する規定。
企業は、これら正当な理由に該当しない限り、労働者の副業を単なる「気に入らない」という理由で制限することはできません。
ルールを定める際は、「何が、どのように本業の損害につながるか」を客観的に説明できる合理性が必要不可欠です。
依然残る「副業禁止規定」の合法性と合理性の検証
労働者の副業は憲法上の「職業選択の自由」に根差すため、企業がこれを制限するには「職務専念」「企業秩序」「安全配慮」といった合理的な理由が必要です。
この法的原則が、厚生労働省が2018年に「モデル就業規則」から原則的な副業禁止規定を削除した背景です。
そして現代において、企業が就業規則に依然として「全面的な副業禁止規定」を残し続けることには、大きな法的リスクが伴います。
全面的な副業禁止の危険性|合理性リスクの検証
現在でも中小企業を中心に「副業禁止」を掲げる企業は少なくありません。
しかしこれは、企業にとって以下のような「合理性リスク」を抱えることになります。
- 懲戒処分無効のリスク
- 裁判所は、従業員が本業に支障なく、企業の信用も損なわない範囲で行った副業に対して、全面禁止規定を根拠に行った懲戒処分を「権利の濫用」として無効と判断する可能性が高いです(例:東京都私立大学教授事件、十和田運輸事件)。
- 禁止規定があるという事実だけでは、もはや懲戒処分の正当性は担保されません。
- 優秀な人材流出のリスク
- 副業解禁は「人的資本投資」の一環です。
- 全面禁止は、多様なスキル獲得や柔軟な働き方を求める優秀な人材にとって、企業選択の際の大きなマイナス要因となります。
- 安全配慮義務違反のリスク増大
- 企業が禁止している場合でも、従業員が無断で副業を行い、過労状態に陥るケースは後を絶ちません。
- 企業は副業の事実を知らないため労働時間を通算管理できず、結果的に従業員の健康を害した場合、安全配慮義務違反を問われる可能性が高まります。
- これは、制度を容認し適切に届出管理するよりも、かえって大きなリスクとなります。
不合理な副業制限の是正|労働者の生活権や低賃金とのバランス
さらに、副業禁止の合理性を検証する際、現代の経済状況において看過できないのが、「労働者の生活権」とのバランスです。
現代の日本経済は、物価上昇にもかかわらず、企業側が十分な賃上げ原資を確保できないケースが増加しています。
社員の副業は、企業が抑制する「給与転嫁策」としての側面を帯びています。
このような構造的背景の中で、企業が以下の状況にある場合、副業禁止は「不合理な制限」と判断される可能性が高まります。
- 賃金水準が低い、または生活賃金が低い地域で働く従業員が、生活維持のために副業を必要としている場合。
- 本業の勤務実態が時間外労働の少ないホワイトな環境であり、余暇を副業に充てても健康に影響がない場合。
裁判例においても、企業側の都合や漠然とした懸念だけで労働者の「私生活上の経済活動の自由」を制限することは、正当な理由がない限り許容されないという判断が主流です(例:マンナ運輸事件)。
企業は、副業禁止の就業規則を維持する場合、その禁止が単に「管理が面倒だから」という理由ではなく、「特定の情報漏洩リスクや過重労働リスクを回避するため」という、客観的かつ具体的な合理性を常に証明できる必要があります。
副業時代の企業運営において、「一律禁止」の壁は、法的にも実務的にも、もはや立ち行かなくなりつつあると言えるでしょう。
実務的な「副業ルール」の四つの運用パターンとその設計
繰り返しになりますが、企業が副業を制限できるのは、「職務専念義務」「企業秩序維持義務」「安全配慮義務」という限定的な合理的な根拠がある場合のみです。
この原則を踏まえ、企業は自社の事業特性や組織文化に合わせ、以下の四つの運用パターンのうち一つを選択し、就業規則に具体的に定める必要があります。
パターンA|副業の届出制(原則容認・例外禁止)
現在、厚生労働省のモデル就業規則が採用している、最も推奨される運用形態です。
原則として副業を容認し、上記の法的原則に違反する場合のみ例外的に禁止または制限します。
| メリット | デメリット |
| 法的リスクの低減 労働者の自由を尊重するため、懲戒処分無効のリスクが低い。 | 管理の煩雑さ 労働時間や健康管理に関する従業員の正確な申告に依存するため、情報収集とチェックの体制構築が必要。 |
| 人材採用・定着への効果 柔軟な働き方を求める優秀な人材を惹きつけやすい。 | 本業の意識低下リスク 副業に力を入れすぎ、本業への職務専念意識が希薄化する可能性がある。 |
| 安全配慮義務の履行 副業の事実と労働時間を把握できるため、過重労働のリスクをチェックしやすい。 | 機密管理の難しさ 情報漏洩リスクを完全に排除できないため、研修や教育による対策が別途必要。 |
安全配慮義務を果たすための「届出」の具体的な必須事項
届出制を採用する最大の目的は、安全配慮義務を果たすことにあります。
そのため、届出内容には以下の項目を必須として含めるべきです。
- 業務内容
- 具体的な事業活動の内容。
- 労働時間
- 1日および1週間あたりの概ねの労働時間(本業と通算するため)。
- 期間
- 副業開始日と終了予定日。
企業は、この届出内容と本業の労働時間を合算し、過重労働になるリスクがないかをチェックし、問題がある場合は指導や調整を求めることで、安全配慮義務を果たします。
パターンB|副業の許可制(原則禁止・例外許可)
就業規則で副業を原則禁止とし、個別の申請に対して企業が許可を与えた場合のみ副業を認めます。
企業の管理体制を維持しやすい一方で、不許可の判断には高い合理性が求められます。
| メリット | デメリット |
| 管理の徹底 競業避止や情報漏洩のリスクを、許可段階で事前に排除できる。 | 法的リスク 「不許可」の判断が不当だと、労働者の職業選択の自由の侵害として訴訟リスクを負う(例:マンナ運輸事件)。 |
| 企業秩序の維持 企業の信用を損なう可能性のある副業を水際で食い止めやすい。 | 運用コスト 許可・不許可の審査に人的リソース(時間と専門知識)を要する。 |
許可・不許可の判断基準を客観的かつ明確にする方法
許可制を合法的に運用するためには、不許可の理由を就業規則に客観的かつ明確に定めることが必須です。
<許可を出さない明確な基準の例>
- 本業と副業の合計が、法定労働時間または時間外労働の上限を超過する蓋然性が高い場合(安全配慮義務違反)。
- 本業と同業種で、機密情報の漏洩や顧客の奪取につながる具体的な危険性がある場合(企業秩序維持義務違反)。
- 本業の遂行に重大な支障を及ぼすことが明らかである場合(職務専念義務違反)。
許可制を採用する場合でも、企業は「単に許可を与えたくない」という理由で不許可にすることはできず、常に上記の法的根拠に照らした説明責任を負います。
パターンC|副業の禁止(極めて例外的なケース)
就業規則で副業を全面的に禁止する運用形態です。現在の労働環境や法的原則に照らすと、極めて例外的なケースでのみ、かつ限定的に認められます。
| メリット | デメリット |
| 企業の管理負担が少ない 副業に関する管理工数を大幅に削減できる。 | 法的リスクが非常に高い 合理的な理由のない禁止は憲法違反となる可能性があり、裁判で懲戒処分が無効になる。 |
| 企業秘密の絶対的な保護 機密性の高い企業・職種では、情報漏洩リスクを最小化できる。 | 優秀な人材の獲得機会を失う 副業に理解のある他社に人材が流出しやすい。 |
| 安全配慮義務が果たせないリスク 従業員が隠れて副業を行い、企業が労働時間を把握できなくなる。 |
適用可能な業界・職種の限定と、その法的限界
全面禁止が法的に正当化されやすいのは、以下の条件をすべて満たすような、特殊な事業や職種に限られます。
- 職務の特性上、高度な機密性・公共性・忠実義務が不可欠であること。
- 競業・情報漏洩のリスクが極めて高いこと。
- 本業の勤務時間が極めて不規則で、安全配慮義務を全うするために他社での就労を物理的に禁止せざるを得ないこと。
企業は、全面禁止を採用する代わりに、パターンB(許可制)を導入し、上記のような高リスクの職種に対してのみ不許可基準を厳格に適用する方が、法的リスクを低減しつつ管理実態に合わせることができます。
パターンD|副業の規定を設けない(無規定状態)
これは、企業が副業容認・禁止の判断を意図的に保留している、あるいは単に未整備な状態を指します。
一見、労働者の自由を尊重しているように見えますが、企業側にとっては最も法的リスクが高い運用形態となります。
| メリット | デメリット |
| (形式上)労働者の自由を最大限尊重している 規則がないため、社員は自由に副業ができる。 | 過重労働・安全配慮義務違反リスクの極大化 労働時間通算の情報を一切把握できず、社員が過労状態に陥っても企業が責任を問われるリスクが高い。 |
| 就業規則改定の手間がない 規則を作るための労力やコストがかからない。 | 法的根拠の喪失 情報漏洩や本業への支障が発覚しても、懲戒処分や制限措置をとる正当な根拠を失う。 |
| 労使トラブルの増大 副業が発覚した際、企業が恣意的に判断していると受け取られ、不信感やトラブルにつながりやすい。 |
「規定なし」が誘発する最大の課題
規定がない場合、企業は社員の副業に関する情報を一切把握できないため、安全配慮義務(労働契約法第5条)を果たすことが事実上不可能になります。
従業員が副業で健康を害した場合、企業は「副業の事実を知らなかった」としても、労働時間の通算管理を怠ったとして、安全配慮義務違反を問われるリスクが極めて高くなります。
したがって、企業は副業を容認するにせよ禁止するにせよ、最低限、「届出の義務」を設けることがリスクヘッジの観点から不可欠です。
副業がもたらす企業リスクと労働者の生活権を両立させる規定設計の要諦
これまでに、副業を制限する際の法的限界と、実務的な運用パターン(届出制、許可制、禁止制、無規定)について詳しく解説してきました。
最終的に貴社がどのような副業ルールを選択されるかは、企業文化や事業内容により判断いただくことです。
しかし、社会保険労務士としての専門的な見解から、無規定状態(パターンD)と全面禁止(パターンC)は、現代において推奨できません。
これらは法的リスクと人材流出リスクを過度に高めるからです。
推奨されるのは、届出制(パターンA) または 許可制(パターンB) の採用です。
副業の届出制と許可制の比較と推奨論
社会保険労務士として、多くの企業には届出制を推奨しています。
これは、届出制の方が「法的リスクの回避」と「人材活用の促進」という二大テーマを両立しやすいためです。
| 項目 | 届出制(パターンA:原則容認) | 許可制(パターンB:原則禁止) |
| 法的リスク | 低リスク 原則容認のため、労働者の「職業選択の自由」を侵害したとして訴訟になるリスクが低い。 | 高リスク 不許可の判断が不合理とされた場合、「不当な制限」として訴訟(懲戒処分無効など)のリスクが高い(例:マンナ運輸事件)。 |
| 運用負担 | 低負担 届出内容のチェックと労働時間通算が主となり、審査負担が少ない。 | 高負担 個別の副業申請に対し、企業側が詳細な審査と合理的な説明責任を負うため、審査コストが高い。 |
| 人材戦略 | 優位 柔軟な働き方を尊重する姿勢を示せ、優秀な人材の採用と定着に繋がる。 | 劣位 原則禁止の姿勢が、多様な働き方を求める人材にとってネガティブな要因となり得る。 |
| 安全配慮 | 優位 届出により副業の事実と労働時間を把握でき、過重労働の防止に繋がりやすい。 | 劣位 許可が下りない場合、社員が無断で副業を行う可能性が高まり、労働時間の把握が不可能になる。 |
必須規定|すべての副業ルールに共通して明記すべき3つの柱
貴社が「届出制」であれ「許可制」であれ、以下の3点は例外なく規定に盛り込んでください。
これらは、企業が法的な責任を果たし、秩序を守るために最低限、就業規則に明記すべき「必須規定」です。
導入しなければ安全配慮義務違反という最大の労務リスクを放置することに等しくなります。
1. 労働時間通算のルールと報告義務(過労防止のための具体的な管理方法)
- 明記すべき事項
- 労働時間は通算されること。
- 従業員は、副業先の労働時間、休日、時間外労働の実態について正確に報告する義務があること。
- 企業の権限
- 通算の結果、法定労働時間や過労死ラインを超過する恐れがある場合、副業の調整や中止を指示する権限を企業が持つこと。
2. 秘密保持・競業避止義務の明確化
- 明記すべき事項
- 本業で知り得た機密情報を副業で利用することを厳禁する秘密保持義務を改めて確認すること。
- 競業の定義
- 競合他社での副業を禁止する場合、その「競業」の範囲を客観的かつ具体的に定義すること。
3. 懲戒処分の規定とその合理性の担保
- 明記すべき事項
- 懲戒事由を、「無届けにより安全配慮義務違反のリスクを生じさせた場合」など、企業に実害が及んだ場合に限定して明確に規定すること。
- 処分の合理性
- 懲戒権の濫用とならないよう、処分が違反行為に対し社会通念上の相当性があることを担保する運用プロセスを明確化すること。
まとめ|副業解禁の本質と、企業が果たすべき責務
副業解禁は、「人的資本投資」という戦略的側面と、「労働者の生活基盤支援」という経済的側面の二重のメッセージを内包しています。
企業が目指すべきは、旧来の「副業禁止=リスク回避」という発想から脱却し、副業を「社員が自律的にスキルアップする機会」として捉えることです。
その上で、届出制や明確な許可制を通じて、過重労働を防ぎ、機密情報を守るというバランスの取れた管理を実行することが、企業リスクを最小限に抑えつつ、人材の成長を最大限に引き出す、現代の理想的な制度設計の要諦と言えるでしょう。
次回予告|労働時間管理と安全配慮義務
今回の記事では、副業制度を設計する上で不可欠な「法的根拠」と「必須規定」について明確にしました。
次回は、就業規則にルールを定めた後の、最も難解で重要な「実務運用」に焦点を当てます。
特に、複数の企業で働く労働者の「労働時間管理」と、それに伴う企業の「安全配慮義務」の課題を深掘りします。
次回の記事は👉副業容認のリスク管理|労働時間通算と安全配慮義務の実務ポイント
ご期待ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。
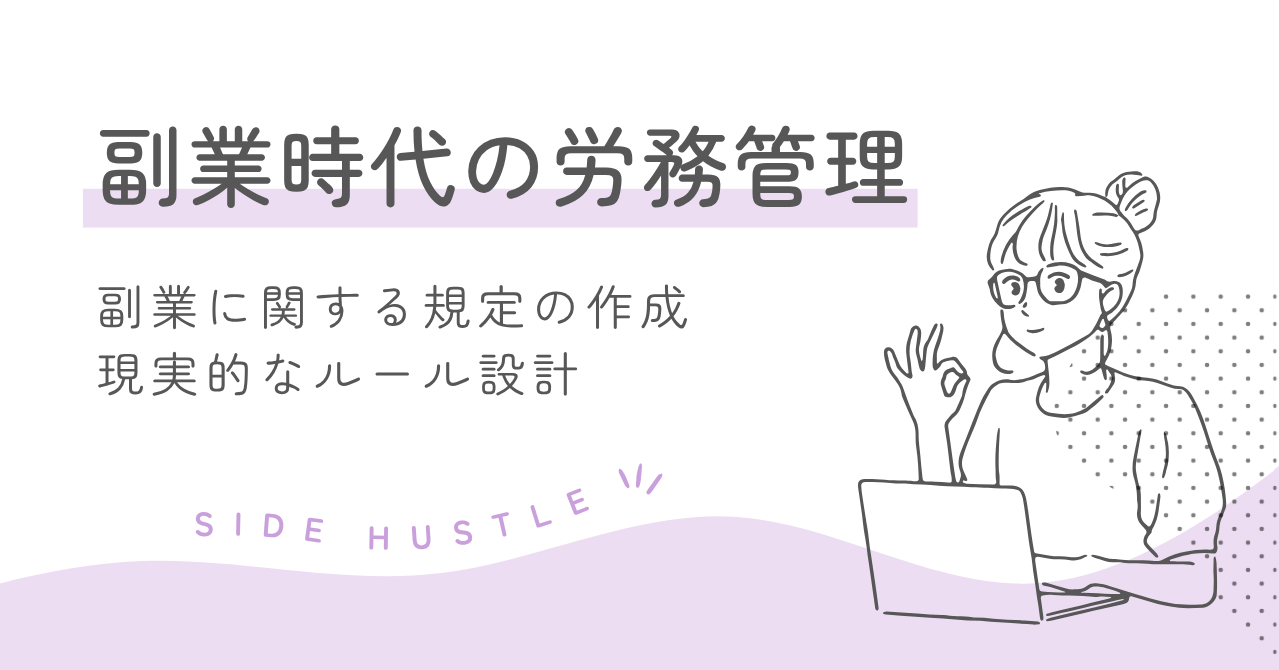
コメント