本記事は「会社員の給料とお金の基本」シリーズの第1話です。
「基本給が低いのは危険信号?」「年俸制で残業代は本当にゼロになるの?」
会社員として働く私たちは、自分の給与や契約について、多くの疑問を抱えながらも、曖昧にしたまま放置しがちです。
会社からもらうお金には、「給料」「給与」「賃金」「報酬」と様々な呼び方があります。
しかし、これらの言葉が指す金額の範囲や、法律上の意味が異なることをご存じでしょうか?
一見、些細な違いに見えますが、この曖昧さが、残業代の計算ミスや将来の年金額、さらには税金の過払いといった、会社員にとって大きな損に繋がる可能性があります。
この記事では、日常の会話で使う言葉と、あなたの権利とお金を決める法律上の言葉を明確に区別し、「収入」と「所得」といった税金の基礎知識までを整理します。
これからのキャリアで損をしないための、最も重要な基本知識を身につけましょう。
この記事でわかること
- 「給料」「給与」「賃金」「報酬」の違いを法律・税金の観点から整理
- あなたの給与明細に書かれた「金額の意味」がわかるようになる
- 「収入」と「所得」の違いを理解し、手取りを正しく把握できる
- 将来のキャリア・年金・税金で損をしないための知識が身につく
なぜ「給料・給与・賃金・報酬」の違いを知る必要があるのか?
はっきり言って、「給料」「給与」「賃金」といった言葉の違いを厳密に知らなくても、多くの人は日常生活に支障をきたすことはありません。
毎月決まった日に、指定口座にお金が振り込まれさえすれば、特に気にしないという方が大半でしょう。
ですが、これからの時代、自分の働き方やキャリアを自分でコントロールし、不測のトラブルから身を守るためには、これらの違いを知っておいたほうが絶対的に得です。
なぜなら、これらの言葉が単なる呼び方の違いではなく、法律や税金の世界では、あなたの権利とお金に直結する全く異なる意味を持っているからです。
似て非なる“お金の言葉”が招く3つの落とし穴
私たちが日常で使う言葉と、法律・税制で使う言葉が異なっていることで、あなたは知らず知らずのうちに以下のようなリスクを負う可能性があります。
1. 給料・給与・賃金|「言葉は違うが意味は同じ」ではない
「給料」「給与」「報酬」は、言葉も違うし、意味も違うケースが大半です。
- 例えば、あなたの残業代や手当を含む「総額」を指すのか(給与)、それとも基本給だけを指すのか(給料)、という金額の範囲が異なります。
- さらに、「賃金」と「報酬」は、一見同じ働く対価に見えますが、それぞれ労働基準法と社会保険法という異なる法律で定義されており、その適用範囲が変わります。
2. お金にまつわる「権利」を知らないと損をする
労働者の権利を守る労働基準法では、残業代や手当を含むすべての働く対価を「賃金」と呼んでいます。
- もし会社から未払いのお金があった場合、法律に基づいて請求する際、「賃金」の正確な範囲を知らないと、本来もらえるはずの金額を請求し損ねる可能性があります。
3. 税金・社会保険料の仕組みを誤解して“手取り”が減る
あなたの手取り額を決定づける税金や社会保険料は、「給与」や「報酬」に基づいて計算されます。
- 特に、「収入」(額面)と「所得」(もうけ)の違いを理解していないと、年末調整や確定申告で自分がどれだけ税金を納めるべきか(または戻ってくるか)が判断できません。
- この知識がないと、手取りを増やす節税のチャンスも見逃してしまいます。
これらのリスクを回避し、自分の受け取るお金の全体像と権利を正しく理解するために、まずは「言葉が違うだけでなく、意味も異なる」それらの用語の厳密な定義を見ていきましょう。
給料・給与・賃金の違いとは? 働く対価をめぐる法律上の定義
会社から支給されるお金は、管轄する法律や目的によって、呼び方と内容(定義)が変わるという点が、この話の最も重要なポイントです。
給料・給与・賃金・報酬の違いを法律上の目的で整理
| No. | 用語 | 主な使用シーン | 定義と意味合い |
| ① | 賃金 | 労働基準法 | 労働の対価として使用者が労働者に支払うすべてのもの。 労働者保護のための最も広い概念。 |
| ② | 給与 | 所得税法 | 給料・賃金・賞与等を含む労働所得の総称。 税金計算のための概念。 |
| ③ | 報酬 | 社会保険法・民法 | 広い意味で役務提供の対価。 社会保険では保険料算定の基礎となる。 |
| ④ | 給料 | 日常会話・社内用語 | 毎月受け取るお金のうち、主に基本給(手当・残業代を含まない)を指すことが多い。 |
給料・給与・賃金の法律用語と日常用語の境界線
上記の通り、これら4つの言葉は並列で使われますが、①~③は法律上の目的を持つ専門用語であり、④だけは日常的な慣習語であるという決定的な違いがあります。
① 賃金|労働者の権利を守る言葉
「賃金」は、残業代の計算や未払い賃金の請求など、労働者を保護するためのルールを定めた労働基準法で使われます。
- 特徴
- 基本給、通勤手当、住宅手当、家族手当など、労働の対価として支払われるものは原則すべて賃金に含まれます。
- ただし、結婚祝金のような恩恵的なものや、出張旅費のような実費弁償的なものは含まれません。
- 注意点
- 労働基準法が適用されない役員に対する報酬は、賃金には含まれません。
- この「賃金」を正しく知ることが、あなたの残業代計算の土台となります。
② 給与|所得税を計算する言葉
「給与」は、国に納める所得税のルールを定めた所得税法で使われます。
- 特徴
- 会社が従業員に支払う賃金・給料・賞与等を含む労働所得の総称です。
- 賃金よりも広い概念であり、賃金は給与の一部として理解されます。
- 非課税の手当も総額には含みますが、所得税の課税対象となる金額からは除外される点が重要です。
③ 報酬|社会保険料と役務提供の対価を指す言葉
「報酬」は、最も広い意味では雇用契約がない、委任や請負契約での支払いにも使われます。
会社員にとっては、社会保険料の算定基礎として使われます。
- 社会保険法上(会社員の場合)
- 健康保険や厚生年金保険の保険料を計算する基礎であり、労働者に支払われる賃金・給料・手当などをまとめて「報酬」と定義しています。
- 注意点
- 年4回以下の賞与は月々の標準報酬月額の計算には含めませんが、それ以外は賃金とほぼ同じ総額を指します。
④ 給料|最も誤解を生みやすい日常的な言葉
「給料」は、他の3つの法律用語と異なり、法律上の厳密な定義を持たず、慣習的に使われるという特殊な位置づけにあります。
- 特徴
- 多くの企業や日常会話では、残業代や各種手当を含まない、基本の固定額(基本給)を指す傾向が強いです。
補足|法律上の「給料」の定義
厳密には、労働基準法第11条の「賃金」の定義の中に「賃金、給料、手当、賞与…」とあります。
しかし、これは「給料という名称のものも含めてすべて賃金ですよ」という意味であり、「給料=賃金」という図式ではありません。
「給料」は、「賃金」という大きな概念を構成する一つの要素(基本給部分)を指す傾向が強いという点で特殊なのです。
会社員のお金の核心|賃金・給与・報酬の違いを理解する
会社員が受け取る労働の対価の総額という意味では、「賃金」「給与」「報酬」はほぼ同じ金額を指しますが、全く同じではありません。
本質的な違いは、「どの法律で何のために定義されているか」という目的の違いにあり、この目的の違いが、ごくわずかな計算の範囲の違いを生んでいます。
| 法律上の立場 | 呼び方 | 目的(何を計算するか) |
| 労働者保護(労基法) | 賃金 | 残業代、有給休暇中の賃金 |
| 税金計算(所得税法) | 給与 | 所得税、住民税 |
| 保険料計算(社保法) | 報酬 | 健康保険料、厚生年金保険料、将来の年金基礎 |
収入と所得の違いをわかりやすく解説|税金計算の基本
「賃金」「給与」「報酬」が働く対価の総額を指す言葉であるのに対し、「収入」と「所得」は、特に税金を計算する上で非常に重要な概念です。
会社員が自分の手取り額を正しく理解し、税金で損をしないためには、この二つの違いを明確にする必要があります。
給与の額面総額=収入|会社からもらうお金の全体像
収入とは、あなたが労働や事業を通じて得たお金の総額(いわゆる額面)を指します。
これは、税金や社会保険料が差し引かれる前の金額全体です。
- 定義
- 労働で得たお金の総額(額面)。
- 会社員の場合
- 「給与収入」や「年収」と呼ばれます。
- 毎年会社から発行される源泉徴収票には、この金額が「支払金額」として記載されています。
所得とは|税金がかかるお金の“もうけ”を解説
所得とは、収入から、その収入を得るためにかかった「必要経費」を差し引いた金額、つまりあなたの実質的な「もうけ」を指します。
住民税や所得税は、この「所得」に対して課税されるため、いくら税金を納めるかを決める最も重要な数字です。
所得金額=収入金額-必要経費
所得の計算において、「収入から差し引く項目」は、雇用形態によって大きく異なります。
会社員(給与所得者)の場合
会社員が稼いだお金は「給与所得」に分類されます。
| 項目 | 差し引くもの | 概要 |
| 給与所得控除 | 必要経費の代わり | 会社員は原則、個別の経費計上が認められないため、収入金額に応じて国が定めた概算の経費。 控除後の金額が「給与所得」となる。 |
給与所得=給与収入(年収)-給与所得控除
個人事業主(事業所得者)の場合
個人事業主が稼いだお金は「事業所得」に分類されます。
| 項目 | 差し引くもの | 概要 |
| 実際にかかった経費 | 事業所得 | 売上を得るために実際に使用した費用(仕入れ、家賃、通信費、広告費など)。 領収書や帳簿に基づき、実額が控除される。 |
事業所得=売上などの事業収入-実際にかかった経費
この「収入」と「所得」が混同されることで、世間の平均年収がそのまま自分の手取り額だと誤解したり、本来使えるはずの節税対策を見逃したりする原因となります。
まとめ|働くお金の用語を押さえると得られるメリット
ここまで見てきた「賃金」「給与」「報酬」「給料」、そして「収入」「所得」といった専門用語の違いを知ることは、あなたのキャリアや生活において、直接的なメリットをもたらします。
これらの用語の違いを理解することで、以下の2つの核となる知識を習得する土台ができます。
1. 「もらうべき権利」の把握(労働法)
働く対価の総称である「賃金」の定義を正しく理解することで、会社が支払うべき残業代や各種手当が、法律上の賃金の範囲に含まれているかをチェックできるようになります。
これにより、未払いや計算ミスといった不測のトラブルから、自分の労働者としての権利を守ることができます。
2. 「納めるべき金額」の確認(税・社会保険)
「給与」と「報酬」の定義、そして「収入」と「所得」の違いを理解することで、給与明細に書かれた金額から、なぜこれほど税金や社会保険料が引かれているのか、その計算根拠が明確になります。
適正な金額が引かれているかを確認でき、手取りを増やすための税制上の知識や節税対策へと繋がります。
次回予告|「基本給」が低いのは危険信号? 企業が給与を細かく分ける裏の理由
なぜ、企業はわざわざ「基本給」「住宅手当」「役職手当」のように、給与を細かく分けて支払うのでしょうか?
まとめて「基本給」としてくれれば分かりやすいはずなのに…。
実はこの「内訳」の分け方こそが、あなたの残業代や将来の資産形成に大きく影響しています。
多くの企業では、残業代の計算の土台となる「基礎賃金」を低く抑えるために、給与の内訳を意図的に調整しています。
つまり、額面が同じでも、基本給が低いと、あなたの残業代は少なくなってしまうのです。
「額面総額」だけに惑わされず、給与の内訳を正しくチェックし、自分の価値を確保する方法を身につけましょう。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|29240010号)
- 会社員歴30年以上、転職5回を経験した氷河期世代の社会保険労務士です。自らが激動の時代を生き抜いたからこそ、机上の空論ではない、働く人の視点にたった情報提供をモットーとしています。あなたの働き方と権利を守るために必要な、労働法や社会保険の知識、そしてキャリア形成に役立つヒントを、あなたの日常に寄り添いながら、分かりやすく解説します。
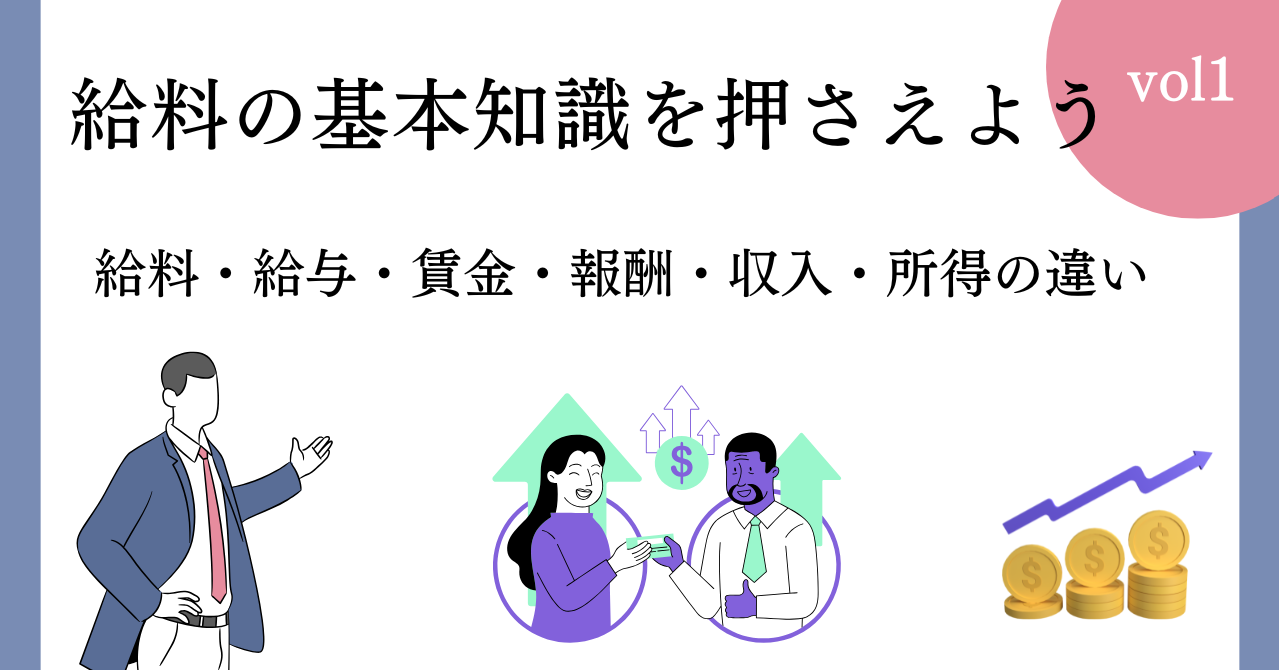

コメント