昼休みになりました。昨年と違って、今年はお弁当を持参していたので、昼食の時間に余裕があります。
社労士試験界隈では「昼休みに選択式の答え合わせをしない方がいい」とよく言われます。
理由は明白で、今さら確認しても結果は変わりませんし、もし予想外の間違いに気づいてしまった場合、不合格が確定することも無きにしも非ずだからなのでしょう。
メンタルに悪影響を与えるくらいなら、むしろ触れないほうがいい――それが一般的な考え方です。
しかし、私としてはやはり労一の解答が気になりました。
一番気になったのは完全に当てずっぽうで選択した「ジョブメンター」。選択式の試験が終わり、トイレに行った後、即「ジョブメンター」という言葉を検索しました。
これはなんか違うな、とすぐわかりました。ヤバい、外してんなぁ。
もう一問の迷って解答したこれ👉「障害者の法定雇用率を満たしていない事業主(常用雇用労働者【□】の事業主に限る)」…100人超で正解でした。
判例問題はちょっと検索したのですが、よくわからずでした。
しかし、不安だった2つの内1ついけているので、これは基準点クリアしているのではないか?というわずかな希望を抱きつつ、昼休みが終わっていきました。
時計の針は12時50分。受験生がぞろぞろと会場に戻り、着席します。
試験官による長い説明が続き、やがて13時20分、いよいよ択一式試験がスタートしました。
3時間30分、全350肢との闘いが始まります。
社労士試験 択一式試験スタート|労働関係科目で直面した未知の問題
まずは労働基準法です。最初の3問目くらいまでは順調です。特に問題はありません。
しかし第4問目あたりからちょっと不穏な空気が漂い始めました。
五肢択一の形式で、まったく初見の肢が紛れ込み出したのです。
五肢とも初見ということは無いのですが、チラホラ見たことも聞いたことも無いような選択肢が紛れ込み始めます。2つ、3つは正誤の判断をつけられる。しかし残りの肢がどうにも判断できない。「これは正しいよな?」「これは間違ってるよな?」と微妙に思えるものと、「初めて見るけど、なにこれ?」という肢が並び、どちらかを選ばざるを得ない――そんな問題が頻発しました。
私の勉強方法は、徹底した過去問演習です。過去10年分を文字通り解き尽くし、最新の法改正も「月刊社労士受験」でフォローしてきました。それなのに、今まで触れたことのない論点が目の前に次々と現れる。
一言で言うと手ごたえが全くありません。労働関係科目全般で同じような感触が続き、徐々にメンタルが削られて行きます。「ヤバい、これは…」。そんな不安が頭を支配していきます。
社労士試験 一般常識科目の戦略|最低限の点数を確保するために凌ぎます
一般常識科目は、白書・統計の問題が3問。社会保険労務士法からの問題が1問。残りはテキストから。という感じです。
正直この科目は8点9点狙える科目ではありません。とりあえず凌ぐ一手です。
いかに失点を抑え、最低限の点数を確保するか――それだけを意識します。
社労士試験 社会保険科目で挽回|健康保険法・年金科目の手ごたえ
こうなったら、気を取り直して、社会保険科目で取り返すぞ。
時間は14時50分。時間配分だけはうまくいっている。社会保険科目3科目残してあと2時間あります。労働関係科目を見直して再考する時間もありそうです。
ここから挽回すれば大丈夫だ――そう思いたい気持ちで、まずは健康保険法に取りかかりました。
しかし、健康保険法がちょっとこれも難しいのです。初見事項、重箱の隅をつつくかの如く細かいところを問う問題もあり、苦戦します。
この時点で既にメンタルに限界がきて泣きそうになってます。あれだけ勉強したのにこれか。もうだめだ。
と泣き言を言っていても始まりませんが、社労士試験の択一式試験は、社会保険科目で点数を稼ぐ、というのが定石なのです。それができそうにない。
多少の手ごたえ年金科目(厚生年金・国民年金)
続いて厚生年金保険法。難易度は例年より少し難しいかくらいです。
これまでのような「見たことも無いような肢」は特にありません。9点10点は無理かもしれないが、7点前後は取れているのでは。
国民年金法も同じような感じ。TACの模試と比べて初回に受けた模試くらいの難易度かな、とは感じでした。7点前後はいけてるのでは、という手ごたえです。そんなに捻った問題、細かい論点の問題は無かったように思えます。
この2科目は他の科目と違って、確信をもって解答ができた問題が多かったので、すごく「できた」感はありました。
それでも「完璧」という手応えでは無かったです。全7科目が全部これくらいの手ごたえならばよかったのですが、最初の労働関係科目と一般常識、健康保険法の手ごたえの無さが、ひどい。
課題だった択一式試験の時間配分と再考
時間はやはり25分ほど余りました。
労働科目の再考を試みましたが、目を皿にして問題を眺めても、正解は降ってきません。初見の肢は初見のまま。頭を捻っても結論は変わらないのです。
ふと、「孫子の兵法」の一節が頭をよぎりました。
未だ戦わずして廟算して勝つものは、算を得ること多きなり。未だ戦わずして廟算して勝たざる者は、算を得ること少なきなり
これは、戦う前の計算によって勝敗がほぼ決まるという意味です。
つまり、勝つ者は戦う前に勝利の見通しを立てており、負ける者は戦いながら勝利を探す、ということです。
試験中に見たこともない問題に直面しても、結局はどうにもならない。試験が始まる前にどれだけ準備できていたかで勝敗は決している。なんか、この択一式試験中の私のようです。
16時50分。令和4年度社労士試験択一式試験終了です。
社労士試験終了後の心境
択一式試験の手応えの無さに打ちのめされながら、私はコスモスクエア駅へと向かいました。会場からあふれ出す受験生の群れに混ざり、とぼとぼと歩きます。
周囲には仲間と談笑する受験生の姿も見えましたが、私はそんな余裕はなく、ただ深い傷心を抱えたまま足を運んでいました。
すると、左のほうで40歳前後でしょうか、男性の受験生が電話で誰かと話しています。「今終わった」相手は同僚かもしれないし、奥さんかもしれません。
彼は続けます。「昨年よりはだいぶ出来たわ。そう考えるとおそらく…」昨年僅差で落ちたのでしょうか。今年は手応え的には合格してるだろう、という事でしょう。
そうか。合格するような人はやはり終わったときに「これは受かったな」と思うのでしょう。そう考えると…ダメか。
そんな思いに苛まれながら、私は重い足取りで家路につきました。続く。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 50歳を目前に、会社員として働きながら、様々な事情により社会保険労務士試験への独学での挑戦を決意しました。不合格という苦い経験もしましたが、そこで諦めることなく合格を勝ち取りました。
- このブログでは、自身の経験を踏まえ、特に「仕事と受験勉強の両立に悩む会社員の方」や「独学で合格を目指す方」にとって有益となる社労士試験合格への道のりをお届けします。
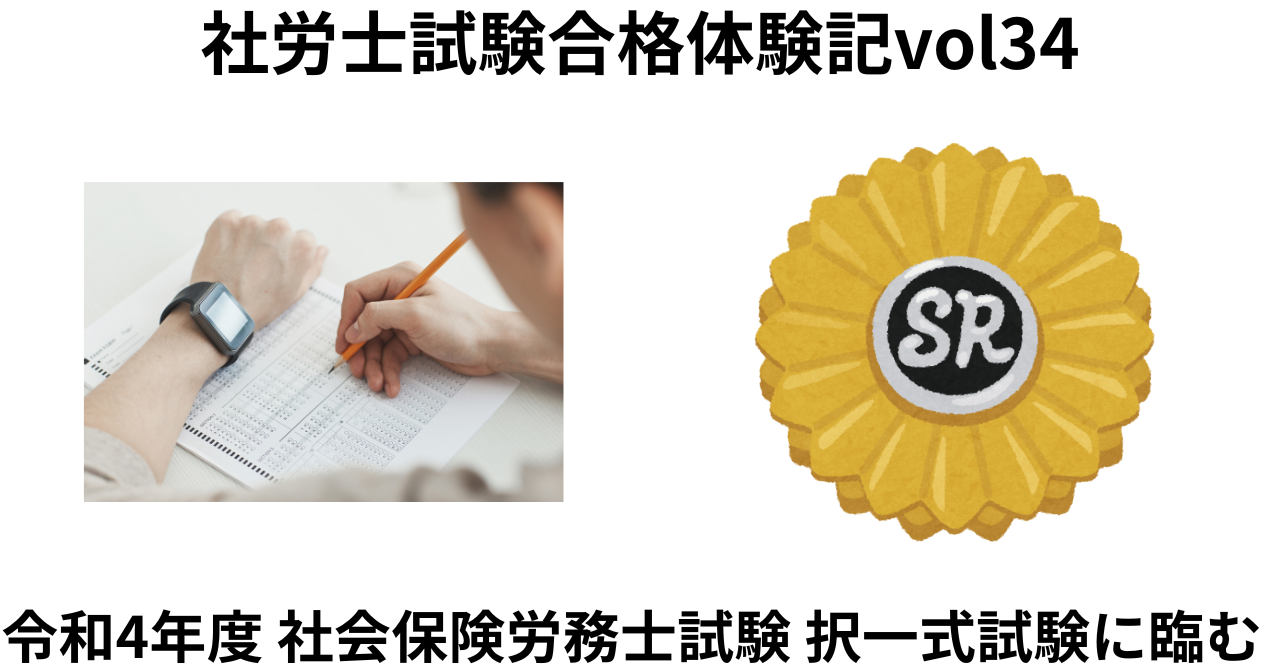
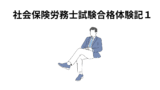

コメント