
執筆者:社会保険労務士 戸塚淳二
戸塚淳二社会保険労務士事務所の代表として、日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わるさまざまな課題に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方、人事制度の整え方まで、はじめての方にもわかりやすく解説することを心がけています。本記事では、「これだけは知っておきたい」労務の基礎について、専門家の視点からやさしくお伝えします。
社会保険労務士登録番号:第29240010号
本記事は「【社労士が解説】企業のための熱中症対策 実践講座」シリーズの第8話です。第1話は👉熱中症は「他人事」ではない!企業に求められる安全配慮義務の基礎
シリーズ全体の記事はコチラからご覧ください👇
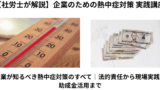
前回、熱中症対策の基本として、WBGT測定によるリスクの「見える化」と、マニュアル・就業規則による「ルール化」の重要性について解説しました。
これらは企業としての体制を整える上で不可欠な要素です。
前回の記事は👉中小企業でもできる!低コストで“訴えられない”熱中症対策 前編
しかし、どんなに優れたルールやマニュアルがあっても、それを「知っている」だけで終わっては意味がありません。
実際に現場で働く従業員一人ひとりが内容を理解し、実践できて初めて、真の効果が生まれます。
そこで不可欠となるのが、教育と訓練です。
特に中小企業では、外部の専門家を招くのが難しい場合もありますが、工夫次第で十分に内製化できます。
熱中症予防の教育・訓練の内製化 小規模でもできる効果的な取り組み
「教育や訓練と聞くと、大がかりで大変そう…」と感じるかもしれません。
でも、心配はいりません。
小規模な会社でも、日常業務の合間や既存のツールを活用して、効果的な熱中症予防の教育・訓練を内製化できます。
なぜ熱中症予防の教育・訓練が必要なのか?
教育・訓練は、以下の点で従業員の安全と会社の信頼を守る上で極めて重要です。
- 従業員一人ひとりの意識向上、自己管理能力の育成
- 熱中症は個人の体調管理も大きく影響します。
- 従業員が熱中症の危険性や症状、予防策を正しく理解することで、各自が自主的に水分補給をする、休憩を取る、体調異変を申告するといった自己管理能力が向上します。
- マニュアルの実践、緊急時対応能力の向上
- 作成したマニュアルや就業規則に書かれたルールは、教育を通して初めて従業員の行動に落とし込まれます。
- また、万が一熱中症患者が発生した場合に、適切な応急処置や報告が迅速に行えるよう、具体的な訓練を通じて緊急時対応能力を高めることが不可欠です。
熱中症予防の教育・訓練の内製化の具体例と実施方法
では、具体的にどのような教育・訓練を、どのように進めればよいでしょうか。
以下に、中小企業でも取り入れやすい内製化の具体例をご紹介します。
短時間勉強会の実施(朝礼時や休憩時間など)
- 毎日や週に数回行う朝礼や短い休憩時間を活用して、5分から10分程度のミニ勉強会を開いてみましょう。
- 熱中症の症状と対処法
- めまい、立ちくらみ、頭痛などの初期症状や、具体的な応急処置(体を冷やす場所、冷却部位など)を簡潔に伝えます。
- WBGTの見方と行動基準
- 「今日のWBGTは〇〇℃だから、水分補給は〇分おきにしよう」「〇〇℃を超えたら、作業を中断して必ず休憩を取る」など、マニュアルで定めたWBGT値と行動を繰り返し確認します。
- 水分補給の重要性
- のどが渇く前に飲むこと、スポーツドリンクや塩分補給の重要性などを繰り返し呼びかけます。
- 過去の事例共有
- 自社や他社の熱中症事例(個人が特定できない範囲で)を共有することで、熱中症は「誰にでも起こりうる」ことだと認識させ、危機意識を高めます。
- 熱中症の症状と対処法
動画の活用(厚生労働省等の無料コンテンツ、自社での簡易作成)
- 視覚情報は理解を深めるのに非常に有効です。
- 公的機関の無料動画
- 厚生労働省の「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」サイトなどでは、熱中症予防に関する啓発動画を無料で公開しています。例えば👉動画で学ぶ職場における熱中症予防対策👉東京労働局公式Youtubeチャンネル
- これらを休憩時間中に流したり、共有サーバーに置いていつでも視聴できるようにしたりするのも良いでしょう。
- 自社での簡易作成
- スマートフォンを使って、実際の作業現場での水分補給のタイミングや休憩の取り方、体調不良時の声かけの様子などを短く動画にまとめ、社内で共有するのも効果的です。
- 身近な環境での映像は、従業員にとってよりリアルに感じられます。
- 公的機関の無料動画
啓発ポスターの掲示(目立つ場所への設置)
- 休憩室や更衣室、作業現場の入り口など、従業員の目に触れやすい場所に熱中症予防のポスターを掲示しましょう。
- 厚生労働省提供のポスター
- 無料でダウンロード・印刷できるものが多数あります。例えば👉熱中症を防ぐために知っておきたいこと 熱中症予防のための情報・資料サイト
- 自社作成ポスター
- WBGT値に応じた行動基準や、緊急連絡先などを大きく分かりやすく記載したポスターを自社で作成するのも良い方法です。
- デザインに凝る必要はなく、重要な情報が伝わることを最優先にしましょう。
- 厚生労働省提供のポスター
ロールプレイング(体調不良者発見時の対応シミュレーション)
- 万が一の事態に備え、体調不良者を発見した際の声かけ、報告、初期対応をロールプレイング形式でシミュレーションしてみましょう。
- 例えば、「同僚が急にふらついた」「意識がもうろうとしている」といった状況を設定し、どのような手順で行動すべきか(声をかける→涼しい場所に移動→体を冷やす→管理者に報告→必要なら救急車を呼ぶ)を実践してみることで、緊急時に冷静に対応できる能力が高まります。少人数でも十分実施可能です。
「熱中症予防声かけ運動」の推進
- 従業員同士が互いに体調を気遣い、声をかけ合う文化を醸成することも大切です。
- 「〇〇さん、ちゃんと水分取ってますか?」「休憩しましょうか」といった声かけを推奨し、従業員間で予防を意識し合う環境を作りましょう。
- 特に、一人で作業することが多い従業員には、定期的な声かけや連絡を義務付けるなど、孤独な作業環境にさせない工夫も重要です。
これらの取り組みは、特別な設備や大きな予算を必要としません。
日々の業務の中に少しずつ取り入れることで、従業員一人ひとりの熱中症に対する意識を高め、安全な職場環境を無理なく築き上げていくことが可能です。
熱中症関連の助成金の有無・連携先紹介 利用可能な外部支援を活用する
熱中症対策は企業の努力だけでなく、外部からの支援を賢く活用することで、さらに強化できます。
特にコストやリソースに限りがある中小企業にとって、助成金や専門機関のサポートは心強い味方となるでしょう。
熱中症対策に直接関連する国の助成金は?
残念ながら、現状、国が提供する助成金で「熱中症対策」単独を直接支援するものは限られています(2025年7月時点)。
しかし、安心してください。
直接的ではなくても、間接的に熱中症対策に資する設備投資や制度整備に活用できる可能性のある助成金は存在します。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コースなど)
- この助成金は、労働時間短縮や年次有給休暇取得促進のための取り組みを支援します。
- 例えば、労働環境改善の一環として、熱中症対策につながる空調設備の導入、休憩所の設置、遮熱塗料の塗布などが、間接的に助成対象となる可能性があります。
- 働き方改革を推進する中で、従業員の働く環境を改善する費用の一部を賄えるかもしれません。
業務改善助成金
- 事業場内の最低賃金を引き上げ、同時に業務改善のための設備投資などを行う場合に利用できる助成金です。
- 例えば、労働生産性向上に資する設備として、熱中症リスクを軽減する換気設備の導入や、作業負担を軽減する省力化機械の導入などが対象となる可能性があります。
地域ごとの自治体補助金・助成金
- 国だけでなく、各地方自治体(都道府県、市区町村)が独自に、中小企業の省エネ化、労働環境改善、DX推進などの名目で補助金や助成金を提供している場合があります。
- これらの中には、熱中症対策に関連する設備投資や専門家への相談費用を支援するものが含まれている可能性があるので、所在地の自治体のウェブサイトを定期的に確認してみましょう。
助成金を検討する際は、各助成金の詳細な要件や対象経費を個別に確認し、自社の熱中症対策が合致するかどうかを事前に確認することが重要です。
困ったときに頼れる相談・連携先
熱中症対策は専門的な知識も必要となるため、困ったときは迷わず外部の専門機関や専門家を頼りましょう。
- 労働基準監督署
- 職場での安全衛生に関する指導や相談を受け付けています。
- 熱中症対策に関する法的な義務や具体的な対策方法について、疑問点があれば相談できます。
- 地域産業保健センター
- 中小企業の事業者や従業員を対象に、産業医や保健師による健康相談、メンタルヘルス相談、さらに職場巡視によるアドバイスなどを無料で提供しています。
- 熱中症予防のための職場環境改善について、専門的な視点からの助言が得られますし、関連する助成金情報についても教えてもらえることがあります。
- 都道府県労働局
- 労働基準監督署の上位機関で、労働法全般や助成金に関する広範な情報を提供しています。
- 働き方改革関連助成金など、熱中症対策と関連しうる助成金について詳しく知りたい場合は、こちらに問い合わせてみましょう。
- 社会保険労務士
- 就業規則の整備、安全衛生活動へのアドバイス、労働関係助成金の情報提供や申請支援など、労務管理全般の専門家です。
- 熱中症対策における就業規則への明記、労働環境整備のための助成金活用について、具体的なサポートを依頼できます。
- 戸塚淳二社会保険労務士事務所も、この分野でのサポートが可能です。
これらの外部支援を積極的に活用することで、中小企業でも無理なく、そして効果的に熱中症対策を進め、「訴えられない」安心できる職場環境を構築できるでしょう。
まとめ|安全と安心のための「無理のない」熱中症対策を
ここまで、前編・後編にわたって「中小企業でもできる!低コストで訴えられない熱中症対策」について解説してきました。
前編では、WBGT測定によるリスクの「見える化」、そして社内マニュアルや就業規則による「ルール化」という基盤作りの重要性を。
そして後編では、従業員一人ひとりの意識を高めるための教育・訓練の内製化、さらには助成金の間接的活用や外部専門機関との連携のヒントをお伝えしました。
多額の費用をかけなくても、これらの対策を段階的に進めることで、従業員の安全を守り、万が一の事態に「訴えられない」強固な企業体制を築くことは十分に可能です。
大切なのは、熱中症対策を一時的なものではなく、企業の持続可能な成長と従業員の健康を守るための継続的な取り組みと位置づけることです。
次回予告|熱中症対策で活用できる助成金について解説
次回以降は、今回触れた間接的に熱中症対策に活用できる助成金について、さらに深掘りして解説していきます。
- 「働き方改革推進支援助成金と中小企業の熱中症対策」
- 「業務改善助成金と中小企業の熱中症対策」
といったテーマで、それぞれの助成金が熱中症対策のどの部分に、どのように活用できるのか、具体的な視点から分かりやすくご紹介していく予定です。
次回の記事は👉【中小企業必見】熱中症対策に使える!働き方改革推進支援助成金の活用法➀
どうぞご期待ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。


コメント