本記事は「知っておきたい!年次有給休暇のすべて」シリーズのvol10です。
前回の記事では、2019年4月1日よりすべての企業に義務付けられた、年10日以上の有給休暇が付与される従業員に対する年5日間の有給休暇取得義務について、その背景から、就業規則の改定ポイント、有給休暇管理簿の適切な整備と運用方法に至るまで、中小企業の皆さまが対応すべき実務的な側面を詳しく解説しました。
前回の記事は👉【企業向けガイド】年5日間の有給休暇義務化にどう対応する?就業規則と管理簿の整備ポイントを徹底解説
今回はその続編として、多様化する働き方、特に非正規雇用者の有給休暇に焦点を当て、中小企業の総務担当者や経営者の皆さまが直面する具体的な課題と、その解決策について深掘りしていきます。
非正規雇用者増加による有給休暇管理の複雑化と企業対応策
近年、日本の雇用形態は大きく変化し、パート、アルバイト、契約社員といった非正規雇用で働く方が増えています。
厚生労働省の調査(※1)によると、2022年の非正規雇用労働者数は2,101万人に達し、役員を除く雇用者全体に占める割合は36.9%となっています。
これは、1990年の約20%から30年余りで約2倍に増加した計算になります。
2020年、2021年には一時的に減少したものの、2022年以降は再び増加傾向に転じており、多くの企業が多様な雇用形態の従業員を抱えるようになりました。
※1 厚生労働省「2023年度第1回雇用政策研究会 参考資料集」および「非正規雇用」の現状と課題(2022年データに基づく)
これに伴い、有給休暇の管理はより複雑化しています。
企業成長に役立つ有給休暇の活用法|従業員エンゲージメントと生産性向上
有給休暇は、労働者の心身のリフレッシュを図り、健康を維持するために労働基準法で定められた大切な権利です。
適切に有給休暇を取得させることは、従業員のエンゲージメント向上やモチベーション維持に繋がり、ひいては企業の生産性向上にも貢献します。
しかし、単に法的義務だからというだけでなく、多様な働き方をする従業員がいきいきと働ける環境を整えることは、現代の企業にとって不可欠な経営戦略と言えるでしょう。
働き方改革関連法で非正規雇用者にも有給休暇義務|企業への影響と対応策
2019年4月1日に施行された働き方改革関連法は、日本企業の働き方に大きな変革をもたらしました。
その柱の一つが、年10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、年5日間の有給休暇を確実に取得させることの義務化です。
詳しくは👇よりご確認ください。


これは、正社員だけでなく、週の所定労働日数・時間に応じて有給休暇が付与される非正規雇用者も例外ではありません。
これまで、非正規雇用者への有給休暇の付与自体は法律で定められていました。
しかし、実際に取得を推進する仕組みは企業任せの部分が大きかったのが実情です。
しかし、この義務化によって、企業は非正規雇用者に対しても、有給休暇の取得状況を正確に把握し、必要に応じて取得を促す義務を負うことになりました。
「大変」では済まされない!中小企業が直面する有給休暇管理の法的リスクと対応策
中小企業の皆さまの中には、「パートやアルバイトの有給休暇まで細かく管理するのは大変だ。」「そもそも、うちの会社では非正規雇用者には有給休暇は関係ないと思っていた。」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、義務化の対象となる従業員に適切に有給休暇を取得させないと、労働基準法違反となり、罰則の対象となる可能性があります。
企業向け!有給休暇管理で押さえるべき実務的対応策
本記事では、非正規雇用者の有給休暇の基本的なルールから、多様な働き方における運用のポイント、そして5日取得義務化への具体的な対応策まで、中小企業の皆さまが今日から実践できる実務的な情報を提供します。
複雑に思える有給休暇管理も、正しい知識と適切なツールがあれば決して難しいものではありません。
企業のコンプライアンス強化と、従業員が安心して働ける職場環境づくりに向けて、共に学んでいきましょう。
非正規雇用者の有給休暇付与ルール|企業が押さえるべき基本ポイント
「うちの会社では、パートさんやアルバイトさんには有給休暇はないよ」。
もし、今でもそう考えているなら、それは大きな間違いです。
労働基準法では、正社員か非正規雇用かに関わらず、一定の要件を満たすすべての労働者に有給休暇の付与を義務付けています。
特に、短時間勤務の非正規雇用者には「比例付与」という考え方が適用されます。
その基本ルールを正しく理解することが、適正な有給休暇管理の第一歩となります。
非正規雇用者の有給休暇の基本的な付与ルール(比例付与、出勤率など)については、
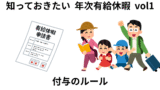
でも触れております。
特にシフト制アルバイトなど変則的な働き方をする従業員の有給休暇管理については、

にて詳細に解説しております。
これらの記事では、週の所定労働日数に応じた有給休暇の付与日数テーブル、出勤率の計算方法、具体的な付与日数のシミュレーションなど、基本的な情報を網羅しています。
まずはそちらで基礎をご確認いただくことをお勧めします。
本稿では、基本的なルールを前提とした上で、中小企業の総務担当者や経営者の皆さまが直面しやすい、より複雑なケースや見落としがちな実務上の注意点に焦点を当て、深く掘り下げて解説していきます。
雇用形態変更時の有給休暇|非正規社員の権利と管理方法
企業成長や従業員のキャリアパスに伴い、非正規雇用から正規雇用へ、あるいは異なる非正規雇用形態へと従業員の雇用契約が変更されることは少なくありません。
この際、有給休暇の取り扱いを誤ると、従業員とのトラブルや法令違反に繋がりかねません。
1. 非正規雇用から正社員への転換
パートや契約社員として働いていた従業員が正社員に登用されるケースはよくあります。この場合、転換前の非正規雇用時の勤続年数は通算され、有給休暇の付与日数にも影響します。
- 残有給休暇の引き継ぎ
- 非正規雇用時に付与され、消化しきれなかった有給休暇は、原則として正社員になってもそのまま引き継がれます。
- 消滅時効(2年)にかからない限り、利用可能です。
- 次回の付与日数の変更
- 正社員となった後の最初の基準日(入社日または統一された基準日)からは、正社員としての週所定労働日数(通常週5日以上)に応じた有給休暇が付与されます。
- この際、通算された勤続年数に応じた日数が適用されるため、勤続年数が長い場合は初年度から多くの有給休暇が付与されることになります。
- 例: 週3日勤務のパートとして4年6ヶ月勤務し、有給休暇12日付与の条件だった従業員が正社員になった場合、次回の基準日からは勤続5年6ヶ月の正社員の基準(18日)が適用されます。
2. 非正規雇用間の雇用形態変更(例:週3日勤務から週4日勤務へ)
同じ非正規雇用内でも、契約更新時に週の所定労働日数や所定労働時間が変更されることがあります。この場合も、有給休暇の付与日数に影響が出ます。
- 変更後の比例付与への適用
- 労働条件が変更された場合、次回有給休暇が付与される基準日からは、変更後の労働条件(週の所定労働日数または時間)に応じた比例付与の日数が適用されます。
- この際も、勤続年数は通算されます。
- 変更前の残日数
- 変更前の労働条件で付与された有給休暇の残日数は、そのまま引き継がれ、消滅時効まで利用できます。
「全労働日の8割以上出勤」ルールの注意点|有給休暇付与のグレーゾーン解説
有給休暇付与の要件である「全労働日の8割以上出勤」は、非正規雇用者、特にシフト制で働く従業員にとって、計算が複雑になりがちです。
基本的な考え方は前述の通りですが、実務で迷いやすい点を掘り下げます。
労働日数の算出基準
- シフト制の場合、会社が「労働日」と定めている日が何日になるのかを明確にすることが重要です。
- 従業員の希望シフト通りに出勤しなかった場合、それが会社の責か、従業員の責かによって「欠勤」の扱いが変わることもあります。
不就労期間の取り扱い
- 傷病手当金受給中の休業
- 私傷病による休業で傷病手当金を受給している期間は、原則として欠勤扱いとなり、出勤率に影響します。
- ただし、会社の判断で出勤とみなす場合は、就業規則に明記する必要があります。
- 生理休暇、慶弔休暇など
- 法定外休暇(就業規則で定める休暇)や、法定休暇でも無給の休暇(一部の生理休暇など)は、就業規則の定め方によって出勤率の算定に影響を与えることがあります。
- 原則は欠勤扱いですが、企業が「出勤とみなす」と定めていればその限りではありません。就業規則で明確にしておくことがトラブル防止に繋がります。
これらの事項は、法律上の解釈が非常に複雑です。さらに企業の裁量に委ねられる部分が含まれるため、判断に迷いやすい「グレーゾーン」となりがちです。
そのため、トラブルを避けるためには、「自社の就業規則を詳細に確認する。」「不明な点は労働基準監督署や社会保険労務士などの専門家に相談する。」など明確な運用基準を設けることを強くお勧めします。
実務でよくある有給休暇管理の落とし穴と対策|非正規雇用者も安心
非正規雇用者の有給休暇管理は、正社員以上にきめ細やかな対応が求められます。
労働条件通知書と雇用契約書の再確認
- 有給休暇の適切な管理には、従業員との間で労働条件が明確に共有されていることが大前提です。
- 特に中小零細企業においては、口頭での取り決めになりがちな部分もあるかもしれません。
- しかしながら、労働基準法では、労働契約締結時に特定の労働条件を書面で明示することが義務付けられています。これは、従業員との認識の齟齬を防ぎ、後のトラブルを未然に防ぐ上で極めて重要です。
- もし、現在、労働条件通知書や雇用契約書といった書面による労働条件の明示を行っていない場合は、速やかに作成し、従業員に交付してください。
- これは企業の法的義務であり、怠ると罰則の対象となる可能性があります。
- 労働条件通知書の内容確認/作成
- 有給休暇の付与条件(勤続年数、週所定労働日数に応じた付与日数)が明確に記載されているかを改めて確認してください。
- 従業員の雇用形態(パート、アルバイト、契約社員など)ごとに、適用される有給休暇の条件が正しく示されているかを見直しましょう。
- 雇用契約更新時の再明示
- 雇用形態変更時や契約更新時には、労働条件通知書の内容を更新し、有給休暇に関する事項も必ず再提示することが重要です。
- 口頭での説明だけでなく、書面で残すことで、認識の齟齬を防ぎ、将来的な紛争のリスクを低減できます。
- 労働条件通知書の内容確認/作成
正確な勤怠記録の徹底
- 有給休暇の付与や消化には、正確な勤怠記録が不可欠です。
- 非正規雇用者の場合、シフトの変更や欠勤が頻繁に発生します。日々の出勤状況を確実に記録する仕組みを構築しましょう。
- クラウド型の勤怠管理システムを導入することで、複雑な勤務形態の従業員の有給休暇管理も効率化でき、手作業によるミスを大幅に削減できます。
- システムによっては、自動で比例付与日数を計算してくれる機能もあります。
従業員への積極的な周知と理解促進
- 有給休暇は従業員の権利ですが、「自分には関係ない。」「どうせ取れない。」と考えている非正規雇用者も少なくありません。
- 「定期的に有給休暇制度の説明会を実施する。」「分かりやすいリーフレットを作成・配布したりする。」など、従業員が自身の有給休暇付与日数や取得状況を把握できるよう、積極的に情報提供を行いましょう。
- 特に、5日取得義務化の対象となる非正規雇用者には、企業から時季指定を行う可能性があることも、事前に丁寧に説明しておくことが重要です。
非正規雇用者も対象!有給休暇5日取得義務化への実務対応ガイド
2019年4月1日から施行された働き方改革関連法により、企業は、年10日以上の有給休暇が付与されるすべての労働者に対して、年5日間の有給休暇を確実に取得させることが義務付けられました。
この義務の対象は、正社員だけではありません。所定労働日数に応じた比例付与によって年10日以上の有給休暇が付与される非正規雇用者も対象となります。
有給休暇5日取得義務化の対象者とは?非正規雇用者の適用範囲を徹底解説
この義務化の対象となるのは、「毎年10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者。」です。具体的には、以下の条件を満たす非正規雇用者が該当します。
- 週の所定労働日数が4日、または週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者で、勤続期間が3年6ヶ月以上の者。
- この場合、付与日数は10日以上となるため、5日取得義務の対象となります。
- 週の所定労働日数が3日、または週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者で、勤続期間が5年6ヶ月以上の者。
- この場合も、付与日数は10日以上となり、5日取得義務の対象となります。
つまり、入社から間もない非正規雇用者や、極めて短時間の勤務の従業員は対象外となるケースが多いです。
しかし、ある程度の勤続年数がある非正規雇用者であれば、この義務化の対象となり得ます。
個々の従業員の付与日数を正確に把握し、対象者を特定することが不可欠です。
有給休暇5日取得義務化への企業対応策|非正規雇用者も含む全従業員の取得促進方法
義務化の対象となる非正規雇用者に対し、企業は以下のいずれかの方法、またはこれらを組み合わせて有給休暇を5日間取得させる必要があります。
1. 計画的付与制度の活用
- 計画的付与制度とは、労使協定を締結することで、有給休暇の付与日数のうち5日を超える部分について、企業があらかじめ取得時期を定めることができる制度です。
計画的付与に関しては👇よりご確認ください。
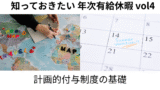
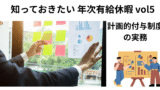
- 非正規雇用者への導入可否と留意点
- 非正規雇用者に対しても、労使協定を締結すれば計画的付与を導入できます。ただし、シフト制など勤務日が不定期な従業員の場合、一斉付与やグループ別付与が難しいことがあります。
- その場合は、個人別に計画的付与日を定める方法や、特定の繁忙期を避けるなどの工夫が必要です。従業員の合意形成が特に重要となります。
2. 個別指定方式での取得促進
- 従業員が有給休暇を5日取得していない場合、企業は従業員の意見を聴いた上で、取得時季を指定して有給休暇を取得させる必要があります。これが「時季指定権」の行使です。
時季指定権に関しては👇よりご確認ください。

- 声かけ、取得状況の可視化
- 総務担当者や各部署の管理職が、対象となる非正規雇用者の有給休暇取得状況を定期的に確認し、取得日数が不足している従業員には積極的に声かけを行いましょう。
- 取得状況を本人に分かりやすく通知する仕組み(例:勤怠システムでの残日数表示、個別の通知)も有効です。
- 希望の尊重
- 時季指定を行う場合でも、従業員の業務や私生活の希望を最大限尊重し、可能な限り調整に努めることが円滑な運用には不可欠です。
- 一方的な指定は、従業員の不満やモチベーション低下に繋がりかねません。
3. 企業として取り組むべき環境整備
- 有給休暇の取得は、制度があっても職場の雰囲気や業務体制が整っていなければ進みません。非正規雇用者が気兼ねなく有給休暇を取れる環境づくりが重要です。
- 業務の平準化
- 特定の従業員に業務が集中しないよう、業務を標準化し、誰でも一定レベルで対応できるようにマニュアル整備や情報共有を徹底しましょう。
- 多能工化の推進
- 複数の従業員が多様な業務に対応できるよう、スキルアップ研修やOJTを積極的に行いましょう。これにより、急な有給休暇取得時でも、他の従業員が業務をカバーしやすくなります。
- コミュニケーションの促進
- 上司や同僚が有給休暇取得に理解を示し、応援する雰囲気を醸成することも大切です。「お互いさま」の意識を育むことで、従業員は安心して休暇を取得できるようになります。
有給休暇5日義務化の違反リスク|非正規雇用者管理での罰則と企業の法的責任
年5日の有給休暇取得義務は、企業にとっての「義務」であり、違反した場合には罰則の対象となります。
罰則
義務対象となる労働者に対して年5日の有給休暇を取得させなかった場合、労働基準法第120条に基づき、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
企業のレピュテーションリスク
罰則だけでなく、義務違反は企業のコンプライアンス意識の低さを示すものとして、社会的な信用を失うレピュテーションリスクも伴います。
採用活動への悪影響や、既存従業員のエンゲージメント低下にも繋がりかねません。
従業員とのトラブル
有給休暇の取得に関する不満は、従業員との間に深刻なトラブルを引き起こし、労使紛争に発展する可能性もあります。
非正規雇用者を含む全ての従業員が適切に有給休暇を取得できる体制を整えることは、法的遵守はもちろんのこと、従業員満足度の向上と企業の持続的な成長のために不可欠です。
まとめ|非正規雇用者の有給休暇管理と企業成長・法令遵守への投資
ここまで、多様な働き方が進む現代において、特に非正規雇用者の有給休暇管理がいかに重要か、そしてその実務上の複雑な側面について深掘りしてきました。
「うちの会社には関係ない。」「管理が大変。」といった声があるかもしれません。しかし、非正規雇用者への有給休暇の適切な付与と管理は、単なる法的義務の遵守に留まりません。
- 法的なリスクの回避
- 労働基準法の義務違反による罰則や、従業員とのトラブルを防ぎます。
- 従業員エンゲージメントの向上
- 自身の権利が尊重されていると感じることで、従業員のモチベーションや企業への貢献意欲が高まります。
- 企業の競争力強化
- 従業員が心身ともに健康で、安心して働ける環境は、結果として生産性向上に繋がり、人材定着にも寄与します。これは、採用難の時代において企業の競争力を高める重要な要素です。
正確な付与日数の把握、雇用形態変更時の適切な対応、そして「出勤率」における細かな解釈など、管理には確かに手間がかかる部分もあります。
しかし、これらは全て、従業員が安心して長く働ける職場環境を整備し、企業の未来を盤石にするための重要な投資と言えるでしょう。
勤怠管理システムの導入や就業規則の明確化、そして何よりも従業員との丁寧なコミュニケーションを通じて、それぞれの企業に合った最適な有給休暇管理体制を構築していくことが、今、中小企業に求められています。
次回予告|フレックスタイム制・裁量労働制・在宅勤務における有給休暇の実務対応
次回の記事では、いよいよ多様な働き方の中でも特に質問の多い、フレックスタイム制や裁量労働制、そして在宅勤務・リモートワークにおける有給休暇の具体的な運用方法と、実務上の注意点について詳しく解説していきます。
変則的な勤務形態での有給休暇の考え方や、時間単位年休の活用法など、より複雑な事例に対応するためのヒントが満載です。どうぞご期待ください!
次回の記事は👉【企業担当者向け】多様な働き方と有給休暇 |フレックス・裁量・リモートワークの実務と偽装請負対策
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。


コメント