2022年4月15日、ついに官報で社会保険労務士試験の試験要項が発表されました!
試験日は8月28日、合格発表は10月5日。
今年は2回目の受験だから、大学の卒業証明書は不要で、昨年度の受験票があればOKです。事務的なことはサッサと終わらせる主義なので、迷わず受験料を支払って申し込みを完了しました。
X(旧Twitter)を見ていると、勉強の進捗具合で受験するか迷っている人が結構いるみたいですね。5月末まで悩みに悩んで、結局「今年は受ける」「受けない」を決める人もいるとか。
毎年5万人くらいが申し込んで、実際に受験するのは4万人くらい。そう、申し込んだけど「今年はやっぱりやめておく…」という受験生が相当数いるんです。
社労士試験を1回だけですけど経験した身としてみれば、分からんでもないな、というのが正直なところです。
※1年目の道のりをまだ読んでいない方は、まずはこちらからどうぞ。
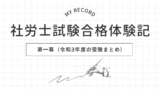
何を隠そう、今、この記事を書いている時点でも、行政書士試験に向けて勉強はしているものの、本業の仕事、社労士としての仕事、たまのアルバイト、そしてブログ執筆…と、勉強時間の確保がままならないことばかりです。
正直、今年度の行政書士試験は見送ろうかと考えているくらいです。
社労士試験 独学440時間の勉強記録と初学者脱却へのステップ
2022年4月に入るまで(つまり3月31日)の累計勉強時間は、約440時間です。勉強時間は順調に積み上がっていました。
しかし、ここにきて「そろそろ、初学者のような基本知識だけを積み上げていくような勉強方法から脱却する時期になってきているのではないかな。」という考えが頭をもたげてきました。
朝勉で一問一答形式の問題集をひたすら解き、通勤の行き帰りの電車の中でテキストえお読み込む、悪くない、でもこれだけではあの悪名高い「社会保険労務士試験」には太刀打ちできまい。
社労士試験独学者の宿命?教材選びの光と影
私は基本的に、テキストや問題集はAmazonで買っていました。書店では目当ての本が見つからないことが多いし、何より「中古の古いバージョンで安く済ませよう」というセコい魂胆があったので、社労士試験で使ったほとんどの教材はAmazon、一部はYahoo!フリマでゲットしました。
でも、Amazonでの購入には弱点があります。実際に買ってみないと中身が分からない、つまり「自分に合っているか」を事前に判断しづらいんです。おかげで、「買ったはいいけど結局ほとんど使わなかった」というテキストも少なくありませんでした。
Amazon、Yahooフリマの購入履歴を見ますと
みんなが欲しかった! 社労士全科目横断総まとめ 2021年度 (TACみんなが欲しかった! シリーズ)
- 2022年1月3日購入、正月やん。新品だと2680円だけど前年度版を739円で購入。
- やはり社労士試験独特の学習方法である「横断学習」をしなければ、と思い購入。個人的な感想を言うと「買う必要はなかったかな」です。
- 全く役に立たない、とかではないのですが、意外と分厚い本なのに、横断学習的な部分は、全体の5分の1くらいだったと思います。残りの部分は普通のテキストの簡略版みたいで、正直「なんだこりゃ」でした。
2022年度版 出る順社労士必修過去問題集 労働編 社会保険編 (出る順社労士シリーズ)
- 2022年3月30日購入。新品だと各々1980円で合計3960円かかるところ、なぜか中古で両方で1500円でYahooフリマで販売されていたので即購入。
- 労働編
- 社会保険編
- 3月一杯までは、朝勉で使っていた問題集は、一問一答形式のものを使っていましたが、これを購入したのをきっかけに、「本試験出題形式」の問題集で、過去問を回すようにしました。
- この問題集は過去10年分の問題が掲載されており、解答の解説が非常に充実しており、基礎学力向上に加えて、5肢択一という出題形式に慣れるにも、もってこいだと思います。
社労士V イラストでわかる労働判例100
- 2022年4月6日購入。判例集ですね。2090円の定価で購入、中古本が無かったのか、定価で買ってます。
- これは以前のブログでもご紹介したと思うのですが、独学社労士試験受験生にとっては必須アイテムでしょう。ここ数年の試験の出題の傾向として、特に選択式の対策としては外せないテキストだと思います。
よくわかる社労士 別冊合格テキスト 直前対策 2022年度版 (TAC出版)最強の一般常識対策本
- 2022年4月27日購入。これはさすがに新品で発売と同時に買いました。1980円。
- この本は最初から買おうと思っていました。一般常識の対策は、過去問だけでは絶対無理だと思っていたので、独学の身としては必須アイテムでしょう。
2022年5月13日購入社労士V2022年度版 選択式・労一を切り抜ける! 厚労省パンフレット・リーフレット攻略問題集
- 2022年5月13日購入。定価1100円で購入。👉Amazon👉楽天市場
- このテキストも買うことは以前から決めてました。ちゃんと確認したわけではないのですが、令和3年度の選択式の労一の内の一問は、この前年度版の中から出題された、との話は聞いたことがあります。
- このテキストに載ってる内容が、ピンポイントで出題されるかどうかは分かりませんが、一般常識をしっかり押さえておくには、このテキストは良かったと思います。
2021年版 社労士労基・安衛・労一ズバッと解放【判例・予想問強化エディション】 古川飛祐 (著)。
2022年6月5日購入。昨年度版を中古で購入。672円。
- 当時は労働基準法、労働安全衛生法に対してちょっと苦手意識がありました。特に安衛法は、ちょっと「とっつきにくい」というか、「こんなん憶えなあかんの?」というのが多々あったので、購入してみましたが、完全なる失敗でした。
- このテキストが良い、悪いではなく、今使っている「出る順社労士 必修基本書【2分冊セパレート・赤シート・科目別導入講義動画付き】 (出る順社労士シリーズ) 」で事足りる内容であったため、この本が到着してから10分くらいパラパラと眺めて、それ以来一度もこのテキストは開きませんでした。
社労士試験本試験まで5ヶ月を切って|中級者へのステップアップ
2022年4月に入り、本試験までのこり5ヶ月を切っております。勉強方法、というか勉強内容も自然と変わっていきます。
基礎固めから実戦形式へシフト
今までは一問一答を中心に択一式の試験に対しての対策をしながら、基礎学力を上げていき、通勤時間は、テキスト読みをし、ひたすらインプットに勤しむ。
ここまでくると最早、私は「初級者」は既に脱し、「中級者」にはなっているだろうと思い、毎月定期購入している「月刊社労士受験」にも本格的に取り組もうと決意します。今まではこの月刊誌の一つの売りである、山川靖樹先生の動画だけ拝聴していただけだったのですが、これからはその他の部分ももれなく読破して、レベルアップしていこうと考えました。
独学にありがちな、「なんでそんなテキスト買ってんの?」みたいなのも多少ありましたが、これで一旦、何をどのように使い勉強していくか決まりました。
4月からの社労士試験学習計画と合格戦略
ざっくりいうとこんな感じ。
- 今まで通り基本の勉強法は「択一対策」。これは4月からはこれ👉2022年度版 出る順社労士必修過去問題集 労働編 社会保険編 (出る順社労士シリーズ)
- 通勤電車の中でのの勉強はテキスト読み👉2025年版 出る順社労士 必修基本書
- 判例対策👉社労士V イラストでわかる労働判例100
- 一般常識対策👉よくわかる社労士 別冊合格テキスト 直前対策 2022年度版 (TAC出版)最強の一般常識対策本👉社労士V2022年度版 選択式・労一を切り抜ける! 厚労省パンフレット・リーフレット攻略問題集
- 法改正、その他全般的な対策👉月刊社労士受験
4月からの計画は完璧です。
社労士試験独学者の羅針盤|模試で実力と進捗を確認する重要性
あとは実際に遂行できるか?あとは今年は何回か模試を受けて自分の立ち位置、遅れている科目の把握をしていきます。
告白すると、この時点では、合格できる、とはあまり思ってませんでした。言ってみれば徐々にジグソーパズルのピースは順調に埋まっていっているという感覚はあるのですが、完成図全体からして、どれくらいの割合のピースが埋まっているのかがやはりよくわからないのですよね。
やはり独学者に必須行為としては「模試を受ける」は外せません。続く

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 50歳を目前に、会社員として働きながら、様々な事情により社会保険労務士試験への独学での挑戦を決意しました。不合格という苦い経験もしましたが、そこで諦めることなく合格を勝ち取りました。
- このブログでは、自身の経験を踏まえ、特に「仕事と受験勉強の両立に悩む会社員の方」や「独学で合格を目指す方」にとって有益となる社労士試験合格への道のりをお届けします。
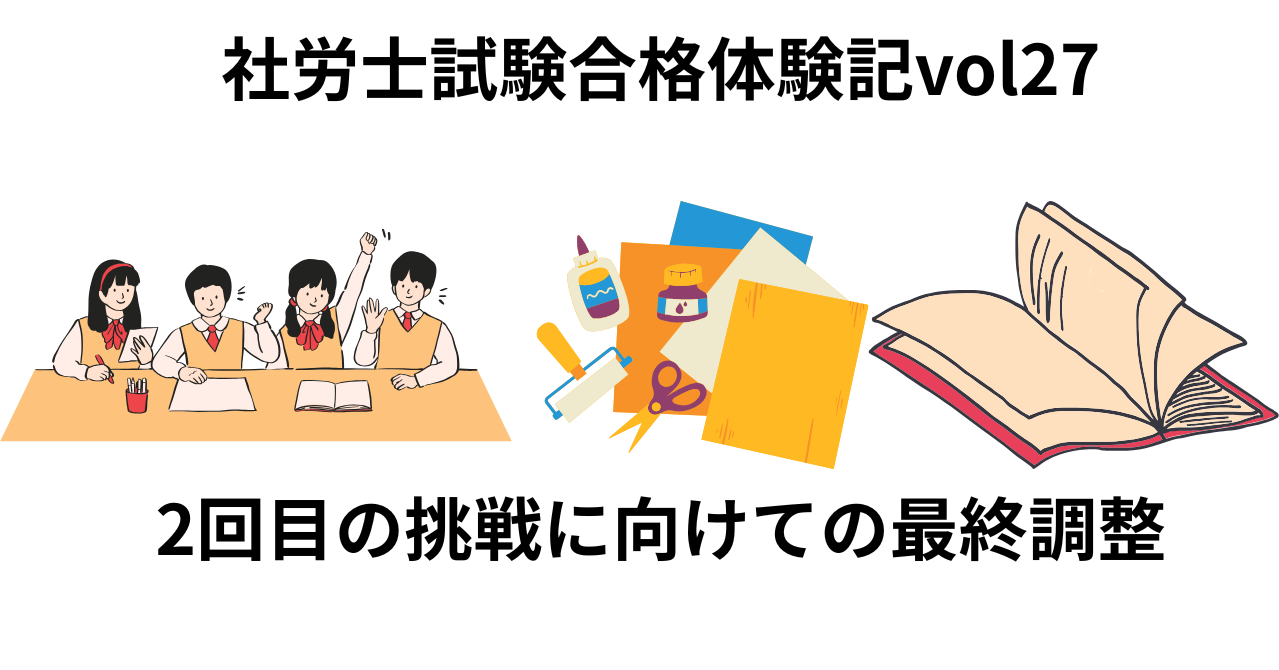
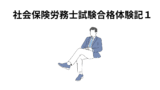





コメント