本記事は「2025年改正育児介護休業法シリーズ」の第44弾です。他のシリーズの記事はコチラから👉2025年育児介護休業法改正|企業がすべき対応と助成金情報
前回は、両立支援等助成金「柔軟な働き方選択制度等支援コース」の概要と、具体的な活用事例について解説しました。
前回の記事は👉両立支援等助成金「柔軟な働き方選択制度等支援コース」➀|中小企業向け助成金活用ガイド
制度の目的や、企業にとってのメリット、そして実際にいくらの助成金がもらえるのか、ご理解いただけたかと思います。
今回は、いよいよ助成金を実際に受け取るための具体的なステップについて詳しく見ていきましょう。
どんなに素晴らしい制度を導入しても、申請手続きを正しく行わなければ、助成金は受け取れません。
ここでは、制度導入計画の策定から支給申請までの流れを、分かりやすく解説します。
この記事で分かること
- 申請の第1歩は、制度導入の「1ヶ月前」までに労働局へ計画届を提出すること
- 就業規則には「対象者」「申請手続」「費用負担」などを具体的に規定する必要がある
- 制度を導入した事実だけでなく、全従業員への「周知」の証拠(メールや資料)が必須
- 「新規導入(20万円)」に加え、「利用者増加(1人5万円等)」の2段構えで受給可能
- 受給には「6ヶ月間の運用実績」が必要であり、その間の正確な勤務記録が不可欠
中小企業向け|柔軟な働き方助成金の申請手順まとめ
助成金を受給するためには、正しい手順で申請を進めることが不可欠です。
ここでは、制度導入を思い立ってから助成金を受け取るまでの3つのステップを解説します。
ステップ1|制度導入計画の作成方法|柔軟な働き方助成金の申請準備
助成金申請の第一歩は、柔軟な働き方制度を導入するための「制度導入計画」を立て、管轄の労働局に届け出ることです。
- 計画書の作成(様式第2号、3号 Excel)(様式第2号、3号 PDF)(記載例)
- 導入したい制度(テレワーク、フレックスタイム制など)の内容、対象となる従業員、制度の実施期間、助成金の目標などを具体的に記載します。
- 労働局への届出
- 作成した計画書を、制度導入の1ヶ月前までに労働局に提出します。
- この届出を怠ると、助成金の対象外となるため、最も重要なステップと言えます。
ステップ2|柔軟な働き方制度の運用方法|従業員への周知ポイント
計画書が受理されたら、実際に制度を導入し、従業員に周知します。
- 就業規則等の改定
- 導入する制度の内容を就業規則に明記します。
- 就業規則に記載された内容が、実際の制度運用と合致していることが求められます。
- 制度の運用と周知
- 制度導入後、従業員が実際に利用できる状態にし、全従業員への説明会や社内掲示板などを通じて周知を徹底します。
- 制度を利用する従業員が現れたら、助成金申請のための準備は完了です。
助成金を受給するための運用上の注意点
助成金を受給するためには、制度をただ導入するだけでなく、適切に運用することが不可欠です。以下の3つの点に特に注意しましょう。
1. 就業規則に必ず記載すべき項目|助成金申請の必須条件
制度導入の際は、必ず就業規則に詳細な規定を設けてください。
単に「テレワークを導入する」と定めるだけでなく、以下のような項目を具体的に記載する必要があります。
- 対象者
- 誰が制度を利用できるのか(例:育児・介護を行う従業員、勤続1年以上など)
- 申請手続き
- どのように申請するのか(例:1ヶ月前までに書面で申請)
- 賃金や評価
- 制度利用中の給与計算や人事評価の方法
- 通信費の負担
- テレワーク時の通信費や光熱費の負担区分
就業規則に規定がない、または曖昧な場合、制度が正式なものと認められず、助成金が不支給となる可能性があります。
2. 全従業員への周知徹底方法|制度利用率を高めるポイント
制度が正しく運用されるためには、すべての従業員が制度の存在と内容を理解している必要があります。
- 説明会の開催
- 制度導入時に全従業員を対象とした説明会を開き、質問に答える場を設ける。
- 社内掲示板やイントラネットへの掲載
- いつでも制度内容を確認できるよう、情報を公開する。
- 個別面談
- 制度の利用を検討している従業員に対し、個別に相談に乗る。
周知が不十分だと、「制度があることを知らなかった」という理由で利用者が増えず、助成金の支給要件を満たせない場合があります。
3. 勤務実績の管理方法|助成金支給に必要な記録の整え方
助成金の支給申請時には、制度を利用した従業員の勤務実績を証明する書類が必要です。
- 勤務記録
- テレワークやフレックスタイム制の場合も、出勤簿やタイムカードなどで勤務時間を正確に記録する。
- 日報や業務報告
- 遠隔で働く従業員の業務内容を把握するため、日報や週報などで業務内容を記録する。
これらの記録がなければ、助成金の支給要件を満たしているか確認できず、申請が受理されない可能性があります。
助成金は、これらの留意点を守って制度を「形だけ」でなく「実効性のあるもの」として運用する事業主を支援するものです。
計画から申請まで、一つひとつのステップを丁寧に進めてください。
ステップ3|助成金支給申請の方法|必要書類と提出手順を解説
制度を運用し、実績が伴ったら、いよいよ助成金の支給を申請します。
このステップでは、必要な書類を正確に揃え、期限内に提出することが最も重要です。
支給申請書の様式と主な必要書類
支給申請には、以下の書類が必要です。
- 支給申請書
- 就業規則
- 導入した制度の内容(テレワークやフレックスタイム制など)が明記されている就業規則の写しが必要です。
- 各社で作成したものを、労働基準監督署に届け出た際の受付印付きで提出します。
- 出勤簿・賃金台帳
- 制度を利用した従業員の勤務実績や給与が分かる書類です。
- 普段から会社で使っている様式で問題ありませんが、労働時間や賃金が適切に管理されていることが分かる内容である必要があります。
- 制度の周知状況がわかる書類
- 従業員への説明会の資料、メールの写し、社内掲示板への掲示物の写真など、制度が従業員に周知されたことを証明する書類です。
- その他必要な書類
- 上記のほか、計画の策定と届出時に提出した面談シート(様式第2号)や支援プラン(様式第3号)などの控え・写し等、いくつかの書類を提出する必要があります。
【ポイント】 申請書類は、労働局に提出した「制度導入計画」の内容と一致している必要があります。もし計画から変更が生じた場合は、その理由を明確に説明できるよう準備しておきましょう。
2. 支給申請の期限
支給申請は、制度の導入・運用から一定期間内に行う必要があります。
具体的な期限については、提出した「制度導入計画」の期間終了後、2カ月以内を目安に、管轄の労働局に必ず確認してください。
期限を過ぎてしまうと申請できなくなるため、事前の確認と計画的な準備が不可欠です。
具体例で解説|柔軟な働き方制度助成金の受給フロー(株式会社T事例)
前回の記事ご紹介したWebデザイン制作会社「株式会社T」の事例を、実際に助成金を受給するまでの具体的なフローで見ていきましょう。
株式会社Tは、ウェブサイトのデザインや開発を手掛ける従業員70名の中小企業です。
これまでもテレワークを試験的に導入していましたが、本格的な制度として整備し、助成金を活用することにしました。
1. 新規導入制度の助成金受給フロー|時系列での解説
2026年10月1日
- 助成金受給に向けた検討開始 正式な制度導入と助成金活用を決定。
- 厚生労働省のウェブサイトで要件を確認します。
2026年10月10日
- 制度導入計画書の作成
- テレワーク希望者10名と面談し、勤務内容を確認。
- 面談記録を様式第2号「面談シート」にまとめ、制度の内容を様式第3号「柔軟な働き方支援プラン」に記入します。
- この際、運用期間を「2026年11月1日〜2027年4月30日(6ヶ月間)」と設定します。
2026年10月25日
- 労働局への計画届出
- 様式第2号、第3号を添えて、制度導入の1か月前までに労働局へ提出します。
2026年11月1日
- 制度開始と就業規則改定・届出
- 就業規則にテレワーク規定を明記し、労働基準監督署に届け出ます。
- 同日より、希望者10名がテレワークを開始します。
2027年4月30日
- 制度の運用期間終了
- 設定した運用期間(6ヶ月間)が終了します。
- この期間中、勤務実績を正確に記録・管理します。
2027年5月1日〜2027年6月30日
- 新規導入分の支給申請
- 運用期間終了後、2か月以内に以下の書類を労働局に提出します。
- 支給申請書(様式第1号)
- 就業規則の写し
- テレワーク利用者の出勤簿、賃金台帳
- 計画時に提出した様式第2号、第3号の控え など
- 運用期間終了後、2か月以内に以下の書類を労働局に提出します。
2027年7月
- 新規導入分の助成金受給
- 書類審査後、テレワーク制度の新規導入分として20万円が支給されます。
2. 利用者増加時の柔軟な働き方制度助成金受給フロー
2027年5月1日
- 利用者増加分の記録開始
- 新規導入分の助成金申請と並行して、テレワーク利用者が増えた場合の助成金受給に向け、新たな利用者数の記録を開始します。
- この期間中に、地方在住のデザイナーを2名新規採用し、テレワーク制度を利用しました。
2027年10月31日
- 利用者増加分の運用期間終了
- 利用者増加分についても、最低6ヶ月間の運用期間が必要です。
- この期間(2026年5月1日〜2026年10月31日)が終了します。
2027年11月1日〜2027年12月31日
- 利用者増加分の支給申請 増加期間終了後、2か月以内に以下の書類を労働局に提出します。
- 支給申請書(様式第1号)
- 増加したテレワーク利用者の出勤簿、賃金台帳
- 様式第2号、第3号の控え など
2028年1月
- 利用者増加分の助成金受給 書類審査後、利用者増加分として10万円(5万円×2名分)が支給されます。
まとめ|助成金で柔軟な働き方制度を導入する方法
この記事では、両立支援等助成金「柔軟な働き方選択制度等支援コース」について、その概要から申請フロー、具体的な事例までを詳しく解説しました。
記事の要点再確認|柔軟な働き方選択制度等支援コースの概要
- 中小企業が対象
- 一定の資本金や従業員数などの要件を満たす中小企業が助成金の対象となります。
- 多様な働き方を支援
- テレワーク、フレックスタイム制、短時間勤務制度といった柔軟な働き方の導入を支援する助成金です。
- 支給額
- 1制度の新規導入で20万円、利用者が増えた場合は追加の助成金が支給されます。
- 申請フロー
- 計画の策定・届出から、制度の運用、そして支給申請という3つのステップで進めます。
- 特に、6ヶ月以上の運用期間や、提出書類の様式には注意が必要です。
柔軟な働き方選択制度は、従業員の離職を防ぎ、生産性を向上させるだけでなく、優秀な人材確保にもつながる、企業にとって大きなメリットをもたらす施策です。
助成金を活用すれば、制度導入にかかる金銭的な負担を大幅に軽減できます。
より良い職場環境を築き、企業を成長させるための一歩として、ぜひこの助成金の活用をご検討ください。
申請手続きにご不安がある場合は、社会保険労務士などの専門家への相談も有効です。
専門家の力を借りて、確実に助成金を受給することをお勧めします。
次回予告|育休中等業務代替支援コースの助成金を分かりやすく解説
次回は、両立支援等助成金の別コースである「育休中等業務代替支援コース」に焦点を当てて解説します。
- 育児休業中の従業員の業務を、他の従業員が代替した場合に受けられる助成金とは?
- 代替要員を雇用した場合と、既存の従業員が業務を兼務した場合の支給額の違い
- 申請に必要な要件や具体的な手続き
育児休業中もスムーズに業務を継続し、従業員が安心して復帰できる職場環境を整備するための助成金について、詳しく解説します。
次回の記事は👉育休中等業務代替支援コースとは?助成金額・活用メリットを解説
ぜひご期待ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。
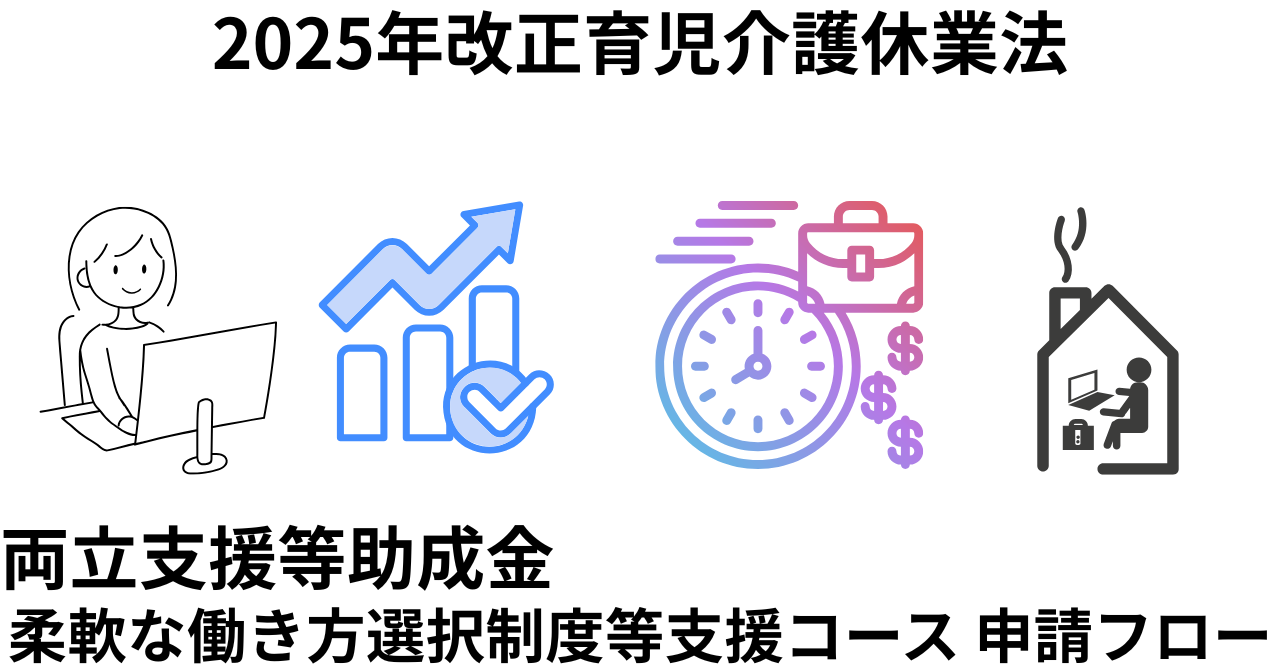

コメント