本記事は「2025年改正育児介護休業法シリーズ」の第39弾です。他のシリーズの記事はコチラから👉2025年育児介護休業法改正|企業がすべき対応と助成金情報
前回は、両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の概要や、育児休業に入る前の準備として、就業規則の整備や事前の面談の重要性について詳しく解説しました。
前回の記事は👉2025年改正対応|育児休業等支援コース助成金の支給対象と支給額
しかし、助成金の受給は、休業前の準備だけで完結するものではありません。
今回は、いよいよ従業員が育児休業に入ってからの企業としての適切な対応と、助成金の中でも特に重要な「育児休業取得時」の申請に焦点を当てて解説します。
育児休業中の従業員へのきめ細やかなサポートが、スムーズな職場復帰だけでなく、助成金受給へのカギとなります。
この記事で分かること
- 育児休業中の「情報提供(社内ニュースの送付等)」は助成金受給の必須要件
- 取得時助成は「3か月以上の休業」が終了した翌日から2ヶ月以内に申請
- 復帰時助成は、原職復帰後に「6か月以上継続雇用」されることが絶対条件
- 面談記録、プラン、賃金台帳、代替要員の証明など、多岐にわたる必要書類の整理術
- 申請から入金までは約3〜4ヶ月。最新要件の確認と専門家活用の重要性
育児休業中の従業員に必要な情報提供のポイント|助成金申請の要件も解説
この育児休業中の従業員は、職場から離れることで不安を感じたり、情報から取り残されることを懸念したりする場合があります。
企業が積極的に情報提供を行うことは、従業員の不安を軽減し、復帰への意欲を高める上で非常に重要です。
これは単に「従業員のため」というだけでなく、両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の支給要件の一つとして、企業が育児休業中の従業員に対し、適切な情報提供等の措置を講じていることが求められているためです。
つまり、この情報提供は、助成金を受給するための必須事項であり、怠ると支給対象外となる可能性がある重要なプロセスなのです。
就業規則に定めた情報提供の措置に基づき、以下の点に留意して実施しましょう。
育児休業中の従業員への具体的な情報提供方法|安心して復帰できる体制づくり
- 会社の状況に関する情報提供
- 人事異動や組織変更、社内制度の変更など、従業員の復帰後の業務や環境に関わる重要な情報は、適宜共有しましょう。
- 業務に関する情報提供
- 本人が希望する場合、担当業務の変更や新しいプロジェクトの立ち上げなど、復帰後に役立つ情報も提供を検討してください。
- 連絡方法と記録の徹底
- 従業員の希望に応じて、メール、オンライン面談、電話など、適切な方法で定期的に連絡を取りましょう。
- 連絡や情報提供を行った際は、日時、内容、相手の反応などを必ず記録に残してください。この記録は、助成金申請時に提出を求められる「必須書類」の一つとなります。
情報提供は、単なる義務ではなく、助成金受給の重要な要件を満たすと共に、育児休業中の従業員との良好な関係を維持し、円滑な職場復帰を促すための積極的なコミュニケーションと捉えましょう。
育児休業取得時の助成金申請フローと必要書類|両立支援等助成金の実務ガイド
従業員が安心して育児休業を取得し、3か月以上継続して休業した場合、企業は「育児休業取得時」の助成金を申請できます。
この助成金は、長期の育児休業取得に伴う企業の負担を軽減するものです。
育児休業等支援コースの助成金申請時期とタイミング|3か月以上の休業後に申請可能
- 従業員が育児休業を連続して3か月以上取得し、その育児休業が終了した日の翌日から2か月以内が原則的な申請期間となります。
- この期間を過ぎると申請できなくなるため、注意が必要です。
育児休業等支援コース助成金の申請窓口|管轄ハローワークで手続き
- 企業の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)が申請窓口となります。
- 事前に管轄のハローワークに問い合わせ、申請に必要な情報や最新の様式を確認しておくことをお勧めします。
育児休業等支援コース|助成金申請に必要な書類一覧と準備ポイント
申請には、以下の書類が一般的に必要となります。
抜け漏れがないように、事前に準備を進めましょう。
支給申請書(様式第1号)
- 厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます。正確に記入してください。
- 具体的な様式は、年度やコースによって変更される場合があります。
- 最新の情報は、以下の厚生労働省ウェブサイト「両立支援等助成金」のページでご確認ください。
- 厚生労働省 両立支援等助成金 案内ページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
- このページ内の「電子申請用の様式」や各コースの案内から、最新の「育児休業等支援コース(育休取得時)」に関する様式([育休取得時]様式第1号)を探してダウンロードしてください。
- [育休取得時]様式第1号~3号※面談シート、プラン含む 👈このように書いているところです。
育児休業申出書
- 従業員が育児休業を取得する際に提出した正式な申出書の控え。
就業規則(育児休業に関する規定部分)および労働基準監督署への届出控え
- 育児休業制度が法的に整備され、適切に届け出られていることを証明する書類。
育児休業中の賃金台帳、出勤簿、雇用保険被保険者証の写しなど
- 対象従業員の雇用状況や休業期間中の賃金・出勤状況を確認するための書類。
母子手帳の写しなど、子の出生日や従業員との関係がわかる書類
- 育児休業の対象となる子の情報と、従業員との親子関係を証明する書類。
育児休業中の情報提供に関する記録(面談記録、メール履歴など)
- 企業が育児休業中の従業員に対し、適切に情報提供を行ったことを示す証拠。前述の記録がここで役立ちます。
生産性要件を満たす場合は、関連する決算書類(損益計算書など)
- 生産性要件による増額を申請する場合に必要となります。事前に要件を満たしているか確認し、準備してください。
代替要員に関する証明書類
- 代替要員を確実に確保したことを証明するため、申請時には関連する書類の提出が必要です。
- 具体的には、代替要員を新たに雇用した場合には雇用契約書や採用通知書、派遣社員で対応した場合には派遣契約書を添付します。
- また、実際に代替要員が勤務していたことを示すために、賃金台帳や出勤簿などの労務管理に関する記録も提出する必要があります。
これらの書類は、助成金の種類や年度によって変更される可能性があるので、必ず最新の情報を厚生労働省のウェブサイトや管轄のハローワークで確認してください。
職場復帰時の手続きと助成金申請ポイント|育児休業等支援コース対応
従業員が休業から無事職場に戻り、その後も継続して活躍できる環境を整えることこそ、企業の真のサポートと言えます。
今回は、従業員が育児休業から職場に復帰する際の具体的な手続きと、その後の継続雇用で支給される「職場復帰時」の助成金申請について、詳しく見ていきましょう。
育児休業後の職場復帰支援|スムーズな復帰の具体的ステップと企業対応ポイント
育児休業を終える従業員がスムーズに職場に適応し、安心して働き続けられるよう、企業は積極的に復帰支援を行う必要があります。
これは単に義務ではなく、助成金受給の重要な要件であり、従業員の定着や生産性向上にも直結します。
以下に、実施すべき具体的な支援策を挙げます。
育児休業終了前の面談と合意形成
- 育児休業が終わる前に、対象従業員と必ず面談を実施しましょう。
- この面談では、復帰後の業務内容、勤務時間、配置、必要なサポート体制(例:短時間勤務、フレックスタイム制度、テレワークの利用など)について詳しく話し合い、従業員の意向も踏まえて合意を形成します。
- 面談の内容は、日時、参加者、話し合った内容、確認事項などを詳細に記録に残してください。
- この記録は、助成金申請時に「復職支援面談記録」として提出が求められる、非常に重要な書類となります。
- 後々の確認や申請に備え、適切に保管しましょう。
両立支援制度の適用と利用実績の管理
- 従業員の希望や状況に応じて、育児・介護休業法で定められた短時間勤務制度や、企業独自のフレックスタイム制度、テレワーク制度などを柔軟に適用しましょう。
- 制度を適用するだけでなく、その制度が実際に利用され、継続していることを確認し、勤務実績(短時間勤務であればその時間、テレワーク実施日など)を記録しておくことが重要です。
- これにより、育児と仕事の両立を実質的にサポートできると共に、助成金申請時に制度の利用実績を証明する書類(出勤簿、勤務記録など)として必要になります。
業務における支援と記録の推奨
- 復帰後の業務が円滑に進むよう、必要な研修機会の提供や、担当業務の変更、丁寧な引継ぎなどを実施しましょう。
- これらの支援についても、面談記録に含めるか、別途記録として残しておくことが強く推奨されます。
- 例えば、受講した研修の記録や、業務変更・引継ぎの内容を記した書類などは、企業が適切に復帰支援を行ったことの客観的な証拠となり、万が一の確認の際に役立ちます。
これらの支援を適切に行うことで、従業員は職場復帰後のギャップを感じにくくなり、モチベーションを維持しながら長く働き続けることができるでしょう。
継続雇用の確認|職場復帰後の助成金支給条件と注意点
「職場復帰時」の助成金は、単に復帰しただけでなく、その後に従業員が企業に定着したことを評価するものです。
- 6か月以上の継続雇用が必須
- 助成金の支給を受けるためには、育児休業から原職等に復帰した従業員が、復帰後も継続して6か月以上雇用されていることが絶対条件です。
- 対象外となるケース
- この6か月の期間中に従業員が退職した場合や、復帰後に雇用形態が大きく変わった場合(例:正社員からアルバイトへ変更など、従業員にとって不利になる変更)は、助成金の対象外となる可能性があります。
- 復帰後の雇用条件や状況には十分注意しましょう。
「職場復帰時」助成金の申請フローと必要書類|育児休業等支援コース対応
従業員の職場復帰支援が適切に行われ、6か月以上の継続雇用が確認できたら、いよいよ「職場復帰時」の助成金を申請できます。
申請時期
- 従業員が育児休業終了後、6か月以上継続して雇用された日の翌日から2か月以内が原則的な申請期間となります。
- 育児休業取得時と同様に、この期間を過ぎると申請できなくなるため、期日を厳守しましょう。
申請窓口
- 企業の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)が申請窓口です。
- 申請前には、最新の情報や様式を必ず確認してください。
主な必要書類
申請には、以下の書類が一般的に必要となります。抜け漏れがないように、事前に準備を進めましょう。
支給申請書(様式第2号)
- 厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできる専用の様式です。正確に記入してください。
- 厚生労働省 両立支援等助成金 案内ページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
- このページ内の「電子申請用の様式」や各コースの案内から、最新の「育児休業等支援コース(職場復帰時)」に関する様式([育休取得時]様式第2号)を探してダウンロードしてください。
- [育休取得時]様式第1号~3号※面談シート、プラン含む 👈このように書いているところです。
職場復帰後の賃金台帳、出勤簿、雇用契約書など
- 従業員が復帰後、6か月間継続して雇用され、適切に賃金が支払われていることを証明する書類です。
復職支援面談記録
- 育児休業終了前に実施した面談の記録。職場復帰支援が適切に行われたことを示す重要な証拠となります。
育児休業取得時で既に提出済みの場合は省略可能な書類あり
- 就業規則など、以前の申請で提出済みの書類は、改めて提出が不要な場合があります。
- 事前にハローワークに確認しましょう。
- 生産性要件を満たす場合は、関連する決算書類(損益計算書など)
- 生産性要件による増額を申請する場合に必要となります。
これらの書類も、助成金の種類や年度によって変更される可能性があるので、必ず最新の情報を厚生労働省のウェブサイトや管轄のハローワークで確認してください。
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)|申請から支給までの期間と確実受給のポイント
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の申請を検討する際、多くの方が気になるのが「いつ頃、いくら支給されるのか」という点でしょう。
支給額については、前回の記事で「育児休業取得時」と「職場復帰時」のそれぞれで中小企業・大企業別の具体的な金額、さらに「情報公表加算」についても詳しく解説済みです。
ここでは、実際に助成金が手元に届くまでの期間と、確実に支給を受けるための注意点について、改めて確認しておきましょう。
申請から支給までの期間の目安とスケジュール
助成金の申請から実際に支給されるまでには、ある程度の期間を要します。
支給決定までの目安
申請書類をハローワークに提出してから、助成金の支給決定通知が届くまでには、通常2〜3ヶ月程度を見ておく必要があります。
この期間中には、提出された書類の細かな審査や内容確認が行われます。
場合によっては、追加書類の提出を求められたり、企業の状況確認のために実地調査が行われたりすることもあります。
申請が集中する時期や、書類に不備が多い場合は、さらに審査に時間がかかる可能性も十分にあります。
実際の入金までの目安
支給決定の通知を受け取ってから、指定された口座に助成金が実際に振り込まれるまでには、おおよそ1ヶ月程度かかります。
これは、支給決定後の内部処理や振込手続きに要する期間です。
合計期間のまとめ
したがって、助成金の申請書を提出してから、実際に助成金が企業に入金されるまでには、合計で約3〜4ヶ月程度を見込んでおくと良いでしょう。
この期間はあくまで目安であり、各ハローワークや労働局の事務処理状況、申請内容の複雑さによって前後する可能性があることを理解しておくことが重要です。
もしお急ぎの場合は、申請時に管轄のハローワーク担当者に具体的な審査期間の目安を確認してみることをお勧めします。
両立支援等助成金の受給を確実にする最終チェックポイント
これまでの記事で両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の主要な支給要件と、特に重要な手続き上のポイントは網羅されています。
しかし、「これで抜かりなく助成金が支給される」と断言することは、残念ながらできません。
助成金申請には、常にいくつかの不確実な要素が伴うためです。
助成金申請に潜む不確実な要素
- 最新の要件変更
- 助成金制度は、法改正や社会情勢の変化に伴い、支給要件や必要な書類が頻繁に更新されることがあります。
- そのため、この記事の作成時点では最新の情報を反映していますが、申請を行う際には、その時点での最新情報を必ず確認する必要があります。
- 個別具体的な状況による影響
- 各企業の就業規則の内容、従業員の雇用形態、育児休業の取得状況、復帰後の勤務状況など、個別具体的な状況によっては、通常の書類以外に追加の確認事項や書類の提出が必要となる場合があります。
- 審査機関の判断
- 提出された書類や記録に基づき、ハローワークや労働局の審査担当者が総合的な判断を行います。
- 万が一、記載内容に不備があったり、要件を満たしていることの証明が不十分であったりすると、残念ながら不支給となる可能性もゼロではありません。
- その他の基本的な要件
- 今回の解説では主要な要件に絞っていますが、例えば事業主が労働保険料を滞納していないか、過去に不正受給がないかといった、基本的な要件も全てクリアしている必要があります。
確実に支給を受けるための2つの最終ステップ
これらの不確実な要素を考慮し、確実に助成金を受給するために最も重要となるのは、以下の2点です。
- 申請前の最新情報確認の徹底
- 助成金は年度ごとに要件が変わることが多いため、申請を行う直前には必ず、厚生労働省の公式ウェブサイト、または管轄のハローワークに直接問い合わせて、最新の「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」の支給要件、様式、提出書類を最終確認してください。
- 専門家(社会保険労務士)への相談
- 助成金申請は、手続きが複雑で専門的な知識を要する場面が多々あります。
- そのため、社会保険労務士に相談することを強くお勧めします。社会保険労務士は、貴社の具体的な状況に合わせて就業規則の確認・修正、必要な書類の準備、申請書の作成・提出代行など、一連のプロセスを専門的な視点からサポートしてくれます。
- これにより、不備による不支給のリスクを大幅に減らし、安心して申請に臨むことができるでしょう。
まとめ|育児休業等支援コースのポイント|助成金活用で人材定着と企業成長を実現
前回と今回の記事では、両立支援等助成金の中でも中心となる「育児休業等支援コース」について、その概要から育児休業開始前の準備、休業中の企業対応、そして「育児休業取得時」および「職場復帰時」の助成金申請、さらに申請から支給までの期間と確実に受給するための最終ポイントまで、詳細に解説しました。
従業員の育児休業取得から職場復帰、そして継続雇用まで一貫して支援することで、企業は助成金を活用しつつ、人材の定着と企業の持続的な成長を実現できます。
助成金の申請手続きは複雑に感じるかもしれません。
しかし、この記事で解説したポイントをしっかりと押さえ、必要に応じて社会保険労務士などの専門家の支援も活用することで、確実に受給を目指すことができます。
次回予告|男性育休を後押しする「出生時両立支援コース」を徹底解説!
さて、次回は、男性の育児休業取得を強力に後押しする「出生時両立支援コース」について、その具体的な内容、支給要件、申請方法までを徹底的に解説します。
次回の記事は👉出生時両立支援コースとは?助成金の種類と第1種の助成金額解説
男性育休の取得促進を目指す企業にとって非常に重要な助成金ですので、ぜひご期待ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。
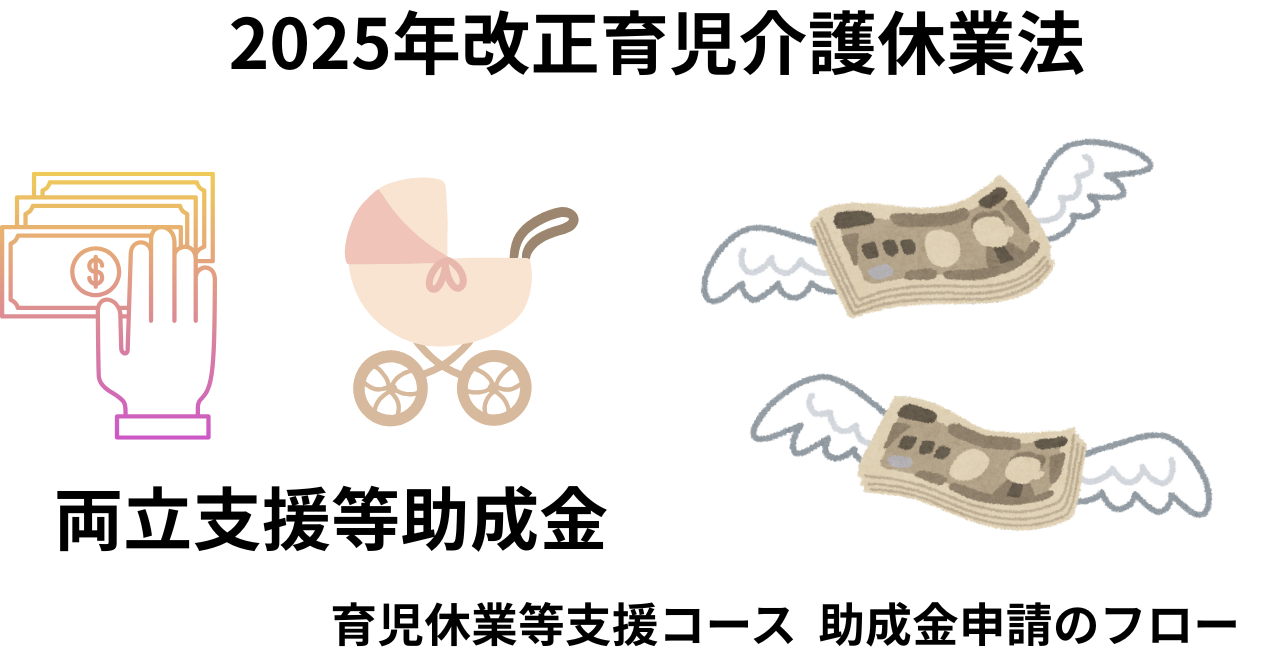

コメント