本記事は「2025年改正育児介護休業法シリーズ」の第38弾です。他のシリーズの記事はコチラから👉2025年育児介護休業法改正|企業がすべき対応と助成金情報
前回の記事では、2025年育児介護休業法改正の全体像と、それに伴う両立支援等助成金の重要性についてお話ししました。
前回の記事は👉2025年育児介護休業法改正と両立支援等助成金|企業の活用戦略
法改正によって企業に求められる対応が増える中、助成金を戦略的に活用することは、企業の負担を軽減し、むしろ競争優位性を確立するための重要な鍵となります。
さて、今回からはいよいよ、各助成金コースについて具体的に掘り下げていきます。
この記事で分かること
- 「育児休業等支援コース」は、取得時と復帰時の2フェーズで最大60万円(中小企業)が受給可能
- 受給には「雇用保険の加入」と「法適合した就業規則の届出」が絶対条件
- 取得時助成の鍵は「連続3か月以上の育休」。産後休業も含めてカウントできる実務的解釈
- 「両立支援のひろば」への情報公表で、1回限り2万円の上乗せ加算が受けられる
- 育休開始「前日」までに完了すべき、面談記録の作成と申出書の受理フロー
育児休業等支援コースの概要と活用法
今回の記事では、多くの企業にとって最も身近な両立支援の課題である「育児休業」に焦点を当てた「育児休業等支援コース」について、その概要と具体的な活用法を解説します。
この助成金に限らず、「両立支援等助成金」は、その名の通り仕事と育児の両立を支援する企業を応援するための制度であり、その根拠となる法律は「雇用保険法」です。
つまり、雇用保険の適用事業主である企業が、ハローワークを通じて申請する公的な支援策となります。
これは、育児休業中の従業員を雇用保険の枠組みの中でサポートし、企業の継続的な成長を後押しすることを目的としています。
この記事では、この「育児休業等支援コース」について、どんな時に、いくらもらえるのか、どのような企業や従業員が対象になるのか、そして申請までの具体的なフローと必要書類まで、分かりやすく徹底解説していきます。
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の助成内容と支給額
仕事と育児の両立は、現代の企業にとって重要な課題です。
従業員が安心してキャリアを継続できるよう支援することは、企業の人材定着や生産性向上にも直結します。
そんな企業を強力に後押しするのが、厚生労働省が提供する「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」です。
この助成金は、従業員の育児休業取得から職場復帰まで、企業が講じる支援策に対して支給されます。
具体的にどのフェーズで、いくらもらえるのか、詳しく見ていきましょう。
育児休業取得時に活用できる助成金内容と支給対象企業
従業員が育児休業を円滑に取得できるよう、企業が代替要員を確保するなどの体制整備を行った場合に支給されるのが「育児休業取得時」の助成金です。
- 支給対象
- 雇用保険に加入している従業員(男女を問いません)が、育児・介護休業法に基づく育児休業を取得し、企業が代替要員を確保した場合に対象となります。(原則として3か月以上の育休取得が要件ですが、子が1歳までの育休であれば3か月未満でも対象となるケースがあります。)
- 支給額
- 中小企業
- 従業員1人につき 30万円
- 大企業
- 従業員1人につき 20万円
- 生産性要件を満たす場合
- 中小企業は36万円に増額
- 大企業は24万円に増額
- 中小企業
この支給は、従業員が長期の育児休業に入ることへの企業の負担を軽減し、育児休業取得をためらうことなく選択できる環境作りを促します。
育児休業からの職場復帰支援|復帰後の定着を促す助成金
育児休業を終えた従業員がスムーズに職場に復帰し、その後も安心して働き続けられるよう支援する企業に対して支給されるのが「職場復帰時」の助成金です。
- 支給対象
- 育児休業を取得した従業員が、休業終了後に原職または原職相当職に復帰し、その後6か月以上継続して雇用された場合に支給されます。
- この「6か月以上継続雇用」が、助成金支給の重要な要件となります。
- 支給額
- 中小企業
- 従業員1人につき 30万円
- 大企業
- 従業員1人につき 20万円
- 生産性要件を満たす場合
- 中小企業は36万円に増額
- 大企業は24万円に増額
- 中小企業
両立等における「中小企業」の区分基準
| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時雇用する労働者数 |
|---|---|---|
| 小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| その他(製造業、建設業、運輸業など上記以外全て) | 3億円以下 | 300人以下 |
補足事項
- 「常時雇用する労働者数」とは、2か月を超えて雇用される者であり、かつ、週当たりの所定労働時間が、その事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等(概ね40時間)である者を指します。パートタイマーやアルバイトであっても、上記の要件を満たせば「常時雇用する労働者」に含められます。
- 資本金がない場合(一般社団法人、NPO法人)は、常時雇用する労働者数のみで判断されます。
- ご自身の会社が上記の「中小企業」の定義に当てはまらない場合、自動的に「大企業」として扱われ、助成金額も大企業向けに設定されたものが適用されます。
- いわゆる「みなし大企業」(中小企業の条件を満たしていても、実質的に大企業の子会社や関連会社である場合)の扱いについては、助成金の種類や詳細な状況によって判断が異なる場合がありますので、具体的な申請時には管轄の労働局や専門家にご確認いただくのが確実です。
情報公表加算とは?育児休業等支援コースでの支給額2万円上乗せ
上記の「育児休業取得時」または「職場復帰時」の支給に加えて、企業が「両立支援のひろば」に育児休業等に関する情報を公表した場合には、2万円が加算されます。
- 加算額
- 1事業主につき 2万円
- 適用回数
- 「育児休業取得時」または「職場復帰時」のいずれか1回限り加算されます。
この加算は、企業の育児休業取得状況や両立支援への取り組みを社会に公表することで、より一層の透明性と企業のイメージアップを図ることを奨励するものです。
両立支援等助成金(生産性要件なし)の最大支給額と加算の仕組み|いくらもらえる?
この助成金では、1人の従業員が育児休業を取得し、その後の職場復帰要件も満たした場合、中小企業であれば最大で合計60万円(取得時30万円+復帰時30万円)が支給されます。
大企業の場合は合計40万円となります。
「両立支援のひろば」への情報公表加算2万円は、従業員の人数に関わらず、事業主(企業)に対して1回限り支給されるものです。
したがって、例えば複数の従業員が育児休業を取得し、それぞれに最大60万円(中小企業の場合)が支給されたとしても、情報公表加算は企業全体で一度だけ、最大で2万円の加算となります。
各従業員に対して62万円が支給されるわけではありません。
企業としては、最大で「60万円(1人あたり)×対象従業員数」に、「情報公表加算2万円」が別途1回のみ加わる形になると理解しておくと良いでしょう。
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)は、従業員のワークライフバランスを重視し、多様な働き方を推進する企業にとって、非常に有効な支援策です。
これらの助成金を活用することで、従業員の定着率向上や企業イメージアップにも繋がり、持続可能な組織づくりに貢献できるでしょう。
「生産性要件を満たす場合〇〇円」と触れましたが、この生産性要件とは、企業全体の生産性が向上している場合に、助成金の支給額が割り増しされる仕組みです。
具体的には、助成金の申請を行う会計年度の直近3年間で、「労働者の付加価値」が6%以上伸びていることが主な要件となります。
「労働者の付加価値」の具体的な計算方法
「労働者の付加価値」は、以下のいずれかの方法で計算されます。
- 最も一般的な計算式(簡便法)
- 付加価値 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費 + 動産・不動産賃借料 + 租税公課
- もう一つの計算式
- 付加価値 = 売上高 - (売上原価 + 販売費・一般管理費 - 人件費 - 減価償却費 - 動産・不動産賃借料 - 租税公課)
これらの費用項目は、原則として会社の決算書(損益計算書など)の数値を使用します。
一般的な会計の「限界利益」や「粗利益」とは異なる、助成金制度独自の概念である点にご注意ください。
いつの期間の生産性を比較するの?
生産性の向上を判断するためには、過去と現在の「労働者の付加価値」を比較します。
- 比較対象期間
- 助成金の支給申請を行う会計年度の直近3年間を使用します。
- たとえば、会社の会計年度が4月1日~3月31日で、令和7年7月に助成金を申請する場合、比較対象となるのは令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)と令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)の付加価値です。
- 比較基準
- 基準期間
- 直近3年間の中で最も古い会計年度(最初の1年間)の「労働者の付加価値」
- 先ほどの例では令和4年度
- 比較期間
- 直近3年間の中で最も新しい会計年度(最後の1年間)の「労働者の付加価値」
- 先ほどの例では令和6年度
- 基準期間
- OKとなる基準
- [比較期間(令和6年度)の付加価値 - 基準期間(令和4年度)の付加価値] ÷ 基準期間(令和4年度)の付加価値 この計算結果が 6%以上 であれば、生産性要件を満たしたと判断されます。
なぜ生産性が上がると助成金が増額されるのか?
この点に疑問を持つ読者も多いでしょう。
「育児休業を取得したから生産性が上がった」と断言できるほど、単純な話ではありません。
育休期間中にたまたま別の要因で業績が伸び、生産性が上がったというケースもいくらでも考えられます。
しかし、助成金制度には、以下のような考え方があります。
企業の成長を後押しするため
- 助成金は単に制度を導入したから支給されるだけでなく、企業が実際に生産性を向上させるような経営努力をしている場合に、より多くの支援をすることで、企業の持続的な成長を促す目的があります。
財源(雇用保険)の有効活用
- 国民から集められた雇用保険料を財源とする以上、その活用は効果的であるべきです。
- 生産性が向上している企業に厚く助成金を出すことで、その投資がより大きな経済効果や社会的なリターン(例:雇用安定、人材育成)に繋がると考えられています。
「働きやすさ」と「生産性」の好循環を期待
- 「従業員を大切にし、働きやすい環境を整える経営努力をしている企業は、他の面でも生産性を上げるための工夫をしている可能性が高い」という、間接的な相関関係に着目しています。
- つまり、両立支援の取り組み自体が、従業員のモチベーション向上や優秀な人材の定着、業務の効率化など、長期的に企業の潜在的な生産性向上に寄与する「投資」と捉えられているのです。
簡単に言えば、生産性要件は、「助成金を出すに値する、成長意欲のある健全な企業であるか」を測るための、一つの指標として使われています。
これにより、助成金がより効果的に、そして適切に活用されることを目指しているのです。
この生産性要件を満たしているかどうかの確認や、詳細な計算方法、必要書類については、厚生労働省のパンフレットや、社会保険労務士などの専門家にご確認いただくことを強くお勧めします。
助成金申請の第一歩|対象となる企業と従業員の確認ポイント
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)は、すべての企業や従業員が対象となるわけではありません。
この助成金を活用するためには、厚生労働省が定める特定の要件を満たす必要があります。
ここでは、どのような企業や従業員が対象となるのか、その詳細を明確に解説します。
対象企業の条件|両立支援等助成金を受けられる会社
この助成金は、以下の条件を全て満たす事業主が対象となります。
雇用保険の適用事業主であること
- まず大前提として、雇用保険の適用事業主であることが必須です。
- 従業員を雇用し、雇用保険に加入させている企業が対象となります。
育児・介護休業法に適合した育児休業制度を規定していること
- 労働者が育児休業を取得できるよう、育児・介護休業法に基づいた育児休業制度を就業規則などに適切に定めている必要があります。
- この規定は、労働基準監督署に届け出て受理されている必要があります。
- 単に制度があるだけでなく、法律の要件を満たし、社内で周知されていることが重要です。
その他の支給要件を全て満たすこと
- 上記の基本的な要件に加え、助成金の各支給フェーズ(育児休業取得時、職場復帰時など)に定められた詳細な要件も満たす必要があります。
- これには、育児休業中の情報提供や、職場復帰支援の実施などが含まれます。
- 過去に育児休業等に関する法違反がないこと
- 申請を検討する際は、厚生労働省の最新のパンフレットや管轄の労働局に確認し、不明な点は社会保険労務士などの専門家へ相談することをおすすめします。
助成金の対象従業員とは|両立支援等助成金を受給できる社員の条件
助成金の支給対象となる従業員は、以下の条件を全て満たしている必要があります。
- 育児休業開始日に雇用保険の被保険者であること
- 育児休業を開始した日時点で、その従業員が雇用保険の被保険者であることが必須です。
- パートタイマーや契約社員など、雇用形態に関わらず雇用保険に加入していれば対象となり得ます。
- 2025年改正育児・介護休業法に基づく育児休業を取得していること
- 取得する休業が、育児・介護休業法に則った正式な育児休業である必要があります。
- 育児・介護休業法に規定されていない任意の休暇制度は対象外です。
- 育児休業取得時支給には、連続して3か月以上の育児休業取得が必須
- 特に「育児休業取得時」の助成金を受け取るためには、対象となる従業員が連続して3か月以上の育児休業を取得していることが絶対条件です。
- この期間には、産後休業(出産後の8週間)を含むことも可能です。
- 3か月未満の育児休業の場合、この支給区分は対象外となりますので注意が必要です。
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)は、これらの要件を満たす企業が、従業員の仕事と育児の両立を積極的に支援するための強力なツールです。
自社がこれらの条件に当てはまるかを確認し、ぜひ助成金の活用を検討してみてください。
育児休業前の準備と助成金申請手続き|必須事項をチェック
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の受給を目指す上で、最も重要と言えるのが、従業員が育児休業を開始する「前日」までに、企業が適切な準備を完了していることです。
この初期段階での対応が、その後のスムーズな申請手続きと助成金受給の成否を分けます。
ここでは、育児休業開始日前日までに、企業が必ず実施すべき事項を詳しく解説します。
1. 助成金申請に必要な就業規則の整備と届出の手順
両立支援等助成金は、法律に基づいた企業の制度整備を評価するものです。
育児休業に関する社内制度が法的に適切に整備され、従業員に周知されていることが、助成金支給の絶対条件となります。
育児・介護休業法に準拠した規定の明確化
- 貴社の就業規則に、育児・介護休業法に則った育児休業に関する規定が明確に盛り込まれているかを確認してください。
- 単に「育児休業が取れる」だけでなく、取得可能な期間、申出の手順と期限、育児休業中の待遇(給与・社会保険の扱いなど)、職場復帰に関する規定、そして育児休業中の情報提供等の措置に関する定めまで、具体的に記載されている必要があります。
労働基準監督署への届出と受理
- 整備・改定した就業規則は、必ず所轄の労働基準監督署に届け出て、受理されている必要があります。
- 届出の控えや受理印のある就業規則の写しは、助成金申請時に提出を求められますので大切に保管してください。
従業員への周知徹底
- 就業規則に規定した内容は、全従業員がいつでも閲覧できる状態にするなど、適切に周知されている必要があります。
- 従業員が制度を理解し、安心して利用できる環境を整えることが求められます。
両立支援等助成金の要件を満たすための「育児休業等に関する就業規則」のドラフトを作成します。
これはあくまで一般的なドラフトであり、貴社の具体的な状況や最新の法令、労働慣行に合わせて、必ず社会保険労務士などの専門家にご確認・修正いただく必要があります。
育児休業等に関する就業規則(ドラフト)
目的
第〇条 この規則は、育児介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)に基づき、育児を行う労働者が職業生活と家庭生活との両立を図ることができるよう、育児休業、育児のための所定労働時間の短縮等の措置、子の看護休暇等の制度について定めるものとする。
育児休業の対象者
第〇条 育児休業は、子が1歳に達する日までの間(以下「育児休業期間」という。)において、労働者が申し出ることにより取得することができる。ただし、以下のいずれかに該当する労働者は対象としない。
- 入社1年未満の労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
- 子の1歳到達日を超えて雇用が継続しないことが明らかな労働者
- 前項にかかわらず、労働者は、子が1歳に達した日後も、一定の要件を満たす場合に限り、子が1歳6か月に達する日まで、または子が2歳に達する日まで、育児休業を延長することができる。
- 配偶者が育児休業を取得している場合、労働者は、子が1歳2か月に達する日までの間、育児休業を取得することができる(パパ・ママ育休プラス)。
育児休業の申出
第〇条 育児休業の申出は、育児休業開始予定日の1か月前までに、会社所定の育児休業申出書を人事担当部署に提出することにより行うものとする。
2.前項の規定にかかわらず、子の出生後8週間以内に開始する育児休業(出生時育児休業)の申出は、原則として休業開始予定日の2週間前までに行うものとする。
育児休業期間中の待遇
第〇条 育児休業期間中、労働者に対して賃金は支給しない。
2.育児休業期間中も、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の被保険者資格は継続し、所定の手続きにより保険料が免除される。雇用保険料は免除されない。
3.育児休業期間中の賞与、昇給、退職金の算定については、別途定めるものとする。
出生時育児休業
第○条 労働者は、配偶者の出産後8週間以内において、4週間までの範囲内で分割して2回まで出生時育児休業を取得できる。申出は原則として休業開始予定日の2週間前までに行うものとする。
育児休業中の連絡及び情報提供
第〇条 会社は、育児休業中の労働者に対し、本人の希望に応じて、会社の制度変更、人事に関する情報、業務に関する資料等を提供するものとする。
2.育児休業中の労働者は、会社からの連絡に対し、速やかに対応するよう努めるものとする。
職場復帰
第〇条 育児休業期間が終了した労働者は、原則として休業開始前の原職または原職に準ずる職務に復帰させるものとする。
2.会社は、育児休業終了予定日の1か月前までに、育児休業中の労働者と面談を実施し、復職後の業務内容、勤務時間、配置、必要なサポート体制等について確認し、その結果を記録するものとする。面談の記録は、所定の様式(復職支援面談シート)により作成し、当該労働者の人事記録とともに3年間保存するものとする。
3.労働者は、育児休業期間の終了後、速やかに職場に復帰するものとする。ただし、やむを得ない事情により復帰が困難な場合は、事前に会社と協議するものとする。
育児のための所定労働時間の短縮等の措置
第〇条 会社は、3歳に満たない子を養育する労働者が申し出た場合、所定労働時間を短縮する措置(1日の労働時間を原則として6時間とする)を講じるものとする。
2.前項の措置のほか、会社は、育児を行う労働者が利用できる以下の措置を講じるものとする。
- フレックスタイム制度
- 始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ
- 育児のためのテレワーク
3.会社は、3歳に満たない子を養育する従業員がテレワークによる勤務を希望した場合、可能な範囲で制度を整備し、対応に努める。
4.これらの措置の利用を希望する労働者は、所定の手続きに従い、会社に申し出るものとする。
子の看護休暇
第〇条 会社は、小学校第3学年の終期に達するまでの子を養育する労働者が申し出た場合、1年に5日(子が2人以上の場合は10日)を上限として、子の看護休暇を与えるものとする
2.子の看護休暇は、1日単位または時間単位で取得することができる。
3.子の看護休暇は、原則として無給とする。
ハラスメントの防止
第〇条 会社は、育児休業等の制度利用に関するハラスメント(妊娠、出産、育児休業等の取得等を理由とした不利益な取り扱い、嫌がらせ等)を防止するため、必要な措置を講じるものとする。
2.会社は、ハラスメント防止のために以下の措置を講じる。
- 就業規則等に禁止規定を定める
- 相談窓口を設置し、秘密保持・迅速対応を確保する
- 管理職を対象とした定期研修を実施する
- 再発防止に向けた措置を適切に行う
その他
第〇条 この規則に定めのない事項については、育児介護休業法その他の法令、労働協約、就業規則本則、その他会社の諸規定によるものとする。
重要事項
- このドラフトは一般的な内容であり、貴社の事業内容、従業員規模、既存の就業規則、労働協約等に合わせて詳細な修正が必須です。
- 必ず社会保険労務士などの専門家にご相談の上、最終的な就業規則を作成・届出してください。
- 最新の法令改正(特に2025年育児介護休業法改正)に完全に対応しているか、専門家による確認が不可欠です。
- 作成した就業規則は、労働基準監督署への届出が必要です。
- 従業員への周知徹底(いつでも閲覧できる状態にする、説明会開催など)も忘れずに行ってください。
2. 育児休業の申出受付と事前計画のポイント|スムーズな休業取得のために
従業員からの正式な申出を受け付けることは、育児休業が法的に成立した証拠となります。
また、事前の計画と合意形成は、休業中のトラブルを防ぎ、スムーズな職場復帰に繋がります。
育児休業申出書の適切な受理と保管
- 従業員から育児休業の申出があった際には、必ず所定の様式(会社で用意したもの、または任意様式)の「育児休業申出書」を提出させ、これを適切に受理し、保管してください。
- この申出書は、助成金申請の重要な証拠書類となります。
従業員との面談を通じた計画と合意形成
- 育児休業に入る従業員と、事前に面談を実施し、以下の点について具体的に話し合い、合意内容を明確にしておくことが推奨されます。
- 育児休業の具体的な期間(開始日と終了予定日)
- 休業中の連絡方法と頻度(例:月に1回メールで連絡、緊急時のみ電話など)
- 職場に関する情報提供の要否(例:人事異動、組織変更、社内制度の変更などの情報を休業中に共有するかどうか)
- 職場復帰に関する意向(例:短時間勤務の希望の有無、復帰後の業務内容に関する希望など)
- これらの話し合いの内容は、面談記録として残しておくことが望ましいです。
- 書式は任意で構いませんが、日時、参加者、話し合った内容、確認者などを記載しておくと、後の申請時に役立ちます。
これらの「育児休業開始日前日までの必須事項」を確実に実行することが、両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の支給要件を満たすための第一歩となります。
制度の趣旨を理解し、従業員が安心して育児休業を取得できる環境を整備していきましょう。
まとめ|育児休業開始前の準備を押さえて、助成金取得への第一歩を踏み出そう
これらの「育児休業開始日前日までの必須事項」を確実に実行することが、両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の支給要件を満たすための第一歩となります。
制度の趣旨を理解し、従業員が安心して育児休業を取得できる環境を整備していきましょう。
今回は、両立支援等助成金の中でも中心となる「育児休業等支援コース」の概要と、育児休業開始前日までに企業が準備すべき重要なポイントに焦点を当てて解説しました。
特に、就業規則の整備や従業員との事前のコミュニケーションがいかに大切かをご理解いただけたかと思います。
次回予告|育児休業中・復帰時の助成金申請と実務対応
いよいよ「育児休業中の企業対応と、育児休業取得時の助成金申請」、そして「職場復帰時の手続きと助成金申請」について、さらに深掘りしていきます。
次回の記事は👉育児休業等支援コース|助成金申請フローと必要書類|徹底解説
育児休業中の従業員への具体的な情報提供方法や、復帰後のフォローアップ、そしてそれぞれの助成金申請に必要な書類とフローを詳細にご紹介しますので、ぜひご期待ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。
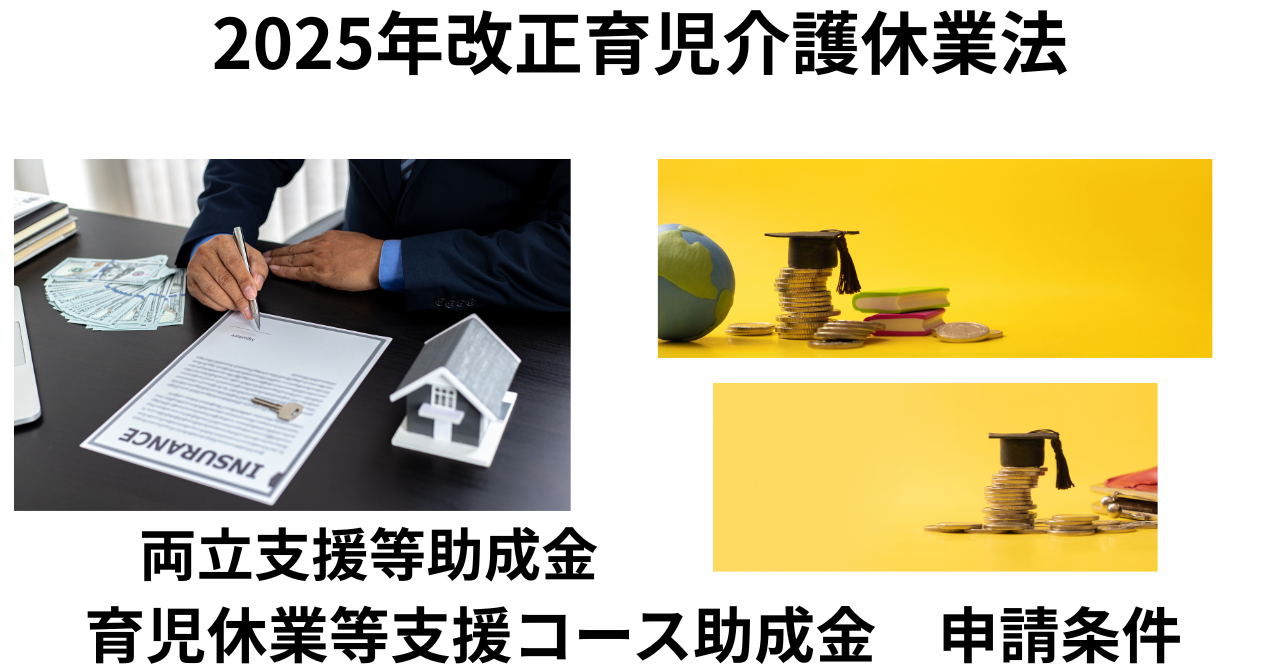

コメント