これまでの連載では、2025年4月施行の育児・介護休業法改正のポイントを、「①男性の育児休業取得促進」「②介護離職の防止」「③仕事と家庭の両立支援」といった観点から、7回にわたって解説してきました。
今回は、改正の4つ目の柱である
「企業の対応格差を是正し、育児・介護支援を当たり前に」
というテーマについて、より掘り下げていきます。
この項目は、他のテーマと比べて抽象的に聞こえるかもしれませんが、実は本改正の核心にあるともいえる重要な視点です。なぜ、いま「企業間の格差の是正」が求められるのか?――その背景には、少子高齢化・働き方改革・地域経済といった多層的な課題が横たわっています。
なぜ「企業間の格差是正」が必要なのか?
2025年の改正で政府が明確に打ち出したのが、「制度を持っているだけでは不十分」という視点です。
たとえば、法律で定められた育児・介護の支援制度は、多くの企業がすでに導入済みです。しかし、「それを実際に使える環境かどうか」は、企業ごとに大きな差があります。
この「制度の使いやすさの格差」が、社会問題になりつつあるのです。
制度が「ある」ことと「使える」ことのギャップ
法律上の制度が存在していても、それが実際に職場で活用されていなければ、現実的な意味はありません。たとえば、「育児休業制度」は法的にすべての労働者が利用できる権利ですが、企業によっては、
- 管理職に制度への理解がなく、利用希望者が萎縮してしまう
- そもそも育休や介護休暇の制度内容が社内で周知されていない
- 業務が属人化しており、誰かが抜けると仕事が回らない
といった理由で、事実上、使えない状態にあることも少なくありません。
これは、「制度の形骸化」と呼ばれる状態です。形はあっても、実質的に使えなければ、機能していないのと同じです。この「制度と運用のギャップ」こそが、企業間格差の本質なのです。
働く人の「人生の選択肢」が企業に左右される不平等
さらに深刻なのが、「企業規模による格差」です。大企業は人材も多く、業務も分業化されているため、誰かが休んでも代替が効きやすい。一方で中小企業は、一人の離脱が事業継続に直結することもあり、「育休は歓迎したいが、実際は難しい」といったジレンマを抱えている経営者も少なくありません。
加えて、社労士などの専門家や外部支援制度(助成金や社内研修)にアクセスしやすいかどうかも、企業規模によって異なります。この結果、同じ「育児・介護支援制度」があっても、企業間で「使える現実度」が大きく変わってしまうのです。
A社では育児休業が当たり前に取れるのに、B社では取得希望すら言い出せない――同じように働いているのに、こうした差が生まれてしまう現状は、本人の能力や努力では埋められない「構造的な格差」です。
これは、雇用の世界における「機会の不平等」であり、特に非正規雇用や中小企業に勤める労働者にとっては深刻です。
制度が活用できるか否かが、「育児か仕事か」という二者択一の人生を強いることにもつながる
だからこそ、企業間の格差をなくすことは、働く人すべてに「選べる未来」を保障するために不可欠なのです。
人手不足時代における「人材の偏在リスク」
労働力人口の減少が進む日本では、限られた人材をどう有効に活かすかが喫緊の課題です。
しかし現状では、育児・介護支援が整っている一部の大企業に人材が集中し、制度が未整備の中小企業では人材確保が難しくなっています。
- 働きやすさ=大企業
- 働きにくさ=中小企業
というイメージが定着してしまうと、地域経済を支える中小企業が人材流出に苦しみ、「人材の偏在」という構造的な問題が加速してしまいます。
実際、育児・介護を理由とした退職や就業断念は、中小企業で多く発生しており、企業体力の違いがそのまま「人材確保の格差」につながっている現状があります。
「どの企業でも働きながら家族を支えられる」という環境がなければ、社会全体の労働力活用は限界に達する
そのため、企業規模に関わらず一定レベルの支援体制を整えることは、社会全体で人材を循環させる土台作りともいえるのです。
地域経済・地方創生との関係
格差の問題は、企業規模だけでなく、都市部と地方の違いにも現れています。
地方企業では、人的資源・情報・専門家ネットワークが限られており、支援制度の導入・活用が進みにくい現実があります。これが「地方では育児や介護と両立しながら働けない」という状況を生み、若年層の都市部流出を加速させているのです。
つまり、育児・介護支援の企業間格差は、地方創生の阻害要因でもあるのです。
企業ごとの差を縮め、全国どこでも一定の安心感を持って働ける社会にすることは、都市への人口集中を抑制し、地域の持続可能性を守るうえでも極めて重要です。
2025年改正で進む「格差の見える化と底上げ」
こうした課題意識を背景に、これまでの投稿の中でも取り上げたとおり、2025年の法改正では企業間格差の是正に向けた具体的な制度改革が進められています。
育児休業取得状況の「公表義務」の対象拡大
これまでは「常時1000人超の企業」のみに課されていた育児休業の取得状況の公表義務が、2026年4月からは301人以上(300人超)の企業にも拡大されます。
取得率や取得人数といったデータが「見える化」されることで、企業の取り組み姿勢が外部から比較可能となり、社会的プレッシャーが「対応の底上げ」を促す効果が期待されています。
個別周知と意向確認の徹底
育児・介護に関する制度については、個別周知と意向確認が義務化され、「すべての労働者が制度を知ったうえで選択できる」「制度を知らないまま機会を逃す人を減らす」ような体制が求められるようになります。
これは特に、中小企業や非正規雇用の多い職場でこそ効果がある施策です。「知らなかった」「誰に聞けばいいかわからなかった」――そんな「制度の死蔵」を防ぐための一歩です。
育児・介護支援の「当たり前化」こそが、企業の持続可能性に直結する
働きやすさが「企業ごとの特色」だった時代は、終わりを迎えようとしています。
企業が育児・介護支援を整えることは、「福利厚生」の範囲を超えた、「企業価値」そのものの一部になりつつあります。
- 採用力を高めたい
- 離職率を下げたい
- 社員の定着とスキル蓄積を図りたい
そうした企業課題の多くが、育児・介護と両立できる環境づくりと密接に結びついているのです。
格差の是正は「義務」ではなく「チャンス」
今回の法改正が目指しているのは、単にルールを強化することではありません。
「どんな会社で働いていても、育児・介護と両立しながら活躍できる」
そんな未来を実現するための、「ボトムアップ型の仕組みづくり」なのです。
中小企業や地方企業が、今こそ制度を見直し、使いやすくする工夫を取り入れることで、むしろ「人が集まる魅力ある職場」へと変わっていくことも可能です。
育児・介護支援は、もはや「オプション」ではなく、「共通基盤」の時代へ。
この流れをいかにチャンスに変えていくか――そこに、企業と働く人の未来がかかっています。
これまで8回にわたって、2025年の育児・介護休業法の改正点についてお届けしてきましたが、ひとまず今回で法改正の解説は一区切りです。
次回からは、総務や人事の現場で「実際にどう対応していくか?」にフォーカスしてお伝えしていきます。より実務に即した内容になりますので、ぜひご期待ください!


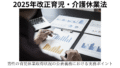
コメント