「育児は母親がするもの」という考え方は、もはや過去のものになりつつあります。育児休業法が施行されてから30年以上が経過しています。その後何度かの改正が行われてきました。しかしながら、現実には男性の育児休業取得率はまだ十分とは言えません。多くの家庭では育児の負担が女性(母親)に偏るケースが少なくありません。
政府の男性の育児休業取得率の目標は、2025年までに50%です。さらに2030年までには85%を目指しています。そのような中で、2025年4月から改正育児・介護休業法が施行されます。男性が育児休業を取りやすい環境づくりがさらに進められます。今回の2025年改正育児・介護休業法は、これまでの方針を大きく転換するものではありません。既存の施策をさらに強化し、男性の育児休業取得を一層促進することを大きな目的の一つとしています。
本記事では、改正のポイントを押さえながら、男性の育児休業取得率を向上させるための施策について考えていきます。
2025年の改正育児・介護休業法では、男性の育児休業取得率をさらに向上させるために、以下のような施策が盛り込まれています。
- 育児休業取得状況の公表義務の拡大
- 3歳未満の子を養育する労働者へのテレワーク選択肢の提供(事業主の努力義務)
- 育児休業制度の周知・意向確認の強化
- 柔軟な育児休業取得の促進
今後、数回にわたり上記の施策に関して解説していきます。
今回は「育児休業取得状況の公表義務の拡大」について見ていきましょう。
これまでの制度
2023年4月から、従業員数1000人超の企業に対して、男性の育児休業取得率などの公表が義務化されていました。
この制度は、企業の育児休業取得状況を「見える化」し、男性の育児休業取得を促進することを目的としています。
改正後の変更点
2025年4月の法改正により、公表義務の対象が「従業員数300人超の企業」に拡大されます。
公表すべき内容
- 男性の育児休業等の取得割合:公表前事業年度中(要するに昨年度)に、男性労働者が育児休業等を取得した割合
- 男性の育児休業等および育児目的休暇の取得割合:公表前事業年度中(昨年度のこと)に、男性労働者が育児休業等または育児目的の休暇制度を利用した割合
公表方法
- 企業は、自社のウェブサイトや求人情報などを活用し、公表する必要があります。
- 具体的には、厚生労働省が示す形式に従い、誰でも閲覧できる形で公開することが求められます。
企業にとってのメリットと課題
メリット
- 企業の社会的評価向上:育児休業取得率を公表することで、企業が社会的責任を果たしている姿勢を示せます。特に、男女平等やワークライフバランスを重視する姿勢が評価され、従業員や求職者からの信頼を得やすくなります。さらに、企業が育児休業取得を積極的に推進していると見なされれば、企業イメージの向上やブランド価値の強化にもつながります。
- 透明性の向上と公平性の確保:育児休業取得状況の公開は、企業内での育児休業取得に対する透明性を確保することにつながります。これにより、特に女性社員が育児休業を取得しやすい環境を作るだけでなく、男性社員の育児休業取得を促進するきっかけにもなります。公表により、企業内で育児休業を取得することが一般的かつ推奨される行動として認識されるようになり、育児に対する企業の支援姿勢が明確に示されます。
- 法的・社会的責任の履行:法的義務として育児休業取得率を公表することで、企業は法律を遵守していることが示されます。また、社会的責任を果たすという意識のもとで、企業は持続可能な働き方改革を進めやすくなります。公表義務の実施は、企業が政府の育児支援政策に協力していることを示し、社会的に認められる存在となります。
- データ分析による改善点の明確化:取得率を公表することにより、どの層の従業員が育児休業を取得しやすいか、取得しにくいかというデータを収集でき、企業はその結果をもとに育児休業取得に対するアプローチを改善できます。例えば、男性社員の取得率が低ければ、男性の育児休業取得を支援する施策を強化することが可能となります。
課題
- 取得率が低い企業へのプレッシャー:企業の中には、育児休業取得率が低い場合もあります。こうした企業が取得率を公表することで、自社のイメージや社会的信用に悪影響を及ぼす可能性があります。特に、企業文化が依然として「長時間労働」や「育児休業を取得しづらい環境」の場合、取得率が低いことが企業の評判にマイナスの影響を与える可能性があります。取得率が低いことが外部から指摘されることによるプレッシャーが企業側にとって負担となり、短期的には経営面でのストレスを生じることがあります。
- 不正確なデータによる問題:企業が育児休業取得率を公表する際、データの正確性や信頼性が重要です。不正確なデータや誤解を招くような情報が公表されると、企業に対する信頼が損なわれ、逆効果となる可能性があります。また、企業が育児休業取得を「義務感」で推進し、実際には取得が奨励されない状況を作り出してしまうと、形式的な取得率の向上にとどまり、実際の育児支援が不十分になってしまう恐れがあります。
- 人員配置や業務の調整に関する課題:育児休業の取得が促進されると、一時的に人員が不足する可能性があります。特に、業務がピークの時期やプロジェクトの最中に育児休業を取得する場合、業務の引き継ぎやカバー体制の調整が必要となります。企業は、育児休業取得後の職場復帰や、代替要員の確保に関する計画を立て、スムーズに業務を回すための準備が必要です。このような調整が十分でないと、業務の効率や生産性に悪影響を及ぼす可能性もあります。
- 職場での差別や偏見の問題:育児休業を取得する従業員に対して、職場での偏見や差別が発生することが懸念されます。特に、男性の育児休業取得が少ない場合、男性社員が育児休業を取得したことで、キャリアに悪影響を与えるのではないかという懸念や、昇進の機会が減少するといった問題が生じる可能性があります。のような偏見や差別を防ぐためには、企業の文化改革や、上司や同僚の理解とサポートが欠かせません。
育児休業取得率の公表義務には、企業の社会的評価向上や透明性の確保、育児支援への取り組みが進むという大きなメリットがあります。一方で、取得率が低い企業へのプレッシャーやデータ管理の難しさ、職場での差別や偏見の問題といった課題も存在します。
企業がこれらの課題に対処するためには、データの正確な収集と公正な公表、職場の意識改革、業務管理の効率化が必要です。企業は育児支援を促進するだけでなく、育児休業取得が自然に行える職場環境を整えることが求められます。
こうした負担を軽減し、法令遵守を確実にするためには、社会保険労務士などの専門家に相談することが非常に効果的です。社会保険労務士は、育児休業に関する最新の法令を熟知しており、企業が法的な問題に直面する前にアドバイスを提供することができます。さらに、手続きの代行や、従業員との円滑なコミュニケーションをサポートすることも可能です。
専門家のサポートを受けることで、企業は法的リスクを回避し、社員にとっても安心できる環境を整えることができます。その結果、育児休業に関するトラブルを未然に防ぎ、企業内の労働環境をより良いものにすることができます。
育児休業取得率の公表義務の拡大は、単なる数字の開示にとどまらず、企業の姿勢や職場環境の質を問われる施策でもあります。男性も育児に積極的に関われる社会の実現には、制度の整備だけでなく、それを活かせる「職場の文化」や「風土づくり」が欠かせません。
そのためにも、社内の仕組みを見直し、必要に応じて専門家のサポートを活用しながら、持続可能な育児支援体制を構築していくことが求められています。
さて、次回は、2025年改正で新たに努力義務として位置づけられた「3歳未満の子を養育する労働者へのテレワーク選択肢の提供」について取り上げます。
テレワークが果たす役割と、それがなぜ男性の育児参画を後押しすることにつながるのか、実務的な観点から掘り下げて解説していきます。お楽しみに!

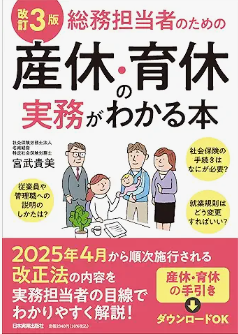
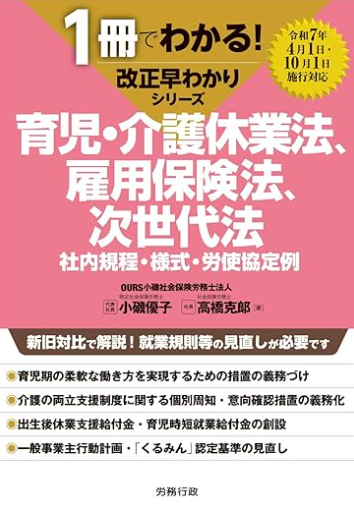


コメント