本記事は「やさしく学ぶ年休シリーズ」シリーズの第9話です。
前回は、退職時の有給休暇の消化方法や、買取りの可否について解説しました。
前回の記事は👉退職する時に有給休暇は全部使える?法律と円満退社のポイント【やさしく学ぶ年休シリーズ 第8回】
退職日を後ろ倒しにすることで、未消化の有給を使い切るという現実的な解決策がある、というお話でしたね。
さて、今回はいよいよシリーズ最終回。
多くの人が見過ごしがちな「有給休暇の時効」について、詳しく見ていきましょう。
有給休暇はいつ消える?時効の基本ルールをわかりやすく解説
皆さんの有給休暇、いつの間にか減っていたり、消えていたりした経験はありませんか?
- 「いつの間にか有給が消えていた…」
- 「2年で消滅するって本当?」
- 「せっかくもらった有給を無駄にしたくないけど、どうすればいいの?」
こうした疑問を抱えている方は少なくありません。
この記事では、あなたの貴重な有給休暇が消えてしまわないよう、時効の仕組みと具体的な対策について解説していきます。
有給休暇は2年で時効?法律で定められた基本ルールを解説
まず、有給休暇の時効について、最も大切なルールをお伝えします。
労働基準法第115条によって、有給休暇の権利は付与された日から2年間で時効によって消滅することが定められています。
これは、入社日や基準日(会社によって異なる、年1回の付与日)から2年が経過すると、その年に付与された有給休暇は、残っていても使えなくなる、ということです。
たとえば、2023年4月1日に付与された有給休暇は、2025年3月31日をもって時効消滅します。
このルールを理解していないと、「いつの間にか有給が消えていた」ということになりかねません。
自分の大切な権利を守るためにも、まずはこの2年という有効期限をしっかりと頭に入れておきましょう。
有給休暇の時効消滅を防ぐ2つの具体策
せっかくの有給休暇を時効で失効させないために、私たちはどうすれば良いのでしょうか。
ここでは、具体的な対策を2つご紹介します。
1. 有給休暇を計画的に取得して時効消滅を防ぐ方法
最もシンプルで効果的な対策は、何といっても計画的に有給休暇を取得することです。
有給休暇には2年間の有効期限があることを常に意識し、古い有給から順に使うように心がけましょう。
「でも、自分の有給がいつ付与されたものか分からない…」という方もいるかもしれません。
ご安心ください。
会社には、労働者ごとの有給休暇の取得状況や残日数を記録した「年次有給休暇管理簿」を作成し、3年間保存する義務があります。
自分の有給残日数については、会社の担当部署に定期的に確認するようにしましょう。
年休管理簿の開示請求の方法
退職を控えたタイミングや、有給休暇の残日数に疑問を感じた際、「自分の有給休暇の残り日数が本当に正しいのか?」と不安になることがあるかもしれません。
そんなとき、労働者として確認できる心強い資料が「年次有給休暇管理簿(年休管理簿)」です。
これは、労働基準法第39条および同法施行規則第24条の7によって、すべての企業に作成・3年間の保存が義務づけられている帳簿で、労働者ごとに以下の内容が記録されます。
- 有給休暇の付与日
- 付与日数
- 使用日
- 残日数
開示請求はできるの?
法律上、労働者が企業に「見せてください」と求めた場合に企業が開示する義務があるかどうかについて、明確に「開示義務がある」とは規定されていません。
しかし、年休管理簿は労働者本人の労働条件に密接に関わる情報であり、実務上は本人確認のうえで開示に応じることが望ましいとされています。
多くの企業では、労務担当者や人事部門に問い合わせることで、残日数を確認したり、帳簿の内容を閲覧したりすることが可能です。
開示請求のステップ
- 社内の人事・労務担当者に問い合わせる
- まずは所属部署または人事部に「年休管理簿の内容を確認したい」と伝えましょう。
- 退職予定がある場合は「退職日までに年休をすべて使いたいので、正確な残日数を確認したい」と伝えると、よりスムーズです。
- 本人確認を求められることも
- 個人情報保護の観点から、口頭やメール、社内システムを通じて本人確認が行われる場合があります。
- 紙またはデータでの開示を依頼
- 閲覧だけでなく、書面やPDFでの交付を希望する場合は、その旨を丁寧に申し出ましょう。
- 会社によっては、就業規則や規定に準じた対応となります。
トラブルを防ぐために
年休の誤記録や、更新漏れが起こることは現実にあります。
そのため、自分の取得記録(たとえば給与明細や申請書控え)と照らし合わせて確認することが大切です。
また、退職日を含めた有給消化スケジュールを組む際には、必ず最新の残日数を確認した上で行動することが、トラブル回避につながります。
まとめ
- 年休管理簿は、労働基準法により企業に作成・保存が義務付けられている。
- 労働者本人の情報であるため、実務上は開示に応じるのが一般的。
- 残日数に疑問があれば、退職前に人事・労務担当者へ確認を。
- 自分の有給休暇は、自分で守るという意識が大切。
2. 計画的付与制度で有給休暇の時効消滅を防ぐ方法
会社に「計画的付与制度」がある場合は、積極的にこれを活用するのも有効な対策です。
関連記事
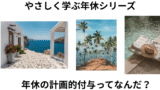
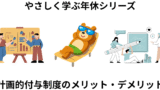
この制度は、会社が労働者の意見を聞き、労使協定を結んだ上で、有給休暇の取得日をあらかじめ決めておくものです。
これにより、従業員は時効で消滅しそうな有給休暇を、強制的にではありますが、確実に消化することができます。
会社側にとっても、従業員の休暇取得日を計画的に管理できるため、業務の平準化や生産性の向上といったメリットがあります。
もしあなたの会社でこの制度が導入されているなら、時効消滅を防ぐ有効な手段として利用を検討してみましょう。
有給休暇の時効消滅分は買取りできる?法律と実務のポイント
時効で消滅しそうな有給休暇を、「お金に換えられないかな?」と考える方もいるかもしれません。
有給休暇の買取りは、原則として法律で禁止されています。
これは、労働者に「休むこと」を促すという有給休暇本来の目的を損なわないためです。
しかし、時効によって消滅した有給休暇については、すでに労働者の権利が消滅しているため、会社が任意に買い取ることに法律上の問題はありません。
これは労働者にとってはメリットがありますが、あくまで企業の裁量によるものであり、法律上の義務ではありません。
有給休暇の時効消滅分を買取りできる例外とは?理由を解説
なぜ時効消滅分は例外なのでしょうか?
それは、時効を迎えると、労働者の有給休暇は文字通り「ゼロ」になってしまうからです。
それは、時効を迎えて権利が消滅すれば、労働者の有給休暇は文字通り「ゼロ」になってしまうからです。
そこで、会社が従業員の不利益を救済する目的で、特別に買い取るケースが例外的に容認されています。
これにより、労働者は本来消滅するはずだった有給休暇をお金に換えられるというメリットがあります。
有給休暇の買取りは会社の善意?注意すべきポイント
ただし、この買取りはあくまで会社の善意による対応であり、法律上の義務ではありません。
労働者が「時効で消えそうだから、買い取ってほしい」と会社に要求する権利は法的にはありません。
会社に買取りの義務はないため、あくまで会社の判断に委ねられる、という点に注意が必要です。
あなたの会社が時効消滅分の有給休暇の買取り制度を設けているかどうかは、就業規則などで確認してみることをお勧めします。
有給休暇は自分で守る!時効・買取り・計画的取得のポイント総まとめ
ここまで、有給休暇の時効について解説してきました。
最後に、大切なポイントをもう一度確認しましょう。
有給休暇の時効や消化ルールを再確認
- 有給休暇は2年で時効を迎えて消滅する
- あなたの有給休暇には、有効期限があります。
- 付与されてから2年が経過すると、残っていても消えてしまいます。
- 時効消滅を防ぐには、計画的な取得が最も重要
- 古い有給から順に使うことを意識し、残日数を常に把握しておきましょう。
- 会社の計画的付与制度も活用しよう
- もし会社に制度があれば、時効消滅を気にせず、確実に有給を消化できる有効な手段となります。
- 時効消滅分は例外的に買い取られることがあるが、会社の任意である
- あくまで会社の善意による対応であり、労働者側から強制する権利はないことを覚えておきましょう。
読者の皆さんへ|有給休暇を賢く使うための最終メッセージ
全9回にわたる「やさしく学ぶ年休シリーズ」は、今回で最終回となります。
有給休暇は、あなたの心身を守り、日々の生活を豊かにするための大切な権利です。
自らその日数を意識し、積極的に使うことで、あなたの権利は守られます。
ぜひこのシリーズで学んだ知識を活かして、有給休暇を賢く利用してください。
これまでお読みいただき、ありがとうございました。
今後も、皆さんの働き方をより良くするための情報をお届けしていきますので、どうぞご期待ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|29240010号)
- 会社員歴30年以上、転職5回を経験した氷河期世代の社会保険労務士です。自らが激動の時代を生き抜いたからこそ、机上の空論ではない、働く人の視点にたった情報提供をモットーとしています。あなたの働き方と権利を守るために必要な、労働法や社会保険の知識、そしてキャリア形成に役立つヒントを、あなたの日常に寄り添いながら、分かりやすく解説します。

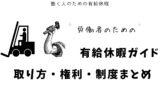
コメント