本記事は「やさしく学ぶ年休シリーズ」シリーズの第6話です。
前回は、年次有給休暇の計画的付与制度を導入する際の具体的な手続き、そして「全社一斉」「班・グループ別」「個人別」という3つの主な運用方式があることを解説しました。
前回の記事は👉計画的付与って何?—会社が決めた日に年休を取る仕組み【やさしく学ぶ年休シリーズ 第5回】
会社によってさまざまな方法があることがおわかりいただけたかと思います。
さて、これらの話を聞いて、「会社に年休を強制されるの?」と疑問に感じる方もいるかもしれませんね。
たしかに、会社が取得日を指定するという点で、通常の年休とは少し違って見えます。
しかし、計画的付与は、単なる「強制」とは異なり、私たち労働者の大切な権利や、会社が果たすべき義務も考慮された上で運用されるべき制度です。
今回は、計画的付与と「強制」の違い、そしてこの制度が導入されている場合に、あなたが「ここだけは知っておくべき」注意点について詳しく見ていきましょう。
計画的付与と強制の違い|年次有給休暇で知っておくべき注意点
計画的付与では、会社があなたの年休の取得日を指定します。
だから「強制される」と感じるかもしれませんね。でも、会社が勝手に日を決められるわけではありません。
1. 計画的付与の注意点|「いつ休むか」は会社が決めるけど、勝手には決められない!
この制度を導入するには、会社と私たち労働者の代表(労働組合、または従業員の過半数を選ぶ代表者)との間で、必ず「労使協定」という書面での約束事を結ぶ必要があります。
これは、会社と従業員の代表が「この制度をこんなルールで導入しましょう」と話し合って合意した証拠なんです。
つまり、あなたの会社に計画的付与があるなら、それは労働者側の代表が同意したルールに基づいて運用されているということ。
この労使協定がなければ、会社は勝手に計画的付与を進めることはできません。
2. 年次有給休暇の計画的付与|休みを変更できないルールとは
普段の年休は、あなたが「この日に休みたい」と申請した後に、会社の「時季変更権」によって別の日を提案されることがありますよね。
でも、計画的付与で指定された年休については、原則としてあなたも会社も、その日を変更することはできません。
- あなたから
- 「やっぱりこの日は用事ができたから休む日を変えたい」と思っても、基本的に会社が指定した日は変えられないんです。
- 会社から
- 一度決めた計画的付与の日を、「急に忙しくなったから出社してほしい」と会社側が一方的に変更することも、原則できません。(ただし、災害など、本当にどうしようもない緊急事態の場合は、例外的に変更が認められる可能性もありますが、非常に稀なケースです。)
これは、計画的付与が、会社と私たち従業員の双方が「この日に休む(休ませる)」と計画を立てることで、業務もプライベートもスムーズに進めるための制度だからです。
一度決まった計画は、お互いに守るのがルールなんです。
3. 年次有給休暇がない従業員への配慮|計画的付与制度の注意点
もし、あなたが新しく入社したばかりでまだ年休がなかったり、または、すでに年休を使い切ってしまっていたりする状況で、会社が指定した計画的付与の日が来たらどうなるでしょうか?
この「年休がない従業員への対応」は、計画的付与の方式によって少し意味合いが変わってきます。
全従業員が一斉に休む、または部署・グループで交代で休む場合(全社一斉・班・グループ別交替制)
- これらの方式では、特定の日や期間に多くの人が休むことになります。
- もし、その時にあなただけ年休がなくても、一人だけ出社しても仕事が成り立たないケースがほとんどでしょう。
- このような場合、会社は年休がないあなたに不利益がないよう、必ず配慮しなければなりません。
- 会社が結んだ労使協定には、具体的に以下のような対応が定められているはずです。
- 特別休暇の付与
- 年休がないあなたに、その日を有給の「特別休暇」として休ませる。
- 休業手当の支払い
- やむを得ず休業させる場合、法律に基づいた「休業手当」(あなたの平均賃金の60%以上)を支払う。
- 欠勤扱いにしない
- 無給の「欠勤」扱いにして、給与が減ったり評価に響いたりすることがないようにする。
- 特別休暇の付与
あなたの希望を聞きながら個別に決める場合(個人別付与方式)
- この方式は、あなたが実際に持っている年休の中から、「いつ休みたいか」を会社と相談して計画を立てていくものです。
- そのため、そもそも年休がない状態であれば、この制度の対象にはなりません。
- 会社が年休がない人に「この日に休め」と強制することはありませんから、上記の特別な配慮が必要になるケースは少ないでしょう。
このように、計画的付与は、単に会社が「休む日を決める」だけの制度ではありません。
私たち労働者の代表が合意したルールに基づいており、万が一、年休がない人が対象になったとしても、会社はあなたの不利益にならないよう、きちんと対応する義務があるのです。
計画的付与制度のメリット・デメリット|会社と従業員に与える影響
計画的付与制度は、あなたの会社に導入されることで、会社側にも私たち従業員側にも、それぞれ異なる影響をもたらします。
どんな「良いこと」と「困ったこと」があるのか、確認してみましょう。
計画的付与制度が会社にもたらすメリット
まず、会社が計画的付与制度を導入するメリットは、主に次の4つです。
- 年休取得率向上で「ルール違反」を防げる
- 会社には、従業員に年5日の有給休暇を確実に取得させる義務があります。
- 計画的付与制度を導入すれば、従業員の年休取得を計画的に進められるため、この法的な義務を果たしやすくなり、法令違反のリスクを減らせます。
- 仕事の段取りがスムーズになる
- 従業員がいつ休むかが事前に決まるので、会社は人員配置や業務のスケジュールを立てやすくなります。
- 「あの人が急に休んだから仕事が止まる!」といった事態を避けやすくなり、結果的に会社全体の生産性アップにもつながるんです。
- 社員のリフレッシュで会社が元気に
- 計画的に休みを取れることで、私たち従業員は心身ともにリフレッシュしやすくなります。
- 体が休まり、気分転換ができれば、仕事へのモチベーションも向上し、結果的に会社全体の活気や生産性の向上にもつながるというわけです。
- 「ホワイト企業」としてイメージアップ
- 従業員の有給休暇取得を積極的に奨励し、ワークライフバランスを重視する姿勢は、会社のイメージを良くします。
- 「働きやすい会社」という評判は、優秀な人材を惹きつけ、定着率を高めることにもつながります。
計画的付与制度で労働者が得られるメリット
次に、私たち従業員にとってのメリットを見ていきましょう。
- 気兼ねなく年休を取れるようになる
- 「休みたいけど、周りの目が気になる…」「忙しそうだから言い出しにくいな…」といった遠慮から、有給休暇を取りづらいと感じる人は少なくありません。
- 計画的付与があれば、会社が「この日は休んでいい日」と明確に指定してくれるので、周囲に気を遣うことなく、堂々と休めます。
- プライベートの予定が立てやすい
- 年休の取得日が事前に決まっているため、旅行の計画を立てたり、家族との大切なイベントの予定を入れたり、資格の勉強に充てたりと、プライベートを計画的に充実させられます。
- 急な出費や予定変更の心配も減るでしょう。
- せっかくの年休を「取り忘れ」て損しない
- 「気づいたら年休が消滅してた!」という経験はありませんか?
- 計画的付与があれば、会社が指定した日に年休が消化されていくため、取り忘れや消化不足で年休が消滅してしまうのを防げます。
- せっかくの権利を無駄にせず活用できるのは、大きなメリットです。
計画的付与制度のデメリット・注意点
しかし、計画的付与制度には、良い面ばかりではありません。私たち労働者にとっては、次のようなデメリットや課題も考えられます。
- 会社の都合で休みが決まってしまう
- 最も大きな点は、自分の「休みたい日」と「会社が指定する日」が必ずしも一致しない可能性があることです。
- 「この時期にプライベートでどうしても休みたいのに、会社が指定した日とは違う…」といった不満を感じるかもしれません。
- あなたの自由な取得希望とのバランスが課題となります。
- 繁忙期でも休む必要がある
- 会社によっては、業務の特性上、繁忙期に計画的付与日を設定せざるを得ない場合もあります。
- 本来ならその時期は休みにくいと感じるかもしれませんが、制度によって指定されてしまうため、業務調整に苦労する可能性があります。
- 会社側の業務調整の手間
- これは主に会社側の課題ですが、計画的付与を導入・運用するには、会社側もそれなりの手間と調整が必要です。
- 特に、班・グループ別や個人別付与の場合は、きめ細やかな管理が求められます。
- この「手間」が、制度の適切な運用を妨げる要因になる可能性もゼロではありません。
労働者向け|有給休暇の計画的付与を会社に提案する方法
年次有給休暇の計画的付与は、働きやすい環境を整えるために有効な制度ですが、まだ導入されていない会社も少なくありません。
『もっと計画的に休みを取りやすくしてほしい』と感じているあなたにとって、会社に制度導入を提案することは、働き方を改善する第一歩です。
会社に新しい制度の導入を提案するのは、少し勇気がいるかもしれません。
でも、ポイントを押さえて準備し、適切な方法で伝えれば、あなたの声が会社を動かすきっかけになる可能性は十分にあります。
Step1|計画的付与を会社に提案する前の準備と情報整理
まずは、提案を成功させるための土台作りです。
制度の正確な理解を深める
- 「計画的付与って、結局何?」と聞かれたときに、きちんと説明できるように、このシリーズ記事で学んだ制度の定義、法的根拠、導入要件(労使協定が必要なこと)、対象日数(5日を超える部分)などを正確に理解しておきましょう。
- あいまいな知識では、説得力に欠けてしまいます。
会社と従業員双方のメリットを整理する
- 会社に提案する際、最も大切なのは「会社にとってどんなメリットがあるのか」を明確に伝えることです。
- 会社側
- 年休取得義務の確実な達成(法律遵守)
- 業務の計画性向上、生産性向上
- 従業員のリフレッシュによるモチベーション向上
- 会社のイメージアップ(採用力強化など)
- といった点を具体的に整理しましょう。
- 従業員側
- あなた自身や同僚が感じている
- 「気兼ねなく有給休暇が取れる」
- 「取り忘れ・消化不足の防止」
- 「計画的なプライベートの充実」
- といったメリットも、会社が制度を導入する「意義」として伝えられます。
- あなた自身や同僚が感じている
- 会社側
自社の現状と課題を分析する
- あなたの会社で、年休の取得率はどのくらいですか?
- 「休みにくい雰囲気」はありませんか?
- 繁忙期と閑散期ははっきりしていますか?
- これらの現状を把握し、「計画的付与制度が導入されれば、うちの会社のこんな課題が解決できるはずだ」という具体的なイメージを持つことが重要です。
- 例えば、「みんなが遠慮して年休がなかなか消化できていない現状を改善できる」といった具体的な課題と解決策を結びつけましょう。
Step2|計画的付与制度を会社に提案する場の選び方と伝え方
準備ができたら、いよいよ誰に、どのような形で提案するかを考えます。
まずは直属の上司に相談(推奨)
- 最も身近な存在である直属の上司に、まずは個人的な意見として「計画的付与制度について、会社で検討してもらえないでしょうか」と相談してみるのがおすすめです。
- 上司が制度に理解を示してくれれば、そこから話を進めやすくなります。
- 会社のメリットも簡潔に伝えつつ、あなたの思いを率直に話してみましょう。
労働者の代表者(労働組合または過半数代表者)に相談
- 計画的付与制度の導入には「労使協定」が必須です。
- そのため、労働組合がある場合は組合に、ない場合は従業員の過半数を代表する者(労働者代表)に相談するのが最も効果的なルートです。
- 彼らは従業員の意見を会社に伝える役割を担っており、他の従業員の意見も集約して、会社と交渉してくれる可能性があります。
人事部・総務部への提案
- 会社の規模によっては、直接人事部や総務部の担当者に相談することも可能です。
- ただし、まずは直属の上司や労働者代表を通す方が、社内の手続きや人間関係を考慮するとスムーズに進む場合が多いでしょう。
Step3|計画的付与制度を会社に提案する具体的な進め方
提案の場が決まったら、実際にあなたの提案を具体的に伝えます。
提案書を作成する(任意だが効果的)
- 口頭での説明だけでなく、提案書としてまとめるのは非常に効果的です。提案書には、以下の内容を簡潔に盛り込みましょう。
- 提案の背景
- なぜこの制度が必要だと考えるのか(例:年休取得率の低さ、休みにくい雰囲気など)。
- 制度の概要
- 計画的付与制度とは何か。
- 導入のメリット
- 会社と従業員双方にとっての具体的なメリット。
- 具体的な導入イメージ
- 例えば、「年5日分を夏季休暇に繋げる形で一斉付与してはどうか」など、具体的な運用方法のアイデア。
- 年休がない従業員への対応案
- (もしあれば)特別休暇の付与などの配慮案。
- 希望する今後のプロセス
- 「まずは検討委員会を立ち上げてほしい」など、次のステップへの希望。
- 提案書は、あなたの本気度を示すだけでなく、会社側が検討する際の資料としても役立ちます。
- 提案の背景
話し合いの場を持つ
- 提案が受け入れられた場合、会社側と労使の代表者間で、制度導入に向けた具体的な話し合いの場が設けられるでしょう。
- この場では、あなたの提案だけでなく、会社側の懸念や他の従業員の意見なども出てくるはずです。
- 建設的な議論を通じて、より良い制度設計を目指しましょう。
Step4|計画的付与提案後のフォローアップ方法
提案して終わりではありません。導入に向けて動き出したなら、その後の進捗も気にかけましょう。
進捗状況を確認する
- 提案後、定期的に会社(または労働者代表)へ進捗を問い合わせてみましょう。
- 具体的な動きが見られない場合は、再度働きかけることも必要かもしれません。
必要に応じて柔軟に対応する
- 会社側から「この点は難しい」「こんな懸念がある」といった意見が出た場合、あなたの提案に固執しすぎず、代替案を考えたり、まずは一部の部署から試行することを提案したりするなど、柔軟な姿勢を持つことも大切です。
- お互いの歩み寄りが、制度実現への近道となります。
このように、計画的付与制度の導入提案は、事前の準備と、会社との建設的な対話が鍵となります。
あなたの声が、会社全体の働き方を変える大きな一歩になるかもしれません。
まとめ|有給休暇計画的付与で働きやすい職場を実現
年次有給休暇の計画的付与制度って、最初は「会社が勝手に休みを決めるの?」と戸惑うかもしれません。
でも、ここまで読んでみて、その仕組みや導入方法、そして何より「ただの強制じゃない」ことがわかってもらえたでしょうか。
この制度は、会社が私たちの年休取得をサポートし、私たちも遠慮なく休めるようにするための、会社と私たちのお互い様の仕組みなんです。
大切なのは、ただ制度があるだけでなく、それが本当に私たちの働きやすさにつながるように運用されること。
労使協定を通して私たちの声が届き、一人ひとりの事情にも配慮されるからこそ、この制度は力を発揮します。
計画的付与をうまく活用できれば、あなたは「休みづらい…」というストレスから解放され、心置きなくリフレッシュできる時間を手に入れられます。
旅行や家族との大切な時間、趣味や自己投資など、プライベートを計画的に充実させられるって、すごく嬉しいことですよね。
計画的付与制度を会社に提案するメリット|従業員の声を活かす方法
そして、今回このシリーズの最後で「会社に提案してみるフロー」についても詳しく解説しましたね。
もしあなたの会社にまだこの制度がないとしても、今回学んだことを活かして、会社に「提案してみる」こと自体に大きな意義があります。
あなたの声が、会社に「従業員の働き方をもっと良くできるんじゃないか?」と考えるきっかけを与えます。
たとえすぐに導入に至らなくても、「従業員はこんなことを考えているんだ」と会社に気づいてもらう第一歩になるはずです。
そして、何より、あなた自身が「自分の働き方」や「職場の環境」に対して、主体的に関わろうとする姿勢は、会社にとっても非常に価値のあることです。
小さな一歩が、やがて会社全体の働き方改革につながり、誰もが安心して休みを取り、心身ともに健康で、イキイキと働ける「働きやすい職場」へと進化していくことを、心から願っています。
次回予告|年休取得で知っておきたい「時季変更権」解説
ここまで、年次有給休暇の計画的付与について、その良い面も、知っておきたい注意点も見てきました。
でも、普段の年休取得では、「この日に休みたい」と申請したのに、会社から「その日は困るから別の日にしてほしい」と言われた経験がある人もいるかもしれませんね。
次回は、年休取得の際に会社が持つ「時季変更権」という特別な権利に焦点を当てます。
次回の記事は👉【労働者・会社員向け】時季変更権とは?会社が年次有給休暇の申請を拒否できる条件を解説【やさしく学ぶ年休シリーズ 第7回】
「会社はいつでも年休を拒否できるの?」という素朴な疑問を解消し、時季変更権が認められるケースや、会社が勝手な理由で拒否できない理由について、あなたの年休を守るために知っておきたい大切なルールを徹底解説します。
どうぞお見逃しなく!

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|29240010号)
- 会社員歴30年以上、転職5回を経験した氷河期世代の社会保険労務士です。自らが激動の時代を生き抜いたからこそ、机上の空論ではない、働く人の視点にたった情報提供をモットーとしています。あなたの働き方と権利を守るために必要な、労働法や社会保険の知識、そしてキャリア形成に役立つヒントを、あなたの日常に寄り添いながら、分かりやすく解説します。
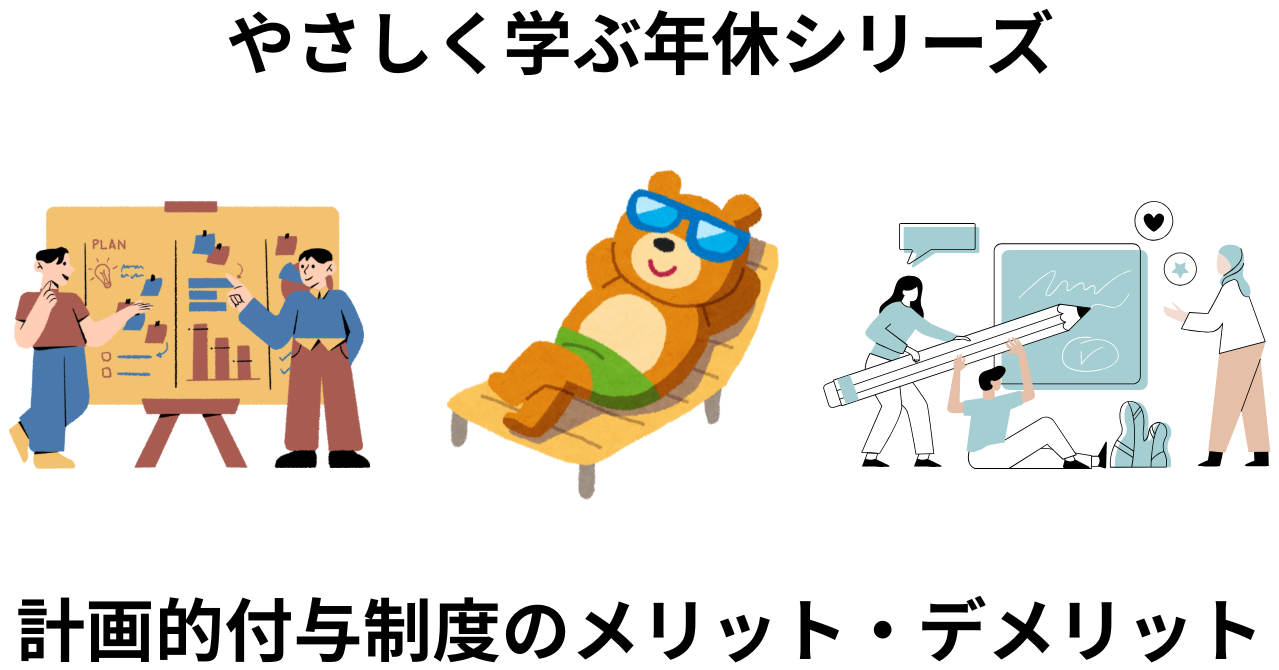
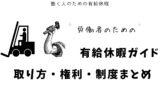
コメント