本記事は「やさしく学ぶ年休シリーズ」シリーズの第5話です。
前回までは、年次有給休暇(年休)が労働者に与えられた大切な権利であり、正社員だけでなくパートやアルバイトにも取得する権利があることをお伝えしました。
前回の記事は👉会社員向け|有給休暇申請のコツ|病欠時の年休・時間単位年休等
原則として、年休は労働者自身が「いつ休むか」を決めて請求するものです。
でも、こんな課題を感じている会社や従業員もいるんじゃないでしょうか?
- 会社側
- 「うちの会社、繁忙期にみんながバラバラに休むと業務が回らないな…」「計画的に休んでもらえないと、事業運営が滞ることもある…」
- 従業員側
- 「年休は欲しいけど、職場の雰囲気を考えると、なかなか言い出しにくいんだよな…」「気づいたら、せっかくの年休が消えちゃってた!」
そうなんです。せっかくの制度があっても、なかなか利用しづらいという声は少なくありません。
計画的付与制度とは?年次有給休暇の課題を解決する仕組み
そこで登場するのが、年休の取得を強力に後押しする「計画的付与制度」です。
この制度は、会社が従業員の年休取得日をあらかじめ決めることで、より計画的に年休を消化してもらい、会社全体の年休取得率アップや業務効率化につなげることを目的としています。
従業員も「休んでいい日」が明確になるので、遠慮なくリフレッシュできるメリットがあります。
今回は、この「計画的付与制度」について、その仕組みや導入方法、注意点などをわかりやすく解説していきますね。
年次有給休暇は、従業員が「いつ休むか」を自由に決めるのが原則です。
しかし、会社と従業員の双方にとって、もっと年休を有効活用できるように考えられたのが「計画的付与制度」です。
この制度を一言でいうと、会社と従業員の代表者が話し合って協定を結べば、会社が従業員の年次有給休暇の取得時期をあらかじめ決めることができる仕組みのこと。
具体的な根拠は、労働基準法第39条第6項に定められています。法律で認められている制度なんですね。
計画的付与制度が必要な理由とは?年休取得率向上と業務効率化のメリット
この制度が導入された背景には、主に3つの大切な目的があります。
- 従業員の年休取得率向上
- 「休みたいけど、周りに迷惑をかけそう…」といった遠慮から、せっかくの年休を使いきれずに消滅させてしまう従業員は少なくありません。
- 計画的付与があれば、「この日は休んでOK」と会社が明確に示してくれるので、従業員は気兼ねなく年休を取得できます。
- 結果として、会社全体の年休取得率アップに繋がり、法律で義務付けられている年5日の年休取得も促進されます。
- 企業の計画的な業務運営・生産性向上
- 従業員がそれぞれ好きな時に年休を取ると、繁忙期に人手不足になったり、業務の進捗が滞ったりすることがあります。
- 計画的付与制度を導入すれば、会社は業務計画に合わせて年休取得日をあらかじめ設定できるため、効率的な人員配置が可能になり、事業の円滑な運営や生産性向上に貢献します。
- ワークライフバランスの推進
- 従業員が計画的に休みを取れることで、プライベートの時間を充実させやすくなります。
- 家族との時間、自己啓発、リフレッシュなど、メリハリのある働き方が可能になり、結果的に従業員のモチベーションやエンゲージメント(会社への愛着や貢献意欲)の向上にも繋がります。
- これは、従業員が長く健康的に働き続けるために非常に重要な要素です。
このように、計画的付与制度は、単に年休を消化させるだけでなく、会社と従業員の双方にとって多くのメリットをもたらし、より良い職場環境を築くための有効なツールなんです。
計画的付与制度の対象年休日数とは?自由取得分と指定可能分の違いを解説
「計画的付与制度」は、会社が年休の取得日を指定できる便利な仕組みですが、実は従業員に付与された全ての年休を会社が一方的に指定できるわけではありません。
ここには大切なルールがあります。
計画的付与は年休5日超から!対象範囲と法律で保障された自由取得分のルール
労働基準法では、従業員が付与された年休のうち、最低5日分は「労働者が自由に取得できる」と定めています。
これは、急な体調不良や家族の用事など、従業員が予測できない事態に対応するための大切な権利として保証されているからです。
したがって、計画的付与制度の対象となるのは、年次有給休暇の付与日数のうち「5日を超える部分」に限られます。
具体例で見てみましょう。
例えば、ある従業員に年間10日の年次有給休暇が付与された場合を考えてみましょう。
- まず、法律で保障されている最低5日分は、従業員が自分の好きなタイミングで自由に取得できる「自由取得分」として確保されます。会社はこの5日間の取得時季を指定することはできません。
- 残りの5日(10日 − 5日 = 5日)が、労使協定に基づいて「計画的付与」の対象となる部分です。会社はこの5日分の年休について、取得時季を指定することができます。
もし、年間15日の年休が付与された従業員であれば、5日は自由取得分、残りの10日が計画的付与の対象となります。
このように、計画的付与制度は、従業員の自由な年休取得の権利を保障しつつ、企業全体の年休取得率向上と業務の円滑化を図るためのバランスの取れた仕組みとなっています。
計画的付与制度の導入手順と必要な手続き【労使協定・就業規則・周知方法を解説】」
「計画的付与制度」が、会社と私たち労働者双方にメリットがある仕組みだということは、ご理解いただけたでしょうか。
では、この制度が皆さんの会社で実際に導入されるには、どのような手続きが必要になるのでしょうか?
会社が「明日から年休は会社が決める!」と一方的に決められるわけではありません。
大切なステップがいくつかあります。
労使協定の締結方法と内容のポイント【計画的付与制度で決めるべきこと】
まず最も重要なのが、会社(使用者)と、私たち労働者の代表(労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者)との間で、「労使協定」という書面による約束事を結ぶことです。
これは、会社と私たちの代表が「この制度を導入しましょう」「こんなルールで運用しましょう」と話し合い、正式に合意した証です。
つまり、私たち労働者側の意見も反映されるべき重要なステップなのです。
この労使協定には、具体的に以下のことを定める必要があります。
- 計画的付与の対象者
- 誰にこの制度が適用されるのか(例:全従業員、特定の部署の従業員など)。
- 計画的付与の具体的な方法
- どのように年休取得日を指定するのか(例:夏休みやお盆に会社全体で一斉に休む「一斉付与方式」、部署ごとに交代で休む「交替制付与方式」など)。
- この後で詳しく解説しますね。
- 対象となる年休日数
- 何日分の年休が計画的付与の対象になるのか(前述の通り、年5日を超える部分です)。
- 年休がない、または残日数が少ない従業員への対応
- 例えば、新しく会社に入ってまだ年休が付与されていない人や、すでに年休を使い切ってしまっている人が、計画的付与の日に休むことになったらどうなるのか、というルールです。
- 不利益がないように、特別休暇を与えるなどの配慮が協定で定められることが一般的です。
就業規則に計画的付与制度を明記する方法と注意点
労使協定が締結されたら、次に会社は就業規則(会社のルールブックのようなもの)に、この計画的付与制度を導入する旨を明確に記載する必要があります。
就業規則は、会社の労働条件や服務規律などを定めた重要なルールです。ここに明記することで、この制度が会社の正式なルールとして位置づけられます。
計画的付与制度の周知方法|労働者への通知と理解促進のポイント
最後に、会社は計画的付与制度について、私たち労働者全員にきちんと知らせる(周知する)義務があります。
具体的には、説明会を開いたり、書面を配布したり、社内掲示板やイントラネットに掲載したりするなど、様々な方法で、制度の内容や取得日が明確にわかるように伝えられます。
これは、私たちが安心して制度を利用し、計画的に行動できるよう、非常に大切なステップです。
これらの手続きがきちんと行われて初めて、計画的付与制度は法的に有効に運用されることになります。
もし皆さんの会社でこの制度が導入される際には、これらのプロセスが透明に行われているか、確認してみると良いでしょう。
計画的付与制度の主な方式|全社一斉・交替制・個人別の3タイプを解説
一口に「計画的付与」と言っても、その具体的な運用方法にはいくつかのパターンがあります。
会社の業種や規模、業務内容によって、最適な方式は異なります。
ここでは、代表的な3つの方式をご紹介します。
1. 全社一斉付与方式とは?計画的付与制度で会社全体が同日に休むメリット・デメリット
- 概要
- 事業場や会社全体の従業員が、同じ日に一斉に年次有給休暇を取得する方式です。
- 具体例
- 夏季休暇やお盆休み、年末年始休暇などに、数日間の計画的付与日を追加し、大型連休にする。
- 会社の創立記念日など、特定の日に全社を休業にする。
- メリット
- 管理がシンプル
- 会社全体で一斉に休むため、個別の調整が不要で、管理がしやすいです。
- 業務効率の向上
- 全員が休むことで、業務を完全にストップさせることができ、集中してリフレッシュできます。
- 一体感の醸成
- 全員が同じ時期に休むことで、連帯感が生まれることもあります。
- 管理がシンプル
- デメリット
- 業務の特性による制約
- 365日稼働しているサービス業や製造業など、業務の特性上、一斉に休むことが難しい会社には向きません。
- 従業員の希望とのずれ
- 個人の希望する時期に休暇が取れない場合があり、不満につながることもあります。
- 業務の特性による制約
2. 班・グループ別交替制付与方式とは?計画的付与制度で業務影響を抑える方法
- 概要
- 部署、課、班、または特定のグループごとに、交代で年次有給休暇を取得する方式です。
- 具体例
- 製造ラインのA班とB班が、それぞれ異なる週に計画的付与を取得する。
- コールセンターで、担当グループごとに時期をずらして休暇を取る。
- メリット
- 業務への影響を最小限に
- 全員が同時に休むわけではないため、業務を継続しながら計画的付与を導入できます。
- 柔軟な運用
- 部署や業務の状況に合わせて、比較的柔軟に休暇時期を設定できます。
- 業務への影響を最小限に
- デメリット
- 管理の複雑さ
- グループごとの調整が必要になるため、一斉付与方式より管理が複雑になります。
- グループ間の不公平感
- 休暇時期に偏りが出ると、グループ間で不公平感が生じる可能性もあります。
- 管理の複雑さ
3. 個人別付与方式とは?希望を反映した計画的年休の取り方
- 概要
- 従業員一人ひとりの希望を聞き、個別に年次有給休暇の取得計画を立てて付与する方式です。
- 具体例
- 従業員が事前に希望する休暇日を会社に提出し、会社が業務状況と調整して計画的付与日として指定する。
- 「誕生日休暇」や「アニバーサリー休暇」など、個人の記念日に合わせて計画的に休暇を付与する。
- メリット
- 従業員の満足度が高い
- 個人の希望が反映されやすいため、従業員の満足度が高まります。
- ワークライフバランスの向上
- 計画的にプライベートな予定を立てやすくなります。
- 従業員の満足度が高い
- デメリット
- 管理の手間が大きい
- 従業員一人ひとりの希望を聞き、業務と調整する必要があるため、会社側の管理負担が最も大きくなります。
- 調整の難しさ
- 希望が集中したり、業務の都合で調整が難航したりする場合があります。
- 管理の手間が大きい
まとめ|計画的付与制度で年休を有効活用するポイント
今回は、年次有給休暇の計画的付与制度について、その全体像を詳しく解説しました。
この制度が、私たちが持つ年休の「5日を超える部分」を対象とし、会社と私たちの代表が結ぶ労使協定に基づいて導入されること、そして就業規則への記載や従業員への周知が必要なことをお分かりいただけたでしょう。
また、計画的付与には、全社一斉に休む方式、部署やグループで交代で休む方式、そして個人の希望を聞きながら決める方式の3つがあることをご紹介しました。
どの方式があなたの会社に合っているかは、それぞれの業務内容によって異なりますが、この制度が私たち労働者の年休取得を促進し、会社全体の業務効率を上げるための有効なツールであることが理解できたはずです。
この制度を正しく理解することは、あなたのワークライフバランスを守るためにも非常に重要です。
次回予告|計画的付与制度のよくある疑問を徹底解説
次回の記事では、この計画的付与についてよくある疑問「会社に年休を強制されるの?」という点に焦点を当てます。
次回の記事は👉年次有給休暇の計画的付与で損しないために|労働者が押さえる注意点【やさしく学ぶ年休シリーズ 第6回】
計画的付与が単なる「強制」ではない理由、そして制度が運用される上で知っておきたい注意点、さらには年休がない従業員への会社の配慮について、あなたの視点から徹底的に掘り下げていきます。
「自分の年休、これで大丈夫?」そんな不安を解消するために、ぜひ次回の記事も参考にしてください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|29240010号)
- 会社員歴30年以上、転職5回を経験した氷河期世代の社会保険労務士です。自らが激動の時代を生き抜いたからこそ、机上の空論ではない、働く人の視点にたった情報提供をモットーとしています。あなたの働き方と権利を守るために必要な、労働法や社会保険の知識、そしてキャリア形成に役立つヒントを、あなたの日常に寄り添いながら、分かりやすく解説します。

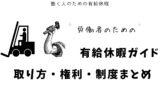
コメント