本記事は「知っておきたい!年次有給休暇のすべて」シリーズのvol14です。
「知っておきたい!年次有給休暇のすべて」シリーズも、いよいよ最終回です。
これまで、私たちは有給休暇の基本ルールから始め、シフト制アルバイトや非正規雇用者への適用、時季指定権・時季変更権の深い内容を探ってきました。
また、計画的付与や時間単位年休といった具体的な活用法、さらには年5日取得義務化への実務対応や管理簿の作成方法まで、多岐にわたるテーマを掘り下げてきましたね。
これまでの記事で、有給休暇を巡る具体的なトラブル事例とその対処法を詳細に解説しました。
従業員側、そして企業側それぞれの視点から、トラブルを未然に防ぐ予防策も考察しています。
有給休暇は単なる「休む権利」ではありません。
従業員のリフレッシュ、企業の生産性向上、そして健全な労使関係構築に不可欠な要素だとご理解いただけたはずです。
常に変化する労働環境と有給休暇運用の重要性
労働を取り巻く環境は常に変化しています。
法改正や新たな判例によって、有給休暇の運用に関する解釈や企業の対応は常に更新されるのです。
例えば、働き方が多様化する現代では、フリーランス保護新法のような新しい法律が、有給休暇の議論に間接的に影響を与えることもあります。
最終回となる今回は、これまでの知識を総仕上げとします。
企業が今後も法令を遵守し、適切に有給休暇を運用するために不可欠な「最新の法的トレンド」と「企業が備えるべき具体的な注意点」に焦点を当てて解説していきます。
複雑に思える有給休暇の運用も、本シリーズで学んだ知識と最新の動向を踏まえれば、きっと自信を持って対応できるでしょう。
注目すべき法改正の動向【2025年 有給休暇・労働法対応】
労働法の改正は、企業の有給休暇運用に直接的または間接的に影響を与えます。特に2025年に向けて、いくつかの重要な法改正が控えており、これらへの対応が求められます。
2025年改正 育児・介護休業法と有給休暇への影響
2025年には、育児・介護と仕事の両立支援をさらに強化する改正が施行されます。
子の看護休暇等の対象拡大、育児のためのテレワーク努力義務化、育児休業取得状況の公表義務対象拡大などが主な内容です。
これらの改正は、労働者が育児や介護と両立しながら働く環境を整えます。
結果として、より柔軟な働き方や休暇取得へのニーズが高まるでしょう。
企業が今すべきこと
企業は、これらの制度改正を理解し、従業員がより安心して休暇を取得できる環境整備に努める必要があります。
詳細については、関連する別記事で詳しく解説していますので、そちらもご参照ください。👇
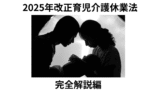
フリーランス保護新法と多様な働き方への対応
2024年4月27日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(通称:フリーランス保護新法)が施行されました。
この法律は、直接的に有給休暇の付与を義務付けるものではありません。
しかし、フリーランスとして働く人々が増える中で、その労働環境を保護するための法整備が進んでいます。
本法は、発注事業者とフリーランス間の契約明確化やハラスメント防止などを定めます。
将来的に、労働者性の判断基準や、フリーランスに対する休息や補償のあり方に関する議論に影響を与える可能性があります。
企業には、多様な働き方に対応できる体制がこれまで以上に問われます。
契約内容を改めて確認し、適切な休息や補償の概念への意識を持つことが重要です。
高年齢者雇用安定法改正とシニア社員の年休管理課題
2025年4月1日からは、高年齢者雇用安定法に基づく65歳までの雇用確保措置が完全に義務化されます。
定年を65歳未満に定めているすべての企業は、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
- 65歳までの定年の引き上げ
- 希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度の導入
- 定年の廃止
高齢労働者が増加することで、企業は有給休暇の付与日数やその管理、そして個々の高齢労働者の健康状態や働き方に応じた両立支援策を、よりきめ細かく検討していく必要が生じます。
雇用保険法の改正(高年齢雇用継続給付の見直し・教育訓練休暇給付金の新設)
2025年4月1日以降に60歳になる労働者から、高年齢雇用継続給付の給付率が段階的に縮小されます(現行最大15%から10%に引き下げ)。
一方で、2025年10月には、労働者が自発的な教育訓練のために仕事から離れることを支援する「教育訓練休暇給付金」が新設される予定です。
これらの改正は、経済的な側面から労働者のキャリア形成やスキルアップのための休暇取得を促進する可能性があります。
企業は従業員の学習意欲を支援する視点を持つことが求められます。
労働安全衛生規則改正(熱中症対策義務化)と休暇取得
2025年4月より、労働安全衛生規則に基づく熱中症対策が正式に義務化されます。
企業にはより具体的な措置が求められます。
作業場所のWBGT(湿球黒球温度)値測定・記録、冷房・送風設備の設置推奨、水分補給・休憩指導、教育訓練の義務化などが含まれます。
この改正は有給休暇に直接関連するものではありません。
しかし、暑熱環境下での労働者の健康確保が厳格化されることで、体調不良時の休暇取得の重要性が増します。
企業は従業員の健康を守るために、必要に応じて有給休暇の取得を促すなど、柔軟な対応が求められる可能性があります。
詳細については、関連する別記事で詳しく解説していますので、そちらもご参照ください。👇

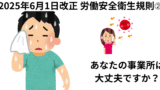
最新判例から学ぶ有給休暇運用の実務ポイント
法改正だけでなく、過去の判例も有給休暇の適切な運用を考える上で重要な指針となります。
特に労使間で争いになりやすいポイントについて、判例が示す原則を理解しておくことが、トラブル回避につながります。
時季変更権の行使は「事業の正常な運営」がカギ【判例解説】
企業が従業員の有給休暇取得時季を変更できる「時季変更権」は、その行使が認められる要件が非常に厳格です。
判例では、「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、単に「忙しい」「人手不足」といった抽象的な理由ではありません。
代表的な判例・事例
代替要員の確保が著しく困難であること、その労働者が休むことで事業全体に具体的な損害が生じることなど、客観的かつ具体的な事実に基づいている必要があるとされています。
安易な拒否は労働基準法違反となる危険性が高いため、企業は常に慎重な判断と、代替要員確保への努力が求められます。
電電公社帯広電報電話局事件(最高裁昭和62年7月10日判決)
- 概要
- 職員が勤務日に有給休暇を申請しました。
- 所属長は「事業運営上支障がある」として時季変更権を行使しましたが、職員はデモに参加するため欠勤した事案です。
- 判旨のポイント
- 最高裁は、有給休暇の利用目的は労働基準法の関与しないところであり、利用目的を理由に時季変更権を行使することは許されないとしました。
- このケースでは、所属長が職員のデモ参加を阻止したいという意図があったと推測されますが、それが「事業の正常な運営を妨げる」客観的な理由にはならないと判断されたのです。
- 時季変更権の行使が違法とされ、職員の欠勤は有給休暇として扱われるべきと判断されました。
時事通信社事件(最高裁平成4年6月23日判決)
概要
- 報道記者が24日間の長期有給休暇を申請したところ、会社が後半の10日間について時季変更権を行使しました。
- 記者は原子力発電所の問題について専門的な知識を持ち、その間に取材が入る可能性がありました。
- 記者は会社の時季変更権行使に従わず休暇を取得し、その後会社から懲戒解雇されました。
- この懲戒解雇の有効性を争うため、記者が会社を訴え、裁判となりました。
判旨のポイント
- 最高裁は、会社による時季変更権の行使を適法と認めました。
- その根拠としては、以下の点が総合的に考慮されました。
- 報道機関としての社会的使命と公共性
- 時事通信社がリアルタイムで正確な情報を伝えるという公共性の高い使命を負っており、特に原子力発電所という社会的に重要な問題に関する取材は、予測不能かつ緊急性が高い業務であること。
- 当該記者の専門性と代替性の困難さ
- 当該記者が原子力発電所問題に関する専門知識を持ち、その業務における代替要員の確保が極めて困難であったこと。
- 長期かつ連続の休暇申請であること
- 24日間という長期にわたる連続休暇であり、そのうちの後半の10日間に時季変更権を行使したこと。
- 事前調整の欠如
- 記者が長期休暇の時期指定をするにあたり、会社の業務計画や他の労働者の休暇予定等との事前の調整を十分に行わなかったこと。
- 報道機関としての社会的使命と公共性
これらの理由から、最高裁は、会社には有給休暇の時季変更にある程度の裁量的判断が認められるとし、時季変更権が適法に行使されたと判断しました。
その結果、適法な業務命令に従わなかった記者の行為は業務命令違反となり、懲戒解雇も有効であると判断されました。
これは、長期かつ専門性の高い業務に関わる有給休暇取得において、例外的に時季変更権が認められた重要な事例として知られています。
東海旅客鉄道事件(東京高裁令和6年2月28日判決)
概要
- 新幹線運転士らが年次有給休暇を申請したところ、会社が時季変更権を行使しました。
- これに対し運転士らは、会社の恒常的な要員不足を主張し、時季変更権の行使は違法であるとして損害賠償を求めて会社を訴えました。
- 会社が時季変更権を行使した理由
- 東海道新幹線は社会的に重要な公共交通機関であり、その安定的な運行には高い専門性を持つ運転士が不可欠です。
- 会社は、運転士らが希望する日に年休を取得すると、特に需要予測が難しい臨時列車の運行などで、安全かつ定時運行という事業の正常な運営に支障が生じると判断しました。
- 会社は、勤務日の5日前までに時季変更権を行使するか判断する運用をしており、これは新幹線の機動的な運行体制から見て合理的であると主張しました。
判旨のポイント
- 一審の東京地裁は、一部の運転士の請求を認めて会社に賠償を命じましたが、二審の東京高裁は、会社による時季変更権の行使を適法と認め、運転士らの請求をすべて棄却しました。
- 高裁は、東海道新幹線の公共性や運行の特殊性、運転士の専門性の高さ、代替要員確保の難しさなどを重視しました。
- また、会社が基準人員に基づき要員を配置し、年度中の乗務員数の推移を踏まえて業務量を調整したり、休日勤務の指定や予備担当乗務員の活用など、代替要員確保のための努力をしていた点を評価しました。
- その上で、高裁は会社が「恒常的な要員不足」に陥っていたとは認められないと判断し、勤務日の5日前の時季変更権行使も、事業の性質上、不当に遅れたものとは言えないと結論づけました。
結論
- この判例は、特に公共性が高く、専門性の高い事業においては、その事業の正常な運営を確保するためには、労働者の時季指定権が一部制限され、時季変更権の行使が認められる場合があることを明確に示しました。
有給休暇取得を理由とする不利益取扱いは禁止【判例解説】
労働基準法附則第136条により、企業は労働者が年次有給休暇を取得したことを理由として、いかなる不利益な取扱いをすることも明確に禁止されています。
具体的には、賃金の減額、人事評価の引き下げ、昇進・昇格の遅延、配置転換、賞与や退職金の減額などがこれにあたります。
代表的な判例・事例
過去の判例では、有給取得を間接的に評価に反映させたケースでも不利益取扱いと認定された事例があります。
企業は評価制度の設計や運用において、この原則を徹底し、透明性を確保することが極めて重要です。
沼津交通事件(最高裁平成5年6月25日判決)
- 概要
- 年次有給休暇を取得した労働者に対し、会社が皆勤手当を減額したことが不利益取扱いに該当するかが争われた事案です。
- 判旨のポイント
- 最高裁は、有給休暇の取得を理由に皆勤手当を不支給または減額することは、労働者の有給休暇取得の権利行使を事実上抑制するものであり、労働基準法136条(当時)の趣旨に反すると判断しました。
- この判例により、皆勤手当の支給要件から有給休暇取得日を除外することは原則として認められないという考え方が定着しました。
日能研関西ほか事件(大阪高裁平成25年11月28日判決)
- 概要
- 塾講師が有給休暇を申請した際、上司が「有給申請により評価が下がる」と発言して取得を妨害した事案です。
- 判旨のポイント
- 裁判所は、上司のこの発言が従業員の有給休暇取得権を侵害する行為であり、違法な不法行為に当たると認定しました。
- 会社に対しても、使用者責任として損害賠償を命じています。
- この判例は、有給休暇取得への心理的圧力をかける行為も不利益取扱いに準ずる違法行為となることを明確に示しました。
退職時の有給休暇消化ルールと判例の傾向【判例解説】
退職を控えた従業員が残っている有給休暇を一括で消化したいと申し出た場合、企業が時季変更権を行使することは、退職日をずらせない限り事実上困難であるとされています。
代表的な判例・事例
判例上も、退職日までの期間が限られている中で、時季変更権の行使は認められにくい傾向にあります。
企業としては、従業員から退職の意思表示があった際には、速やかに有給休暇の残日数を確認しましょう。
そして、消化希望期間について円滑な話し合いを進めることが肝要です。
特別な場合を除き、有給休暇の買い上げは義務ではありませんが、トラブル防止のために労使間で合意形成を図る努力が求められます。
就業規則に退職時の有給休暇の取り扱いについて明確に記載しておくことも重要です。
大阪地裁令和6年3月27日判決(病院の事業譲渡に伴う有給消化の事案)
- 概要
- 病院の事業譲渡に伴い、全職員が譲渡日に退職し、その後新事業者に雇用されることとなりました。
- その際、職員の3分の2にあたる232名が一斉に退職前の有給消化を申請した事案です。
- 判旨のポイント
- 裁判所は、232名が一斉に有給申請すると病院業務に重大な支障が生じることは明らかであるとし、このような事情がある場合には、退職前の有給消化であっても、使用者は労働者ができるだけ有給を取得できるよう配慮しながら時季変更権を行使することは許されると判断しました。
- これは、退職時であっても、事業への著しい影響がある場合には、時季変更権の行使が例外的に認められる可能性を示唆するものです。
- ただし、企業側の配慮義務も強調されています。
全日本空輸事件(最高裁昭和62年7月10日判決)
- 概要
- 客室乗務員が退職直前に残っていた年次有給休暇の全てを消化したいと申し出たのに対し、会社が時季変更権を行使したことの適法性が争われた事案です。
- 会社は、訓練中の客室乗務員不足を理由に時季変更権を行使しました。
- 判旨のポイント
- 最高裁は、退職予定者が残りの有給休暇の時季指定をした場合、時季変更権の行使が許されるのは、客観的に他の時季に変更することが不可能と認められる場合に限られると極めて厳しく判断しました。
- この事案では、会社側の主張する「事業の正常な運営を妨げる」事情は認められず、会社による時季変更権の行使は違法とされました。
- 労働者の退職日が迫っている場合、事実上、有給休暇を他の時季に変更することはできないということを明確にした、労働者側の権利を強く擁護した判例です。
これらの判例から、有給休暇の運用においては、単に法律条文を形式的に遵守するだけでなく、その趣旨を理解し、個々の状況に応じて適切かつ誠実に対応することが極めて重要であることがわかります。
企業が今すぐ取り組むべき有給休暇運用の対策
法改正や判例の動向を踏まえ、企業が持続的に健全な有給休暇運用を行うためには、以下の点を強化していく必要があります。
有給休暇に関する法改正・判例をチェックする仕組みの確立
労働法は常に変化し続けています。
厚生労働省や都道府県労働局のウェブサイトを定期的に確認しましょう。
また、労働法に詳しい社会保険労務士などの専門家と顧問契約を結ぶなど、常に最新の情報を入手できる体制を整えることも重要です。
社内でも、法改正や新たな判例に関する情報を共有し、定期的な勉強会を開催するなどして、全従業員、特に管理職の知識をアップデートしていくことが求められます。
有給休暇制度を柔軟かつ透明性高く運用する方法
従業員の働き方やライフスタイルは多様化しています。
時間単位年休やテレワーク制度など、既存の柔軟な働き方と有給休暇を組み合わせることで、従業員がより有給休暇を取得しやすくなる環境を整備しましょう。
有給休暇に関するルール、申請手続き、時季変更権の行使基準、年5日取得義務への対応方針など、運用プロセス全般を就業規則に明確に記載することも大切です。
従業員に分かりやすく周知することで、不要な誤解や不満を防ぎ、透明性の高い運用を心がけましょう。
有給休暇運用で労使間の信頼関係を築くポイント
有給休暇に関するトラブルの多くは、労使間のコミュニケーション不足や不信感から生じます。
日頃から上司と部下、人事担当者と従業員の間で、業務状況だけでなく、有給休暇の取得希望やキャリアプランについても定期的に話し合う機会を設けましょう。
有給休暇が「労働者の権利」であり、同時に「従業員のリフレッシュを通じて企業の生産性を高める資産」であるという共通認識を労使間で醸成することで、協力的な関係を築くことができます。
有給休暇管理を効率化するテクノロジー活用法
勤怠管理システムやHRテック(Human Resources Technology)を導入することで、有給休暇の管理を効率化できます。
これにより、従業員の有給休暇残日数や取得状況をリアルタイムで把握し、年5日取得義務の達成状況も自動で管理することが可能になります。
また、取得データを分析することで、特定の部署や時期に有給休暇が取得されにくい傾向がないかなどを把握し、改善策を検討するための根拠とすることもできます。
まとめ|有給休暇を巡る課題と法改正への継続的な対応策
ここまで、「知っておきたい!年次有給休暇のすべて」シリーズを通して、年次有給休暇を巡るさまざまなトラブル事例とその対処法を、労使双方の視点から深く掘り下げてきました。
従業員からの突然の申請や退職時の有給消化、企業側の取得制限や不利益取り扱い、そして年5日取得義務の未達成といった、日々の業務で起こり得る具体的なケースとその解決策を学んできたかと思います。
放置すると危険!有給休暇トラブルのリスクと対応策
有給休暇に関するトラブルは、一見すると些細なことに思えるかもしれません。
しかし、これらを放置すると、従業員のモチベーション低下や不満の蓄積を招きます。
最悪の場合、労働基準監督署からの指導や罰則、さらには訴訟といった大きなリスクに発展する可能性もあります。
これは、企業のイメージ悪化や優秀な人材流出にも繋がりかねません。
だからこそ、トラブルを未然に防ぎ、適切に対処することの重要性は計り知れません。
有給休暇取得が企業にもたらす効果とメリット
有給休暇は、単に法律で定められた義務ではありません。
従業員が心身ともにリフレッシュし、仕事への活力を養うための大切な時間です。
従業員が計画的に休暇を取得し、リフレッシュできる職場環境は、結果として企業の生産性向上にもつながります。
疲労が蓄積した状態では、ミスが増えたり、創造性が低下したりする可能性がありますが、適切な休息はこれを防ぎ、業務効率を高める効果があるのです。
最終的に目指すべきは、労使が協力し、働きやすい環境を構築することの意義を共有することです。
従業員が安心して有給休暇を取得できる職場は、エンゲージメントを高め、離職率を低下させ、企業の持続的な成長に貢献します。
このシリーズを通じて、有給休暇に関する正しい知識と運用方法を習得し、ぜひ貴社の健全な発展に役立ててください。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。


コメント