本記事は「あなたの働く人生を守るセーフティネット!雇用保険のすべて」シリーズの第9話です。第1話は👉雇用保険とは?何のためにある?|加入メリットや目的を解説
前回の記事では、失業保険の給付を受けるための第一歩として、あなたの退職理由が「自己都合」「会社都合」「特定理由」のどれに該当するのかを見極めることが重要だとお伝えしました。
前回の記事は👉退職理由で失業給付が変わる!自己・会社都合・特定理由の見極め
手続きの複雑さや給付制限期間の有無など、様々なルールがある中で、多くの方が一番知りたいのは「結局、自分はいくらもらえるのか?」ということではないでしょうか。
失業保険は、離職前の給料や勤続年数、退職時の年齢など、一人ひとりの状況に合わせて計算されます。
これは、失業期間中の生活を安定させるための、公平で合理的な仕組みです。
今回の記事では、その具体的な計算方法を分かりやすく解説します。
この記事を読めば、あなたの離職前の給料をもとに、もらえる給付額と給付日数を自分で計算できるようになるはずです。
この記事でわかること
- 計算の基本|失業保険の金額を決める「賃金日額」「給付率」「所定給付日数」の3要素
- 賃金日額の計算|離職前6ヶ月の賃金総額から1日あたりの基準額を割り出す方法
- 基本手当日額の決定|賃金日額が低いほど給付率が高くなる(最高80%)仕組み
- 所定給付日数|退職理由、年齢、加入期間に応じた給付期間(90日〜330日)の確認方法
失業保険の計算に不可欠な3つの要素
失業保険の金額は、以下の3つの要素によって決まります。
これらの要素を順に見ていくことで、最終的にもらえる給付金の総額を把握することができます。
- 賃金日額
- これは、あなたが離職する前の給与額から算出される、1日あたりの金額です。
- 賃金日額を正しく計算することが、失業保険の金額を割り出す上での最初のステップとなります。
- 給付率
- 賃金日額が算定されると、次にその金額に応じて「給付率」が決まります。
- 給付率とは、賃金日額のうち、給付金として受け取れる割合のことです。
- 実は、離職前の給与額が低い人ほど、この給付率が高くなるように設定されています。
- 所定給付日数
- これは、失業保険がもらえる期間を指します。所定給付日数は、あなたの退職理由(自己都合、会社都合など)、年齢、そして雇用保険の加入期間(被保険者期間)によって異なります。
ステップ1|賃金日額を計算しよう
失業保険の金額を計算する上で、まず最初に知るべきなのが「賃金日額」です。
これは、あなたが離職する前の1日あたりの平均的な賃金を表す金額で、失業保険の給付額を算定するための基準となります。
賃金日額とは?
以下の計算式で求めることができます。
賃金日額 = 離職前6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180
ここでいう「賃金総額」には、基本給だけでなく、通勤手当、残業代など、毎月支払われる手当のすべてが含まれます。
ただし、年2回支払われるようなボーナス(賞与)は、賃金総額には含まれませんので注意が必要です。
計算例と賃金日額の上限・下限
では、実際に具体的な例を使って計算してみましょう。
例|退職日が9月30日で、給料日が毎月25日の場合
この場合、離職前6ヶ月間の賃金総額は、4月から9月までの給与を対象とします。
- 4月25日支給分
- 350,000円
- 5月25日支給分
- 320,000円
- 6月25日支給分
- 300,000円
- 7月25日支給分
- 310,000円
- 8月25日支給分
- 310,000円
- 9月25日支給分
- 320,000円
これらを合計すると、賃金総額は1,910,000円となります。
- 賃金日額 = 1,910,000円 ÷ 180 = 10,611円
この「10,611円」が、あなたの賃金日額となります。
ただし、賃金日額には、離職時の年齢に応じて上限額と下限額が定められています。
これは、毎年8月1日に「毎月勤労統計」の平均給与額の増減を基準に見直され、その年の経済状況に合わせた給付水準になるよう調整されます。
これにより、給付額が極端に高くまたは低くならないように、制度の公平性が保たれているのです。
どれだけ多くの賃金を得ていても上限額を超えず、反対に賃金が少なかった場合でも下限額は保証されます。
賃金日額の上限額と下限額(令和7年8月1日改定)
| 年齢 | 上限額 | 下限額(全年齢共通) |
| 30歳未満 | 13,890円 | 2,746円 |
| 30歳以上45歳未満 | 15,440円 | 2,746円 |
| 45歳以上60歳未満 | 16,990円 | 2,746円 |
| 60歳以上65歳未満 | 15,800円 | 2,746円 |
先の例で算出した10,611円は、仮にあなたが35歳(30歳以上45歳未満)であれば、上限額15,440円を下回っていますそのため、そのまま10,611円があなたの賃金日額として適用されます。
具体的な金額は毎年見直されますので、最新の情報は厚生労働省のウェブサイトやハローワークで確認するようにしましょう。
賃金日額を決めるのは?
賃金日額は、離職者の賃金総額に基づいて、ハローワークの職員が算定します。
具体的には、退職者が提出した離職証明書に記載されている、離職前6ヶ月間の賃金総額を180で割って計算します。
この額を基に、個々の受給資格者証に「賃金日額」が記載されます。
ステップ2|給付率を適用して基本手当日額を計算しよう
賃金日額が分かったら、次に「給付率」を適用して、実際に1日あたりいくらもらえるのか(基本手当日額)を計算します。
基本手当日額とは?
基本手当日額とは、失業保険として1日あたりにもらえる金額のことです。
この金額に、後ほど解説する「所定給付日数」を掛けることで、最終的な受給総額がわかります。
給付率の仕組み
失業保険の給付率は、賃金日額の金額に応じて決まります。
基本的には、賃金日額が低い人ほど高い給付率(80%)が適用され、賃金日額が高くなるにつれて給付率が段階的に下がっていく仕組みです。
これは、賃金が低かった人でも、失業期間中の生活を安定して送れるようにするための、生活保障としての側面が強いためです。
この給付率のルールは、離職時の年齢によって大きく2つのパターンに分かれます。
60歳未満の方
29歳以下、30歳以上45歳未満、45歳以上60歳未満の3つの年齢区分に共通して適用される給付率の基本ルールです。
| 賃金日額の目安 | 給付率 |
| 賃金日額の下限額から約5,200円未満 | 80% |
| 約5,200円から約12,800円 | 80%から50%まで逓減 |
| 約12,800円から上限額まで | 50% |
賃金日額が5,200円から12,800円の間では給付率が段階的に下がりますが、その計算は非常に複雑です。
しかし、賃金日額が5,200円に近いほど給付率は80%に、12,800円に近いほど50%に近づくため、ご自身の賃金日額がこの範囲のどのあたりにあるかで、おおよその目安を把握することができます。
60歳以上65歳未満の方
この年齢区分では、賃金日額が比較的高い場合に給付率が異なります。
| 賃金日額の目安 | 給付率 |
| 賃金日額の下限額から約5,200円未満 | 80% |
| 約5,200円から約11,500円まで | 80%から45%まで逓減 |
| 約11,500円から上限額まで | 45% |
このように、60歳以上65歳未満の方は、賃金日額が11,500円を超えると、給付率が45%となります。
基本手当日額の計算方法と例
以下の簡単な計算式で求めることができます。
基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率
例えば、あなたの賃金日額が10,611円だったとします。
もしあなたが60歳未満であれば、上の表の「約5,200円から約12,800円まで」の範囲に入ります。
これは5,200円と12,800円のほぼ中間にあるため、給付率も80%と50%の中間あたり、おおよそ60%前後が目安となります。
その場合、基本手当日額は約6,300円程度となります。
ご自身の正確な給付額や基本手当日額は、離職票の情報を基に、ハローワークで決定されます。この記事は、ご自身がもらえる金額の目安を把握するためのものとしてご活用ください。
ステップ3|所定給付日数を確認しよう
基本手当日額を計算したら、次に「所定給付日数」を確認します。
この日数が、あなたが失業保険をもらえる期間を決定する重要な要素です。
所定給付日数とは?
所定給付日数とは、失業保険(基本手当)を受給できる期間のことです。
この日数は、以下の3つの要素によって決まります。
- 離職理由:自己都合退職、会社都合退職など
- 離職時の年齢
- 雇用保険の被保険者期間
雇用保険の被保険者期間とは?
被保険者期間とは、あなたが雇用保険に加入していた期間を指します。
失業給付金の受給資格を得るには、この被保険者期間が一定以上必要です。
一般的に、離職日以前の2年間に、雇用保険の加入期間が通算して12ヶ月以上あることが条件となります。
ただし、倒産や解雇などの会社都合で離職した場合は、離職日以前の1年間に通算して6ヶ月以上あれば、受給資格を得られます。
パターン別の給付日数表
ここでは、主な離職理由別に所定給付日数をまとめました。
自己都合退職(給付制限あり)
正当な理由がなく自己都合で退職した場合の給付日数です。
| 被保険者期間 | 給付日数 |
| 1年未満 | 支給対象外 |
| 1年以上5年未満 | 90日 |
| 5年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
会社都合退職(特定受給資格者)および特定理由離職者
倒産や解雇など、会社都合で退職した場合、または契約期間満了などの特定の理由で離職した場合の給付日数です。
この場合、離職時の年齢によって給付日数が変わります。
| 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ━ |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
最終ステップ|トータルでもらえる金額を計算しよう
いよいよ、これまでのステップで計算した数字を組み合わせて、あなたが受け取れる失業保険の総額を算出します。
合計受給額 = 基本手当日額 × 所定給付日数
この計算式で、失業期間中に受け取れるお金の総額がわかります。
実際の計算例でシミュレーション|モデルケース|Aさん
ここでは、具体的なモデルケースを挙げて、合計受給額を計算してみましょう。
- 年齢
- 35歳
- 雇用保険の被保険者期間
- 5年以上10年未満
- 離職理由
- 会社都合による退職(特定受給資格者)
- 離職前の賃金総額(直近6ヶ月)
- 1,910,000円
ステップ1|賃金日額を計算
まず、離職前6ヶ月の賃金総額から賃金日額を計算します。
- 1,910,000円 ÷ 180日 = 10,611円
ステップ2|基本手当日額を計算
次に、賃金日額に給付率をかけ、基本手当日額を算出します。
- 賃金日額10,611円は、60歳未満の「約5,200円から約12,800円」の範囲に該当するため、給付率は80%から50%の間で逓減します。
- おおよそ60%前後が目安となります。
- 10,611円 × 約60% = 約6,366円(基本手当日額)
ステップ3|所定給付日数を確認
最後に、年齢と被保険者期間から所定給付日数を確認します。
- 35歳、被保険者期間が5年以上10年未満のため、所定給付日数は180日となります。
最終ステップ|合計受給額を計算
基本手当日額と所定給付日数を掛け合わせます。
- 約6,366円 × 180日 = 1,145,880円(合計受給額)
このケースでは、約114万円の失業保険を受け取れる目安となります。
まとめ|自分でできる失業保険の計算と給付額チェック
失業保険の金額は、離職前の給料だけでなく、年齢や勤続年数、そして離職理由によっても大きく変わることがお分かりいただけたかと思います。
この記事を参考に、自分自身でシミュレーションしてみることで、不安なく再就職活動を進めることができるでしょう。
もし、ご自身の離職理由や被保険者期間に不安がある場合は、ハローワークでしっかり相談することが一番確実な方法です。
次回予告|失業認定日とは?忘れずにハローワークへ行こう
失業保険の金額が分かっても、それだけでは給付を受けることはできません。
失業手当をもらうためには、「失業認定日」にハローワークへ行き、失業していることを申告する必要があります。
次回は、この「失業認定日」の具体的な内容や、忘れた場合のペナルティなど、知っておくべき重要なポイントを解説します。
次回の記事は👉失業認定日とは?失業手当の確実な受給のために|求職活動・持ち物・給付不認定の対応を徹底解説
お楽しみに。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|29240010号)
- 会社員歴30年以上、転職5回を経験した氷河期世代の社会保険労務士です。自らが激動の時代を生き抜いたからこそ、机上の空論ではない、働く人の視点にたった情報提供をモットーとしています。あなたの働き方と権利を守るために必要な、労働法や社会保険の知識、そしてキャリア形成に役立つヒントを、あなたの日常に寄り添いながら、分かりやすく解説します。
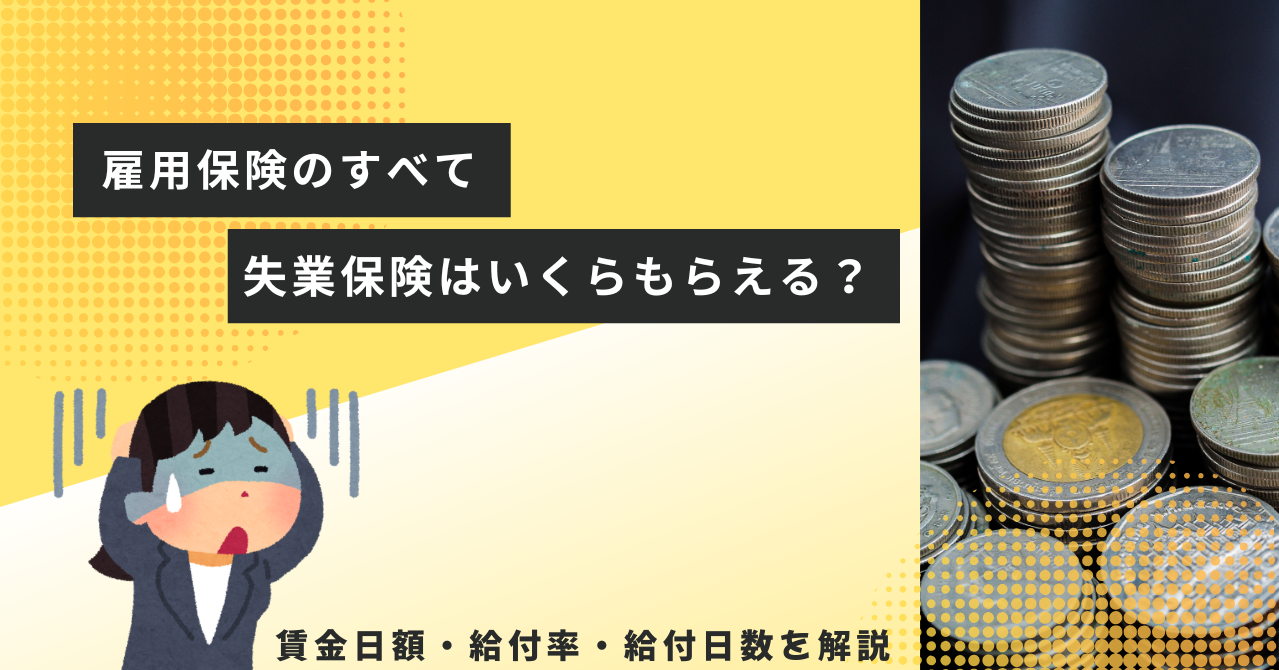
コメント