本記事は「あなたの働く人生を守るセーフティネット!雇用保険のすべて」シリーズの第21話です。第1話は👉雇用保険とは?何のためにある?|加入メリットや目的を解説
前回の記事では、雇用保険のセーフティネット外にいる方が、生活費の不安なく新しいスキルを習得できる国の強力な支援「求職者支援訓練」を解説しました。
前回の記事は👉求職者支援訓練|職業訓練受講給付金で学びながら再就職支援
これで、キャリアをリセットして再挑戦する方への道筋は明確になったはずです。
しかし、一方で、多くの方が抱えるのは、「今は仕事を辞めるつもりはないけれど、将来のためにスキルアップしたい」という切実な悩みでしょう。
キャリアアップに意欲的な在職中の方もまた、「学びたいが、時間がない、費用が高い」という共通のジレンマに直面しています。
「このままでいいのか」という漠然とした不安。
数年後のAI時代に向けたスキルの陳腐化の懸念。
そして「学びたい気持ちはあっても、平日の日中に時間を取るのは現実的ではない」という時間的な制約。
働きながら自己投資をしたいけれど、どうすればいいか分からない――。このジレンマに悩む方は少なくありません。
この記事でわかること
- 在職者訓練の概要|仕事を辞めずに夜間・土日などを利用し、短期間で安価に専門スキルを習得する仕組み
- 在職者訓練の対象者と特徴|主に中小企業に在職する方が対象であり、現職務のスキルアップを目的としている
- コースの柔軟性|ポリテクセンターなどで開催される、夜間や土日など仕事と両立しやすいコースの探し方
- 費用負担をゼロにする交渉術|訓練を会社の研修として位置づけ、費用負担を依頼する具体的なアプローチ
- 申込みのステップ|複雑な書類が不要なシンプルな手続きと、事業主推薦を活用するメリット
働きながらスキルアップできる「在職者訓練」とは?社会人の学び直しを支える制度
本記事の焦点は、まさにこの「仕事を辞めずに、キャリアを確実に前に進めたい」すべての方を対象とした国の支援、「在職者訓練(能力開発セミナー)」にあります。
この制度の最大の価値は、短期間(1〜5日程度)の訓練が、主に夜間や土日に設定されており、仕事との両立が容易であることです。
さらに、国が運営するため受講料が非常に安価です。
これにより、あなたは「時間的な制約」と「高額な自己投資費用」という二重の壁を乗り越え、新しい技術を身につけることが可能になります。
本記事では、この「在職者訓練」の制度概要から、仕事と両立しやすい夜間・土日コースの具体的な探し方、さらには会社に費用を負担してもらうための賢い交渉術までを網羅的に解説します。
費用と時間の不安を解消し、働きながら確実なスキルアップを実現しましょう。
リスキリング時代に必須!なぜ今、働きながらスキルアップすることが重要なのか
「仕事を辞めずにキャリアアップしたい」「夜間や土日に学べる制度はないか?」という在職者の切実なニーズは、変化の激しい現代において、もはや共通の課題です。
年功序列が崩れ、個人のスキルが評価される時代において、自己投資の有無がキャリアの明暗を分けると言っても過言ではありません。
しかし、外部のビジネススクールや専門講座は費用が高く、平日の日中に行われることが多いため、多忙な現役世代にとってはハードルが高すぎます。
その切実な悩みを解決し、仕事とスキルアップの両立を可能にする国の強力な支援こそが、「在職者訓練(能力開発セミナー)」です。
これは、国や公的機関が職業能力開発促進法に基づき、現役世代のスキルアップをサポートするために提供している公的制度です。
本記事を読み進めることで、あなたは「仕事で疲れているから」「時間がないから」という理由で学びを諦める必要がなくなります。
制度の概要から、夜間・土日のコース、そして会社に費用を負担してもらうための賢い活用法までを網羅的に解説し、あなたのキャリア再構築を力強く後押しします。
在職者訓練(能力開発セミナー)の全体像と主な特徴
在職者訓練は、個人のキャリアアップはもちろん、主に中小企業の人材育成を国が支援するための公的制度です。
まずは、この訓練がどのようなもので、なぜ働きながら学ぶ人に最適なのか、その全体像を理解しましょう。
在職者訓練の定義と目的|仕事に直結する専門スキルを短期間で習得
この在職者訓練は、職業能力開発促進法に基づいて、公共職業能力開発施設(ポリテクセンターなど)や都道府県が提供しています。
- 定義と対象
- 主に中小企業に勤める方を対象とした職業訓練です。
- フリーランスや個人事業主は、原則として対象外です。
- 短期間で集中的に学ぶ形式
- その期間は一般的に1日から5日程度と短く設定されており、長期間の通学は不要です。
- 目的
- 現在従事している業務に必要な専門知識や技能・技術の向上を図ることを最大の目的としています。
在職者訓練の対象となる「中小企業等」とは?零細企業も利用できるのか
この制度の主な対象は「中小企業等に在職する方」ですが、その定義は広く、ご自身の会社が当てはまるかどうかが重要です。
- 中小企業(零細企業含む)の具体的な定義
- この訓練における「中小企業等」の定義は、中小企業基本法に準じます。
- あなたの会社が以下の基準の「資本金」または「従業員数」のどちらか一方を満たしていれば、零細企業や小規模な企業を含め、対象となります。
| 業種 | 資本金または出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
| 製造業、建設業、運輸業など | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
- 大企業に勤めている場合は原則対象外
- 原則として、大企業に在職している方は、在職者訓練のメインの対象外です。
- ただし、自治体やポリテクセンターによっては、定員に余裕がある場合などに一般の在職者(大企業の方を含む)の受講を受け付けているケースもあります。
- 詳細は、各実施機関のホームページで確認が必要です。
在職者訓練の最大のメリット|仕事と両立できる柔軟性と低コストの学び
対象者であることが確認できたら、この制度の強力なメリットを活用しましょう。
- 仕事との両立が可能
- 訓練コースの多くは、夜間や土日に集中して開催されています。
- 日中の業務を休むことなくスキルアップに時間を充てられるため、現在の仕事を辞める必要がありません。
- 受講料が比較的安価
- 国や公的機関が運営しているため、民間スクールと比較して受講料が非常に安価です。
- 業務に直結する多様な分野をカバー
- 講座内容は、ものづくり系から、現代ビジネスに必須のIT・Webスキル、OA事務、マネジメントまで、企業の需要が高い多様な分野をカバーしています。
【実践】在職者訓練で仕事と両立!具体的なコース内容と費用の目安
在職者訓練の最大の魅力は、仕事に支障なく受講できるコースの柔軟性と、公的制度ならではの低コストにあります。
ここでは、どこで、どのようなコースが受けられるのか、実践的な情報を見ていきましょう。
訓練の実施機関とコースの探し方
- 実施機関
- 中心となるのは、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が運営するポリテクセンターと、各都道府県が設置・運営する職業能力開発センターです。
- コース名の多様性
- 探す際は、「能力開発セミナー」「スキルアップ講習」「キャリアアップ講習」など、複数の名称で検索が必要です。
業務に直結する具体的なコース例
訓練内容は、企業の即戦力ニーズに合わせて企画されており、受講後すぐに業務で活かせる実践的なスキルが中心です。
| 分野 | コース例 |
| ITスキル | 実践Webデザイン、Pythonプログラミング入門、Excelデータ分析 |
| ものづくり | IoT技術、最新の溶接技術、シーケンス制御、機械保全 |
| ビジネススキル | 管理監督者向けリーダーシップ、生産管理、品質管理(QC) |
どこで受講できる? 居住地と勤務地での比較検討が鍵
在職者訓練を探す際、「自身の住所の都道府県」と「勤務先の都道府県」のどちらを基準にすべきか迷うかもしれませんが、原則としてどちらの訓練を受けても問題ありません。
重要なのは、あなたが「無理なく通えるか」という物理的なアクセスです。
| 検索基準 | メリット | こんな方におすすめ |
| 勤務先の都道府県 | 仕事の後に直行しやすく、時間を有効活用しやすい。 | 平日の夜間コースの受講を検討している方。 |
| 自身の住所の都道府県 | 土日など、休日に自宅から通いやすい。 | 土日開催の集中コースや、会社の場所から遠く離れている方。 |
賢い受講方法
まずは、「居住地」と「勤務地」の両方を管轄するポリテクセンターや職業能力開発センターのホームページで、開催されているコースと時間割を比較検討してください。
コース内容や開催曜日が、どちらかの地域に偏っている場合もあるため、比較することで最も良い機会を見つけられます。
受講料の目安|求職者訓練との決定的な違い
求職者訓練(離職者向け)とは異なり、在職者訓練は原則として有料です。
- なぜ有料なのか?
- これは、在職者訓練が「生活支援」ではなく、「現職務のスキルアップ」という自己投資を目的としているためです。
- 受講料の目安
- 有料ではありますが、国や公的機関が運営しているため、民間スクールに比べて受講料は非常に安価に抑えられています。
- 多くの場合、1日あたり数千円から1万円程度で受講可能です。
- 費用負担をゼロにする方法
- しかし、ご安心ください。次章で解説しますが、在職者訓練は「会社の研修・教育制度」として費用を負担してもらうことが可能です。
- あなたの自己負担を実質的にゼロにするための賢い交渉術が、この制度の最大の活用ポイントとなります。
申込みをする際は、必ず各実施機関の公式ホームページで、受講料の総額と、テキスト代などの別途実費の有無を確認するようにしてください。
在職者訓練の費用を会社に負担させる!賢い活用法と交渉術
在職者訓練は有料ですが、あなたの自己負担を実質的にゼロにするための最も効果的な方法があります。
それは、この訓練が持つ「企業の人材育成」という側面に注目し、会社を巻き込むことです。
この訓練は、単なる個人の自己啓発ではなく、企業の生産性向上に直結する専門スキル習得を目的としています。
この点を最大限に活用し、会社に費用を負担してもらいましょう。
在職者訓練の費用負担交渉の準備|会社の利益になる裏付けを作る
上司や人事担当者に相談する前に、以下の準備を行い、「なぜ会社が費用を出すべきか」を具体的に説明できるようにすることが成功の鍵です。
- 業務貢献度の明確化
- 受講したいコースで習得するスキルが、あなたの現在の業務の課題解決や、将来の部署の目標達成にどう貢献するのかを、具体的かつ論理的に説明できるように準備します。
- コース内容の徹底理解
- 訓練のカリキュラムや、講師が持つ専門性について詳しく把握し、「このスキルは社内では教えられない」という外部研修の必要性を強調できるようにします。
会社への依頼方法|公的制度を「武器」に交渉する
交渉の際は、個人的な要望としてではなく、公的な制度の活用として提案することが重要です。
- 受講の必要性を提案する
- まず、上司や人事担当者に対し、習得したいスキルと、それがいかに会社にとって重要かを熱意をもって提案します。
- 「事業主推薦」制度の存在を伝える
- この在職者訓練は、「事業主推薦(企業推薦)」による受講が可能であり、会社が従業員を研修として派遣することを国が推奨している公的な制度であることを明確に伝えます。
- これにより、「個人的な要望」から「会社の公的な研修機会」へと位置づけが変わります。
- 研修・教育制度としての費用負担を依頼
- 公的訓練である点を根拠に、受講料を会社の研修費用や福利厚生費として負担してもらうよう依頼します。
- 会社側も、従業員のスキルアップを支援することで、優秀な人材の確保や離職防止といったメリットを得られるため、交渉の成功率は高まります。
このアプローチを取ることで、あなたは費用面での心配なくスキル習得に専念できる環境を整え、キャリアアップを実現できるでしょう。
在職者訓練の受講までの具体的ステップと注意点
在職者訓練は、ハローワーク経由の求職者訓練とは手続きが異なります。
会社に費用負担の交渉をするためにも、以下のステップを順序立てて進め、確実に受講の機会を獲得しましょう。
在職者訓練ステップ1|情報収集とコース選定のポイント
- 情報収集の拠点
- ポリテクセンターや各都道府県の職業能力開発センターの公式ホームページで、夜間や土日に開催されるコースに絞り込んで探します。
在職者訓練ステップ2|申込みと選考
受講したいコースが決まったら、いよいよ申込みです。
- 提出書類は非常にシンプル
- 離職者向けの求職者訓練(給付金あり)と異なり、在職者訓練では収入や資産を証明する複雑な書類(所得証明書や預貯金通帳の写しなど)は一切不要です。
- 受講申込みには、基本的に「受講申込書」の提出と受講料の支払いが必須となります。
- 申込み方法の確認
- 「個人での申込み」、または会社に費用負担を依頼した場合は「事業主推薦による申込み」のいずれかで行います。
- 事業主推薦の場合は、会社の推薦書(捺印が必要な場合がある)などの提出が求められます。
- 募集期間と定員を逃さない
- 人気コースはすぐに定員に達します。
- 募集期間を厳守し、迅速な申込み手続きを心がけましょう。
在職者訓練の受講に必要な重要条件
在職者訓練の申込みをする前に、以下の対象者要件を満たしているかを確認してください。
- 基本的な対象者
- 基本的に、中小企業等に在職中であり、「現職務の能力向上」を望む方が対象です。
- あなたの会社が中小企業の定義に該当することが大前提です。
- コースごとの細かい条件
- 訓練コースによっては、「特定の業務経験○年以上」など、さらに細かい受講条件が設定されている場合があります。必ず募集要項の記載を確認してください。
まとめ|在職者訓練の価値とキャリアアップへの一歩
本記事では、仕事を辞めずにキャリアを前に進めたい在職者を対象とした「在職者訓練(能力開発セミナー)」について解説しました。
在職者訓練は、求職者向けの訓練とは異なり有料ではありますが、その「低コスト」と「仕事との両立のしやすさ」は、他の自己投資手段にはない大きな魅力です。
この制度を活用することで、あなたは時間と費用の両面において、最も効率的に業務直結スキルを習得できます。
特に、費用を会社に負担してもらうための賢い交渉術を実行すれば、自己負担ゼロでのスキルアップも夢ではありません。
新しい技術の習得は、あなたの市場価値を高め、将来のキャリア選択肢を広げるための強力な武器となります。
あなたのキャリアアップに向けた第一歩は、情報収集から始まります。
まずは、ポリテクセンターまたは各都道府県の職業能力開発センターのホームページで、あなたの地域で開講されている夜間・土日コースをチェックしましょう。
そして、受講したいコースが決まったら、会社への相談の準備を始め、このチャンスをぜひ掴み取ってください。
次回予告|定年後も安心して働く!高齢者と雇用保険の全知識
さて、これまで私たちは、離職者を対象とした訓練(公共職業訓練・求職者支援訓練)から、在職者向けのスキルアップ支援(在職者訓練)まで、幅広い世代のキャリア支援策を解説してきました。
次回は、いよいよ「高齢者」に焦点を当てます。
60歳以降も働き続けることが一般的となった今、「定年後も安心して働く」ための知識は不可欠です。
次回からは、60歳以上で再雇用された方や、定年退職を迎える方を対象とした、雇用保険の強力な支援策である「高年齢雇用継続基本給付金」や、高齢者が再就職を目指す際に受け取れる「高年齢求職者給付金」など、シニア層の働き方を経済的にサポートする制度を深掘りしていきます。
知っていると知らないとでは、手取り額や生活の安心感に大きな違いが出ます。
次回の記事は👉2025年4月1日改正|高年齢雇用継続基本給付金で手取り減を防ぐ
経済的な安心を得るための、60歳以降の雇用保険の知識にご期待ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|29240010号)
- 会社員歴30年以上、転職5回を経験した氷河期世代の社会保険労務士です。自らが激動の時代を生き抜いたからこそ、机上の空論ではない、働く人の視点にたった情報提供をモットーとしています。あなたの働き方と権利を守るために必要な、労働法や社会保険の知識、そしてキャリア形成に役立つヒントを、あなたの日常に寄り添いながら、分かりやすく解説します。
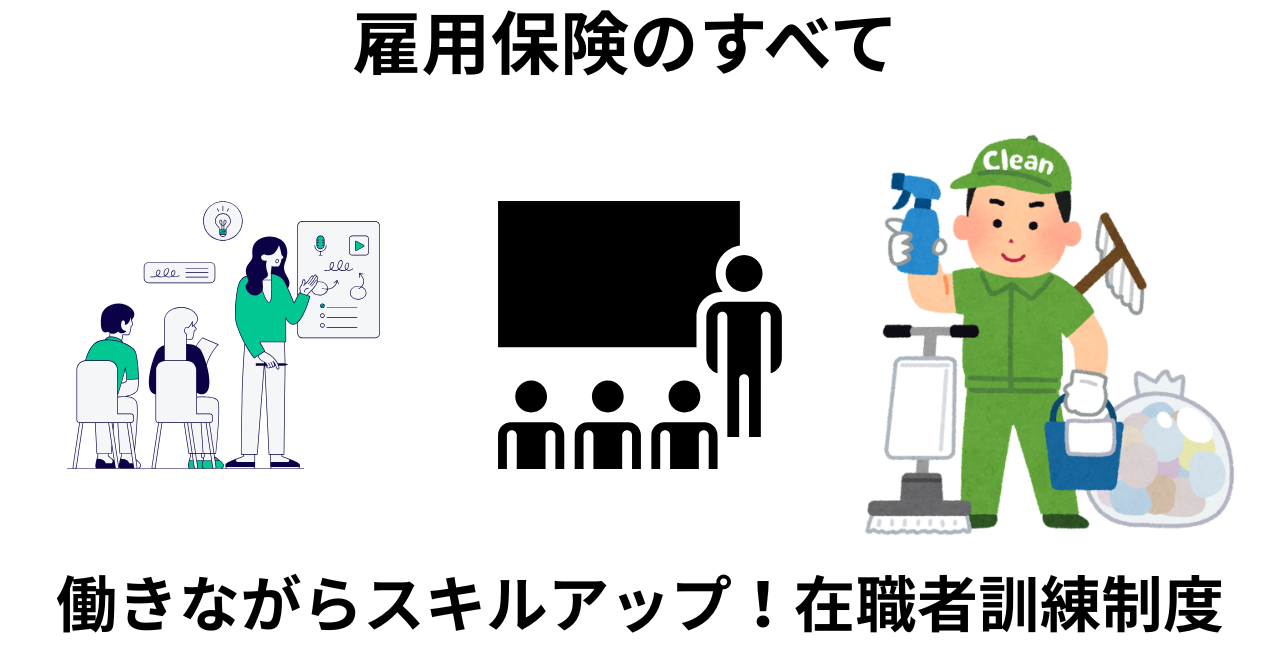

コメント