本記事は「インフルエンザ・コロナと企業の安全配慮義務」シリーズの第7話です。
シリーズの他の記事は👉インフルエンザ・コロナ対策と企業の安全配慮義務|実務ガイド
前回の記事で、予防接種への資金投入という「命の保険」と、就業規則から独立した『感染症対策ガイドライン』という「事業継続の盾」の必要性を解説しました。
前回の記事は👉企業が取るべき感染症対策|マスク・換気・休憩時の行動ルール
企業が安全配慮義務を果たすための「ルール作り」の青写真は、これで整ったと言えます。
しかし、ルールは作っただけでは機能しません。
法律上の強制力がなくなり、マスク着用や隔離が個人の判断に委ねられた今、ガイドラインが直面する最大の壁は、「従業員の納得感と自発的な協力(コンプライアンスの向上)」です。
人事担当者のジレンマはここにあります。
集団感染を防ぐためのルールが、従業員の反発や「監視されている」という感情を招けば、かえって職場内の信頼が損なわれ、ルールの形骸化を招いてしまいます。
本記事は、この「理論と現場のギャップ」を埋めるための実務的な運用ノウハウを提示します。
ここでは、過去の企業対応の成功事例と失敗事例を徹底的に分析します。
これにより、ガイドラインを単なる紙の文書ではなく、従業員からの信頼を勝ち取り、有事の際に確実に機能する「生きたルール」に変えるための、現場で使える具体的なコミュニケーション技術と運用戦略を習得します。
この記事でわかること
- 感染症対策で企業が陥りやすい失敗例
- 失敗を防ぐための具体的な手順や注意点
- 成功事例から学べる、実務で取り入れやすい工夫
- 従業員の協力を引き出す施策のポイント
- 安全配慮義務を守りながら信頼関係を築く方法
感染症対策の成功事例|マスクの自発的着用率を高めた“配慮の訴求”術
法律上の強制力がない時代、企業がルールを「押し付け」ようとすれば、必ず反発が生まれます。
実効性の高いガイドラインとは、従業員が自ら「協力したい」と思える動機付けを提供することに尽きます。
ここでは、「強制」を避け、「相互扶助」の精神と「柔軟な選択肢」を提供することで、高い着用率と業務継続性を両立させた2つの成功事例を解説します。
事例紹介|製造業A社の感染症対策(高齢者・基礎疾患リスクの「見える化」でマスク着用を促進)
A社の課題|相互扶助の精神の欠如
一律のマスク着用推奨を廃止した後、製造業A社では、特に流行拡大期において職場の着用率が低迷しました。
その結果、匿名ではあるものの、高齢の従業員や基礎疾患を持つハイリスク層から、「自分の命を守るための配慮が失われている」といった強い不安の声が人事部門に寄せられ始めました。
ルールだけでは、個々の「配慮」を引き出せないという課題に直面したのです。
成功の鍵|「守るべき同僚」の存在を具体的に訴求
A社が採ったのは、ルールではなく倫理観に訴えかける戦略です。
- リスクの数値化と共有
- 匿名性を厳守しつつ、「全従業員の約20%が、重症化リスクの高い年齢層または基礎疾患を申告しています」といった社内のハイリスク従業員の割合を具体的な数値で全社に公開しました。
- メッセージの転換
- メッセージングを「会社の指示」から「相互扶助の精神」へと転換しました。
- 「マスク着用は、あなた個人のためだけではありません。私たちはチームです。このチームの継続と、ハイリスクな仲間の安心を確実にするための配慮として、着用にご協力ください。」
- メッセージングを「会社の指示」から「相互扶助の精神」へと転換しました。
このメッセージにより、従業員の行動は「義務」から「同僚への思いやり」へと変わり、非着用者への非難ではなく、「配慮の輪」が広がりました。
強制をゼロにしたにも関わらず、有事の推奨時における着用率は90%以上に回復。
従業員の自主的な協力によって、ガイドラインが持つ実効性が飛躍的に高まりました。
事例紹介|IT企業B社(マスク着用を“選択肢”として扱う柔軟な感染症対策)
B社の課題|コミュニケーション阻害への抵抗
IT企業B社は、日常的なブレインストーミングやクライアントとの密な対話が必須のクリエイティブな職種が多く、従業員から「マスクは表情や声のトーンを隠し、創造的なコミュニケーションを阻害する」という強い抵抗がありました。
流行拡大期でも、一律の着用推奨が業務効率やエンゲージメントを下げるリスクがあったのです。
成功の鍵|「配慮の選択肢」としてルールの多様性を提供
B社は、リスク回避を「マスク着用」という単一の行動に限定せず、複数の「配慮の選択肢」を提供することでこの課題を克服しました。
- 環境による選択肢の提供
- 非着用者向けの配慮として、換気が徹底されたオンライン会議ブースや、周囲との距離が確保された個別換気席といった物理的な環境を整備しました。
- 行動による代替案の明示
- ガイドラインの着用推奨が発動した際でも、「会議中にマスクを着用する」という指示だけでなく、「オンラインで参加する」「会議の場所を換気の良い大部屋に変更する」といった代替行動を明確に示しました。
これにより、従業員は「会社に強制されている」と感じることなく、「業務の性質に合わせて、最も効果的で負担の少ないリスク低減策」を自ら選べるようになりました。
結果として、従業員エンゲージメントを損なうことなく、業務の性質を考慮した上での適切なリスク低減行動が定着し、業務継続性が向上しました。
この二つの事例が示すように、実効性の鍵は「いかに上手にルールを強制するか」ではなく、「いかに自主的な行動変容を促すコミュニケーションを行うか」にあります。
感染症対策の失敗事例|マスク着用をめぐる反発が招いた“集団感染リスク”の落とし穴
どれほど論理的で完璧なガイドラインを作成しても、その運用方法を誤ると、従業員からの信頼を失い、かえって職場内の混乱と反発を招きます。
特に「推奨」と「強制」の境界線が曖昧になる運用は、ハラスメントリスクに直結します。
ここでは、明確な意図を持ちながらも、運用で失敗し、集団感染リスクを抑えられなかった2つの事例を分析します。
事例紹介|サービス業C社(マスク着用を“懲罰的”に扱った結果、職場が分断)
C社の課題と失敗の原因
サービス業C社では、流行拡大期に一部の従業員がマスク着用推奨を無視する動きが出始めました。
これに対し、人事部門はルールの実効性を高めようと、策定したガイドラインの文言を以下のように強化しました。
失敗の原因となった文言
「全社推奨期間中、正当な理由なく着用推奨事項に違反した場合、人事評価に影響を与える場合がある。」
結果と教訓|ハラスメントリスクへの直結
この一文が致命的な反発を招きました。
従業員からは、「推奨ではなく、これは事実上の強制だ」「着用しない自由を奪い、それを不当な評価基準に利用している」「これはパワーハラスメントに当たるのではないか」といった声が噴出しました。
結果として、ルールの正当性が完全に崩壊し、推奨に従った従業員と従わなかった従業員の間に激しい軋轢(あつれき)が生じ、職場環境が悪化しました。
教訓
労働契約法に基づく安全配慮義務は、従業員の生命と健康を守るための環境整備を求めるものであり、懲戒や不利益処分を伴うものではありません。
推奨ルールに懲戒や人事評価を絡めることは、安全配慮義務の範囲を超え、ハラスメントリスクに直結する最大の落とし穴です。
失敗事例|不動産業D社(マスク・換気ルールの周知不足が招いた職場混乱)
D社の課題と失敗の原因
不動産業D社は、前回の記事で解説したCO2濃度基準など、科学的根拠に基づいたガイドラインを策定しました。
しかし、ルール作成に満足し、その後の周知徹底のプロセスを大きく省略しました。
失敗の原因は、ガイドラインを全従業員にメールで一斉送信しただけで、ルールの「意図」と「発動条件」に関する現場マネージャーへの説明会や研修を省略したことにあります。
結果と教訓|現場の解釈のばらつきによる軋轢
有事の発動条件(例:社内感染率5%超)が満たされ、全社推奨が発動された際、現場では以下のような混乱が発生しました。
- ある上司は「マスクは強制だ」と断言。
- 別の部門の上司は「個人の判断に任せる」と無関心。
- 「なぜ会議室のCO2濃度が1,000ppmを超えたら人数制限が必要なのか」という科学的な根拠が現場に共有されておらず、ルールがただの「お達し」として扱われました。
ルールがバラバラに解釈された結果、部署間や上司・部下の間で軋轢が生じ、本来守られるべき感染対策の統一行動が取れず、集団感染リスクを効果的に抑えることができませんでした。
教訓
策定したガイドラインが現場で機能するか否かは、現場マネージャーの理解度にかかっています。
ルールはトップと人事だけでなく、すべての管理職に対し、ルールの「意図」と「発動条件」を徹底的に研修し、全社で統一した認識を持つことが不可欠です。
職場での感染症対策ガイドライン運用|失敗を防ぐ3つの実務ポイント
ガイドラインの運用で最も避けなければならないのは、ルールが「従業員間の軋轢(あつれき)」や「ハラスメント」の温床になることです。
成功事例の知見と失敗事例の教訓を活かし、あなたの会社が取るべき具体的な運用技術を3つの鍵として解説します。
1. マスク非着用者への攻撃を防ぐ防御ルールの徹底|職場感染症対策の実務ポイント
「配慮」を促す推奨ルールを設ける場合、その裏側には必ず「配慮しない人」を非難してはいけないという防御壁が必要です。
推奨ルールの運用が、従業員間の「マスク警察」を生み出し、職場の雰囲気を悪化させては本末転倒です。
具体的な明記と位置づけ
「着用」も「非着用」も個人の選択であり、その選択を他者が侵害することは許されないという原則を明確にします。
- 明文化の徹底
- ガイドラインにはもちろんのこと、実効性を高めるために、就業規則の懲戒規定またはハラスメント防止規定において、「他者の着用選択・非着用選択を非難する行為はハラスメントとして対応する」旨を明確に明記します。
- これにより、従業員の行動に対する抑止力と、会社としての強い姿勢を示せます。
相談窓口の設置と周知
従業員が不安や被害を訴える場を明確にすることで、潜在的なハラスメントを早期に検知し、エスカレートを防ぎます。
- 窓口の明確化
- マスク着用に関する「ハラスメント相談窓口」を明確にし、従業員が匿名で安心して相談できるルートを確保します。
- これは、非着用者が攻撃されたケースだけでなく、過度な強制をされたケース(失敗事例C社のような上司による「事実上の強制」)にも対応する窓口となります。
2. 感染症対策における発動条件の明確化|客観性と透明性を保つ実務手順
ルールが現場で受け入れられるかどうかは、ルールの発動や解除の基準がどれだけ客観的で透明かにかかっています。
曖昧な判断は「恣意(しい)的だ」「会社に都合が良い」といった不信感を生み、ルールの信頼性を著しく損ないます。
発動・解除の透明性
ルール運用を感情論から切り離し、データと根拠に基づいた信頼性の高いものにします。
- 客観的根拠の明示
- ルールの発動や解除のタイミングは、自治体が発表する公式な警報レベルや社内の客観的なデータ(CO2濃度、感染率など)といった根拠を添えて全社に通知します。
- 迅速な情報公開
- 発動条件が満たされたら速やかに、どのデータに基づいて決定したのかを全従業員が確認できる形で公開します。
「経営判断」の明確化
社内感染率などの主観的な要素を含む基準で発動する場合、その目的を曖昧にせず明確に伝えます。
- 目的の訴求
- 社内感染率で発動する際は、「〇%を超えたため、業務停止を回避し、事業継続を確実にするために推奨を発動する」と、安全配慮義務の履行という目的と、経営上の必要性を明確に伝えます。
- これにより、推奨が従業員個人の自由を奪うためではなく、会社全体を守るための協働であることを理解してもらいます。
3. 職場感染症リスク低減のための換気見える化と従業員教育の実務手法
従業員の安全配慮義務を履行する上で、空気環境の整備は不可欠です。
しかし、費用をかけた換気設備も、従業員にその効果が伝わらなければ「ただの費用」で終わってしまいます。
CO2濃度の掲示による「見える化」
換気を感覚的なものから科学的なものへと変えます。
- CO2濃度計の活用
- 会議室や密集しやすいスペースにCO2濃度計を設置し、数値をリアルタイムで表示します。
- これにより、換気状態が良好か否かを、誰の目にも明らかにし、従業員自身が「今、この部屋はリスクが高い状態だ」と判断できる環境を提供します。
- 行動の誘発
- 濃度が基準値(例:1,000ppm)を超えた場合に、従業員が自発的に窓を開けたり、会議を切り上げたりする行動を促すトリガーとなります。
「換気の教育」による行動変容
「1,000ppm」という数字が何を意味するのかを理解してもらうことで、ルールに対する納得感を深めます。
- 知識の共有
- CO2濃度が1,000ppmを超えることは、室内に滞留する人の吐く息の量が増えている(換気不足)、つまりウイルスを含むエアロゾルを吸い込むリスクが高まっていることを意味することを、全従業員に教育します。
このように、ルールと環境の「見える化」、そしてそれらがなぜ必要なのかという「教育」を組み合わせることで、企業は法的な義務に依らず、データと根拠に基づいた信頼性の高い感染対策の基準を確立できるのです。
まとめ|感染症対策で従業員の信頼を築く企業姿勢と職場運用のポイント
企業の感染症対策は、「予防接種への資金投入」(前々回の記事)という従業員の重症化・死亡リスクを回避する「命の保険」と、「感染症対策ガイドライン」(前回の記事)という集団感染による事業の停滞リスクを回避する「実務上の盾」の二つが揃って初めて機能します。
本記事で成功事例・失敗事例を分析した結果、実効性の鍵は、ルールを「罰則」としてではなく、「高齢者やハイリスク層の仲間を守るための相互扶助のツール」として運用することにあると判明しました。
安定した事業継続を支える信頼の構築|感染症対策で従業員の協力を最大化
従業員の協力とコンプライアンスを最大化する運用とは、以下の原則に基づいています。
- 強制ではなく、倫理観の訴求
- 失敗事例(C社)のように懲罰的な表現を用いるのではなく、成功事例(A社)のように「チームの継続」と「同僚への配慮」として協力を求めることで、自発的な行動を促します。
- 客観的な根拠と透明性
- ルールの発動・解除は、感情や曖昧な判断に依らず、自治体の警報レベルやCO2濃度計の数値といった客観的なデータに基づいて行い、その決定過程を全従業員に公開します。
- 防御ルールの徹底
- 推奨ルールと同時に、非着用者への攻撃を明確に禁じるハラスメント防止の防御ルールを徹底することで、従業員が安心して働ける職場環境を守ります。
感染症リスクを年間対策に|職場で実践するリスクマネジメント
感染症対策は、一時的な対応ではなく、季節性インフルエンザと同様に年間を通じて存在するリスクマネジメントとして定着すべき「ニューノーマル」です。
本記事で得た理論と事例を組み合わせることで、貴社は法的な義務に依らず、データと根拠に基づいた信頼性の高い感染対策の基準を確立できます。
この体制こそが、労働契約法に基づく安全配慮義務を全うし、従業員の信頼を確保し、どのような感染症の波が来ても安定して業務を継続できる強固な企業姿勢を確立することにつながります。
次回予告|冬シーズン総まとめ・チェックリスト|ガイドラインを実効化する「冬前の行動リスト」
感染症対策は、予防接種という「命の保険」、ガイドラインという「実務の盾」、そして運用事例という「成功のノウハウ」を経て、いよいよ最終段階に入ります。
次回の記事では、これまでの理論や事例をすべて集約し、人事・労務担当者が冬の流行期前に迅速かつ確実に実行すべき、具体的な行動チェックリストとして提供します。
法律上の強制力がない今、冬場の集団感染は企業にとって最大の試練です。
冬の流行期に備えるための最終点検項目
- 発動ルールの最終確認
- 有事の推奨ルールをスムーズに発動させるための、客観的基準の最終確定リスト。
- オフィス環境の緊急点検
- CO2濃度計の設置状況、加湿設備の確認、消毒備蓄量の確保など、物理的対策の総点検項目。
- そのまま使える通達テンプレート
- 従業員への健康管理再徹底、休憩・食事ルール、予防接種の推奨に関する社内マニュアルや通達でそのまま使える文例集。
このチェックリストを活用することで、貴社は感情論ではなく、データと根拠に基づき、冬の感染症リスクを確実に抑え込み、安定した事業継続の基盤を確立できるでしょう。
次回の記事は👉冬の感染症対策|企業向け安全配慮義務チェックリスト(インフル・コロナ)
ご期待ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。
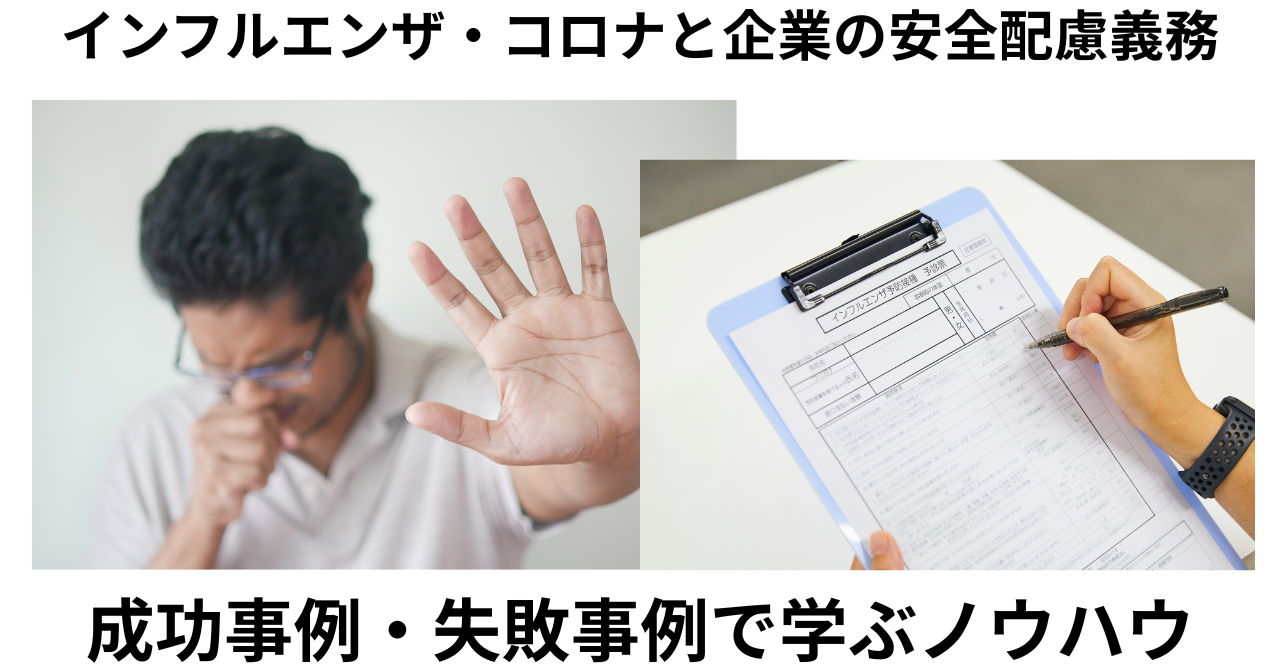

コメント