本記事は「インフルエンザ・コロナと企業の安全配慮義務」シリーズの第2話です。
シリーズの他の記事は👉インフルエンザ・コロナ対策と企業の安全配慮義務|実務ガイド
前回の記事では、企業が冬季の感染症に備える重要性についてお伝えしました。
前回の記事は👉冬季に備える職場の感染症対策|インフルエンザとCOVID-19
いよいよ流行シーズンが目前に迫る中、企業は具体的な対策を講じる必要があります。
しかし、一言で「インフルエンザやコロナ対策」と言っても、その法的な位置づけや、企業に課される義務は、感染症の種類によって異なります。
本記事では、まずインフルエンザと新型コロナウイルス感染症の基本的な知識を整理し、企業が知っておくべき法的な違いについて解説します。
この記事で分かること
- インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の法的な違い
- 感染症法に基づく出勤停止の基準と企業の義務
- 感染症時における休業手当の支払いルール
- 傷病手当金など、従業員が利用できる公的補償制度の概要
企業担当者必見|インフルエンザ・コロナの基礎知識と法的分類
インフルエンザと新型コロナウイルス感染症は、どちらも発熱や咳などの呼吸器症状を引き起こす感染症です。
しかし、その病原体や法的な扱いは全く異なります。
企業が適切な対策を取るためには、まず両者の違いを正確に理解しておくことが不可欠です。
冬季対策|季節性と新型インフルエンザの違いと法的分類
インフルエンザには、大きく分けて季節性インフルエンザと新型インフルエンザの2種類があります。
- 季節性インフルエンザ
- 毎年冬に流行するインフルエンザで、主にインフルエンザA型とB型のウイルスが原因です。
- 多くの人が過去の感染やワクチン接種によってある程度の免疫を持っているため、大きな社会問題に発展することは少ないとされています。
- これは、私たちが「ただのインフルエンザ」と呼んだり、ニュースで「今年のインフルエンザはA型が主流です」といった情報が流れたりする、最も一般的なインフルエンザのことです。
- 新型インフルエンザ
- 過去にヒトが感染したことのない、全く新しいタイプのインフルエンザウイルスによるものです。
- 多くの人が免疫を持たないため、急速に広範囲にまん延し、国民の生命や社会機能に重大な影響を及ぼすおそれがあります。
- 法律上では「新型インフルエンザ等感染症」として特別な分類がなされています。
- 具体例
- 2009年に世界的に大流行した新型インフルエンザ(H1N1)や、2003年以降にアジアを中心に発生した高病原性鳥インフルエンザ(H5N1)のヒトへの感染例などがこれに該当します。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の法的分類と企業の対応
新型コロナウイルス感染症は、インフルエンザウイルスとは異なる「コロナウイルス」が原因で、医学的にはインフルエンザではありません。
しかし、その法的な扱いは、流行の初期と現在とで大きく変わりました。
- 当初
- 2023年5月7日までは、未知のウイルスとして、感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」に準ずる「指定感染症」として扱われていました。
- これは、爆発的な感染拡大のリスクがあったためです。
- 現在(2025年)
- 2023年5月8日以降、ウイルスの特性や社会的な対応状況の変化を踏まえ、季節性インフルエンザと同じ「5類感染症」に移行しています。
- これにより、行政による強制的な外出自粛要請や就業制限はなくなりました。
企業が知っておくべき感染症時の従業員出勤停止の法的ルール
インフルエンザや新型コロナウイルス感染症に罹患した従業員を、企業は法的に休ませなければならないのでしょうか。
この疑問に答えるためには、まず感染症法における分類を理解しておく必要があります。
感染症法に基づく分類|社員の出勤停止を決める基準
日本の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(通称:感染症法)」は、病気の危険度や感染力に応じて感染症を分類しています。
感染症の分類の詳細はコチラの記事にて
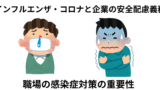
この分類こそが、企業が従業員に休業を命じる法的な根拠の有無を分ける鍵となります。
出勤停止の義務がある感染症
以下の感染症に罹患した従業員には、感染症法第18条に基づき、都道府県知事などが就業を制限または禁止する行政の命令を出す可能性があります。
企業は、この命令に従わなければなりません。
- 1類~3類感染症
- エボラ出血熱や結核など、国民の生命や健康に重大な影響を及ぼす可能性が高い感染症です。
- 新型インフルエンザ等感染症
- これは、1類から5類とは別の特別な分類です。
- 過去に人類が経験したことのない新しいウイルスによるものです。
- 多くの人が免疫を持たないため、全国的かつ急速にまん延し、国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがあることから、法律上、特別な位置づけがなされています。
これらに該当する場合、企業は行政からの命令に従う義務があるため、結果として従業員を休ませなければなりません。
これは、個々の企業の判断ではなく、社会全体の公衆衛生を守るための強制的な措置です。
出勤停止の義務がない感染症
- 4類感染症
- 狂犬病やデング熱など、人から人への感染はほとんどなく、主に動物や食品、蚊などを介して感染する病気です。
- このため、法律上の就業制限の対象ではありません。
- 5類感染症
- 季節性インフルエンザや、現在(2025年9月)の新型コロナウイルス感染症がここに分類されます。
- この分類の感染症については、法律上の就業制限の対象にはなっていません。
したがって、企業はこれらの感染症に罹患した従業員を休ませる法的義務はありません。
企業と学校の「休ませる法律」の違い
小学校や中学校では、学校保健安全法に基づいて、インフルエンザに罹患した生徒の出席停止期間が明確に定められています。
これは、子どもたちを感染症から守るという強い目的を持つ公共機関だからです。
具体的には、学校保健安全法施行規則の第19条に規定されており、インフルエンザ(第5類感染症)に罹患した児童生徒は、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで」は登校してはいけないとされています。
これは、感染のまん延を防ぐための法的義務です。
一方で、企業の場合、法律上の就業制限がないため、従業員を休ませる義務はありません。
ただし、労働契約法に定められた安全配慮義務に基づき、感染拡大を防ぐための自主的な対応が求められます。
発熱などの症状がある従業員に出勤を控えるよう促すことなどがこれに該当します。
インフルエンザ・コロナ時の休業手当|企業が知るべき支払いルール
従業員が病気で休んだとき、賃金が支払われるかどうかは、多くの人にとって関心が高い問題です。
この問題を理解する上で、まず「休業手当」が何を指すのかを正確に把握しておく必要があります。
休業手当の基礎知識|労働基準法に基づく企業の支払い義務
休業手当とは、企業側の都合で従業員を休ませた際に支払われる手当のことです。
これは、労働基準法第26条に基づき、企業に支払い義務があるものです。
具体的には、企業の責任(「使用者の責に帰すべき事由」)によって休業が生じた場合、企業は従業員に平均賃金の60%以上を支払わなければなりません。
ここで重要なのは、「企業側の都合」という点です。従業員本人の病気やケガで休む場合は、この休業手当の支払い対象にはなりません。
感染症ごとの休業手当|企業が知るべき支払い義務の違い
この「休業手当」の考え方は、感染症による休業にも適用されます。
- 季節性インフルエンザ・新型コロナウイルス(5類)
- これらの感染症は、法律で就業を強制的に制限する対象ではありません。
- そのため、従業員が体調不良で自主的に休む場合は、私傷病による欠勤扱いとなり、企業に休業手当の支払い義務はありません。
- ここが最も重要なポイントです。
- 従業員が感染していても、本人が「しんどいので休みます」と申し出た場合は、賃金の支払い義務は生じません。
- しかし、もし企業が「感染拡大を防ぐために出社しないでください」と強制的に休業を命じた場合、それは会社都合の休業と見なされます。
- たとえ善意からであっても、この場合は労働基準法第26条に基づき、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う義務が発生します。
- この違いは、企業の担当者が必ず把握しておくべき事柄です。
- 新型インフルエンザ等感染症
- この感染症は、感染症法第18条に基づく行政命令の対象です。
- 行政からの命令に従って従業員を休業させるため、これは企業側の都合ではなく、不可抗力と見なされます。
- したがって、このケースでは、原則として企業に休業手当の支払い義務は発生しません。
従業員が休業したときの最終手段|傷病手当金の基礎知識
傷病手当金とは、業務外の病気やケガで会社を休み、賃金が受けられない場合に、健康保険から支給される手当です。
この制度は、健康保険法(同法第99条)に基づいています。
これは、企業に勤める人が加入する協会けんぽや健康保険組合などの被用者保険に適用される制度です。
特に、季節性インフルエンザなどで従業員が自主的に休むものの、有給休暇をすべて使い切ってしまった場合や、万が一のために有給を残しておきたい場合など、賃金が途絶えてしまう際の重要な選択肢となります。
支給要件
- 業務外の事由による病気やケガであること。
- 仕事に就くことができない状態であること。
- 連続して3日間(待期期間)休み、4日目以降の休みであること。
- 休んだ期間について給与の支払いがないこと。
国民健康保険(国保)の場合
国民健康保険(国保)には、原則として傷病手当金の制度はありません。
国保は、自営業者やフリーランス、無職の人などが加入する健康保険であり、被用者保険とは異なる制度設計になっています。
ただし、例外的に、新型コロナウイルス感染症に限り、一部の市区町村が独自の条例に基づき、傷病手当金を支給する特例措置を設けている場合があります。
しかし、この特例は恒久的なものではなく、期限が設けられていることがほとんどです。
まとめ|企業担当者必読|感染症別の対応と休業補償
冬季の感染症対策において、企業がまず理解すべきは、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の法的・医学的な違いです。
| 項目 | 季節性インフルエンザ/新型コロナ(5類) | 新型インフルエンザ等感染症 |
| 法的義務 | 休ませる義務はない (企業判断) | 休ませる義務がある (感染症法に基づく行政命令) |
| 休業手当 | 強制的に休ませた場合は必要 (会社都合と見なされるため) | 原則不要 (行政命令のため不可抗力と見なされる) |
| 補償制度 | 傷病手当金の対象になりうる (自主休業の場合) | 傷病手当金の対象になりうる (行政命令による休業の場合) |
このように、感染症の種類と状況によって、企業に求められる対応や従業員が受けられる補償は大きく異なります。
企業の担当者は、それぞれの法的根拠を正しく理解し、適切な対応を取ることが不可欠です。
次回予告|すぐに実践できる!企業が押さえるべきインフルエンザ対策の実務ガイド
これまで、インフルエンザと新型コロナウイルスの法的・医学的な違いや、企業に求められる義務について解説してきました。これらの知識を踏まえ、いよいよ具体的な「実践」へと移ります。
次回の記事では、企業が今すぐ取り組むべきインフルエンザ対策の実務に焦点を当てます。
- 感染拡大を防ぐための社内ルール策定
- 従業員への情報提供と啓発活動
- 出勤停止期間の考え方と勤怠管理の注意点
など、いざという時に慌てないための具体的な対策を、わかりやすくご紹介します。
次回の記事は👉企業必見|第5類感染症(インフルエンザ・コロナ)実務的な対策
来るべき流行シーズンに備え、従業員を守るための準備を一緒に始めましょう。
ご期待ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。


コメント