本記事は「副業時代の労務管理」シリーズの第3話です。
前回の記事では、企業が副業制度を設計する際の土台となる法的な大原則を明確にしました。
前回の記事は👉副業は原則OK?就業規則で許可制・届出制にする場合の注意点
すなわち、従業員の副業を制限できるのは、「職務専念義務」「企業秩序維持義務」「安全配慮義務」という、労働契約から生じる限定的な合理的な根拠がある場合に限られるということです。
そして、法的リスクの回避と人材活用の促進という観点から、「副業の届出制(原則容認・例外禁止)」の採用を強く推奨しました。
届出制であれば、従業員の自由を尊重しつつ、企業側が副業の事実と労働時間を把握できるため、リスクヘッジに繋がりやすいためです。
しかし、就業規則にルールを定めることは、副業時代の労務管理における単なる「スタートライン」に過ぎません。
この記事でわかること
- 法的大原則|副業・兼業における労働時間通算の法的な義務と計算原則
- 割増賃金責任|通算の結果、法定労働時間超過分の割増賃金をどちらの会社が負うか
- 安全配慮義務|企業が負う健康管理の義務と「過労死ライン」によるリスク評価
- 実務的対策|正確な情報収集の書式、就業規則への明記、システムの活用方法
「労働時間通算」と「安全配慮義務」という実務の壁
今回焦点を当てるのは、ルールを定めた後の最も難解で重要な実務です。
それは、従業員が複数の会社で働くことによって生じる「複数事業場間の労働時間通算」の課題と、それと密接に関わる企業の「安全配慮義務」の履行です。
企業が副業を容認または許可する場合、法律上、従業員のすべての労働時間を合算して管理し、過重労働を防止する責任(安全配慮義務)を負います。
この「労働時間通算」のルールを適切に運用できなければ、従業員が健康を害した際に、企業は安全配慮義務違反として高額な損害賠償リスクに直面することになります。
リスク回避と健康管理を両立させる具体的な管理手法の明確化
本記事の目標は、企業がこの難解な課題をクリアし、法的なリスクを回避しつつ、従業員の健康を確実に守るための具体的な管理手法を明確にすることです。
まず「労働時間通算」の法的大原則を明確にし、その後、企業が安全配慮義務を果たすための具体的な実務対応について詳しく解説していきます。
副業・兼業における「労働時間通算」の法的大原則
企業が副業・兼業を容認する際、避けて通れない最大の難題が、労働基準法に基づく「労働時間通算」の実務です。
これは、労働者の健康を守る安全配慮義務を果たすための法的土台となります。
労働基準法第38条第1項の原則|労働時間の通算
労働基準法第38条第1項は、以下の通り、労働時間の通算義務を定めています。
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
— 労働基準法 第38条 第1項
この規定により、労働者が複数の会社(事業場)で働く場合、それぞれの労働時間を合算し、全体として法定労働時間(原則として1日8時間、週40時間)や時間外労働の上限規制を超えていないかをチェックしなければなりません。
労働時間通算の起算点と計算方法|法定原則と具体的な例示
法定の原則では、通算の結果、法定労働時間を超える部分の労働時間は、「後から労働契約を締結した事業場(会社)の労働時間」として取り扱われ、その会社が割増賃金(残業代)の支払い義務を負います。
この原則が、実際の労働時間帯ではなく、契約締結の前後で責任の所在を決定するという点で、実務上の混乱を生じさせます。
例示1|割増賃金の発生
| 項目 | 先に契約した会社(先社) | 後から契約した会社(後社) |
| 契約順 | 1番目(先契約だが1日での勤務時間では後) | 2番目(後契約だが1日の勤務時間では先) |
| 労働時間 | AM11:00~PM18:00(7時間) | AM5:00~AM10:00(5時間) |
| 合計労働時間 | 7時間 + 5時間 = 12時間 | |
| 法定労働時間超過分 | 12時間 – 8時間 = 4時間 |
この場合、通算の結果、4時間分が法定労働時間を超えています。
通算の順序は以下の通りです。
- 先社の労働時間(7時間)が法定内労働時間として優先的に消費されます。
- 残りの法定労働時間枠(8時間 – 7時間 = 1時間)が、後社の労働時間(5時間)のうち、05:00~06:00に充当されます。
- 後社の残りの4時間(06:00~10:00)が、通算の結果、法定外労働(残業)となります。
結論
後から契約した後社が、06:00から10:00までの4時間分について、割増賃金を支払う義務を負います。
例示2|先社で途中退勤した場合
先社(後勤務)で労働者が急用で14:00に帰宅し、後社(先勤務)では通常通り勤務した場合の通算は以下の通りです。
| 項目 | 先に契約した会社(先社) | 後から契約した会社(後社) |
| 実際の労働時間 | 11:00~14:00(3時間) | 05:00~10:00(5時間) |
| 合計労働時間 | 3時間 + 5時間 = 8時間 |
結論
合計労働時間が法定労働時間(8時間)に収まっているため、通算の結果、割増賃金は一切発生しません。
実務上の深刻な課題と安全配慮義務の履行の「管理モデル」導入の必然性
上記の事例は、法定原則を忠実に守ろうとすると、企業が直面する大きな課題を浮き彫りにします。
- 後社は先社の労働時間をどう把握するのか?
- 上記の例で、先社が急用で14時に帰宅したという事実を、後契約の後社がリアルタイムで知る手段は通常ありません。
- 後社は、労働者からの申告がない限り、先社が7時間勤務した前提で通算管理を行い、無駄な割増賃金を支払うリスクを負います。
- 企業間での情報連携が法的に制度化されていないため、割増賃金責任の所在が情報不足により予見不能となり、実務上の大きな障害となります。
通算の例外(通達)|厚生労働省が示す「管理モデル」とその限界
この「他社の労働時間を正確に把握する困難性」に対処し、企業に安全配慮義務の履行を促すために、厚生労働省は労働者からの申告を前提とした実務的な「管理モデル」を示しています。
このモデルでは、法定の原則に基づく割増賃金の支払い責任の特定よりも、労働者の健康管理(安全配慮義務)を最優先とします。
企業は、労働者からの正確な申告(届出)に基づいて労働時間を合算し、過重労働を防止するための措置(本業の残業抑制、副業の調整指示など)を講じることで、責任を果たします。
しかし、このモデルは「労働者による申告の正確性」に全面的に依存するという限界を抱えています。
申告が不正確であった場合、企業は過重労働の事実を把握できず、結果的に安全配慮義務違反を問われるリスクは残るのです。
したがって、企業は「管理モデル」を採用しつつも、労働者に対し正確な申告の義務を負わせ、制度の実効性を高めるための対策を講じることが、労務リスクを最小化する鍵となります。
企業が負う「安全配慮義務」と過重労働リスク
副業を認める企業にとって、労働時間通算が最終的に目指すのは、従業員の健康を守るという「安全配慮義務」の履行です。
労働時間管理を怠ることは、企業にとって最も深刻な法的リスクにつながります。
安全配慮義務の法的根拠|労働契約法第5条
企業が従業員の健康に配慮する義務は、労働契約法第5条に明確に定められています。
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
— 労働契約法 第5条
この「必要な配慮」には、副業を含む全ての労働時間を通算して把握し、過重な疲労によって健康を害することのないよう措置を講じる義務が含まれます。
労働時間通算管理を怠るリスク|知らなかったでは済まされない
企業が副業の届出制を採用せず、あるいは届出があっても適切な通算管理を怠った場合、従業員が過労によって心身の健康を損なうと、安全配慮義務違反として企業が責任を問われることになります。
- 責任の所在
- 裁判所は、企業が副業の事実を「知らなかった」としても、「知ることができた」状況にあったと判断すれば、その責任を追及する傾向にあります。
- 特に、企業が副業を原則容認しているにもかかわらず、労働時間把握のための届出制度すら設けていない「無規定状態」は、安全配慮義務を放棄していると見なされるリスクが極めて高いです。
- 賠償リスク
- 義務違反と判断されれば、企業は休業補償だけでなく、高額な損害賠償金(慰謝料や逸失利益など)の支払いを命じられる可能性があり、企業の信用を大きく損ないます。
副業解禁の時代において、企業が取るべき行動は、副業を禁止して隠されるリスクを負うことではなく、適切な届出制で情報を把握し、管理責任を果たすことへと完全にシフトしています。
重点管理の必要性|「過労死ライン」の目安による健康リスク評価
労働時間管理においてチェックすべきは、法定労働時間(週40時間)の超過や、36協定に基づく時間外労働の上限(月45時間、年360時間など)だけではありません。
最も重要なのは、健康障害の危険性があるかを判断することです。
この健康リスクを評価するための実務上の重要な目安が、「過労死ライン」です。
| 過労死ラインの目安 | 基準 | 重点管理の必要性 |
| 月80時間 | 2〜6ヶ月間の平均で月80時間以上の時間外労働(休日労働含む) | 健康障害のリスクが高まる水準 |
| 月100時間 | 発症前1ヶ月間に100時間以上の時間外労働(休日労働含む) | 健康障害のリスクが極めて高い水準 |
企業は、本業と副業の労働時間を合算した結果、従業員の時間外労働がこれらのラインに近づいた場合、法定上限を超えていなくても、直ちに産業医による面接指導や労働時間の調整指示といった健康障害防止のための措置を講じる義務があります。
副業制度の運用の成否は、いかにしてこの過重労働リスクを客観的に評価し、適切に対応する体制を築けるかにかかっています。
実務的な「労働時間管理」の具体的な手順とポイント
これまで確認した通り、企業は副業を容認する際、割増賃金責任の有無にかかわらず、安全配慮義務違反という重大なリスクを負います。
このリスクを回避するためには、「管理モデル」に基づき、実効性のある労働時間管理体制を構築することが不可欠です。
従業員の副業の必須情報の収集と書式設計
労働時間を通算し、従業員の健康状態を評価するためには、企業が副業に関する正確な情報を網羅的に把握する必要があります。
必須情報の項目
企業が副業届出書に必ず含めるべき項目は以下の通りです。
- 業務概要
- 副業先の業務内容(職種、具体的な作業内容)と、副業先の名称および所在地。
- 労働時間に関する情報
- 所定労働時間
- 副業先での始業時刻、終業時刻、および休憩時間。
- 勤務日
- 副業先での休日と勤務予定日(週または月のパターン)。
- 時間外労働の有無
- 副業先での時間外労働(残業)の有無と、その想定される頻度・時間。
- 所定労働時間
- 労働時間通算に関する確認
- 健康状態の自己評価
- 副業による疲労蓄積の有無に関する労働者本人のチェック項目。
- 正確な申告の誓約
- 虚偽申告を行った場合の懲戒処分に関する規定を理解し、誓約させる文言。
- 健康状態の自己評価
書式設計のポイント
単に情報を集めるだけでなく、合計労働時間と残業の有無がすぐに計算できるよう、申告書は表形式で具体的に記載する欄を設ける必要があります。
また、「届出内容に変更があった場合は速やかに申告し直す義務がある」旨を明記します。
時間外労働の上限チェックと調整
情報収集の目的は、法定の上限規制と過労死ラインを遵守しているか、本業と副業の合計でチェックする体制を構築することにあります。
チェック体制の確立
- 合計労働時間の把握
- 従業員からの届出情報に基づき、本業と副業の労働時間を月単位で通算し、記録します。この際、時間外労働(残業)部分を分けて集計することが重要です。
- 上限規制のチェック
- 法的上限
- 合計残業時間が月45時間、年360時間(または特別条項による上限)を超えていないかを確認します。
- 健康リスクチェック(過労死ラインの厳格な適用)
- 単月基準
- 時間外・休日労働の合計が月100時間を超えていないか。
- 複数月平均基準
- 発症前2か月間から6か月間の平均で、時間外・休日労働の合計が月80時間を超えていないかを厳しくチェックします。
- 単月基準
- 法的上限
リスク確認後の調整指示の運用
合計労働時間により過重労働のリスクが高いと判断された場合、企業は安全配慮義務に基づき、以下の調整措置を講じます。
- 本業の残業抑制
- まず、自社での残業を制限または禁止します。
- 副業の調整勧告(指示)
- 従業員に対し、副業先での労働時間を削減するか、勤務頻度を減らすよう具体的に調整を勧告します。
- 副業の中止命令(最終手段)
- 調整勧告にもかかわらず、健康リスクが改善されない、または従業員が正確な申告を拒否した場合、「安全配慮義務の履行」を理由に副業の禁止や中止を命令することができます。(ただし、この権限は就業規則に明確に規定されている必要があります。)
産業医・保健師との連携と産業保健体制の構築
過重労働リスクのある従業員の健康を守るには、専門家である産業医・保健師の関与が不可欠です。
面接指導の実施基準
企業は、副業の労働時間を通算した結果、以下の基準に該当する従業員に対し、産業医による面接指導を速やかに実施する必要があります。
- 法的な面接指導基準
- 時間外・休日労働の合計が月80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者。
- 実務上の積極基準
- 合計残業時間が月80時間に満たなくても、従業員が疲労や体調不良を訴えている場合や、業務パフォーマンスに明らかな低下が見られる場合は、積極的に面接指導を実施することが望ましいです。
企業側の産業保健体制の構築
- 産業医への情報提供
- 産業医に対し、本業と副業の合計労働時間や、従業員の申告内容(疲労の有無など)を正確に提供します。
- 指導の実行
- 産業医の意見に基づき、就業場所の変更、業務内容の調整、深夜業の回数の減少など、具体的な就業上の措置を講じます。
これらの実務的な管理手順を厳格に運用することで、企業は労働時間通算の義務を適切に果たし、安全配慮義務違反のリスクを大幅に軽減することができます。
副業時代の労務リスクを最小化する対応策
これまでの実務的な管理手順に加え、企業が副業時代のリスクを法的に、かつ永続的に最小化するためには、「就業規則」「教育」「システム」の3つの側面から対応を固める必要があります。
1. 就業規則の明記|申告制度の実効性確保
労働時間管理を従業員の「申告」に依存する「管理モデル」を採用する以上、その申告が正確に行われるための法的裏付けが不可欠です。
| 項目 | 規定すべき内容 | 目的 |
| 労働時間通算義務 | 労働基準法第38条第1項に基づき、本業と副業の労働時間を通算することを明記。 | 法的義務の遵守を明確化する。 |
| 申告義務 | 副業を開始する際、および副業先の労働時間や業務内容に変更があった際の正確かつ速やかな届出義務を明記。 | 正確な情報を得るための従業員の義務を定める。 |
| 懲戒事由 | 虚偽の申告を行った場合、または申告を怠った結果、企業の安全配慮義務の履行に重大な支障をきたした場合の懲戒処分(譴責、減給、場合によっては諭旨解雇など)の対象となる旨を明記。 | 申告の正確性に対する抑止力を確保する。 |
2. 教育と研修|正確な報告と自己責任の徹底
制度を定めても、従業員がその重要性を理解していなければ機能しません。
企業は、従業員に対する情報提供と意識改革を徹底する必要があります。
- 正確な報告の徹底
- 副業が原因で本業の企業が割増賃金責任や安全配慮義務違反の責任を問われるリスクを具体的に説明し、正確な労働時間申告が会社を守る行為であることを理解させます。
- 健康管理の自己責任
- 従業員自身にも、合計労働時間が過労死ラインを超えないよう自己管理責任があることを啓発します。
- 過労状態にあると感じた際は、速やかに企業へ報告し、面接指導を受けるよう促します。
- 守秘義務の遵守
- 副業先の情報(特に営業時間や業務内容)を本業で知り得た情報と混同しないよう、情報管理の意識も教育します。
3. 勤怠管理システムの活用|労働時間通算管理の効率化と客観性の確保
紙の届出書やExcelシートでの手動管理は、計算ミスや確認漏れのリスクを高めます。
通算管理の負荷を軽減し、客観性を高めるために、勤怠管理システムの活用が有効です。
- 通算機能の活用
- 勤怠管理システムに副業先の労働時間(申告ベース)を入力できる機能や、本業の労働時間と自動で合算し、月間残業時間の合計がアラート基準(80時間など)を超えた際に自動で通知する機能を検討・導入します。
- 客観的記録の蓄積
- システムを通じた管理は、従業員の労働時間記録を客観的な証拠として蓄積できます。
- これは、万一、安全配慮義務違反が問われた際に、企業が「必要な措置を講じていた」ことを証明するための重要な根拠となります。
まとめ|安全配慮義務の履行こそ最優先課題
企業が副業時代のリスク管理を成功させる鍵は、以下の二点に集約されます。
- 最優先課題の認識
- 企業は、割増賃金責任の所在(先契約か後契約か)にかかわらず、従業員の命と健康を守る安全配慮義務の履行を最優先課題とすべきです。
- この義務を怠った場合の損害賠償リスクは、割増賃金リスクを遥かに上回ります。
- 管理の鍵
- その義務を果たすための鍵は、正確な情報収集(届出制の厳格な運用)と、過労死ライン基準に基づく客観的なリスク評価です。
- 就業規則での申告義務の明記と、産業保健体制との連携が不可欠となります。
次回予告|ダブルワーク入社者への対応
これまで解説してきた内容は、主に「自社の社員が副業を始めるケース」を想定した、情報の把握と本業の調整が中心でした。
しかし、実務においてより複雑な問題となるのが、「既に他社でダブルワークをしている人が、新たに自社に入社してくるケース」です。
次回の記事では、このダブルワークで入社してきた社員に関する労務管理に焦点を当てます。
次回の記事は👉ダブルワークの従業員を雇うときの注意点|労働時間・安全配慮を解説
お楽しみに。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。
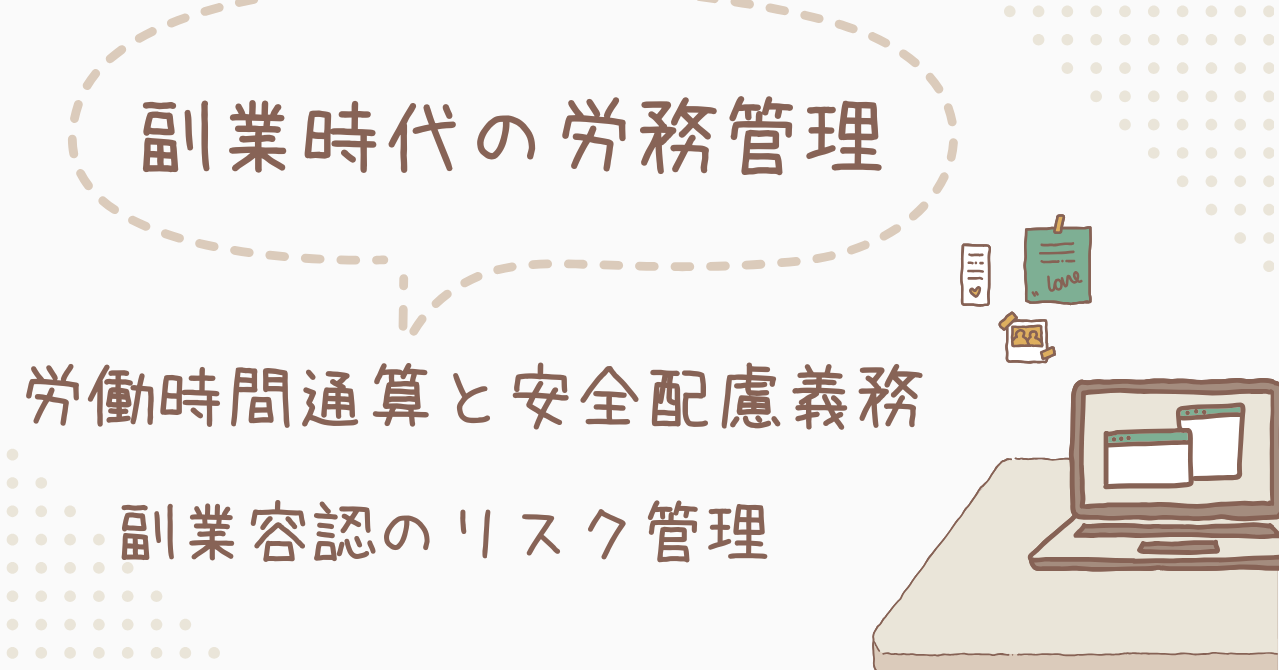

コメント