本記事は「企業のハラスメント対策バイブル」シリーズの第6話です。
前回の記事では、ハラスメント対策の土台となる「ルールを定める」と「意識を変える」という2つのステップについて詳しく解説しました。
前回の記事は👉パワハラを防止する|ルールと意識改革で安全職場を実現
しかし、ルールや意識改革だけでは、ハラスメントが完全に消えるわけではありません。
万が一ハラスメントが発生してしまった際に、被害者を守り、公正に対処し、再発を防止する「仕組み」が不可欠です。
今回の記事では、5つのステップの後半戦
- Step 3|制度を整備する
- Step 4|事実を究明する
- Step 5|再発を防ぐ
について詳しく解説します。
この記事でわかること|パワハラ防止3ステップの実践
- Step 3(制度)|相談窓口の設置義務と、360度評価を含む人事制度との連携
- Step 4(調査)|公正な調査の法的義務と、利害関係のないチームによるヒアリング手順
- 調査のポイント|意見の食い違いの際のファクトベースの対応と、パワハラ3要素での判断
- Step 5(再発防止)|組織風土の改善(業務量見直しなど)を継続する重要性
- 対策の総括|対策はPDCAを回し、心理的安全性と成長基盤を築く未来への投資
Step 3|ハラスメント防止制度を整備する|風通しの良い組織をつくる
ハラスメント対策は、個人の努力だけでなく、組織全体でハラスメントを予防・解決する仕組みが必要です。
相談しにくい環境では問題は再び水面下に隠れてしまい、事態の悪化につながります。
ハラスメント防止の相談窓口|義務化と多様化のポイント
ハラスメントの相談は、被害者にとって心理的な負担が非常に大きいものです。
「誰に相談すればいいのか分からない」という状況は、問題を深刻化させる大きな原因となります。
ここで重要となるのが、パワハラ防止法(労働施策総合推進法)です。
この法律により、2022年4月1日から中小企業を含めすべての事業主にパワハラ相談窓口の設置が義務化されています。
これは単に窓口を設けるだけでなく、従業員に広く周知し、相談内容に応じて適切に対応できる体制を整えることが法律で求められています。
形だけの窓口では義務を果たしたことにはなりません。
- 社内窓口の設置
- 人事、上司、ハラスメント担当者など、複数の相談先を設けることで、従業員が話しやすい相手を選べるようにします。
- 外部窓口との連携
- 社内に相談窓口の運営ノウハウがない場合や、客観性を保ちたい場合は、外部の専門家と連携するのも有効な手段です。
- 弁護士事務所、社会保険労務士事務所、またはハラスメント研修を専門とするコンサルティング会社などと連携した相談窓口を設けることで、より専門的かつ客観的な立場で相談に応じてもらえる安心感を提供できます。
- 匿名での相談
- 報復を恐れることなく、従業員が安心して声を上げられるよう、匿名での相談も可能にしましょう。
ハラスメント防止と人事評価制度の連携
ハラスメント対策を企業の文化として根付かせるためには、それを人事評価に組み込むことが非常に有効です。
特に、部下を持つ管理職の行動を多角的に評価する「360度評価」は、ハラスメント防止に大きな効果を発揮します。
360度評価の深掘り解説
360度評価とは、上司が部下を評価する従来の評価方法に加え、同僚や部下、さらには自己評価など、複数の視点から多角的に評価する仕組みです。
これにより、上司だけでは見えにくい部下への態度や言動が可視化されます。
- ハラスメントの早期発見
- 「部下への配慮に欠ける言動がある」「チーム内の雰囲気を悪くしている」といった問題点が、部下や同僚からの評価によって明らかになります。
- これにより、ハラスメントの兆候を初期段階で発見し、未然に防ぐことができます。
- 責任感の向上
- 評価される側は、上司だけでなく周囲のメンバーからも見られているという意識を持つため、より責任感を持った行動を促すことができます。
- フィードバック機会の創出
- 評価結果を基にしたフィードバックは、管理職自身の成長を促す貴重な機会となります。
人事評価に「部下育成への貢献度」や「チーム内の心理的安全性への配慮」といった項目を加え、360度評価を導入することで、ハラスメントを起こしにくい行動を評価する仕組みを作ります。
従業員の声を活かすハラスメント防止アンケート調査
目に見えないハラスメントの兆候を早期に発見するために、定期的な調査を実施しましょう。
- ストレスチェック・匿名アンケート
- ストレスチェックやハラスメントに関する匿名アンケートを定期的に実施することで、部署やチームごとの傾向を把握し、潜在的な問題を可視化します。
- これにより、問題が大きくなる前に proactive(先回り)な対応が可能になります。
Step 4|ハラスメント事実を究明する|公正な調査で信頼を築く
前回の記事では、ハラスメント対策の土台となる「ルールを定める」(Step 1)、「意識を変える」(Step 2)を解説しました。
そして今回の記事で、「制度を整備する」(Step 3)について解説してます。
これらの備えがあっても、万が一ハラスメントが発生してしまった場合、その対応を誤ると、被害者はさらなる苦痛を受け、組織への信頼は失われてしまいます。
ハラスメント対応の「心臓部」とも言えるのが、この「事実を究明する」(Step 4)です。
ハラスメント防止で公正な調査が重要な理由
企業には、パワハラの訴えがあった場合に事実関係を調査する法的義務があります。
その根拠となるのは労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)です。
この法律は、企業に対して「職場におけるパワハラに係る事後の迅速かつ適切な対応」を講じることを義務付けており、事実を迅速かつ正確に確認することがその対応に含まれます。
調査の不手際は、被害者の二次被害や組織への不信感につながるだけでなく、法的な義務違反として行政指導や損害賠償請求のリスクを招きます。
正確な事実を把握することは、適切な措置を講じるための唯一の道です。
企業が行うハラスメント調査の具体的手順
ハラスメント調査は、専門性と高い倫理観を要するデリケートな作業です。
相談があった際に慌てることがないよう、事前に調査を担当する専門チームを定めておきましょう。
専門チームによる対応
- 担当者の選定
- 人事、法務部門の担当者、または社内のハラスメント担当者などがこれに当たります。
- 利害関係のないメンバー
- 事案が発生した際は、必ず利害関係のないメンバーを選出することが極めて重要です。
- 被害者や加害者と個人的なつながりが強い人間は、調査の公平性や中立性を損なう可能性があるため、調査チームからは絶対に外す必要があります。
ヒアリングの具体的な手順
事実究明の要となるのが、被害者、加害者、目撃者など関係者からのヒアリングです。
それぞれの立場に応じたヒアリングの具体的な手順と注意点を以下に示します。
1. 被害者からのヒアリング 被害者の精神的負担を軽減し、安心して話せる環境を整えることが第一です。
- プライバシーへの配慮
- 周囲に聞かれない個室を用意し、秘密保持を約束します。
- 共感的傾聴
- 被害者の話を最後まで遮らずに聴き、共感を示すことで信頼関係を築きます。
- 事実の確認
- 感情だけでなく、「いつ、どこで、誰が、何を、どのように」という5W1Hを意識して具体的な事実を丁寧に聞き取ります。
- 意向の確認
- 今後の対応について、被害者の意向を必ず確認し、尊重します。
2. 加害者からのヒアリング 事実の確認に徹し、感情的な対立を避けることが重要です。
- 冷静な対応
- 事前にハラスメントの事実を決めつけず、冷静かつ中立的な立場で臨みます。
- 事実の提示
- 被害者や目撃者から得られた具体的な事実を提示し、その事実関係について加害者の言い分を聴き取ります。
- 経緯の確認
- なぜそのような言動に至ったのか、その背景や意図を聴取します。
3. 目撃者からのヒアリング 目撃者からの情報は、事実関係を客観的に証明する上で非常に貴重です。
- 秘密保持の徹底
- 目撃者に対し、ヒアリングの内容や、目撃者から話を聞いたこと自体を、他の誰にも話さないよう秘密保持を強く求めます。
- 客観的事実の確認
- 目撃した事実を5W1Hに基づいて詳細に聞き取ります。個人の感想や推測は含めないように注意します。
意見が食い違っている場合の対処法
関係者間で意見が食い違っている場合は、以下の手順で対処します。
- ファクトベースでの事実確認
- 感情や推測を除外し、客観的な事実(日時、場所、客観的証拠など)に基づいて、何が起きたのかを再確認します。
- 再度ヒアリング
- 関係者全員に個別に再ヒアリングを行い、食い違いの原因を深掘りします。
- 総合的な判断
- 複数の証言や客観的証拠を総合的に評価し、最終的な事実を認定します。
最終的に、パワハラかどうかを判断するには
- 優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
- 労働者の就業環境が害されること
の3つの要素を総合的に考慮します。
Step 5|ハラスメント再発を防ぐ|根本原因の解消と組織改善
これまでの4つのステップで、ハラスメント対策の土台を築き、実際に事案が発生した場合の公正な調査方法を解説しました。
しかし、ハラスメント対策は、問題を解決して終わりではありません。
重要なのは、ハラスメントが二度と起きない組織をどのように作っていくかです。
なぜハラスメント再発防止ステップが重要なのか?
「ハラスメントが二度と起きない組織」を完璧に実現することは、残念ながら現実的には非常に難しいことです。
しかし、だからといって諦めてはいけません。
重要なのは、その理想に向かって、組織全体で継続的に努力し続ける姿勢です。
この努力こそが、従業員が安心して働ける「心理的安全性」の高い職場を作り、企業の成長を支える土台となります。
ハラスメントは個人の資質の問題に見えがちですが、実際には組織の構造や風土に起因することが少なくありません。
過度なストレス、コミュニケーション不足、不適切なリーダーシップなどがハラスメントの温床となります。
そのため、単に加害者へ処分を下すだけでは、根本的な問題は解決しません。
同じような問題が別の場所で発生するリスクが残ってしまいます。
処分後の職場が
- 相談者にとって再び安心して働ける環境になっているか
- 加害者が同じ過ちを繰り返す恐れがないか
- 新たな加害者が生まれるような構造的な問題が放置されていないか
を確認することが不可欠です。
企業が行うハラスメント再発防止の具体策
1. 加害者への適切な処分と再発防止指導
公正な調査で事実が明らかになったら、就業規則に基づき、客観的な事実と懲戒基準に沿って処分を決定します。
この際、なぜその処分に至ったのかを明確に説明し、処分が恣意的なものではないことを示します。
さらに重要なのが、再発防止のための指導です。
必要に応じて、加害者に対して専門家によるカウンセリングや研修を受けさせ、自身の言動が他者に与える影響を深く理解させます。
2. 組織風土の改善と継続的な確認
加害者個人への対処と並行して、組織全体の改善に着手します。
ハラスメントの根本原因を解消するための具体的な施策を継続的に導入し、その効果を定期的に確認します。
- 業務量の見直しとタスクの分散
- 従業員の過度なストレスを軽減するために、業務量が一部の従業員に集中していないか見直します。
- 必要に応じて、タスクの分散や適切な人員配置を行い、精神的・肉体的な負担を減らします。
- チームビルディングの実施
- チームビルディングや相互理解を深める取り組みを通じて、従業員間の閉鎖的な関係性をなくし、オープンなコミュニケーションを促します。
- コミュニケーションの活性化
- 部署横断の交流イベントや、定期的な1on1ミーティングの導入など、組織全体のコミュニケーションを活性化させるための施策を継続的に実行します。
ハラスメント対策は、一度やったら終わりではありません。
これらの改善策を継続的に実施し、その効果を定期的に確認することで、組織はより強く、従業員はより安心して働けるようになるでしょう。
まとめ|職場のハラスメント防止は企業の未来への投資
前回と今回の記事で、ハラスメント対策を5つのステップに分けて解説しました。
- Step 1(ルールを定める)とStep 2(意識を変える)で、組織としての揺るぎない方針と、従業員一人ひとりの当事者意識を確立する土台を築きました。
- Step 3(制度を整備する)とStep 4(事実を究明する)で、パワハラ防止法に基づく相談窓口の設置や、公正な調査体制といった、問題発生時の実効的な仕組みを構築する方法を解説しました。
- そして、最終ステップのStep 5(再発を防ぐ)では、単に問題を解決するだけでなく、組織の構造的な課題に目を向け、ハラスメントが起きにくい風土を築くことの重要性をお伝えしました。
ハラスメント対策は、一度実施したら終わりではありません。
完璧な組織を築くことは難しいかもしれませんが、PDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)を回し続けることで、より安全で健全な職場環境へと着実に進化させることができます。
健全な職場環境は、従業員のエンゲージメントと生産性を高め、結果として企業の持続的な成長を可能にする最も重要な基盤となります。
この5つのステップが、あなたの組織における「未来への投資」の一歩となることを願っています。
次回予告|セクシュアルハラスメント対策の具体的方法を解説
「企業のハラスメント対策バイブル」シリーズの次回は、セクシュアルハラスメントに焦点を当てます。
性的な言動によるハラスメントは、被害者の尊厳を傷つけ、職場環境を著しく悪化させます。
次回の記事は👉職場のセクハラとは|法的義務と企業・従業員の実践的対応策
パワハラとは異なるその特徴や、企業に求められる具体的な対策、そして被害者・加害者の双方を生まないための予防策について、詳しく解説していきます。
どうぞご期待ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。
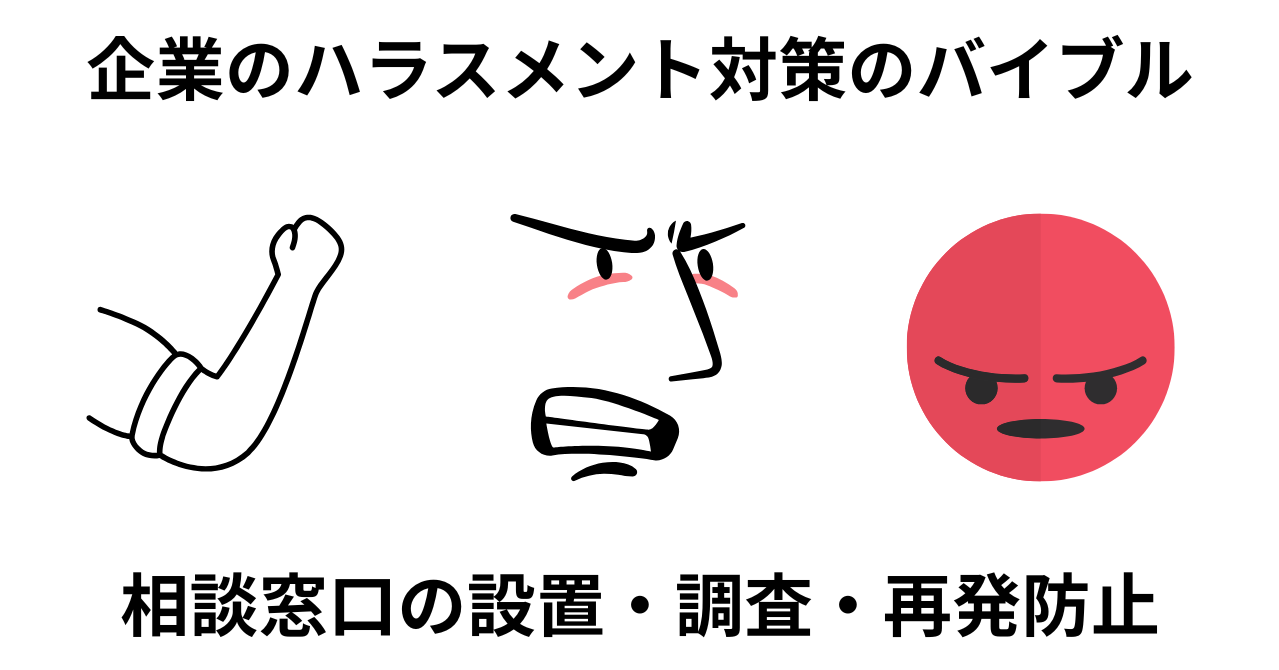

コメント