本記事は「副業時代の労務管理」シリーズの第4話です。
前回は、「自社の社員が他で副業を始めるケース」における労働時間通算と安全配慮義務の基本原則を解説しました。
前回の記事は👉副業容認のリスク管理|労働時間通算と安全配慮義務の実務ポイント
しかし、労務管理の実務において、よりリスクが高く、管理が複雑となるのが、今回焦点を当てる「既に他社でダブルワークをしている人材を、新たに自社が雇用するケース」です。
この場合、自社は後から労働契約を締結する側(後社)となることが多く、割増賃金責任のリスクが格段に高まります。
管理の難しさと法的リスクを理解した読者の皆様は、当然、次のような疑問を持たれるでしょう。
この記事でわかること
- 採用の是非|ダブルワーク者を「雇わない」という選択肢が現実的ではない理由
- 割増賃金責任|自社が「後社」となる場合の割増賃金(残業代)支払いリスクと原則
- 安全配慮の義務|入社時および入社後の過労死ラインチェックと健康リスクの把握
- 管理体制の構築|地域産業保健センターを活用した中小企業向けの現実的なリスク回避法
ダブルワーク社員は採用すべきか?リスク回避の観点から見る採用判断
労働時間通算や安全配慮義務の管理がそこまで複雑でリスクが高いなら、いっそダブルワークの人は最初から採用しなければいいのではないか?
これは、リスクヘッジを重視する企業にとって、きわめて合理的な発想です。
手間とリスクを回避するための、最もシンプルな解決策に見えるかもしれません。
副業・兼業人材を避けられない時代背景と採用リスクの現実
しかし、この「雇わない」という方針は、現代の労働市場においては企業競争力の観点から大きな足かせとなり、もはや企業が安易に選択できる道ではありません。
- 避けられない人口減少の波
- 日本では生産年齢人口の減少が急速に進んでおり、この傾向は今後さらに加速します。
- もはや「自社の理想とする働き方だけをする人材」を選り好みできる状況ではなくなってきています。
- 人材不足が常態化する中、「そうも言っていられない」というのが企業の切実な現実です。
- 多様な働き方の強制的な受容
- ダブルワークは、単に個人の希望というだけでなく、収入補填やキャリアアップのために労働市場全体で拡大している潮流です。
- これを一律に拒否することは、採用のパイを自ら狭め、優秀な人材の獲得機会を大きく失うことを意味します。
- 経験とスキルの有効活用
- ダブルワーク経験者は、複数の企業や業界で培った多様な知識やスキルを持っています。
- 彼らを避けることは、企業に新しい知見やイノベーションをもたらす機会を逸することにつながります。
- 法令の趣旨
- 法令は、雇用者がダブルワーク者を適切に管理するための義務を定めており、これは、労働者の自由な働き方を尊重し、その上で健康を守りながら有効活用することを企業に促していると解釈すべきです。
管理体制の構築こそが本筋
もはや「雇わない」ことが通用しない時代において、企業が取るべき方針は明確です。
ダブルワーク者を恐れて排除するのではなく、「ダブルワーク者でも適切に管理し、安全に雇用できる仕組みを整える」ことです。
本記事では、自社が後社(後から契約を締結する側)としてダブルワーク入社者を安全に受け入れ、法的なリスク(特に割増賃金と安全配慮義務)を最小化するための具体的な実務的手順を詳しく解説します。
ダブルワーク社員を採用する際の入社前チェックリストと後社リスク対策
ダブルワーク入社者を迎える際、企業が負うリスクを最小化し、社員の健康を守るためには、入社前、特に採用内定の段階での対応が決定的な鍵となります。
自社が「後から労働契約を締結する事業場(後社)」となるこのケースは、割増賃金責任の観点から最も厳格な管理が求められます。
実務上の前提|ここで示す手順は、法的なリスクを最小化するための理想的な枠組みです。リソースに制約がある企業は、特に必須情報の収集と安全配慮義務に基づく調整に焦点を当て、段階的な導入を目指してください。
面接段階で確認すべき副業情報|労働時間通算と割増賃金責任の把握
リスクヘッジの土台は、正確な情報把握にあります。
採用選考のプロセス(内定通知前が望ましい)において、労働者から以下の情報を網羅的に収集し、記録することが不可欠です。
| 必須情報の項目 | 収集の目的と重要性 |
| 他社(先社)の業務内容・所在地 | 【職務専念義務・競業避止のチェック】 自社の業務と競合しないかを確認する。 |
| 他社(先社)との労働契約締結日 | 【割増賃金責任の所在特定】 最重要情報。 割増賃金責任は、原則として後契約の自社が負うため、契約順序を確定する。 |
| 他社(先社)の所定労働時間 | 【労働時間通算の基準】 始業・終業時刻、休憩時間などを正確に把握し、自社の労働時間と合算した際の法定労働時間超過有無をシミュレーションする。 |
| 健康状態の自己評価 | 【安全配慮義務の初期判断】 既に他社での勤務による疲労蓄積がないか、初期の健康リスクを把握する。 |
情報提供の信頼性確保(「誓約書」の現実的な代替)
実務現場の現状として、厳格な誓約書や同意書を取得している企業はまだ少数派です。
- 現実的な対応
- 厳格な誓約書が難しい場合は、「副業届出書」の中に「虚偽申告時の対応」に関する規定を明記し、労働者に署名させるだけでも、情報提供の重要性に対する意識付けと、法的証拠としての価値を高めることができます。
- 重要な義務
- 副業の労働時間や業務内容に変更があった場合は速やかに届け出直す義務を、面接時および書類上で必ず確認させましょう。
労働時間通算の実務|割増賃金リスクと過労死ライン対策のポイント
① 割増賃金責任の試算と残業リスクの認識
自社が「後社」となる場合、労働基準法第38条第1項により、割増賃金責任を負うリスクが高まります。
- 通算の原則
- 先契約の他社(先社)の所定労働時間が法定労働時間に優先的に充当されます。
- リスク認識
- 自社が後社の場合、自社で残業をさせた時間のすべてが、通算の結果、法定時間外労働となり、割増賃金支払い義務が発生する可能性が高いことを認識します。
実務上の対応|割増賃金リスクを最小化するため、自社が後社となるダブルワーク社員には、原則として残業をさせない運用を基本とします。
② 安全配慮義務に基づく入社前の調整(最優先対応)
従業員の健康を守ることは、企業規模にかかわらず最優先の義務です。
- 過労死ラインチェックの厳格な適用
- 本業と副業の労働時間を合算した結果、月間の時間外労働が単月で100時間に近づく、または発症前2~6か月間の平均で80時間を超えることが入社前の試算で判明した場合、企業はリスクを「知ることができた」と判断されます。
- 調整の要請と採用の可否判断の明確化
- リスクが高い場合、内定承諾の条件として、従業員に対し他社(先社)の勤務時間を削減するなど、具体的な調整を要請します。
- 調整の要請にもかかわらず、健康リスクが依然として高い状態が続く、または調整を拒否された場合は、安全配慮義務の履行が困難であるという理由により、採用を見送る判断基準を明確にしておく必要があります。
ダブルワーク社員の入社後管理|労働時間と健康リスクを守る運用体制
入社時の情報収集を経てダブルワーク入社者を雇用した後、企業が負う最も重要な責任は、継続的な労働時間通算と安全配慮義務の履行です。
このケースでは、自社が原則として「後から契約を締結した企業(後社)」としての重い責任を負うため、厳格な管理体制を維持しなければ、法的なリスクは増大し続けます。
副業申告制度の運用方法|就業規則と勤怠システムによる通算管理
ダブルワークの労働時間管理は、労働者からの正確な自己申告を前提とする「管理モデル」が基本となります。
これを機能させるには、申告の信頼性を担保する仕組みと、それを活用する体制が必要です。
継続的な申告義務付けと就業規則の整備
労働者側の申告の信頼性を担保するため、就業規則に明確な規定を設けます。
- 正確な申告義務の明記
- 就業規則の「副業・兼業に関する規程」などに、他社(先社)の所定労働時間および実労働時間の変更について、速やかに会社に届け出る義務を明確に定めます。
【就業規則の記載例|届出義務】
- 第〇条(副業・兼業に関する届出と変更)
- 労働者は、入社時までに届け出た他社(先社)の労働時間等に変更が生じた場合、速やかに(遅滞なく)その内容を会社に届け出なければならない。
- 実効性の担保(懲戒事由)
- 申告が遅延・停止した場合や、虚偽申告によって会社の安全配慮義務の履行に重大な支障をきたした際の懲戒事由を、就業規則の懲戒規定に明確に規定し、労働者に周知します。
【就業規則の記載例|懲戒の事由(一部抜粋)】
- 第〇条(懲戒の事由)
- 労働者が、届出内容が虚偽であることが判明し、会社の労働時間通算義務または安全配慮義務の履行に重大な支障をきたしたとき、または正当な理由なく届出を怠ったときは、懲戒処分とすることがある。
勤怠管理システムの活用とアラート機能
- システムの導入(管理モデルの具現化)
- 申告された他社(先社)の労働時間データをシステムに入力し、本業と自動で通算できる仕組みを構築します。
- 過重労働アラート
- 通算した労働時間が、過労死ラインの基準に近づいた際に、人事担当者らに自動で通知されるアラート機能を設定します。
実務上の留意点|高度なシステム導入が難しい場合でも、専用の管理表などで手動で通算することを義務付け、月次で必ず合算時間を確認するチェック体制を構築することが重要です。
後社としての割増賃金責任|残業禁止運用と支払い記録の徹底
自社が「後社」であるという立場から、残業指示は直接的に割増賃金支払い義務につながるため、運用を厳格化する必要があります。
残業指示の原則禁止
- 運用徹底
- 後社としての割増賃金リスクを最小化するため、ダブルワーク社員には、業務の必要性にかかわらず残業を極力避ける運用を徹底します。
割増賃金の精緻な計算と支払い
- 計算方法
- 通算の結果、法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)を超過した部分について、その労働を行わせた自社(後社)が、割増賃金(25%以上)を加算して支払います。
- 記録の徹底
- 支払い記録は、労働基準監督署の調査に備え、計算過程を含めて詳細に残します。
安全配慮義務の実務|過重労働チェックと地域産業保健センターの活用
安全配慮義務は労働時間を通算した総時間に基づいて判断されるため、企業規模にかかわらず最も重い責任として厳格な履行が求められます。
過労死ラインの厳格な適用とリスクチェック
- 継続的なチェック
- 申告された他社(先社)の労働時間と自社の実労働時間を毎月合算し、過重労働リスクチェックを継続的に実施します。
- リスク判断基準
- 合算した時間外労働が単月で100時間に近づく、または複数月平均で80時間を超える場合は、直ちに次のステップに移ります。
過重労働者への介入|理想と現実のギャップを埋める
過重労働リスクが確認された場合、企業が取るべき措置は、まず医師による面接指導です。
- 法的な理想と大企業の対応
- 労働者数50人以上の事業場では、産業医を選任し、その医師による面接指導を速やかに実施することが法的に義務付けられています。
- 中小・零細企業の現実的な対応
- しかし、労働者数50人未満の企業では産業医がいないことが一般的であり、理想的な体制を整えるのは非現実的です。
- このような企業が法的な義務を果たすためには、以下の現実的な代替措置を講じる必要があります。
- 地域産業保健センター(地さんぽ)の活用
- 労働者数50人未満の企業は無料で、医師による健康相談や面接指導サービスを利用できます。
- 過重労働リスクのある従業員に対し、地さんぽの医師による面接指導を速やかに利用することが、最も現実的な代替手段となります。
- ヒアリングと記録の徹底(証拠の確保)
- 労務担当者、人事担当者、または事業主本人が、従業員の疲労蓄積度や健康状態を詳細にヒアリングし、その内容と会社の指導内容を詳細に書面で記録します。
- 「会社はリスクを把握し、対策を講じた」という証拠を残すことが、安全配慮義務履行において極めて重要です。
- 就業上の措置の実施と他社への勧告
- 医師の意見やヒアリングの結果に基づき、業務の軽減、深夜業の回数の減少など具体的な措置を講じます。
- さらに、従業員を通じて他社(先社)との労働時間調整を強く勧告し、その記録を残します。
- 地域産業保健センター(地さんぽ)の活用
まとめ|ダブルワーク社員を安全に雇用するための最低限ラインと実務ポイント
現代において、企業がダブルワーク入社を避けることは、人材戦略上の大きな損失です。
今回の記事で解説した厳格な管理手順は、企業が負う割増賃金責任と安全配慮義務という二大リスクを最小化するための理想的な枠組みです。
しかし、現場のリソースが限られている現実を踏まえ、労務担当者が取るべきは、理想の追求ではなく、「知らなかったでは済まされない」という状況を回避するための最低限のラインを死守するアプローチです。
中小企業が守るべき最低限の対策|情報収集とリスク記録で法的責任を回避
法的な責任を回避し、従業員の健康を守るため、以下の2点は最優先で実施してください。
- 情報収集とリスクの把握(入社時)
- 他社(先社)の労働契約締結日を確定し、合算労働時間が過労死ラインに近づくか否かを必ずシミュレーションすること。
- これにより、「知る努力を怠った」と判断される状況を回避します。
- 措置の履行と記録(入社後)
- リスク判明後、地域産業保健センター(地さんぽ)などの公的サービスを活用し、担当者による詳細なヒアリングとその措置の内容を詳細に記録すること。
- 「安全配慮の措置を講じた」という客観的な証拠を確保します。
現実的な管理体制の強化
最低限のラインを死守した上で、「副業届出書に懲戒事由を明記」し、手動であっても合算時間チェックを月次で継続することが、法的なリスクを軽減しつつ、優秀な人材を安全に活用するための最も現実的かつ効果的なアプローチとなります。
次回予告|社会保険・税務の実務対応
社員が副業・兼業をしている場合に、企業が対応すべき社会保険と税務の複雑な課題について解説します。
- 健康保険・年金
- 二重加入時の保険料算定・按分(あんぶん)ルールと手続き。
- 雇用保険
- どちらの企業で加入手続きを行うべきかの判断フロー。
- 税務処理
- 住民税・所得税の給与計算と報告フロー。
- 簡便運用
- 中小企業でも法令遵守しつつ運用できる現実的な簡便法。
次回の記事は👉ダブルワーク社員の保険対応ガイド|社会保険・雇用保険・労災の実務手順
次回も実務に直結する内容を解説します。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わるさまざまな課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を、はじめての方にもわかりやすく、やさしくお伝えします。






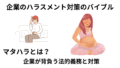
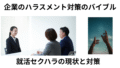
コメント