本記事は「副業時代の労務管理」シリーズの第1話です。
現代の職場の風景は、「働き方改革」と「デジタル化」によって一変しました。
その変化の最たるものが、「副業・兼業」の解禁トレンドです。
かつて終身雇用の下で厳格に禁止されていた副業は、今や大企業を中心に容認されつつあります。
しかし、この解禁の裏には、企業からの二重のメッセージが隠されています。
一つは「社員のキャリアを自律的に支援したい」という前向きなメッセージ、もう一つは「給与を十分に上げられないので、他で稼いでほしい」という経済的な現実です。
本シリーズでは、この副業解禁がどのような構造的背景から始まり、企業が直面するメリットとリスク、そして依然として副業を禁止せざるを得ない企業の課題を総論的に論じます。
この記事でわかること
- 副業解禁が進む背景にある、政府の政策的狙いと経済構造の変化
- 企業が副業を容認する「建前」と「本音」の二重メッセージ
- 大企業と中小企業で分かれる副業容認の現状と、禁止を続ける理由
- 就業規則に副業規定がない場合に生じる法的リスクと対応策
- 副業を容認する企業が直面する主要リスク(情報漏洩・過重労働)とその防止策
- 副業解禁がもたらす戦略的メリット(人材確保・イノベーション・離職防止)
副業解禁の構造的背景とは?政府方針と企業の本当の狙いを読み解く
副業解禁の動きは、企業が自主的に始めたというよりも、国の強力な政策推進が中心となって加速しました。
政府の推進政策|モデル就業規則から「副業禁止」規定を削除した背景
大きな転換点となったのは、2018年に厚生労働省が発表した「副業・兼業の促進に関するガイドライン」です。
政府は、企業が従業員の副業・兼業を原則として認めることが適切であるとの考えを示します。
そして、企業にとっての規範となる「モデル就業規則」から、それまで当然のように存在していた副業禁止の規定を削除しました。
これにより、企業は就業規則を見直すよう促され、副業を容認する企業が加速度的に増加する土壌が形成されました。
政府の副業推進の政策目的|労働力不足への対策と個人の自律支援
政府が副業をこれほどまでに推進する背景には、日本社会が抱える根深い構造的課題と、新しい時代の労働観への転換があります。
主な政策目的は以下の通りです。
- 少子高齢化に伴う労働力不足対策
- 複数の職場で働くことを促進し、労働市場全体の柔軟性を高めることで、減少する生産年齢人口を補う。
- 労働生産性の向上
- 社員が副業で新たな知識やスキル、人脈を獲得し、それを本業に還元することで、組織全体の生産性向上とイノベーションを促進する。
- 個の自律的なキャリア形成支援
- 企業に依存するのではなく、社員一人ひとりが自らの意思でスキルを磨き、キャリアの選択肢を広げることを後押しする。
- 地域活性化
- 都市部の社員が地方の企業や団体で副業を行うことで、地方への人材・知恵の循環を促す。
このように、副業解禁は単なる「働き方の柔軟化」ではなく、国の経済構造と人材戦略そのものを変革する手段として位置づけられています。
副業解禁の裏にある企業の狙い|容認の背景に潜む二重のメッセージ
副業解禁は政府の方針に乗ったものですが、企業側にはより複雑で複合的な意図が存在します。
それは、「建前としての戦略」と「現実としての経済性」という、しばしば矛盾する二重のメッセージ性です。
人材育成とブランド強化を狙う【戦略的側面】(建前)
多くの企業が公式に掲げるのは、社員の成長と組織の活性化を目的とした戦略的な理由です。
副業容認は人的資本投資の一環として位置づけられています。
- スキルと知識の還元(イノベーション促進)
- 社員が副業で獲得した最新の知識、人脈、そして多様なビジネス経験は、そのまま本業にフィードバックされます。
- これにより、新たな視点がもたらされ、組織全体のイノベーションの促進につながります。
- モチベーション向上、離職防止、企業ブランディング効果
- 柔軟な働き方を認めることは、企業イメージ、すなわち企業ブランディング効果を高めます。
- 特に優秀な人材にとって、副業の機会は魅力的な選択肢となり、モチベーション向上や離職防止に貢献します。
固定費抑制と生活補填を期待する【経済的側面】(現実)
しかし、水面下には、現在の厳しい経済状況が影響している側面も否定できません。
この側面は、特に賃上げ原資の確保が難しい企業で見られます。
- 給与抑制と外部委託
- 物価が上昇する中、企業が十分な賃上げ原資を確保できないケースは少なくありません。
- 副業を容認することで、「実質的な給与上昇を外部に委ねる」ことが可能となり、企業は固定人件費を抑制できる側面があります。
- 生活補填手段としての期待
- 賃上げが難しい状況で、社員の副業による収入が生活補填手段となることへの期待も存在します。
- これは、社員の生活安定を支援するという現実的な対応策でもあります。
結論として、副業解禁は企業にとって「人的資本投資」であると同時に、「給与転嫁策」としても機能しており、この二つの側面を理解することが、現代の副業ブームの本質を捉える鍵となります。
副業制度の現状と企業の二極化|進む導入企業と依然慎重な企業の差
政府のガイドライン改定後、企業の対応は明確に二極化しています。
多くの大企業が制度を容認する方向へ舵を切る一方で、根強い懸念から依然として禁止を続ける企業も約半数に上ります。
上場企業・大企業で進む副業容認の現状
人材獲得競争が激しい上場企業や大企業では、副業容認が「主流」となりつつあります。
- 容認企業の割合
- 2025年時点の大手人材コンサルティング会社の調査では、大企業の約55.2%が副業を容認していることが判明しており、副業を認める企業が過半数を占めています。
- 運用形態の主流
- ただし、全面的な自由を認めているわけではありません。
- 過労防止や情報漏洩リスクを管理するため、ほとんどの企業が届出制または許可制を採用しています。
- これは、リスクを最小限に抑えつつ、人材戦略上のメリットを享受しようとする、企業側の慎重な姿勢の現れです。
依然残る「副業禁止の壁」|企業が解禁に踏み切れない構造的課題とは
容認の流れがある一方で、企業全体で見ると「禁止」も依然として大きな割合を占めています。
- 禁止企業の割合
- 厚生労働省や広範な企業調査によれば、全体(中小企業含む)の約50%の企業は依然として副業を禁止しています。
- さらに、そのうち7割の企業は今後も方針を変更する予定がないと回答しており、企業間の格差が鮮明になっています。
禁止継続の主な理由
副業を禁止する企業が挙げる理由は、主にリスク管理と本業専念の確保に集約されます。
- 過重労働・健康リスク
- 最も深刻な懸念の一つが、社員の健康問題です。
- 副業によって労働時間が通算され、心身の疲労が深刻化する懸念があります。
- 特に、既に長時間労働が常態化している企業では、労働時間管理の困難さから、リスク回避のため禁止を選択せざるを得ません。
- 本業専念義務と業務効率
- 企業は、社員が他の仕事にエネルギーを割くことで、本業の生産性や集中力が低下し、業務効率が悪化することを恐れます。
- 機密性・情報漏洩リスク
- 製造業や金融業、インフラ業界など、業務の機密性が高い分野では、情報漏洩や競業防止のリスク回避が、副業禁止を維持する最大の要因となっています。
経営の板挟みと構造的課題
副業禁止を続ける企業の多くは、「経営の板挟み」状態にあります。
賃上げが困難な経済状況であるにもかかわらず、上記のようなリスク懸念や管理体制の未整備から副業解禁もできない状態、すなわち「給与も上がらず副業も禁止」という状況に陥っています。
この状況は、結果的に従業員の生活負担を個人に転嫁し、「働き方改革」の恩恵から取り残されていることを意味します。
2025年の労働市場において、このような企業は優秀な人材の流出を招くリスクの高い構造的課題を抱えていると認識されつつあります。
就業規則に「副業規定なし」の企業が抱えるリスク|トラブル事例と防止策
副業への対応は「容認」と「禁止」の二極化が進む一方で、就業規則に副業に関する規定を設けていない企業も存在します。
これは、現代の労務管理における最大の盲点となり得ます。
規定の有無の法的意味合い
そもそも、労働者が就業時間外に副業を行うことは、日本国憲法に保障された職業選択の自由の下、原則として自由です。
したがって、企業が副業を禁止しないのであれば、就業規則にあえて言及する義務はありません。
この「規定なし」の状態は、社員の自由を尊重している姿勢とも解釈できます。
しかしながら、この「規定なし」こそが、企業側にとっては最もリスクの高い状態となります。
「規定なし」が誘発するトラブル
規定がない場合、企業はトラブル発生時に以下の重要なリスクに対して、規則上の対抗措置をとる根拠を失います。
- 過重労働・安全配慮義務違反リスク
- 労働時間通算のルールや副業の報告義務が明確でないため、社員が副業によって過労状態に陥った場合、企業側の安全配慮義務違反を問われるリスクが極めて高くなります。
- 情報漏洩・競業のリスク管理不能
- 秘密保持や競業避止義務違反が発生した場合でも、就業規則に明確な禁止事項や罰則規定がなければ、企業が副業の停止や懲戒処分を下す正当な根拠を欠いてしまいます。
したがって、規定がない企業は、トラブルが顕在化した際に初めて、その労務管理上の脆弱性が露呈することになり、早急な規定の整備が求められます。
副業容認による企業リスクと戦略的メリット|安全管理と人材活用の両立
副業解禁は、企業に「メリットの最大化」と「リスクの最小化」という二律背反の課題を突きつけます。
持続的に制度を運用するためには、この両側面を冷静に分析し、制度設計に落とし込むことが不可欠です。
企業が直面する副業リスク|制度設計で最小化すべき課題とは
副業を容認することで企業が負う主要なリスクは、その性質から「情報と競争に関するリスク」と「労働と健康に関するリスク」の二つに大別されます。
1. 情報漏洩・競業リスク
- 情報漏洩リスク
- 社員が副業先で、本業で知り得た機密情報、顧客データ、ノウハウなどを意図せず、あるいは意図的に流出させる懸念があります。
- 特にIT企業や機密性の高い技術を扱う製造業では、自社技術の漏洩は企業の存続に関わる脅威となります。
- 競業リスク
- 社員が同業他社や競合となるビジネスを副業として行うことで、自社の競争優位性が直接的に損なわれる可能性があります。
2. 過労・労災リスク
- 過労・健康リスク
- 労働基準法では、本業と副業の労働時間は原則として通算されます。
- 企業側の管理体制が不十分だと、社員が気づかないうちに法定労働時間を超え、心身の健康を悪化させる危険性が高まります。
- 安全配慮義務と労災トラブル
- 社員が過労によって体調を崩した場合、企業は安全配慮義務違反を問われる可能性があり、労災トラブルに発展するリスクも無視できません。
- 労働時間の正確な把握と、適切な健康管理措置の徹底が求められます。
副業容認が企業にもたらす戦略的メリット|人材確保と組織活性化の効果
一方で、リスクを適切に管理することで、副業容認は企業に計り知れない戦略的なメリットをもたらします。
これらは、単なるコスト削減ではなく、「人的資本」への明確な投資効果として現れます。
1. 人材の確保と定着
- 採用競争力の強化
- 柔軟な働き方、特に副業容認は、現代の優秀な人材にとって「選ばれる企業」となるための重要な要素です。
- これが採用競争力を高める強力なツールとなります。
- 離職の防止
- 社員が新たなスキル獲得や収入補填の機会を社外に求めることなく、本業を続けながら自己実現できる環境を提供することで、優秀な人材の離職を防止する効果があります。
2. 組織の活性化
- 知識・スキルの波及
- 副業で得た最新の市場トレンド、異業種の人脈、専門的なスキル(例:プログラミング、デジタルマーケティング)などが本業に還元され、社内に新たな知恵の循環が生まれます。
- イノベーションの促進
- 既存の枠にとらわれない発想や、外部の視点が持ち込まれることで、組織全体の風土が活性化し、イノベーションを促進する土壌が形成されます。
まとめ|副業解禁の本質と企業が果たすべき責務|リスクとメリットの整理
副業解禁は、単なる企業の福利厚生や働き方改革の一環ではなく、「給与転嫁策」と「人材育成策」という現代の経済と労働市場が抱える二つの側面を凝縮した構造的課題です。
企業が副業時代において持続的な成長を望むならば、目先の情報漏洩リスクや過労リスクの回避に留まらず、より高次の目標を掲げる必要があります。
その本質的な役割とは、労働者の生活権とキャリア自律を支援しつつ、企業の健全性(リスクと競争優位性)を担保するという、バランスの取れた制度設計を確立することに尽きます。
次回予告|副業解禁の法的・実務的論点と企業のルール設計
さて、次回の記事では、本稿で浮き彫りとなった副業解禁の法的・実務的な論点を深掘りし、企業が労働者の生活権と企業の健全性を両立するための具体的なルール設計に焦点を当てます。
- 副業禁止規定の合法性と合理性
- どこまでが許され、どこからが不合理な制限となるのか。
- 届出制・許可制・禁止制の運用例と、それぞれのメリット・デメリット。
- 企業リスクと、労働者の生活権や低賃金とのバランスを考慮した規定の作り方。
次回の記事は👉副業は原則OK?就業規則で許可制・届出制にする場合の注意点
次回の詳細な論考にどうぞご期待ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。
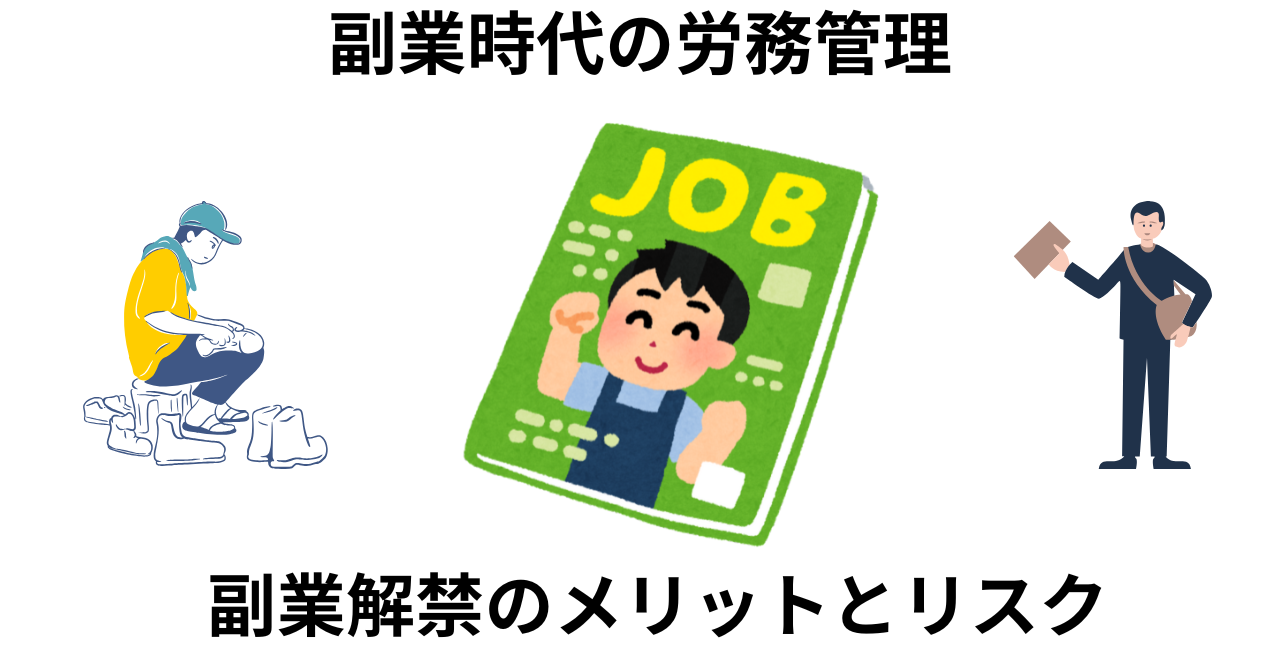

コメント