本記事は「【社労士が解説】企業のための熱中症対策 実践講座」シリーズの第6話です。第1話は👉熱中症は「他人事」ではない!企業に求められる安全配慮義務の基礎
シリーズ全体の記事はコチラからご覧ください👇
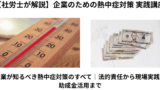
前回の記事では、職場における熱中症対策の具体的なチェックリスト(教育、記録の徹底)について詳述いたしました。
前回の記事は👉熱中症予防教育と記録管理|安全配慮義務を果たす実務ガイド
従業員の安全を守るための予防策がいかに重要であるか、改めてご理解いただけたことと存じます。
熱中症発症時の企業リスクと労災認定のポイント
しかし、残念ながら、どんなに万全の対策を講じていても、熱中症のリスクを完全にゼロにすることは困難です。
特に日本の夏は年々厳しさを増しており、職場での熱中症発症は、もはや他人事ではありません。
万が一、貴社の従業員が職場で熱中症を発症してしまった場合、それは単なる体調不良で済まされない問題となります。
場合によっては、労働災害(労災)認定に繋がり、さらには企業が安全配慮義務違反として法的責任を問われ、多額の損害賠償を請求されるリスクも潜んでいます。
今回の記事では、熱中症発症時の労災認定の判断基準から、企業の安全配慮義務と具体的な責任範囲を明確にします。
そして「注意喚起はしていた」というだけでは済まされない事態にどう向き合うべきか、経営者・総務担当者の皆様が知っておくべき重要なポイントを解説いたします。
熱中症と労災認定の判断ポイント|業務遂行性と業務起因性
従業員が業務中に熱中症を発症した場合、それが労働災害(労災)として認定されるかどうかは、最終的に労働基準監督署が判断を下します。
労災保険は、業務上の事由による負傷や疾病に対し給付を行う制度ですが、熱中症が労災認定されるためには、主に次の2つの重要な条件を満たす必要があります。
業務遂行性とは|業務中の熱中症発症が労災認定される条件
これは、熱中症を発症した際に、従業員が会社の支配下にある状態で業務を行っていたかどうかを指します。具体的には、以下のような状況が含まれます。
- 作業中の発症
- 最も典型的なケースです。
- 休憩時間中の発症
- 業務に付随する行為として、休憩時間中に熱中症になった場合も労災の対象となることがあります。
- 通勤途中の発症
- 特定の状況下では、通勤中の熱中症も労災と認められる可能性もあります。
重要なのは、会社の指揮命令下にあったか、または業務に密接に関連する行動をとっていたか、という点です。
業務起因性とは|業務に内在する危険が原因の熱中症と労災認定
これは、発症した熱中症と業務との間に「相当な因果関係」があるかどうかを判断する要素です。
単に業務中に発症しただけでなく、その業務に内在する危険(ここでは暑熱環境)が原因であると認められる必要があります。
判断にあたっては、以下の要素が総合的に考慮されます。
- 労働環境
- 作業場所の気温、湿度、日差し、風通しなど、暑熱環境の状況。
- 作業内容・運動強度
- 肉体労働を伴う作業や、動きの激しい作業かどうか。
- 作業時間
- 休憩を挟まず長時間作業を継続したか。
- 体調管理
- 企業が従業員の健康状態を適切に把握し、必要な対策を講じていたか。
- 基礎疾患の有無
- 従業員に熱中症のリスクを高める持病がなかったか。(ただし、基礎疾患がある場合でも、業務の過酷さが主要因であれば労災認定される可能性はあります。)
また、医師による医学的な診断も不可欠です。
これらの要素を総合的に判断し、熱中症が業務に起因すると認められれば、労災認定へと進みます。
企業の安全配慮義務と熱中症|損害賠償リスクと法的責任
熱中症が労災として認定された場合、従業員は労災保険から治療費や休業補償などの給付を受けられます。
しかし、それで企業の責任がすべて終わるわけではありません。
企業側には、労働契約法に基づいて、従業員の安全と健康を確保するための「安全配慮義務」があります。
この安全配慮義務とは、単に法律で定められた最低限の基準を満たせば良いというものではありません。
事業の状況や労働環境に応じて、従業員が安全かつ健康に働けるよう、企業が最大限に配慮すべき責任を指します。
企業が講じるべき熱中症対策|具体的な安全配慮措置
具体的には、熱中症対策において以下のような多岐にわたる措置が企業に求められます。
労働環境の整備
WBGT値(暑さ指数)の測定と管理、適切な休憩場所(涼しい場所や冷房設備のある場所)の設置、空調や換気設備の適切な運用など、物理的な環境改善が不可欠です。
作業管理
酷暑時間帯の作業を避ける、休憩時間を十分に確保する、作業負荷を軽減する工夫(複数人での作業、機械の導入など)を取り入れるといった、作業内容そのものへの配慮が必要です。
健康管理
定期的な健康診断の実施に加え、体調不良を訴える従業員への迅速な把握と適切な対応(作業の中止、医療機関への受診勧奨など)、巡視による従業員の状況確認などが求められます。
教育
熱中症の危険性、予防策、緊急時の対応方法などについて、従業員への情報提供や定期的な注意喚起、教育を徹底する必要があります。
もし、企業がこれらの安全配慮義務を怠ったと判断された場合、労災保険からの給付とは別に、従業員やその遺族から損害賠償請求を受けるリスクが生じます。
この場合の損害賠償には、実際に発生した治療費や、熱中症によって失われた「逸失利益」(将来得られたはずの収入)、さらには精神的な苦痛に対する慰謝料などが含まれる可能性があります。
労災保険は最低限の補償であり、企業の安全配慮義務違反が認定されれば、その補償をはるかに超える賠償責任を負うことになる点を認識しておく必要があります。
熱中症に対する注意喚起だけでは企業の安全配慮義務は果たせない
「熱中症に注意してください」「水分補給を促しました」「休憩を呼びかけました」
企業側として、熱中症対策を講じていたという認識があるかもしれません。
しかし、裁判例を見る限り、このような形式的な注意喚起や一般的な声かけだけでは、企業の安全配慮義務を果たしたとは認められないケースが非常に多く存在します。
安全配慮義務は、単に「やったフリ」をするものではありません。従業員の安全を守るためには、具体的な状況に応じた、実効性のある対策が求められます。
形式的な熱中症対策では労働安全衛生法上不十分な理由
企業には、予測可能な危険を回避するための措置を講じる「結果回避義務」があります。
熱中症においては、その危険性を認識(予見可能性)し、発症させないための具体的な措置(結果回避義務)を講じる責任があるのです。
単なる注意喚起は、この「具体的な措置」には当たらないと判断される傾向にあります。
裁判所は、企業が本当に従業員の安全を確保するために、リスクの程度に応じて以下のようにより積極的・具体的な措置を講じていたかを重視します。
客観的な環境管理
- 作業現場の気温や湿度を定期的に測定し、記録する。
- WBGT値(暑さ指数)を積極的に活用し、危険レベルに応じた作業中止や休憩時間の延長などの基準を設ける。
休憩と水分・塩分補給の徹底
- 単なる休憩の呼びかけだけでなく、涼しく、十分に休める休憩所を物理的に設置し、その場所への誘導を徹底する。
- 水分だけでなく、塩分も補給できる飲料(スポーツドリンクや塩飴など)を常備し、摂取を推奨、あるいは義務付ける。
作業管理と服装指導
- 暑熱環境下での作業時間を短縮したり、最も暑い時間帯の作業を避けたりする作業スケジュールの調整。
- 通気性の良い服装や冷却グッズの使用を奨励・指導する。
体調不良者への早期対応
- 従業員からの「だるい」「気分が悪い」といった体調不良の訴えに対し、安易に作業を継続させず、直ちに作業を中断させ、涼しい場所で休ませる。
- 必要に応じて、看護師や医師の判断を仰ぐ、あるいは医療機関への受診を促すなど、迅速かつ適切な対応を取る。
これらの措置は、熱中症リスクを管理するための基本的なステップであり、これらを怠った結果、熱中症が発症すれば、企業は「注意喚起はしていた」という弁明だけでは責任を免れることはできないのです。
企業には、暑熱環境下で働く従業員の命と健康を守るための、より具体的で実効性のある対策が強く求められています。
裁判例から学ぶ企業の責任|熱中症による死亡事故・健康被害
これまで見てきたように、熱中症対策は企業の単なる努力目標ではなく、法的な義務として強く求められます。
実際に、熱中症による死亡事故や健康被害が発生し、企業が安全配慮義務違反を問われ、多額の損害賠償を命じられたケースは少なくありません。
ここでは、多くの判例から共通して見られる、企業が責任を問われ、敗訴に至るポイントと、その教訓を見ていきましょう。
熱中症事例の概要と企業が敗訴した原因
ある裁判例では、以下のような事案で企業の責任が認定されました。
事案の争点
- 夏季の炎天下における屋外作業において、会社が従業員に対し、十分な休憩や水分補給に関する具体的な指示を行わず、WBGT値(暑さ指数)が高温を示す危険な環境下で作業を継続させた結果、従業員が熱中症で倒れ、最終的に死亡に至ったというケースです。
- 遺族が企業に対し、安全配慮義務違反を理由に損害賠償を求めました。
企業の敗因
- 裁判所は、当該企業が作業環境の危険性を十分に認識できたにもかかわらず、熱中症の予防に対する具体的な作業中止基準や休憩基準を設けていなかった点を厳しく指摘しました。
- また、従業員への熱中症予防に関する具体的な教育や情報提供も不十分であったと認定されました。
- 企業側は「休憩を取るように指示はしていた」と主張しましたが、裁判所は、単に「休憩を取るように」といった一般的な指示だけでは、具体的な安全配慮義務を果たしたとは言えないと判断。
- 危険な環境下での労働においては、企業がより積極的かつ具体的に、従業員の健康と安全を管理する義務があると結論付けました。
- この結果、企業には遺族に対して、高額な損害賠償の支払いが命じられることとなりました。
熱中症裁判例に学ぶ企業の安全配慮義務の共通教訓
上記でご紹介したような熱中症に関する裁判例は、インターネット上で『熱中症 裁判例』と検索すると、多くの事例を確認できます。
それぞれ具体的な状況は異なりますが、共通して企業に求められるのは、単なる注意喚起に留まらない、具体的かつ実効性のある予防措置と、万が一の際の適切な対応であるという強いメッセージを発しています。
これらの裁判例が明確に示しているのは、熱中症対策が「やっていれば大丈夫」という安易なものではないという事実です。
企業に求められるのは、以下の点に集約されます。
- 危険性の「予見可能性」
- 暑熱環境下での熱中症発症の危険性を、企業は予見できたはずであるという認識。
- 「結果回避義務」の徹底
- その危険性を予見できたのであれば、実際に熱中症の発症を回避するための具体的な措置を講じる義務があったということ。
つまり、熱中症対策は、単なる「努力目標」や「推奨される行動」ではなく、具体的な行動と結果が求められる企業の法的責務であるということです。
労働安全衛生法や労働契約法に基づく企業の義務を怠った場合、その責任は極めて重いものとなることを、これらの裁判例は私たちに強く警鐘を鳴らしています。
まとめ|熱中症対策は企業の安全配慮義務
熱中症対策は、単に従業員の健康を守るという側面だけでなく、企業の法的・社会的責任として捉えるべき非常に重要な課題です。
予防策を講じることは、従業員の安全と健康を守るだけでなく、万が一の労災発生時における企業の法的リスクを大きく軽減することにも直結します。
これまで見てきたように、「注意喚起だけでは不十分」という厳しい現実が裁判例からも示されています。
労働者の命と健康を守るために、企業には積極的かつ具体的な対策を講じる義務があるのです。
適切な環境整備、作業管理、健康管理、そして継続的な教育・訓練を通じて、熱中症の予防を徹底すること。
そして、もし発症してしまった場合には、迅速かつ適切な対応を取ることが、結果的に企業の信頼性を高め、不要な法的紛争や損害賠償リスクから自社を守ることに繋がります。
熱中症対策は、未来の企業活動を守るための、不可欠な投資であると認識しましょう。
次回予告|中小企業でもできる熱中症対策の実践法
次回は、今回のテーマを受けて、特に中小企業の皆様が実践できる「低コストで訴えられない熱中症対策」に焦点を当てて解説します。
「コストがかかるから…」と対策を諦めていた企業様でも、手軽に始められるWBGT測定方法や、リスクを回避するための社内マニュアル作成例、就業規則でのルール化のポイント、そして助成金の活用法まで、具体的な情報をお届けします。
次回の記事は👉中小企業でもできる!低コストで“訴えられない”熱中症対策 前編
どうぞお楽しみに!
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。
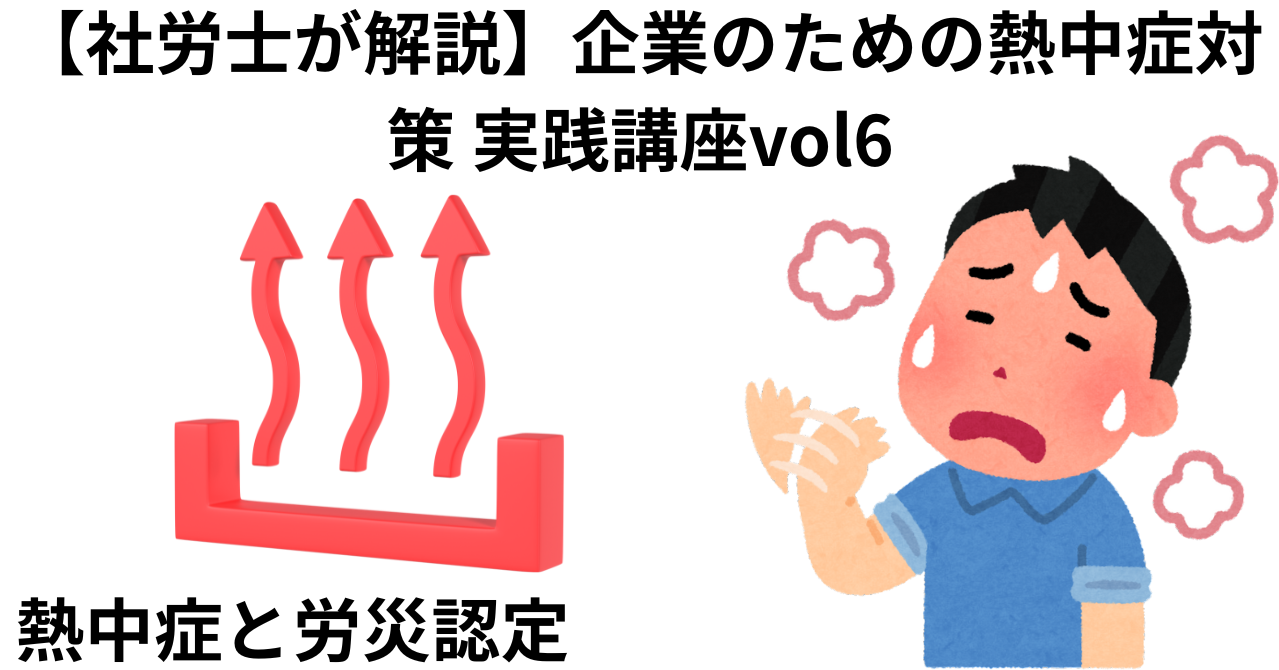

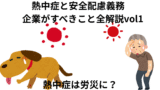
コメント